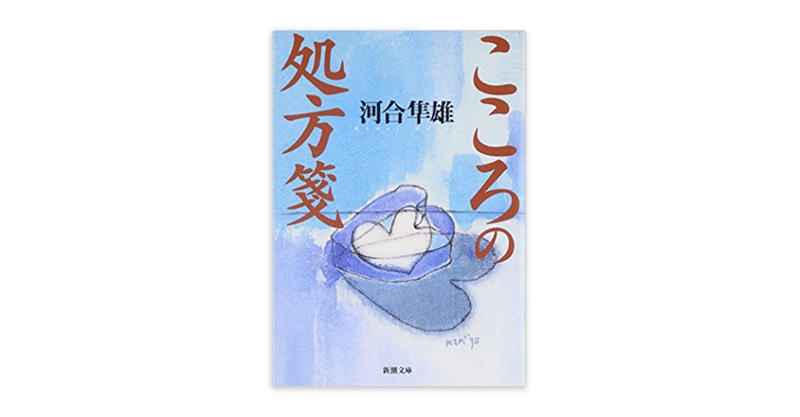
よそおわれた「自己啓発本」―書評『こころの処方箋』河合隼雄
以前、「新潮文庫の100冊」についての記事を書きましたが、今月に入ってラインナップが発表され、あちこちの書店で大々的にフェアがおこなわれています。
ラインナップはいくつかのジャンルにわかれていますが、そのうちの「考える本」に、河合隼雄の『こころの処方箋』が取りあげられていました。
じつは、岩波新書から出ていた『コンプレックス』という一冊も、先月になって改版が刊行されており(初版は1971年なので、ちょうど半世紀!)、その死後もうすぐで14年ほど経とうとしていますが、いまなお河合隼雄の著作がおおくの読者に読まれていることがよくわかります。
さて、そこで今回の一冊。『こころの処方箋』。
この本は、55の章にわかれており、それぞれがきっちり4ページという短さ。むずかしい心理学の講義というよりは、気軽に読めるエッセイ。いや、むしろ「自己啓発本」にちかいスタンスの本だと考えるのがよいかもしれません。
いきなり「あとがき」からで恐縮ですが、河合隼雄じしんのことばをすこし引用してみたいとおもいます。この本にたいする読者の反応を受けて、著者はこのように語っています。
よく言われたことは、「フム、フム、と納得しながら読んでますよ」と言う類のほめ言葉であった。ほめられると嬉しくて、よい気になって書き続けてきたが、よく考えてみると、その人が「フム、フム」とうなずくのは、もともと自分の知っていたことが書いてあるからであって、私の書いていることは、既に読者が腹の底では知っていることを書いているのだ、ということに気づいたのである。端的に言えば、ここには「常識」が書いてあるのだ。
ともすると誤解されがちですが、「自己啓発本」というのは、読者のしらない目からウロコの処世術を読者につきつけてみせる、というものではありません。むしろその逆。たとえば「継続は力なり」とか「早起きは三文の徳」とか、読者がすでにしっているはずの「あたりまえ」のことを声を大にして「再認」させること、そこにこそ啓発本としての役割があります。
それをここで河合隼雄は、「常識」ということばに落とし込んでいます。
じっさい、「人の心などわかるはずがない」とか「イライラは見とおしのなさを示す」とか「やりたいことは、まずやってみる」とか、各章につけられたタイトルは、ほとんど「火を見るよりも明らか」におもえるほどの「常識」的な文言です。
でも、そんなあたりまえなはずの「常識」が、河合隼雄という語り手の口から語られることによって、まるで、かつてしらなかったおどろくべきことのようにぐさぐさと刺さってくる。各章4ページという短い長さでありながら、おもわずそこに何本もの傍線を引きたくなってくる。
もしかすると、この本を「自己啓発本」と呼ぶことに抵抗のあるかたもいるかもしれません。かくいうわたしじしんもほとんどそうした本は読まないですし、正直なところ、「自己啓発本」というジャンルに、すくなからず「きな臭い」ものを感じてしまうタイプです。
けれど、この河合隼雄による「自己啓発本」には、いっさい「きな臭い」ものが感じられません。それは、彼のことばが、頭でっかちな観念から生まれたものではなく、臨床心理学者として、おおくの「患者」の苦悩と向き合ってきたなかで培った人生経験からきているためだろうとおもわれます。
…なんだか、「あとがき」だけで一冊を語るという暴挙に出てしまいましたが、読者それぞれのこころの「症状」にあった「処方箋」が、本書のなかに書かれていることはまちがいありません。
こころのどこかになにか癒えないものをかかえているかた。そんなあなたに、いちど手にとっていただきたい一冊です。
最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。
