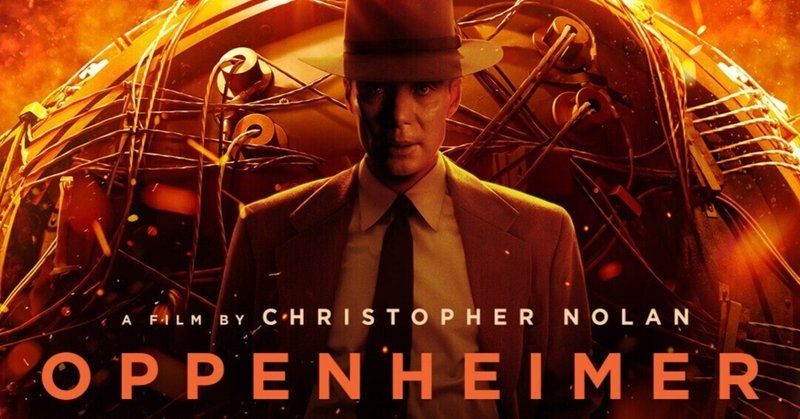
轟音ドラマ『オッペンハイマー』の功罪
『Oppenheimer』★★★☆。
Imdb / Wikipedia / Rotten Tomatoes
映像と音の圧が、同監督の近作と比べても群を抜いている。これに脚本の妙が加わると、一見してスペクタクルに欠ける科学者の地道な研究生活が怒涛のサスペンス作品になる。フラッシュ・インサートも多いし、音基軸のシーン・トランジション、時間軸の入れ替えも頻繁。そこへ重低音鳴り響くルドウィグ・ゴランソンの音楽がひたすらレイヤーを重ねる。ドラマ映画として、とにかく物々しい。Mixの加減で、セリフすら聞き取れないシーンがゴロゴロある。
「原爆の父」を描くことの重さを慮るに、日本公開が躊躇われていても不思議はない。けれど映画自体の軸はそんな議論の焦点から大きく外れている。ノーラン作品としての特徴がなにより色濃く、問題視されるだろうトピックそのものから映画が独立している。キャラクター・スタディ(=人物・人間研究の成果)として、そしてドラマ作品としての印象の方が強い。
根本の話をすると。『オッペンハイマー』は科学者をアーティストに見立てて、アートvsビジネスのせめぎ合いを描く物語だった。原爆を生み出した人間の贖罪に焦点を充てた物語ではなかった。3時間におよぶ総尺のうち40分〜1時間ほどを占める3幕目が、そんなアプローチを決定づけている。人物史としての研究者(=アーティスト)個人の尊厳に絡む問題に執着しているから、映画は原作の原題である「アメリカン・プロメテウス」ではなく「オッペンハイマー」と題された。
そのアプローチそのものを問題視するのも、間違いではないけれど。
映像技術と演出のあり方には好みが大きく分かれるが、それらの粋を極めた一本だ。「全編で轟音鳴り響く『12人の怒れる男』だ」と冗談めかす米レビューサイトの分析がまさに芯を食う。
シーンを跨いで流れ続ける音楽にセリフがかき消されて何度も内容を取りこぼしそうになるのは必至。それでも要所要所でウィットに富んだ会話劇を見せつけられる。キャスティングも、一見するとブームは去ったか、あるいは忘れられた俳優陣を据えて、演技力一本で勝負させるような配役になっているのも特徴的。
大きなスクリーンでこそ見るべきだと感じる。そもそも、もう3時間の映画は家では見切れないし。
(鑑賞日:2023年8月10日@Regal Edwards Kaleidoscope)
註:本稿、2024/1/8付で正しい作曲担当者の名前を記入・訂正してあります。失礼しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
