
認知症予防の教科書【ウォーキングで認知症を乗り越える】
はじめに
なぜ人類は長生きできるようになったのでしょうか。
人類が長生きできるようになった理由は複数あります。
医療技術の進歩
衛生状態の改善
栄養と食生活の改善
など、いろいろな要因があると思います。
その理由はさておき、困った問題も出てきました。
それが認知症です。
長生きするようになったら認知症は避けては通れないのでしょうか。
いえ、そう悲観することはありません。
世界中で認知症の予防法に関して研究が進められています。
何が認知症予防にいいのでしょうか。
ウォーキングが一番、認知症予防になります。
歩くことで認知症を予防できるというエビデンスが、どんどん出てきています。
認知症を予防することもできますし、歩くことで軽度認知障害(認知症の前段階)が改善するというデータもあります。
ウォーキングが、なぜ認知症の予防になるのかについては、おいおい説明していきます。
過去の自分の選択の積み重ねが、現在の自分
もし今、運動不足を自覚しているなら、それは過去の自分が運動しない選択の積み重ねをしてきた結果です。
過去は変えられません。
医師に糖尿病など宣告されて後悔しても無駄です。
現状を受け止めるしかないです。
でも今から運動する選択をすることはできます。
今から将来へ向けて積み上げることはできるし、それ以外の方法はないです。
分かります。
もし医師に糖尿病など宣告されたらショックですよね。
でも将来、
「それがあるから今の運動習慣のある自分になった」
と言える自分になる以外、ないですよね?
もしまだ糖尿病など医師から宣告されていないなら幸いです。
本書を紐解き、読み進めていっていただければと思います。
認知症は『歳のせい』だけではない(1−01)

認知症になるのは歳のせいばかりではなく、ベースに糖尿病が隠れている場合が多いです。
ウォーキングと食事療法に取り組めば、糖尿病は寛解し、認知症予防の可能性を高めることができます。
結論:糖尿病を予防することで、認知症を予防しよう!
65歳を超えると、4人に1人が認知症
厚生労働省は2025年には、認知症の方は700万人を超え、認知症予備軍の方も加えると1300万人にも達すると推計しています。
要するに65歳を超えると、4人に1人は認知症かその予備軍になるということです。
ある認知症医療の第一人者は、講演で「近い将来、65歳以上の6割が認知症になる」とおっしゃっていました。
認知症が増えている原因
糖尿病になると認知症になるリスクが高まることが明らかになっています。
認知症が増えている原因は、ズバリ、『糖尿病が増えている』のが原因です。
歩かない生活が糖尿病を増やす

2型糖尿病の場合、炭水化物の取りすぎと、歩かないことが糖尿病の原因です。
糖尿病の治療は原因の反対で、ご飯やパンなどの主食と甘いものを減らすこと、1日8,000歩をウォーキングすることが土台となります。
脳血管性認知症
糖尿病のために血糖値や、血中インスリン濃度が高い状態が続いていると、動脈硬化が進行してしまいます。
その結果、脳梗塞を引き起こし、認知症を引き起こしてしまいます。
アルツハイマー型認知症
大脳が萎縮すると同時に、脳内に『アミロイドβ』というゴミが溜まってしまうことが原因です。
このアミロイドβというゴミを分解してくれるのが、インスリンを分解する酵素なのです。
ところが高血糖状態が続いてインスリンが高濃度だと、インスリンを分解するので精一杯で、アミロイドβは分解が不十分で脳内に残ってしまいます。
というわけで糖尿病の方は脳内にゴミが溜まりやすく、アルツハイマー型認知症になりやすいのです。
糖尿病は絶対に放置しない!
糖尿病と認知症の関わりについては、まだ解明されていなことも多いですが、糖尿病を放置しないでください。
警鐘を鳴らす意味で、認知症になるリスクについてもインプットしていただいて、ウォーキングの必要性について考え、モチベーションを維持してください。
まとめ

認知症になるのは歳のせいだけではありません。
年を取ったら避けられないと考えている人が多いのですが、実は糖尿病が隠れていることが多いのです。
食事と運動という非薬物療法に取り組み、糖尿病を防ぐことで、認知症を予防しましょう!
認知症予防にウォーキングしよう!(1−02)

先日、かつての会社の同僚が若年性認知症と診断されました。
65歳未満で認知症を発症する若年性認知症の患者さんは、全国で4万人ほどいらっしゃるそうです。
認知症はお年寄りの病気と思っている方が多いと思いますが違います。
若年生認知症の方でなくても、誰でも、もちろん筆者も。
20代から認知症の芽が育ち始めているようです。
結論1:認知症予防に『早すぎる、若すぎる』はない
結論2:認知症予防にウォーキングしよう!
物忘れなの?それとも認知症?

よく言われるのが
「昨夜の夕食、何だったかな?」➡️物忘れ
「昨夜の夕食、食べてない!」➡️認知症
という区分。
要するに、行動したことや経験したこと、そのものの記憶がごっそり全て抜け落ちてしまうのが認知症で、単なる物忘れとは違う、という見解です。
しかし筆者は、物忘れから認知症へ、グラデーションで進行していくと考えてます。
なので物忘れの段階から認知症予防に取り組むべきだとの立場です。
もちろん、認知症と単なる物忘れとは違います。
しかし、「自分は物忘れの状態だから、大丈夫」と考え、対策しない方がいることを懸念しています。
物忘れの延長線上に認知症がある
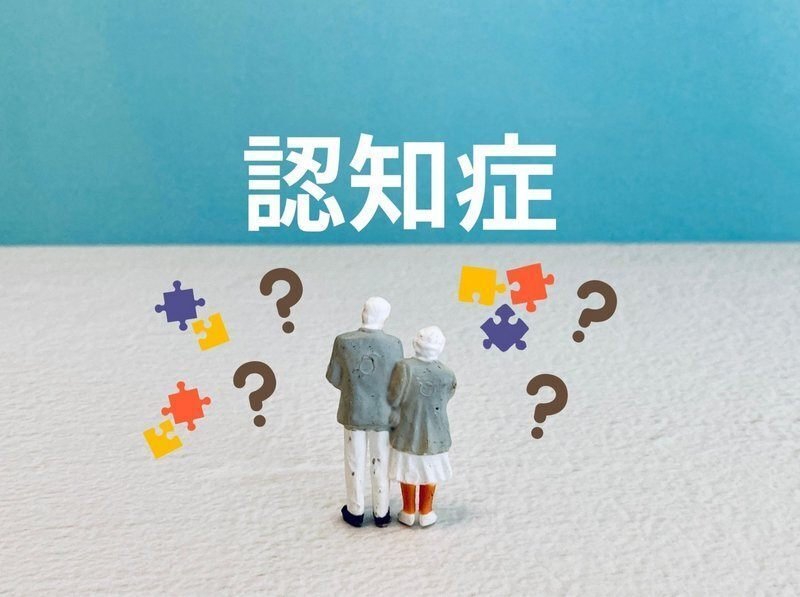
アルツハイマー型認知症に特徴的なアミロイドβやタウ蛋白と呼ばれる脳内のゴミは、認知症の始まる20年前から蓄積が始まっているとされています。
そういう意味で
「記憶力が低下したなー」
と感じる40代頃から、認知症が始まっているとも考えられます。
まとめ

筆者はウォーキングが認知症予防になるとの立場です。
ここまで説明してきた通り、認知症の症状が出てきたのが70歳代でも、その始まりは40歳代からと考えられます。
ということは、認知症は若い人たちにも他人事ではないですし、若いうちから対策することが非常に有効だと考えられます。
『ウォーキングで認知症の対策を!』
というスローガンは、認知症が気になるシニアの皆さんだけでなく、若い方にも取り入れてほしい思っています。
認知症になりやすい人の特徴5選(1−03)

「認知症になるかどうかは、将来、その時になってみないと分からない」
そう思っていませんか?
最近になり、認知症になりやすい人の特徴がわかってきました。
結論:糖尿病の方、喫煙の習慣のある方、歩幅が狭い方、歩くのが遅い方、歩く時の重心が揺れる方は認知症になりやすい
糖尿病と喫煙について

糖尿病は生活習慣病の代表格ですが、糖尿病があると認知症になりやすい。
糖尿病は認知症のリスクを上げる第一の要因です。
喫煙はさまざまながんのリスクを上げることは有名ですが、動脈硬化を起こして血の巡りを悪くするので、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを上げるほか、認知症にもなりやすくなります。
喫煙者は非喫煙者の2倍も認知症になりやすいというデータがあります。
さらに1日40本も吸っているヘビースモーカーは、非喫煙者の3倍も認知症になりやすいというデータもあります。
認知症になりたくなかったら、禁煙にチャレンジしてください。
認知症になりやすい歩き方

歩幅が狭い
歩く速度が遅い
重心が揺れるように歩く
上記のような歩き方は、認知症になりやすいというデータが、国内外で複数出ています。
東京都健康長寿医療センター研究所が群馬県と新潟県に住む高齢者を対象に行った研究によると、歩幅が狭い人は歩幅の広い人に比べて、認知機能が低下するリスクが3倍高かったそうです。
まとめ

普通に考えて、歩くって、足で歩いていると思いますよね?
でも実際は、『頭で考え、歩いている』のです。
その意味で脳で歩いていると考えて、差し支えないです。
なので脳の機能が低下すると、歩き方にも影響が及びます。
歩き方が悪くて認知症になりやすいとしたら、改善したいですよね?
歩き方を改善して、認知症予防に取り組んでください。
【認知症の基礎】四大認知症とは?(1−04)

認知症というのは、
『脳の細胞が少なくなったり働きが悪くなることで、記憶や判断力が失われる病気』
のことを指します。
認知症と診断するためには、最低でも問診、頭部CT、血液検査という3つの検査が必要です。
頭部CTや血液検査が必要な理由は、
『認知症に似た病気を除外するため』
です。
結論:四大認知症と呼ばれる、アルツハイマー型、レビー小体型、ピック病、脳血管性認知症の4つで、認知症の9割以上を占める
認知症は、一つの病気ではない

認知症状態を引き起こす原因には数十種類あります。
この事実はあまり知られていませんが、一方、四大認知症で9割以上を占めているのも事実です。
認知症と診断されるもののうち、半数弱がアルツハイマー型、レビー小体型と脳血管性がそれぞれ2割程度、ピック病が1割程度です。
アルツハイマー型認知症
大脳の萎縮や脳内にアミロイドβが溜まった結果、脳内の神経細胞が次第に壊れてしまう病気です。
この病気になると、記憶力が低下したり、日常生活での判断力が失われたりします。
レビー小体型認知症
脳の神経細胞に「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質がたまり、神経細胞の働きを妨げる病気です。
この病気になると、次第に記憶力や判断力が低下し、幻覚(見えないものを見ること)やパーキンソン症状(手の震えや歩行困難など)が現れることがあります。
脳血管型認知症
脳の血管が詰まったり出血したりして、脳の神経細胞が壊れることで記憶力や判断力が失われる病気です。
記憶力の低下や判断力の喪失が見られ、歩行障害や感情失禁、言語障害などが現れることもあります。
ピック病
前頭側頭型認知症とも呼ばれる認知症で、脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することで引き起こされます。
特に40~60代の比較的若い世代で発症することが多い病気です。
初期の頃は記憶力がはっきりしていることが多い一方、穏やかだった人が声を荒らげるようになったり、別人かと思うほどに性格が変わってしまうことがよくあります。
まとめ

アルツハイマー型がずっとアルツハイマー型かというと、そうでもありません。
レビー小体型に移行することもありますし、ピック病を合併することもあります。
要するに病型はグラデーションであり、時の経過とともに変化していく、と捉えた方が良さそうです。
【認知症の基礎】軽度認知障害(MCI)とは?(1−05)

軽度認知障害とは
『認知症の一歩手前の状態』
のことを指します。
要するに、認知症と正常な状態の狭の状態のことを表す言葉です。
この認知症の前段階というのは医学用語がありまして、MCIと呼びます。
症状が固まって認知症になってしまう前に対策することで、元の状態を維持できる可能性は十分にあります。
結論1:認知症は元には戻らないが、MCIの人は元の状態に戻ることがある
結論2:認知症を治す薬はないので、もしもの時はすぐに対策を!
MCIの気になるサイン

上記のサインは、もしかしたら認知症の前ぶれかもしれません。
もちろん人間の脳は少しずつ衰えていくものなので、ある程度の範囲であれば、老化で片付けられる話ではあります。
しかし明らかに同じ話をする回数が増えたという場合は、MCIが進行している可能性もあります。
単なる物忘れでショックを受ける必要は全くありません。
しかしご自身やご家族の方で、こういった症状が繰り返されるなら、少し注意が必要かもしれません。
もしもの時に、すぐに対策を!

抗認知症は、どの薬も根本的に認知症を治すものではありません。
老化の進行を抑える目的で処方されますが、薬の効果が期待できるのは3割程度とも。
一方で薬の副作用で暴れたり、怒りっぽくなったり、むしろ症状が悪化する人もいます。
ウォーキング
食事(栄養)
環境(コミュニケーション)
脳トレ
薬(抗認知症薬)
上記は、筆者が考える認知症予防に対応する順番です。
もちろん医師と相談のうえで優先順位は決めるべきですが、薬については
「必要な時に必要なだけ、最小限度で使うべき」
と考えています。
まとめ

認知症の一歩手前の症状MCIの症状というのは非常に多彩です。
しかし今回紹介した症状があったからといって悲観はしないでください。
最初に紹介したように、MCIの状態は元に戻ることもありますし、認知症という病気は誰もが人生の中で向き合わなければいけないことが多い病気です。
だからこそ、前向きな気持ちを持って、認知症の前ぶれと向き合って欲しいと思います。
認知症予防についても、もちろん早いに越したことはありません。
しかし症状が出てからでも
家族でウォーキングの習慣を身につける
バランスのいい食事に気をつける
夫婦で認知症という病気について学んだり、向き合う
上記は掛け替えのない貴重な財産になると思いますし、何より健康につながる大切な習慣です。
正しい知識は身を助けます。
これからも一緒に学んでいきましょう!
ここから先は
¥ 100
幸せの連鎖の起点となりたいと思います。そのためには自己研鑽は必須と考えています。よろしければサポートお願いします! いただいたサポートは自己研鑽に使わせていただきます! よろしくお願い致します。
