
人生を通底するWant toとは何か
以前の記事おいて、
コーチングセッションでは、「本音でやりたいこと(Want to)」に基づいて、「現状の外のゴール」を設定する
「Want to」とは、たとえ周囲に止められても、人生を通底して既にやってしまっていること
であるとお伝えしました。
この記事では、「Want to」の解像度を上げて理解いただくための事例として、私自身の人生を振り返り、その中でどのようにWant toを抽出したのかについて、ご紹介したいと思います。
0~6歳:幼稚園
東京都大田区、多摩川のほとりで生まれ育った私は、小さいころから手を動かして何かをつくることが好きでした。

この頃の記憶は曖昧な部分も多いのですが、幼稚園で「粘土で自分の作品をつくる」という課題が出た時のことです。私は自分の作品を、友人達のつくった他の作品と繋ぎ合わせて、全体で一つの作品にしてしまい、先生に驚かれた記憶が残っています。
この頃から、既視の領域を超えて、何か見たことのないものをつくりたい、という欲求が存在していたようです。
6~12歳:小学校
父の仕事の都合で、神奈川県横浜市の小学校に通い始めてからは、身近な自然に触れながら、自転車であちこち走り回り、自由奔放に遊ぶ少年でした。
学校の勉強は、国語だけが何故か異常に得意でした。
小6から準備を開始した中学受験は、4教科受験するように先生から言われたにも関わらず、結局、国語1科目だけで受験できる特殊枠で臨みました。

これは、各教科の中でも、最も幅広い話題に触れることができ、飽きない、ということが大きかったように思います。
一方、算数は、当時あまり得意ではありませんでしたが、塾で習った解法を、友人と情報交換する時間がとても楽しかったことを覚えています。
12~18歳:中学・高校
とにかく音楽に没頭した中高6年間でした。クラシック、ジャズ、ポップス、ロック、メタルなどあらゆるジャンルの音楽に手を伸ばしていました。

私は幼少期からピアノに触れていたこともあり、音像を色彩とともに立体的、空間的に捉えることができました。
楽曲の鑑賞や楽器の演奏を通じて、様々なジャンルの音楽から広がる空間的なイメージの違いを楽しんでいたように思います。
18~24歳:大学・大学院
小学生の頃から続けていた茶の湯に傾倒していました。
機会あって、京都の家元に滞在したことをきっかけに、その世界観の奥深さ、素晴らしさに気づきました。
茶の湯は綜合芸術である、などとも言われますが、茶室、庭、掛け軸、花、茶碗、茶入などの様々な要素が横断的に組み合わさって世界観を形作っているところに惹かれたのだと思います。

また、大学の理工学部において、応用物理の研究に触れていくなかで、社会実装の観点から、より領域横断で学びを重ねていきたいという思いが強くなりました。
そこで、当時まだ設立間もなかったシステムデザイン・マネジメント研究科という、学問分野横断型の大学院に進学しました。
24歳~現在:社会人
大学院終了後は、事業会社→戦略コンサルティングファーム→AIベンチャーと経験を重ねてきました。
学生時代から、これまでのキャリアにおいて通底することとしては、複数の領域を横断的に束ね、マルチドメインで価値を創っていくことだと思います。
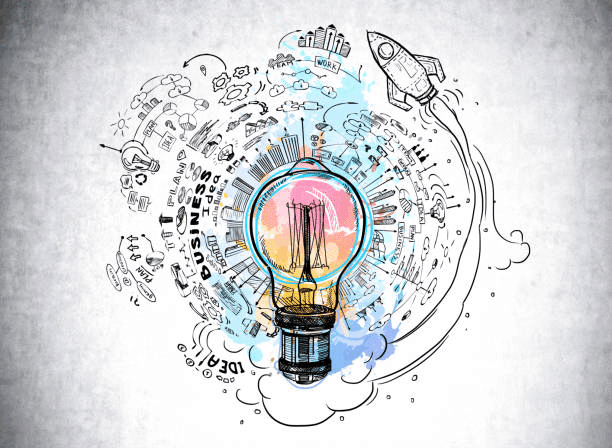
様々な領域において、卓越した才能を持つ方々との出会いを重ね、新しい世界観を創っていきたい、そんな思いが根底にあります。
最後に
人との出会いを重ねて、マルチドメインに未知(最先端・最深部)を探求し、新しい世界観をつくりたい。
そして、その新しい世界観を、一番最初に眺めていたい。
これが、私自身がコーチとの対話を重ねながら人生を振り返り抽出した、自らのコアにあるWant to(本音でやりたいこと)です。
ある時、コーチからこんな言葉をかけていただいたことがありました。
マルチドメインを実践している人たちと、たくさん話せば良いんじゃない?それが最高に楽しいよね
複数の領域を束ねた世界観を、”一番最初の試写会の観客席”で見ていたいんでしょ?
ゴールは、そういう職業自体を、新しく世の中に創り出すことだよね
その瞬間、まさに、これが私のやりたいことだと、直観しました。
そして、いま私は、仕事や趣味の領域のそれぞれで、ゴールの世界に向けた取り組みを重ねています。
まだまだ道半ばではありますが、挑戦を続けていきたいと思っています。
あくまで一個人における経験談ではありますが、読者の皆さまがWant toを抽出、特定していく上で、少しでも参考になれば、幸いです。
