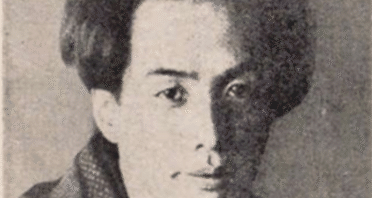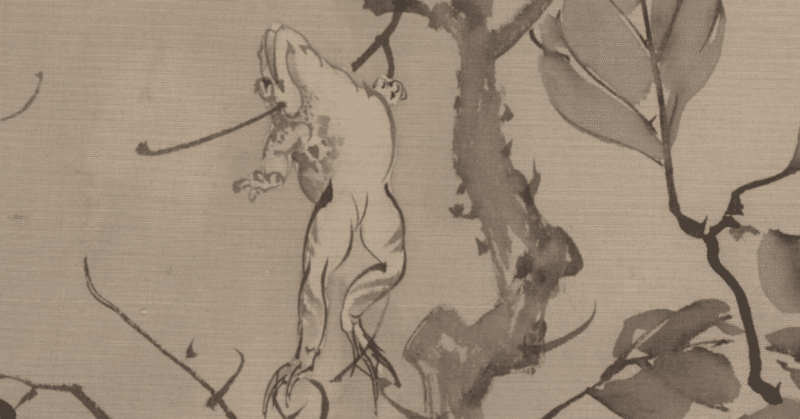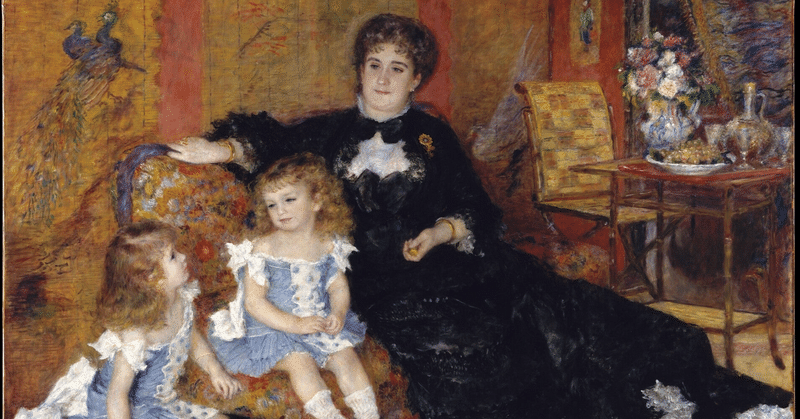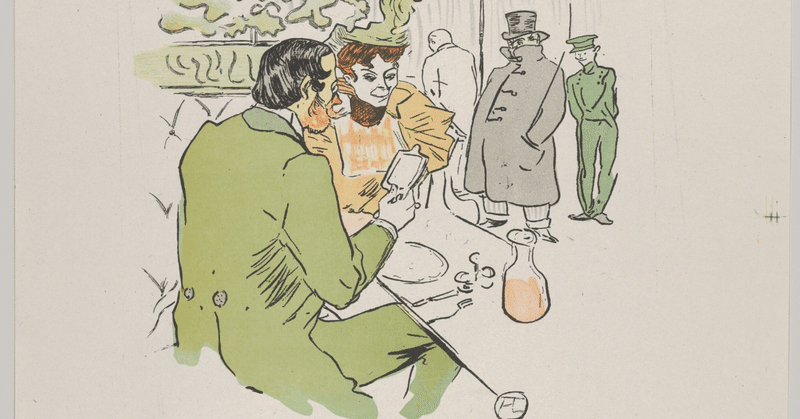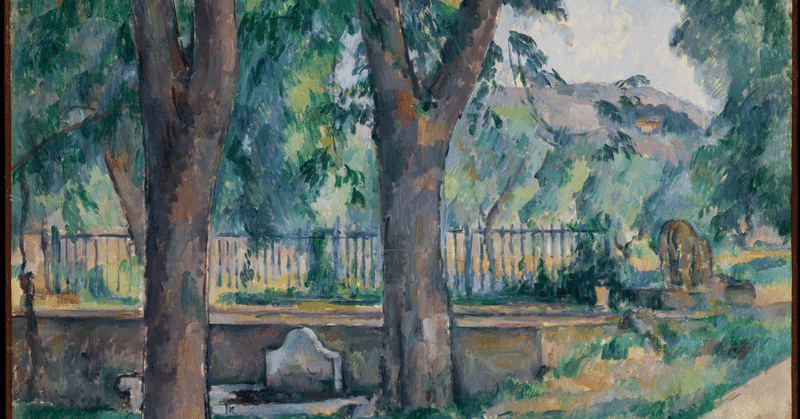#芭蕉
それは見えていないのかもしれない 芥川龍之介の俳句をどう読むか24
金柑は葉越しに高し今朝の霜
この句は殆ど鑑賞されていないようだ。「葉越しに高し今朝の霜」が解らないのではないか。
鶴の巣も見らるゝ花の葉こし哉
という芭蕉の句がある。鶴の巣は四月五月、桜は三月四月。金柑の実は秋の季語、花は夏の季語となる。また白桃の罠が仕掛けられている?
いや、霜があるのだから花はなかろう。
この金柑は実で良い。
金柑は葉越しに高し今朝の霜
……の句には
虚子の句の前につけたか 芥川龍之介の俳句をどう読むか⑪
竹林や夜寒のみちの右ひだり
竹林や夜寒の路の右左
この表記も見られるが、昭和四十六年筑摩書房版の『芥川龍之介全集』では「竹林や夜寒のみちの右ひだり」である。
この句もやはり私は高浜虚子の、
冬田氷る東海道の右左
との連想で見てゆきたいと考えている。
凩や竹にかくれて靜まりぬ 芭蕉
これではあるまい。
ただの「右左」の文字列は、他にも鳴雪の、
鹿の子や巫女が袂の右左
芥川龍之介の『芭蕉雑記』に思うこと⑥ それってあなたの感想ですよね
ちなみに蕪村の春雨の歌は芥川が認めたもののほかにもある。
ここで芥川は「春雨」で蕪村をやっつけようとする。これはさすがに狡いのではなかろうか。「梅」ほどではないにせよ、「春雨」は散々和歌や俳句でこすられ続けてきた言葉なので、時代の古いものほどのびのびと詠めている。今まさに「春雨」で秀句が詠めるかというと、これはなかなか難しいのではなかろうか。
やってみると少し距離を取り過ぎて、つま
芥川龍之介の『芭蕉雑記』に思うこと④ 芥川は『猿蓑』を読んでいなかった
こんなタイトルを見てまさかねと思った人、納得したら本買ってね。
俗語?
芥川が書いているからみんな素晴らしいというわけにはいかない。そこは飽くまで是々非々で行かなくてはならないと思っている。そういう意識を常に忘れてはいけないということだ。
「私雨」👆
なるほど芥川作品や漱石作品を論って天才を褒めるのは手数がかからないことだ。しかし、
こうして天才にケチをつけるのは容易なこと
芥川龍之介の『芭蕉雑記』に思うこと① プラトンなしでソクラテスは有名になれたか?
そもそも何故門人が集まったのか?
改めてそう言われてみると、芭蕉の元に優れた門人が集まってきたのはどうしてだろうと不思議になる。その答えはおそらく「評判を聞いて」「紹介で」という「人づて」というところに落ち着くしかないのだろうが、そもそもどのようにしてそのネットワークが拵えられたのかが不思議である。
夏目漱石の場合は元教え子が最初に集まり、その後著作を読んだ芥川などがやってくる。この著作が