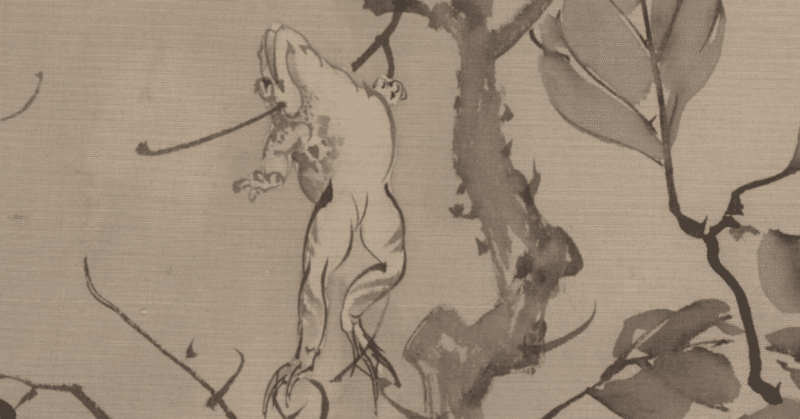
簾戸や雨にまします蝸牛 芥川龍之介の俳句をどう読むか57
簀むし子や雨にもねまる蝸牛
この句に冠しては独特の解釈をしている人がいる。簾虫籠を「簀むし子」に転じていることから、
簀で透けた庭の外にいる子供を部屋の中から見ていて、雨の中でも座り込んでカタツムリ を見ている子供の様子を表していると思います。
……という解釈だ。なかなか面白い解釈だがひとまず置こう。

室生犀星が書いていることが確かならば「簀むし子」は金沢方言で「簾戸」、「ねまる」は「ねている」ではなく、「坐る」という意味になるからだ。
ねま・る 〔自四〕 (語源はネバ(粘)ルか。一説にニラ(睨)ムとも)
①すわる。うずくまる。雑兵物語「細腹が痛んで―・つたれば」
②黙ってすわっている。とじこもる。史記抄「―・りて物を思案する」
③くつろいで居る。楽にすわる。奥の細道「涼しさをわが宿にして―・る也」
④ひれ伏す。平伏する。浄瑠璃、心中宵庚申「軍右衛門が―・り申して手をつかへる」
⑤寝る。臥ふす。和訓栞「東奥にて寝るをも―・ると云ふ」
⑥腐る。日葡辞書「ウヲ・モチ・メシナドガネマル」
ねま・る (動ラ四)
(1)だまってすわる。「―・りて物を思案する/史記抄 2」
(2)くつろいでいる。「涼しさをわが宿にして―・るなり/奥の細道」 (3)寝る。眠る。「もう―・らまいか,女中,寝所をたのみます/滑稽本・膝栗毛 5」
(4)平伏する。膝(ヒザ)をつく。「軍左衛門が―・り申して手をつかへるこりやさ/浄瑠璃・宵庚申(上)」
(5)ねばる。また,食物がくさる。「魚・餅・飯ナドガ―・ル/日葡」
ねま・る [動ラ四]
(1)とじこもる。また、黙座する。「―・りて物を思案することが大人の志のやうなぞ」〈史記抄・周本紀〉
(2)すわる。また、ひれ伏す。「これ軍右衛門が―・り申して手をつかへる」〈浄・宵庚申〉
(3)くつろいで休む。「お草臥(くたびれ)なら―・るベい」〈松の葉・二〉(4)寝る。臥す。「もう―・らまいか」〈滑・膝栗毛・五〉
(5)食べ物が腐る。〈日葡〉
新辞林には項目なし。
ねま・る
《自動詞・ラ行四段活用》活用形
❶うずくまる。ひれふす。
《心中宵庚申・浄瑠・近松》 「軍右衛門(ク゛ンモン)がねまり申して手をつかへる」
《訳》
軍右衛門がひれふし申し上げて手をつく。
❷くつろいで楽な姿勢になる。寝そべる。
《奥の細道・尾花沢》 「涼しさをわが宿にしてねまるなり―芭蕉」
《訳》
涼しさを私の宿のものとし、我が家にいるようにくつろぐことだ。
ねま・る
〔自ラ四〕
1 (「ねめる(睨)」に対する自動詞)にらむさまである。*名語記‐七「人の意趣ありげにて、ことばをもとがめ、気色をもかへ、ねまる如何」
2 (にらみつけている結果、ぶあいそうなさまをするところから)黙座する。とじこもる。蟄居する。*史記抄‐二「ねまりて物を思案すること」
3 すわる。しゃがむ。*仮・東海道名所記‐三「山かがちのねまり申たるよな大飯」
4 くつろいで休む。そこにとどまる。逗留する。*俳・奥の細道「凉しさを我宿にしてねまる也」
5 寝る。*滑・膝栗毛‐五「もふねまらまいか。女中々々。ねどころをたのみます」
6 食物が腐る。*日葡辞書「メシナドガ nemaru(ネマル)」
ねま・る
《自動詞四段活用》〔古語〕
すわる。うずくまる。
寝る。寝そべる。くつろぐ。用例(泉鏡花)
平伏する。ひれ伏す。
明鏡、新明解は項目なし。それぞれ微妙に解釈の違いがあり面白い。実はこの「ねまる」に関しては例によって芥川が多義性に遊んだ可能性があり、どちらともどちらでないとも決めがたいところをわざと持って来たものと考えられるのだ。


涼しさをわが宿にしてねまるなり 芭蕉
この句の解釈に関して
凉さを我宿にして寐まる也 芭蕉
wikisourceは「寐まる」という表記を用いている。岩波書店の芭蕉全集は前者の表現である。「ねまる」の表記の方が圧倒的に多い。


この表記に対しても「寛ぎて起座す」という鑑賞がある。
き‐ざ【起坐・起座】
①起きあがって、すわること。起きなおること。
②座を立つこと。
○涼しさを我宿にしてねまる也-「ねまる」橫になる。つくばふ。餘りに凉しく氣持がよいので、まるで自分の家でもあるかのやうに氣まゝに橫になつたりしてゐることだとの意。
受験奥の細道・鶉衣 西山隆二 著玄鹿洞書院 1936年
さあ、お受験問題になった。大変なことだ。しかもこちらは「橫になつたりしてゐる」という解釈だ。

按ずるにねまるといふ詞に二義あり北國のねまるは他國にて居ると云詞に當るべし又關東にて卑俗のことはに寢はらばふ事を打ねまると云此句意を考るに翁の北國の詞を聞玉ふは此行脚の時初なる故に羽州のねまるを關東のねまると同樣に思ひあやまり給ふにや猶此句に其角の評あり

「ねまる」は此の地方の方言で「坐る」といふ意味だが、語感だけをとつて芭蕉は「寝そべる」といふ意にしたものと思ふ。
実は『奥の細道』で詠まれたそのお隣の「かひやがした」の「かひや」が今を持ってして万葉集注解で語義の定まらない言葉で、芭蕉もそこをさらに「かはず」ではなく「ひき」を持ち出してさらに訳の分からないことにしてしまっているのだが、そのことも全く関係のない話だとも思えないのである。
俊成-定家ラインの権威の確立は『六百番歌合』によるものだ。判者俊成の批評は鋭く、定家の歌も華麗だ。ただしその判に、噛みついた阿闍梨がいた。文学が権威主義に陥ることに一人抗い、消えていった男の陳状を再考すれば、今までとは違った俊成が見えてくる。いまだ続いている文学界の権威主義を解き解すために、近代文学2.0はここまでさかのぼらなくてはならない。
結局根無し草になるまいとして古歌にちなんで、語句の多義性の前に頓珍漢になった歌を芭蕉は揶揄ったのではないか、と私は解釈している。
つまりひねくれ坊主我鬼の二百年前にひねくれ坊主芭蕉がいて、解釈を迷わせる句で遊んでいたわけである。
ならば芥川が遊ばない手はなかろう。








石原や照りつけらるゝ蝸牛 一茶
宵越しの茶水明かりや蝸牛
朝やけがよろこばしいか蝸牛
ぬれたらぬ艸の月よや蝸牛
蝸牛気任せにせよ艸の家
蝸牛蝶ハいきせきさハぐ也
蝸牛我と来て住め初時雨
蕣ハはや風の吹かたつぶり
鶯と留守をしておれ蝸牛
蝸牛角ふりわけよ須磨明石 芭蕉
五月雨や小牛の角の蝸牛 子規
蝸牛の喧嘩見に出ん五月雨
蝸牛の角のぶ頃や五月雨
雨水のしのぶつたふやかたつぶり
一日の旅路しるきや蝸牛
蝸牛と風雅の主や竹の垣
生れるといはぬ身を恥よ蝸牛
大釜の底をはひけり蝸牛
此頃は居らなくなりぬ蝸牛
声あらは何となくらん蝸牛
ちゞまれば広き天地ぞ蝸牛
蝸牛を風雅の主や竹の杓
蝸牛明家の錠のくさりけり
傾城のうらやまれけり蝸牛
五月雨や小牛の角に蝸牛
蝸牛の角のさきなり安芸愛媛
石の上に重なりあふて蝸牛
蝸牛それさへ文字はならひけり
殻ともに踏みつぶされて蝸牛
其角の長さくらべん蝸牛
竹椽や嵐のあとの蝸牛
朝鮮は蝸牛程の大きさよ
蝸牛の角ふりわけよ幾ところ
蝸牛の隣の喧嘩のぞきける
蝸牛や寺の屋陰の大楷子
ぬらくらと蝸牛の文字の覚束な
蝸牛や雨雲さそふ角のさき
蝸牛やおほつかなくもにしり書
我画いて雲に乗り去る蝸牛
長明の車が来たぞ蝸牛
蝸牛の頭もたけしにも似たり
こうして先人たちの句を眺めているうちに、どうやったら蝸牛が座っていることになり、どうやったら蝸牛が寝そべっていることになるのかがわからなくなる。
そもそも蝸牛は坐ったり、寝そべったりしないものなのではなかろうか。そこを芭蕉が遊んだ怪しい言葉でもってわざと解らないように詠んだところに芥川の遊びがある。
金沢方言の句としては外に六句ほどがあり、「簀むし子」に関しては素直に金沢方言を入れたと考えて良いが「ねまる」に関しては、芭蕉や鏡花の影響も含めて広くとらえる必要があるだろう。
まずこの言葉に二つ以上の意味があり、金沢方言と云う以前に古語として「坐る」の意味があることまでは芥川の教養の範囲であろう。さらに芭蕉の句を多く諳んじている芥川が、
涼しさをわが宿にしてねまるなり
……という句を知っていた可能性は高い。
いずれにせよ蝸牛に対して「ねまる」という言葉を用いたことは芥川らしい悪戯であり機智である。
簀むし子や雨にもねまる蝸牛
この句は、
簾戸や雨にもねまる蝸牛
簾戸や雨にもこやる蝸牛
簾戸や雨についゐる蝸牛
いずれでもあり、また
簾戸や雨にさぶらふ蝸牛
簾戸や雨にさもらふ蝸牛
簾戸や雨にいまさふ蝸牛
簾戸や雨におはさふ蝸牛
簾戸や雨にゐたまふ蝸牛
なのであろう。
【余談】
滝の落ち口のお亭の前を通つたときに、この春芥川君が来て泊つたお亭を覗いてみたが、秋深く松葉が散らばり二三本の篠竹の青い色を見られる格子戸に、人のけはひすらしなかつた。亭亭たる松の梢にある飼箱に群れる小鳥の声がするばかりであつた。このお亭にこのごろ泊つたら寒からうと思つた。
春で良かった。そしてその時、あれを見たのか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
