
代表コラム8. みんなで地球に貢献!再配達防止運動
こんばんは。
今日は少しロボットや自動化とは離れ、僕ら一人一人ができる地球への貢献について語りたいと思います。
近年、ネットショッピングの発達やコロナウイルスの影響により宅配便が増えている。これは国土交通省が発表している資料だが、令和2年度の宅配便取扱個数は48億3,647万個であり、このうち約99%がトラックによる運送である。

その増加している宅配便において近年問題になっているのが「再配達」問題である。
再配達とは、再配達とは、不在時などによって宅配荷物を受け取れなかった場合に用いられる制度のことで、指定日時に不在の場合は一旦荷物を持ち帰って後日再度配送を行うこと。
この再配達は何が問題かというと、
●CO2増加
●ドライバーへの負担
などが挙げられます。
ドライバーへの負担については、とある会社が配送ドライバーにアンケート調査を行っており、1回でも辛いが全体の2割弱、2回以上で約半数が「辛い」と答えています。

2017年時では宅配便の個数のうち約2割が再配達となっており、下記にグラフを示しているがその理由の2割は「配達されることを知らなかった」という理由になっていた。

「知らなかった」という理由だけでドライバーがその他配送をして再度届けるために戻ってくる、という無駄が発生している、ということになる。
この2割がどの程度の労働力に該当するかというと、年間9万人のドライバーの労働力に該当するそうです。

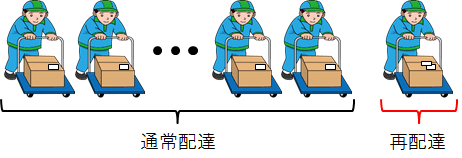
これを走行距離にすると全体の約25%が再配達のための走行距離であり、労働時間に換算すると累計1.8億時間、無駄なCO2排出量としては約42万トン。
これだけ無駄なことにドライバーの時間も無駄なCO2も排出している、という状況にある。
なかなか数字が実態感としてイメージが湧かないが、国土交通省では国土交通省では面白い試算をしています。

42万トンを吸収する木と面積ではどの程度必要か、ということを真面目に試算しており、山手線内側2.5個分と同じ面積にスギを1億7400万本植えるのと同等のCO2排出量ということです。
なんとなく、「すごーく」たくさんのスギの木を「ひろーい」範囲に埋めなければ回収できないほどのCO2を排出してしまっている、ことを理解していただけたと思います。
一人一人が意識をして再配達を無くせば減らせるCO2なのに、誰もがこの「意識」をせずに無駄なCO2を産んでしまっているのが再配達の現状なんです。
無駄なCO2を産むとどうなるか。
一つは絶滅危惧種の動物が増えます。例えばウミガメ。

WWFによると、
こちらは産卵する砂の温度で性別が決まるそうです。温度が高ければメスが生まれ、温度が低い場所ではオスが生まれます。このため、温暖化によりわずかでも気温が上がると、メスばかりが増え、オスとメスのバランスが狂って、繁殖ができなくなる恐れがあります。また、温暖化の主因である二酸化炭素(CO2)の大気中の濃度の上昇は、海に溶け込むCO2を増やして、海水を酸性化させ、アオウミガメの食物である海草をはじめ海中の生態系に大きな影響を及ぼすと考えられているほか、氷河の融解による塩分濃度の低下なども生じるといわれており、こうした問題が、ウミガメの生活史と海の環境に、どのような影響を及ぼすことになるのかが懸念されています。
僕らが何気なく行っている行動が、気づかないところで彼らの命を奪っています。そう考えると再配達なんて必要ないものを排除していくことが大切であると断言できますね。
この再配達、意外と個人ができることが多く、
1.時間帯指定の活用
2.各事業者の提供しているメール、アプリなどを使って配送時間連絡などをやり取りする
3.コンビニや駅の宅配ロッカーなどの自宅以外の受け取り方法活用
これらに気をつけるだけで大きく改善されると思います。
5件に1件が再配達になっている今、一人一人ができる裁量が大きいため改善されるかどうかも我々消費者に委ねられています。
再配達については有料化がいずれなされると思います。ただ我々消費者ができることは「再配達をしない」という目の前のできる小さなことから始めていけばいいんです。
何ができる、何ができないの能力やスキル、投下時間などの制約に影響されることなくいますぐにできる地球貢献が「再配達防止」です。
自分が今目の前で行っていることの意味や影響を考えると、目の前の行動の良し悪しが問える、ということが今回の再配達で私自身よくわかりました。
皆さんで一緒に地球温暖化防止に向けて、活動していきませんか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
