
今年読んだ文学ランキング2019
私たちが本を読むのは、知らないことを知るためではない。私たちは、私たちが知っていることを知っていると知るために、知らない本から知っているものを読み取るのだ。
(樋口恭介 ブンゲイファイトクラブ決勝ジャッジ評より)
まず今年の下半期に読んだ文学作品で特によかったものを、国内はベスト5・海外はベスト10形式で順に紹介する。
【2019年下半期 日本文学ベスト5】
第5位 「林冴花は宗教が苦手」 金子玲介

今年の下半期にインターネットの文学界隈を賑わせたイベントといえば「ブンゲイファイトクラブ」である。原稿用紙6枚という制限の中で小説や詩歌などの文芸がジャンルを問わず競い合い、ジャッジによる優劣をつけられ、ジャッジもまた優劣をつけられるという斬新な形式の祭典は、noteやTwitterで大いに盛り上がった。私もいち観戦者として1回戦から決勝のジャッジまで存分に楽しませてもらった。気に入った作品は数多くあれど「この人の作品をもっと読んでみたい」と最も強く思ったのが、ベスト4まで勝ち抜いた金子玲介氏だった。
1回戦の「アボカド」、2回戦の「あなたと犬と」、そして準決勝の「小説教室」これら全ての金子作品から、散文における会話文と地の文それぞれの有効性や関係性について批評的に向き合っていることが痛いほどに伝わってきた。このオブセッションは、ギャディス『JR』を読んで以来ずっと私の頭の片隅にも住み着いている。そのため、金子玲介という1人の作家のこれからについて、激しい興味を持たざるを得なかった。
そこで現在読むことのできる他の金子作品は、Kindle限定作品集『朔月2019』に収録されている「林冴花は宗教が苦手」だけだと知り、すぐに購入した。本作は第53回文藝賞の候補になっている。(その時の受賞作は「1R1分34秒」で芥川賞を獲った町屋良平の「青が破れる」である)
「林冴花は宗教が苦手」の特徴は、なんと言っても女子大生アイドル林冴花による一人称の地の文と、鉤括弧の会話文が細かくリズムを刻む文体にある。
「なんだろ」山村が重そうに頭を起こした。「まあ言いたいことはいろいろあるんだけど、」私を見た。私は山村の目の表面でこわばっていた。何を言うかを、選ぶ間が置かれた。「まず、」何を言うんだろう。何を。「もったいないだろ」山村は言った。「お前、天才なのに」私を上から下に視線で撫でた。「お前みたいなアイドル他いないよ」そうだろうか。「千駄木もせっかく売れてきてんのに」私たちは、千駄木55という名前のアイドルグループだ。「お前なら天下とれるって俺ずっと言ってるじゃん」それは、知ってる。言われた。再三。「もったいないよ」そうかもしれない。
小説における「地の文」とはいったい何だろうか。「会話文」が会話文として鉤括弧でくくられる必然性や、くくられることによりテクスト全体に及ぼす影響はいったいどれくらいあるのだろうか。そもそも散文における「言葉」とはどんなものか。なぜ小説は小説たりえるのか。こうした切実な問いに真剣に取り組んでいる若い作家が日本にいることを私は心から嬉しく思う。
第4位 「松ノ枝の記」 円城塔
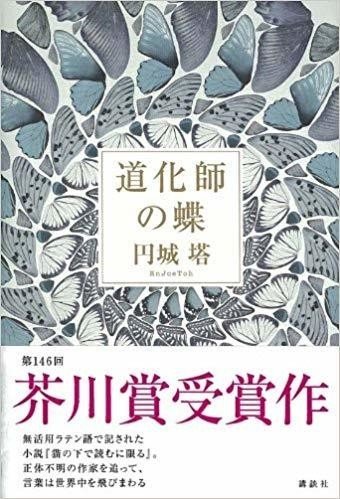
現代の日本の文壇はこの作家の「肯定派」と「否定派」に大きく二分されるとまで言われる円城塔。私は今年の上半期に芥川賞受賞作「道化師の蝶」で初めて彼の小説に触れた。率直に言ってとにかく難しかった。わずか数行を読むのに何度も何度も文を辿り直して何分も費やした。ただ嫌になる難解さではなく、単に自分の読解力が追いついていないだけで、この文章の奥には芳醇な文学的世界が広がっていることが垣間見える類の難解さだったため、他の作品も読んでみようという気になった。
そこで下半期に読んだのが、『道化師の蝶』に併録されていた「松ノ枝の記」である。この短編もやはり難解だった。しかし、表題作よりはその面白さに肉薄できた感がある。
三冊目で箍は緩んだ。彼が翻訳したのは、わたしの訳した『松ノ枝の記』であったから。タイトルを、『A Branch of the Pine Branches』と彼はした。『松ノ枝ノ枝の記』とでもなるだろうか。そこでは松ノ枝家が、松ノ枝ノ枝家へと変貌していた。自作の翻訳を翻訳しかえし、そこでは元々分家たちのものだったお話が、ひとつの分家のお話へと重ね描かれた。偶然と呼ぶか必然としておくべきか、わたしも同時にひっそりと、彼による一冊目の翻訳を翻訳し返す作業を進めていたのは言うまでもない。
お互いがお互いの小説を翻訳し合い、それをまた翻訳し合う。翻訳もひとつの創作であるという信念は、海外文学を読んでいる身としては常に立ち返るべき公理のようなものだ。本作は、この公理を真顔のままギャグテイストで使用することに始まり、途中幾度も物語はその位相ごとうねり、最終的には人類の萌芽と未来に想いを馳せるスケールの広がりを見せる。
円城塔は「書くこと」自体に執着し、実際に書くという行為でしか追求できないやり方でそのテーマにアプローチしているように思える。こうしたポストモダン風味の作風に衒学趣味が重なれば、出来上がる小説はふつう論理性や抽象性が先立ち、鼻について読めたものではないことが多いが、円城塔はそれでも詩的な言語遊戯としての文学性を諦めずに手放していない。そこが好きだ。
第3位 『優雅で感傷的な日本野球』 高橋源一郎
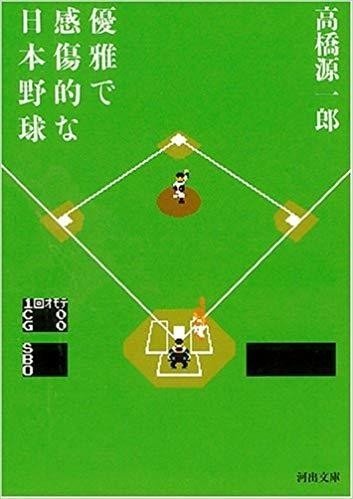
日本におけるポストモダン文学の旗手といえば高橋源一郎だろう。デビュー作の『さようなら、ギャングたち』を読んだのがたしか昨年で、現代詩の感性をそのまま小説に持ち込んだとも言える内容には、強く心を揺さぶられる部分もあったとはいえ、どこか置いてけぼりをくらったような、もどかしい読後感を抱いた。
それに比べて本書は、明確な「笑いどころ」がずっと分かりやすく、素直に楽しめた。『さようなら、ギャングたち』が私の感性の十歩も二十歩も先を歩いていたとすれば、『優雅で感傷的な日本野球』は少し手を伸ばせばその肩に触れることができ、振り向いてその顔を見せてさえくれるほどに「親切」だったように思う。
また暫く歩くと、ベッドがありその上では恐ろしいほど豊満な肉体をもった美女が紐付きのパンティとピンクのキャミソールを着てぼくたちを誘惑しようとしていました。「どっちを誘っているんだい?」とぼくは尋ねました。すると女は「どっちでも。何なら、二人一緒でも」と答えました。どうやら、こいつも複雑なことを考えているにちがいありません。そこでぼくたちは「日本野球」することにしました。
息子よ。それはまた突然なことだな。何かをしたということなのか。よくわからんぞ、わたしには。
「何かした」なんて言ってません。ぼくたちは「日本野球」しただけです。そしてヤクルト・スワローズが優勝しました。要するに、ぼくたちは交換したのです。複雑なものを単純なものに。
相変わらず人を食ったような「ストーリー?何それおいしいの?」的展開はそのままに、デビュー作よりずっとエンタメ性が増した楽しい小説である。
第2位 『夏物語』 川上未映子

私はこの小説をここで紹介してよいものか、いまだに自信がない。というのも、私はこの本を「ものすごい傑作」だと思うと同時に「どうしようもない駄作」だとも思うからである。このアンビバレンスについて少し書いてみたい。
私が読んで「良かった」「面白かった」と思う本の基準。それは到底いくつかに絞って言語化できるようなものではないが、一つ挙げるとすれば「読書に没頭できたか」である。早く読み切れた本が必ずしも好きな本ではない。しかし、読み始めたら止まらなくなり、他のことを全て後回しにして作品世界に浸りたくなるほどの絶大な引力を持つ文学作品には、私はこれまでも最高の思い入れを感じてきた。『ムーン・パレス』然り『わたしを離さないで』然り『夜明け前のセレスティーノ』然り『悪童日記』然り……。
この観点は、私にとって文学とは何よりもまず「体験」である、という信念と深く結びついている。つまり、私が本を読んで「面白かった」「つまらなかった」と評価しているのは、その「作品」自体ではなく、ほんとうは「その本を私が読んだ」という「読書体験」自体の良し悪しを対象としている。その体験は私固有のものであり、他者には、そしてその体験から時間的に離れた今の私自身にも、決して侵害できない聖域である。このような考え方は「芸術作品は鑑賞者がいてはじめて完成する」とか「読まれている間にしかその作品は存在しない」などの、ありふれた芸術批評観とさほど違いはないと思う。
閑話休題。私は、これまでの「人生の一冊」たちと同様に、この『夏物語』に没頭し、朝から晩まで図書館に籠もって500ページ強を2日で読み切った。この体験ができたのは、その時期の自分の精神状態や置かれた境遇も多分に影響しているだろうが、川上氏の紡ぐ文章が素晴らしく魅力的であるためだというのも間違いない。緑子も夏子も巻子もみんな愛おしく、明らかに感動させにきている「いかにも」なシーンの全てで泣いた。「いかにも」を陳腐にするか否かは結局のところ書き手の技術の問題であることがよくわかる。あの観覧車の名場面の影響で、夏に大阪に行ったとき、海遊館の観覧車にひとりで乗った。それほど私にとって大切な物語になった。
ではなにがダメなのか。それは本作のラストである。そもそも私がこの本に興味を持ったのは、エモそうな題名に惹かれたのもあるが、反出生主義を扱っているという噂を聞いたからだ。本書の終盤で、善百合子という人物の口からその主旨が夏子へ語られる。この導入まではなにも文句はない。しかし、百合子に反論できなかった夏子はそれでもある選択をして、幕を閉じる。この結末を私は残念に思う。しかし同時に、この結末を残念に思ってしまう自分を、もっと残念に思う。
小説とはなんだろうか。作者がある「伝えたいこと」を物語の形に仕立て上げたものが小説なのだろうか。文学を読み始めたここ2,3年で私の小説観は大きく変わった。「正しい倫理」とか「メッセージ性」とか、そういうお誂え向きのお題目からかけ離れた場所で自由に遊んでいる作品こそが素晴らしい、という方向に。
『夏物語』は、作品内に非常に強度と毒性のある思想をわざわざ持ち込んだ。持ち込んでおいて、それに対する論理的な応答は一切せずに、強引に物語を終わらせた。ある意味、極めて「文学的」なひとつの回答なのかもしれない。しかし私はこれを論理や倫理や正しさへの侮辱だと受け取ってしまった。文学において「正しさ」なんて唾棄すべきだと常日頃考えているにも関わらず、である。
文学は哲学や倫理学の論文ではないから、その中である思想を紹介したところで、それを論理的に明解に扱う義務も必要もない。だから、やっぱり『夏物語』はこの着地点で正解なのかもしれない。それでも、私にとって文学とは「体験」だから、2日目の夜、図書館でこれを読み終えたときに感じた得も言われぬ落胆こそが、この作品への私の評価である。
以上のような経緯から、私は本書に対して「傑作だし駄作でもある」という矛盾した感想を抱いており、noteにこうして書くこと自体の正しさについて、いまだに疑問と不安が拭えていない。このような複雑な感情を芽生えさせてくれたという点において非常に評価することはできるかもしれないが、そうやってメタに捉えてばかりいるのはただの逃げだろう。
第1位 「面影と連れて(うむかじとぅちりてぃ)」目取真俊
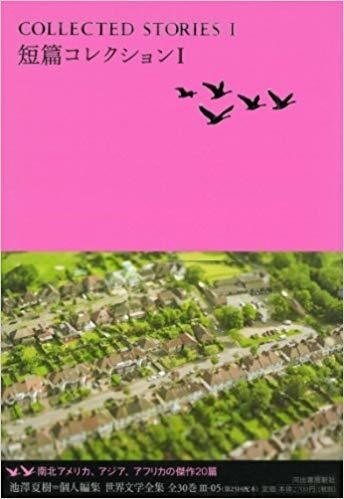
合格発表の時間を間違えてしまい数時間待つ羽目になったため、初めて入る図書館で池澤夏樹編『短篇コレクションⅠ』をつまみ読みした。まず読んだのがオクタビオ・パス「波との生活」で、ノーベル賞詩人であることも納得の詩的描写に思わず唸った。次に選んだのが、目取真俊の「面影と連れて」である("うむかじとぅちりてぃ"と発音する)。半年前、同作者の「水滴」を1位に挙げて絶賛したばかりだが、この「面影と連れて」はそれ以上に刺さった。ちょっと称賛の言葉が出てこないほど素晴らしく、結果として鼻水をダラダラに垂らした状態で合格発表を見に行った。
おばあの語り。この短篇の魅力はこれに尽きる。『百年の孤独』などにおけるガルシア=マルケスの語りと比べてもなんら遜色がないと個人的には思う。日本文学というよりは世界文学といった趣きなので、国内で評価されなくてもいいから海外でもっと評価されるべきだと思う。私は日本人のノーベル文学賞候補に、村上春樹でも多和田葉子でもなく、目取真俊を推す。この地を離れるあと数ヶ月の間に、この作家の著作をなるべく読み切りたい(が、おそらく無理だろう)。
【2019年下半期 海外文学ベスト10】
第10位 『空の青み』 ジョルジュ・バタイユ
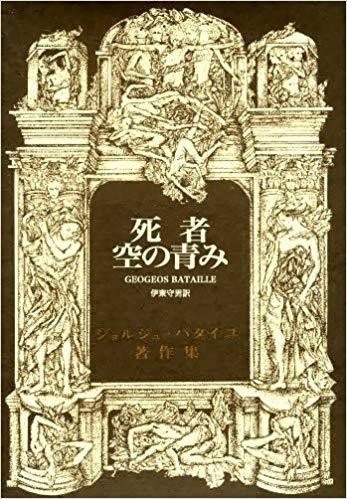
「病気でなかったら、来なかったわ。今は私、病気。これからは私たち幸福になれるわ。とうとう病気なんだから」
エロシティズムの大家である哲学者・思想家バタイユは小説も幾つか書いている。デビュー作『眼球譚』が有名で、これは確かにバタイユ特有の性的倒錯が全開になっている、誠にほほえましい「学校で借りれるエロ本」だ。
一方、『空の青み』は官能性が前面に出ることはなく、とにかく陰鬱で退廃的な恋愛小説である。この表現はどちらのファンからも「分かってない」と言われそうだが、「ちょっと官能的にしたフランス版太宰治」みたいな印象を受けた。スタイリッシュな絶望、とでも言おうか。ものすごく暗いのに、それがなぜか格好良く見えて支持されるところが似ている。
これを手にとったのは、「Riche Amateur」というブログの「文学によって人生を台なしにしたいのなら読むべき30冊の本」リストに入っていたためだ。
このブログで引用されていた、本作の印象的な一文がある。
「彼女の舌が私の舌を求めて来たとき、あまりの美しさに私はもう生きていたくなかった」
なかなかロマンチックな台詞である。しかし実際に作品を読んでみて思ったのは、この一文へと至る文章の流れこそがめちゃくちゃ素晴らしい、ということだ。この一文が目に飛び込んだとき、完璧さにため息が漏れた。もちろんここではそれを丸ごと引用はしないので、気になる人はぜひ読んでみてほしい。
第9位 『フラニーとゾーイー』 J.D.サリンジャー
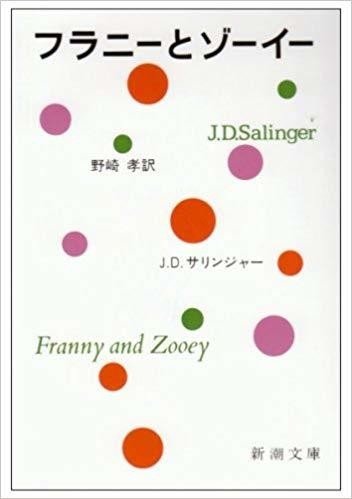
でもいちばんいけないことはね、自分で自分がどんなに退屈な存在かってことを知ってることなのよ。
半年ごとに書いているこのランキングに、再読本が入るのはおそらく初めてだ。初めて読んだのは2年前、村上訳でだった。そのときの感想は「好きじゃない」。なぜなら「ズーイー」(村上訳では「ゾーイ」)における風呂場でのズーイーと母親の延々と続く会話に心底うんざりしたためだ。お互いにもう終わりにしようと言っているのになかなか終わらない。お前らいい加減にしろ!と本を投げそうになった。
再読とはなんて実り多い行為だろう。「だいたいのあらすじを知っている」こと自体が一文一文へと向ける視線の解像度を上げ、じっくりと細部を味わうことを可能にする。初読時の鬼門となった風呂場でのやり取りも、いずれ終わるということが保証されているので、さほどムカつかずに落ち着いて読むことができた。初読時に「終わりが見えない」のは、良くも悪くも、といったところだろうか。
再読時の冷静な目で読んだ端的な感想は、「文章がめちゃくちゃ上手い」ということだ。かのサリンジャー相手に何を今更、ということかもしれないが、これまでサリンジャーには圧倒的なセンスでぶん殴る、天才タイプの文章を書くイメージがあった。だが今回読んで思ったのは、むしろ地に足のついた秀才というか「お手本のような文章」という形容がしっくりくる、実に標準的に上手い文章を書くということだ。
サリンジャーは会話の名手であるとよく言われ、それはもちろん間違っていないが、会話文だけでなく、その合間を埋めるちょっとした仕草や情景の描写の質もほれぼれするくらい高い。本作の書評では後半の「ゾーイー」がよく言及されるが、細かな描写を注意深く読む限り「フラニー」単体でも十分に傑作の短篇だと思う。文章の過不足のなさが本当に素晴らしいのだ。最小限の描写で、その場の雰囲気や人物の関係性を最大限に表現している。やはりサリンジャーは短篇でこそ真価を発揮する。
そもそも再読しようと思った理由は、グラース兄妹の末っ子フラニーが本作で抱えている「悩み」が自分のそれと近い気がして、解決に至るなんらかの糸口が見出だせないかと思ったからである。実益を期待して文学作品を読むなど、実に浅ましい行為だ。(しかし私は実際に浅ましい人間なので気にしない)
そここそわたしがいちばん悩んでる問題じゃありませんか。自分のほしがるものを選り好みするということ──今の場合だと、お金とか威信とか名声とかそういったものをほしがらないで、心の目を開くこと、心の平和を掴むことをほしがってる──そうだからといって、わたしがほかのみんなのように利己的でも自分本位でもないということにはならないわ。むしろわたしはそういう点が人一倍強いのよ!
結局、1冊の本を読むだけでそう簡単に悩みが氷解するはずもなく、当初の目的はかすり気味の空振りに終わったわけだが、それよりこの作品自体への評価がグンと上がったことが何よりの収穫だった。「えっ、もう終わり?」と率直に思えたのはなんだか感慨深い。再読の醍醐味を堪能した。
野崎訳はやや古めかしい言い回しもあるが、そんなに気にならなかった。「お手本のよう」だと思ったのは翻訳によるところも大きいかもしれない。村上訳が悪いわけではないが、思うにサリンジャーと村上春樹の文章は「相性が良すぎる」のではないか。彼がサリンジャーから受けた文体面への影響は計り知れないことから当然だが、その相性の良さというか、方向性の一致によって、もともとサリンジャーの文章にあった特有の「くさみ」がさらに先鋭化している可能性はある。と言っても読んだのは何年も前なので、以上のことは全て根拠のない妄想である。興味があれば読み比べをしてみてほしい。
第8位 『ある島の可能性』 ミシェル・ウエルベック

僕にだってなにかしらの「尊厳」はある(ただしこれまでの人生で挙げられるような例はない)。
初めて読んだウエルベック作品『素粒子』の感想をnoteに書いたのがちょうど2年前だから感慨深い。その2017年の海外文学ベスト10記事はなぜか「海外文学」や「世界文学」でGoogle検索すると1ページ目に出てくるため、未だにコンスタントに訪問者がいる。文学にかぶれて1年目の若造が腕をふるって書き上げた黒歴史が全世界に公開され続けていると思うと誠に恐ろしいものである。
2年前の自分が『素粒子』についてどんな感想を書いていたのか確認したところ、「あまり読みやすい話とは言えない」とのことだ。『素粒子』と『ある島の可能性』はウエルベック作品のなかでもSF系として同じ系統に連なるため、両者の比較はある程度は有意義だろう。今作を読み始めてまず感じたのは、文章の読みやすさだ。言ってることが2年前と正反対である。これは作品ごとの文体の違いというよりは、私の文学経験値が少しは上がったということだろう。
これまで、ウエルベックが売れているのはスキャンダラスな作風の話題性ゆえだと少し思っていた。しかし、人気作家となるにはまず多くの人に読まれないことには始まらない。「読みやすい」というのは(ごく一部の前衛作家を除けば)売れっ子作家の大前提である、という当たり前のことを今更ながら実感したのであった。決して読者を突き放さない。媚びることもせず、その文章技巧でもって、読者を迎え入れ、包み込むのである。
読みやすいとは、内容が薄いことではない。ウエルベックの場合、重厚な思想や知識が背景にあって、しばしば前面にも出てきて、その上でなお読みやすいのだ。この一見地味な離れ業を支えているのは、ウィットと皮肉・ユーモアに富んだ言い回しにあると見た。やはり文学において「笑い」は本質的に重要だと思う。それは主人公ダニエルの職業がコメディアンであることとも決して無関係ではないだろう。
本作には近未来SF要素が挟まれるが、個人的にはそれよりもダニエル1の人生を描いた現代パートが素晴らしかった。とにかく「哀しい」のである。"老い"という、努力ではどうにもならない部分で自分の全てを否定される哀しさ。それが個人の問題というよりは、資本主義を動力とする現代社会のシステム自体に内在する問題であることがいっとう哀しい。個人を通して社会を描くという、実に文学の王道をウエルベックはやりきっている。
こんなにもストレートに哀しさを描いてこられると、こちらも安心しきってその悲恋の物語へと身を委ねられる。まさかウエルベックの小説で涙を流すとは思っていなかった。心の底から哀しみに浸りたいときに重宝する1冊である。
第7位 『エドウィン・マルハウス』 スティーヴン・ミルハウザー

彼は、自分を除いた人類はすべて真面目であると考えているようだった。
アメリカ文学史を塗り替えた傑作小説『まんが』の著者であり、11歳にして悲惨な死を遂げたエドウィン・マルハウス。彼の人生の全てを、幼年期からずっと近くで観察してきた同い年の親友、ジェフリー・カートライトがつぶさに書いた伝記が本書である。
という設定の、スティーヴン・ミルハウザーのデビュー長編。短編の名手として知られるミルハウザーが長編で作家人生のスタートを切っていたというのは意外だ。しかし本作には、その後のミルハウザー作品に現れる、子供・夢・幻想・夜・月・芸術家・狂気などのモチーフが宝石箱のようにぎっしり詰め込まれている。
「僕にとって一番興味のないこと、それは事実なんだ。記録しておきたまえ、ジェフリー君」
「天才児が天才児の伝記を書く」というふざけた設定からして既に"勝っている"と思う。この設定により作品全体がギャグテイストになり、どんなに精緻に言葉を積み上げても「……って小学生にこんなん書けるかい!」とツッコミどころとして捉えることが可能になる。つまり、高尚な文学性を志向すればするほど、一般読者に隙と親近感を与え、作品側から寄り添ってくれる仕掛けになっているのだ。
ミルハウザーは決してアイデア勝負の作家ではない。むしろ同じテーマを何度も変奏して書けることから分かるように、ありふれた題材を卓越した文章能力で傑作に仕立て上げることを得意としている。そのミルハウザーがこんな良い題材を選んだ時点で鬼に金棒である。
伝記作家の果たす役割は、芸術家のそれとほとんど同じくらい、あるいはまったく同じくらい、ことによると比べ物にならないくらい大きいのではないだろうか?なぜなら、芸術家は芸術を生み出すが、伝記作家は、言ってみれば、芸術家そのものを生み出すのだから。つまり、こういうことだ──僕がいなければ、エドウィン、君は果たして存在していただろうか?
この作品には何重にも信頼できなさが敷かれている。エドウィンは実は天才児でもなんでもなく、ジェフリーによってそう仕立て上げられた「普通の男の子」に過ぎないとも考えられるし、エドウィンをジェフリーの想像の産物、イマジナリーフレンドとみなすこともできる。逆にジェフリーこそが架空の存在で、エドウィンが自伝を回りくどく書いている可能性もある。あるいはジェフリーとエドウィンは、現実と架空という合わせ鏡をはさんで向かい合った同一の人物なのではないか……などなど、いくらでも好きに解釈できる。
ただし、こうしてテクストの根底から疑う思考(志向)を突き詰めれば突き詰めるほどに「この伝記はスティーブン・ミルハウザーの"小説"である」という、もっとも外枠あるいは根底に位置する、もっとも確実で明白な要素は後景化し、覆い隠されることになる。
我々が各種の妄想を膨らませているとき、このあまりにも当然の事実を暫定的に忘れている。もちろん、これがフィクションであることを本当に忘れることはあり得ない。だからこそ、この"あり得なさ"──フィクションに対する現実の優越性──に対抗する唯一の手段として、この書物の真の作者は、このような馬鹿げた設定の物語をこしらえたのではないか。
もっとも、上記の感想だって、ひとつのありふれた妄想に過ぎないのだけれど。
こういう読書論はどうだろう。
全ての創作の読み方は「どうせ全部嘘」と「書かれてあることは全部本当」という両極のあいだの何処かに位置付けられる。あるいは、その両極のあいだを彷徨い、もがき続ける行為こそが、「フィクションを読む」ということである。
これは私が適当に思いついたオリジナルの論なのでたいした意味はないが、こんなことを考えさせてくれるほど、本書を読むのは実に楽しい体験だった。
第6位 『リンカーンとさまよえる霊魂たち』 ジョージ・ソーンダース
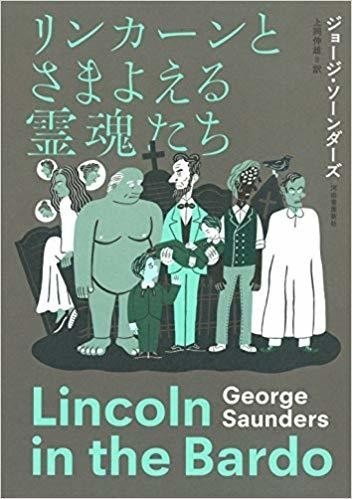
文学に目的を求めるのはお門違いかもしれないが、それでも文学という営みには、それ自身の定義・内実を刻々と更新し開拓していく作用が本質的に内在していると思っている。……客観を装うのはやめてこう言ってもいい。私は文学という地平を押し拡げるような、新たな可能性を見せてくれる作品が好きだ。そのような文学をもっともっと読みたい。そう思っていた矢先、この小説に出会った。これぞ小説の歴史のなかでいまだかつて開拓されていなかった領域の存在を私たちに披露してくれる、新たな挑戦と発想に満ちた文学だった。
本作を一言で表すなら「形式の勝利」だ。これは一種の「発明」と言ってもいい。小説と戯曲のあいだ、地の文と会話文のあいだ、一人称と三人称のあいだ。それらのどちらでもなく、かつどちらでもあるような、ありそうでなかった「語り」の形式をソーンダースは本作で発明した。もうこれだけで、私にとっては、手放しで褒め称えたいし、一昨年のブッカー賞受賞作というのも納得だ。このような作品──本作に似た、ということではなく、これまでのいずれの小説にも似ていない、という意味であるが──にどんどんブッカー賞ほか各種文学賞は与えられるべきだと心から思う。(あと金子玲介氏がもし本書を読んでいなかったらぜひ読んでほしい)
この特殊な形式を実現するにあたって、霊魂たちに語らせた、というのも的を射ているというか、実に慧眼だと思う。新たな地平への第一歩でありながら、ソーンダースはこの形式で叙述される物語としてこれ以上ないくらいふさわしい題材を選び取り、見事に書ききっている。
ここまでべた褒めだが、ちょっと気になった点はストーリーだ。というのも、ちょっとお涙頂戴モノ過ぎやしませんかね…と思ってしまったからだ。たしかにリンカーン親子の悲痛なコミュニケーション(あるいはディスコミュニケーション)は胸に迫る。多種多様な霊魂たちのそれぞれの救済も、戯画的でありながら切実さも伴う。しかしやはり、肝心の物語の核が「息子が死んで悲しむ父親」「その父の姿を霊魂になった息子が見る」という、ありふれた(普遍性のある、といってもよいが)要素に集中してしまっているのは、少し弱い気がする。あるいは、この要素を書くにしても、その描写の密度や強度が少し弱かったか。これはわたしの好みの問題かもしれない。本作で十分に魂を揺さぶられた/られる人はたくさんいるだろうから。
また、長編小説というには少しボリュームが足りないところも気になった。これはもちろん、特異な語りの形式を採用しているために、見かけのページ数に比べて文字数が少ない(余白が多い)から、ある程度は仕方のないことだ。しかしそれを鑑みても、ストーリー上の展開や場面転換に乏しく、プロットとしてはかなり短い。ストーリー展開に乏しい名作なんていくらでもある。それはわかっている。しかし問題なのは、読み終わってそれ相応の充実感を得られるかどうかであり、本書に関しては、わたしはちょっと物足りなさが残った。長編というより、どちらかといえば中編の読後感に近い(これはソーンダースがもともと中短編を得意とする作家であることが関係しているのかもしれない)。だから本の厚さや値段を無意識にでも考慮に入れてしまって、「物足りない」という感情を脳がはじき出したのかもしれない。
あれこれ文句を書いたが、はじめに言ったように、わたしにとってはこの語りを「発明」し、それを極めて高いレベルで使いこなして一冊の小説の形に仕上げてくれただけで「勝ち」であり「絶賛」である。あとストーリーがもう少し充実すれば「完璧」といったところだろうか。
また、本作の大きな魅力のひとつは登場人物(霊魂)たちの「ノリの軽さ」だ。かなりおふざけが入っているし、正直言って下品だし、おちゃらけていて肩の力が抜けるトーンで話は進む。こうしたノリの軽い文体は大好きだ。非常に質の高いオフザケ文章なので、そりゃあピンチョンも推薦文を書くわけだ。12月10日に出たばかりの短編集『十二月の十日』もさっそく買ったので、読むのが楽しみで仕方がない。間違いなく要注目の現代アメリカ作家である。
第5位 『めくるめく世界』 レイナルド・アレナス
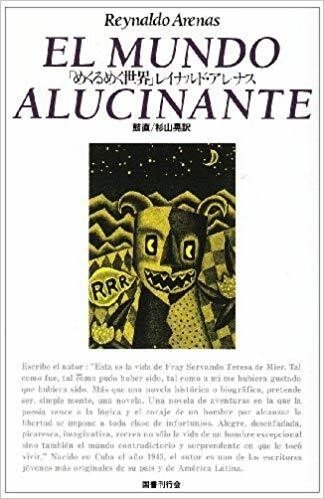
キューバの亡命作家アレナスは、そのデビュー作『夜明け前のセレスティーノ』によってそれまでの私の文学観をこなごなにした。人生の1冊である。そんな彼の代表作『めくるめく世界』にやっと挑む気になった。読み始めたらハナっから最高であった。何しろ、第1章が3回も連続で繰り返されるのである。しかも、1人称・2人称・3人称と律儀に語り口を変えながら。「ははーん、さてはこの小説、1章ごとに3つの人称が併走することで互いを補い合い、矛盾し合うのが狙いの作品だな」と予想したのもつかの間、どうやらそういうわけでもないらしいことがわかってくる。こちらの「常識」とはまったく異なる倫理と道理で動く世界観に「いま自分はアレナスを読んでるんだ」という幸福感が身体の底から沸き上がってくる。
実在したメキシコの僧侶セルバンド師を元ネタにした人生記だが、この怪僧、とにかく牢屋に入れられてばかりである。行く先々で収監され、その度に自分の力で、あるいは不思議な力やめちゃくちゃな理由で脱獄する。獄中譚にいい加減うんざりし始めたところで、過去最大の、おそらく世界中の文学や創作史上もっとも壮大でふざけている脱獄シーンが来る。あまりのスケールのデカさと馬鹿馬鹿しさに、諸手を挙げて「俺が悪かったよ!負けた負けた!」とひれ伏した。
この小説をいちばんつまらなく読む方法は「神話的」という形容とともにページを繰ることであると思った。というか、メタフィクションにしろ不条理小説にしろ信頼できない語り手にしろ、この作品は既存の小説の枠組みのなかで解釈されることを拒み続けているように感じる。いや、拒んですらいない。ハナから眼中にない。あるいは枠という概念すら知らずに遊んでいる。爆発している。ただひとつふさわしいのは、副題である「冒険小説」のみだろうか。3つの人称の駆使にしたって、技巧というよりも戯れであり、駆使してやろうなんてハナから考えていなかったのではないかと、爆発し続ける筆致から思う。
戯れであり必然。これはアレナスの作品の、ほかのあらゆる要素にも言えるのではないか。スラップスティックに人や生き物が次々と死ぬのも、嘘のレベルを越えた荒唐無稽なエピソード群も、我々にはこのように読んでしまうけれど、そのテキストの奥にはもっとイノセントであるがゆえにそうでしかありえないような固有のダイナミズムが潜んでいるような気がしてならない。アレナスを読んでいるあいだ私は、その奔流のほんの一滴を、ごくごく飲んでいる。ほんとうにおいしい。もっと飲みたい。
第4位 『代書人バートルビー』 ハーマン・メルヴィル
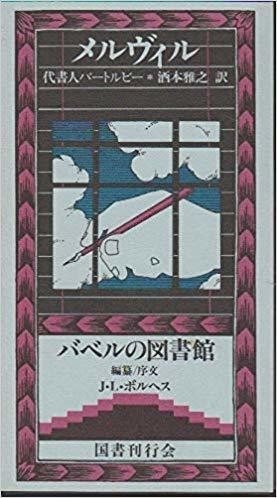
バートルビーのような人種のことを知るには、本人に聞いてみるしか手はないが、それが彼の場合には、ほとんど頼みにならないのだ。
『白鯨』はまだ当分読めそうにないが、メルヴィルの短篇『代書人バートルビー』は読んで本当に良かったと思っている。
十分に個性的なメンツによるドタバタ劇が描かれる序盤は、読んでいて東京03のコントみたいだと思った。しかしバートルビーの登場により場は一変する。彼はブラックホールだ。あらゆる予想や考察や解釈を飲み込み、暗く深い底からは何も吐き出さない。だから、「感想を書くような本ではない」という感想だけを置いて去る人が多いのも納得の、まさに文学でしか描き得ない金字塔的一作だと思う。
「せずにすめばありがたいのですが(I would prefer not to)」という決め台詞は思わず自分も実生活で使いたくなってしまう。読者の解釈を拒み続ける黒い穴でありながら、同時にこのようなキャッチーなフレーズも盛り込まれている。この取っ付きにくさと取っ付きやすさのバランスがたまらなく絶妙なのだ。
メルヴィル、評判に違わぬヤバい作家であった。これは『白鯨』に手を出す日もさほど遠くない……かもしれない。
第3位 『ムッシュー・テスト』 ポール・ヴァレリー
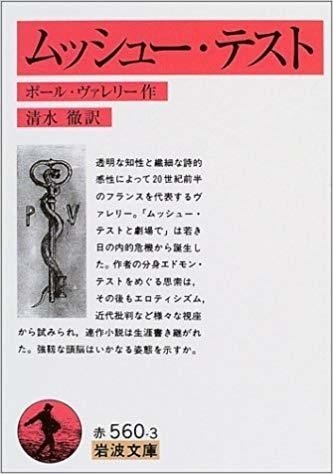
どうだろうきみ、ひどく怖い気がするんだけど、わたしたちは、わたしたちを知らぬ多くのものによってつくられているのではないかしら。だからこそ、わたしたちはわたしたち自身を知らないのだ。もし、そういうものが無限にあるとしたら、いかなる思索も空しいね......
「運命」を感じる本がある。時間的にも空間的にも遠く離れたところで書かれた文章が、まさに今の私のために書かれたとしか思えない──こうした自己陶酔的な感慨は、なんて傲慢なのだろう。しかし私は言い訳がましくもこのように考えてしまう。──あらゆる本を読むという行為は本質的に傲慢なのではないか?ならば開き直ってこう宣言しよう。『ムッシュー・テスト』はほかの誰でもない「わたし」のために書かれた本である。「わたし」はそのように読んだ。そのようにしか読むことができなかった。
わたしの担う、わたし自身にも未知なるもの、それがわたしをわたしたらしめる。(中略)わたしを束縛するのはわたしではない。
いまの自分が求めていたものがここにあった。『フラニーとゾーイー』に求めて満足には得られなかったものが、この小説にはある。自分が小説・文学に求めていたもの、ということではない。人生に求めていたもの、自分自身に求めていたものが、眼の前で小説というかたちを成している。そんな印象を受けた。
この小説で語られていることは、わたしたちとはおよそ関係のない衒学的な些事ではない。むしろわたしたちに近すぎて、普段はまったく気にも留めていないような事柄──自分と他者を見つめること──について、豊饒としか言いようのない文章によって綴られている。
自己は個々の部分的支離滅裂──これが刺戟材となる──に対する瞬間的な応答である。
本書はいわば99%が哲学的な思索、その断章やエッセイ的なものに占められているが、残りの1%の文学的要素の濃さ、密度、洗練具合が途方も無いために、小説以外のなにものでもない。文学的描写の質の高さは、ヴァレリーの詩人性が発揮されているのだろう。とすると、彼の詩集もぜひ読んでみたい。
これほど「1冊を読み終わる」ことが意味をなさない本はない。毎年読み返したい。きっと再読する度に、以前ピンとこなかった部分から宝石を持ち帰るだろうし、以前なんらかの感慨を得た部分を平然と通り過ぎることだろう。
第2位 『シラノ・ド・ベルジュラック』 エドモン・ロスタン

俺たちはな、ただ名前ばかりがシャボン玉のように
膨らんだ、夢幻の恋人に恋い焦がれている。
さあ、受け取れ。この偽りを、真実に変えるのは君だ。
面白すぎる。フランスの戯曲でトップクラスの人気作だというのも納得の面白さ。とにかく全編ずっと面白い。言葉の奔流に呑まれて一気に駆け抜けるように1日で読み終えてしまった。なにせ全てのシーンが名シーンだとさえ言える出来だったのだ。全シーンが素晴らしいと感じたのは、舞台で実際に演じられることを前提に作られていることによる効果もあるだろう。小説だけでなく、戯曲にもまだまだ豊かな未知の文学的地平が広がっていると痛感させられた。
口下手な美男子と、口だけは達者な不細工が結託して美女を落としにかかる。──こんなにワクワクする設定があるだろうか。ラノベにあってもよさそうだ。これぞ一流のエンタメ!と気持ちよく楽しめる作品でありながら、「言葉の力によって運命を変える」ことがテーマの筋書きであり、言語による言語のための言語讃歌としても読める。
本作を読むきっかけは──多くの諸兄と同様に──名作18禁ゲーム『素晴らしき日々 〜不連続存在〜』にて言及されていたためだ。このゲームはウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の思想を下敷きにしていることで有名だが、実際には『論哲』よりも『シラノ』のほうが遥かに印象的に取り上げられていたように思える。
『すば日々』補正を除いても、本当にめちゃくちゃ面白い傑作戯曲だった。名台詞のオンパレードに何も考えず興奮し涙を流すことができ、またそうして「言葉によって人の心を動かす」こと自体に批評的な眼差しを向けることで、さらに読み甲斐が増してゆく傑作だ。本当に面白いものは、本当に面白いので、「本当に面白かった」以外、特に書くことがない。Mon panache!
第1位 『不滅』 ミラン・クンデラ

しばらく経ってから、やっとアヴェナリウスが沈黙をやぶった、「いまどんなものを書いてるんだね、要するに?」
「それは話せるようなものではないよ」
「それは残念だね」
「残念とはなぜだい? むしろ幸運なんだよ。現代では、書かれたものすべてに飛びかかるようにして、映画や、テレヴィ・ドラマや、漫画に変えてしまう。ある小説のなかで、本質的なものは、小説によってしか言うことができないものである以上、どんな脚色であろうと、非本質的なものしか残らない。今日まだ小説を書こうというほどのおかしな人間は誰にせよ、もし自分の小説の防備を確かなものにしたいと思うなら、脚色などできないようなやりかたで、別の言いかたをするなら、話して聞かせることなどできないようなやりかたで、書かなければならないのさ」
「(前略)ぼくは第六部を待ちかねているんだ。ぼくの小説には新しい作中人物がひょっと出てくるんだ。そうして、その第六部の終りで、彼は出てきたときと同じように、跡を残さずに立ちさってゆくだろうよ。彼はなにごとの原因でもないし、どんな結果もつくりださない。それがまさにぼくの好むところなんだ。第六部は小説のなかのひとつの小説になるだろうし、ぼくがこれまで書いたもっとも悲しいエロティックな物語になるだろうね。きみをさえも、その物語はきみをさえも悲しませるだろうな」
アヴェナリウスは当惑して黙りこんでいたが、それから穏やかにこう尋ねた、「それで、きみの小説の題はどうなるの?」
「《存在の耐えられない軽さ》だよ」
「でも、その題はもう使われているじゃないか」
「そう、ぼくによってね! しかし、あのとき、ぼくは題をまちがえたんだよ。あれはいま書いている小説のものになるべきだったんだね」
以上の引用部は、『不滅』のうちでも最も「つまらない」箇所である。
この小説の前では、何を言っても、何を書いてもまったく意味をなさないんじゃないか。感想や評を書けば書くほど、『不滅』というテクストからは離れていくんじゃないか。どんな芸術作品にだって言えるこんなことを、これまで思ったことのない強さで思わせられるのが、この作品の在りようを端的に示しているのかもしれない。
また無意味な言を弄してしまった。この瞬間も私は、この小説から離れていく。ただひとつだけ言わせてほしい。私は、この小説を読むあいだ、ずっと幸せだった。楽しかった。ストーリーの展開などは関係ない。ただ、目の前の1ページを、1行を、1文を噛み締めることがこんなに楽しいんだと感じたことはなかった。小説を読むことはこんなに楽しかったのだと、生まれ変わるような思いだった。
これは不思議な感覚だ。これまで読んできた大好きな小説たち。前述の通り、私が「大好き」だと認めるこれらの共通項は「没入感」にあった。これらを読んでいるとき、そもそも「読んでいる」ということを意識しないまま小説世界へと没入して、いつのまにか読み終わっている。こうしたかけがえのない読書体験をくれた本たちを、私は自分のもっとも大事な本棚へと収めてきた。
ところが『不滅』は違う。「読んでいて幸せだった」と思えるほどには、私はこの小説に「没入」してはいなかった。むしろ一文一文を読むごとにページから顔を上げ、感嘆した。その素晴らしさに溜息をついた。そのような、これまで味わったことのない類の読書体験であった。
本書ほど「傑作」という言葉がふさわしい小説もあまりないんじゃないか。あるいは「完璧な小説」という不遜な言葉も、本作にならふさわしい。自分好みとかそういうレベルではない。ページを繰るあいだ、眼前にそびえ立つ、小説という目に見えない建造物。その完成し切った佇まいに畏怖さえ覚えた。私にとって『不滅』はそんな作品だ。
クンデラは「小説が上手い」。この上なく上手い。「文章が上手い」とか「革新的な小説を書いた」とか「後世への影響がすさまじい」とかなら、他にいくらでもいる。しかし、クンデラほど「小説」という形式に自覚的に向き合って、ただし決してメタフィクション的に煙に巻くやり方ではなくて、真正面から王道のやり方で「小説」を描き切った作家はほかにいるだろうか。
この本の帯には「ジョイス、プルーストで幕を開けた20世紀の文学は、この小説で締めくくられる」と書かれている。私はジョイスもプルーストも未読なので、ここでいう「20世紀の文学」という単語の深遠な意味はわからない。わからないが、ほんとうにこの『不滅』がそれを締めくくるのだとしたら、これほどふさわしい幕引きはないと思ってしまうのだ。
言葉を尽くせば尽くすほどに、本作は矮小化されていく。「読めばわかる」か。「読んでもわからない」か。「わかった」と自分のなかで思うことの傲慢さと、「わからない」とこれ見よがしに言い放つ卑しさをかかえて、私たちは本を読む。
「読まない」こともできる世界で、本を読む。
【2019年下半期に読んだ本リスト】
『』:長編や短編集など、1冊の本となっているもの
「」:短篇など、1冊の本の一部分の作品
重松清『きみの町で』
重松清『ゼツメツ少年』再読
結城浩『数学ガールの秘密ノート/ビットとバイナリー』
ロスタン『シラノ・ド・ベルジュラック』
川上未映子『夏物語』
パヴェーゼ「自殺」
ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟 1』亀山訳
永井均『倫理とは何か 猫のアインジヒトの挑戦』
宮沢賢治「毒もみのすきな署長さん」
パス「波との生活」
目取真俊「面影と連れて」
目取真俊「群蝶の木」
目取真俊「赤い椰子の葉」
ソーンダース『リンカーンとさまよえる霊魂たち』
円城塔「The History of the Decline and Fall of the Galactic Empire」
筒井康隆「おれに関する噂」
円城塔「松ノ枝の記」
筒井康隆『文学部唯野教授』
高橋源一郎『恋する原発』
高橋源一郎『優雅で感傷的な日本野球』
クンデラ『不滅』
コルタサル『愛しのグレンダ』
円城塔「これはペンです」
ウエルベック『ある島の可能性』
サリンジャー 『フラニーとゾーイー』再読
ホーソーン「ウェイクフィールド」再読
メルヴィル『代書人バートルビー』
アレナス『めくるめく世界』
ヴァレリー『ムッシュー・テスト』
ソーンダース『人生で大切なたったひとつのこと』
ヴァレリー「固定観念」
結城浩『数学ガールの秘密ノート 学ぶための対話』
バタイユ『空の青み』
清水徹『ヴァレリー 理性と感性の相克』
バタイユ「死者」
バタイユ『眼球譚』
チェーホフ「犬を連れた奥さん」
金子玲介「林冴花は宗教が苦手」
チェーホフ「イオーヌイチ」
残雪「かつて描かれたことのない境地」
チェーホフ「ねむい」
バルザック「知られざる傑作」
ミルハウザー『エドウィン・マルハウス』
<まとめ>
今年の1作には、上半期のクリストフ『悪童日記』3部作を選びたい。『不滅』も素晴らしいのだが、あの薄さと読みやすさであれだけの衝撃を与えてくれたコスパのエグさに軍配を上げたい。
上半期にかなりのペース(個人比)で読んだ反動を受けるように下半期はあまり数を読めなかった。しかし、何年も積んでいた本に満を持して取り組めたりと、実り自体はとても多かった。ただ『カラマーゾフの兄弟』の1巻を読んで以来、なんとなく次巻に進む気が起きず結局数ヶ月放置してしまっているのが後ろめたい。あと、フォークナーやドノソを読みたい読まなきゃと思って何度も手に取るのだが、怖気づいて棚に戻してしまう。これらを読み切れる日はくるのだろうか?
来年は、今年刊行予定だったはずがいつの間にか延期していたピンチョンの最新作『ブリーディング・エッジ』もいよいよ出ることだし、その前に『ヴァインランド』あたりで肩慣らしをしておきたいし、ドン・デリーロの『ホワイト・ノイズ』が復刊されるという噂だし、『オーバーストーリー』が話題となったパワーズにもいい加減手を出したいし、ギャディス『カーペンターズ・ゴシック』も積んでるし、そろそろジョイスを履修したいし、『ドン・キホーテ』は時間のあるうちに読んでおけと言われているし、ボラーニョも、ブルガーコフも、ル・クレジオも、アディーチェも、ソローキンも読みたい。しかしそもそも環境が変わって本が読めるかどうかもわからない。
いま生きていて一番幸せな瞬間は、深夜に家の鏡の前でひとり踊っているときと、次に読む本についてあれこれ思いを巡らせているときである。
それでは。
【これまでの文学ランキング】
・2017年国内
・2017年海外
・2018年上半期
・2018年下半期
・2019年上半期
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
