
【2017年】世界文学ベスト5【日本文学編】
数日前に今年読んだ文の海外文学個人ベスト10を書きましたが(以下リンク参照)、今回は日本文学編です。
本来であれば日本文学もガイブン編のように「ベスト10」!と銘打って、キッカリ10作品紹介したかったのですが、何しろ読んだ総数が少なく、自信を持って好きだと言えるものだけ個人ベストに挙げたかったので5作品に絞らせてもらいました。
それではどうぞ↓(作品名クリックでAmazonの書籍ページへ飛びます)
【2017年日本文学5選】
5位:乙女の港 / 中里恒子, 川端康成

『ねえ、お姉さま、これから、土曜日の晩には、きつとお手紙書くと、約束して頂戴。』『土曜日でなくたつて、書きたい時、いつでも書くわ。』『いや、土曜日の晩は、どんな差支へあつても、きつと三千子を思つてほしい。そのかはり、ほかの日は、三千子を忘れて、お姉さま、沢山お働きになつてもいいわ。』
日本人初のノーベル文学賞受賞者、川端康成が書いた少女小説。
…だと思っていました。この記事を書くためにwikiを覗くまでは。
どうやら世間的に川端康成作だと思われているこの話、本当は彼の作ではなく、彼に師事していた主婦作家、中里恒子の草稿を川端が加筆・修正する形で書き上げたものらしいのです。(Wikipedia「乙女の港」参照)
確かに「伊豆の踊子」や「雪国」に代表される彼の作品は、ほとんど大きな話の展開が無いのが特徴。それに対してこの「乙女の港」のプロットは正統派というか王道というか、悪く言えば “よくありそうな” 展開です。
この「川端らしくなさ」が自分は好きなのですが、真相から考えてみれば別の作家がプロットを書いたのだから当然ですね。
しかしこの「乙女の港」は、川端の加筆・修正によってちゃんと彼らしい、きれいな文体になっています。よく川端康成を称する言葉として「うつくしい日本語」というフレーズを聞きます。正直これを読むまでその意味が分かっていませんでしたが、読めば自ずとその意味が分かりました。音読すれば普段使う日本語まで浄化されるかのような感覚です。
「乙女の港」の魅力、それは
話の起伏が少なく難解な川端文学の真骨頂である「うつくしい日本語」が、誰でも親しめる王道に沿ったストーリーを通して味わえる
ことに尽きると思います。つまり川端康成初心者は、「伊豆の踊り子」や「雪国」ではなくこれから読み始めれば、挫折することが少ないと思うのでオススメです。
また肝心な内容ですが、一言で言えば「先輩後輩関係の女学生の百合モノ」です。
Sisterから取られた「S(エス)」という単語で友情以上、恋愛未満の微妙な関係が表されており、女学生の純粋かつドロドロしたやりとりが、川端のうつくしい日本語で味わえるのです。
4位:蒲団 / 田山花袋
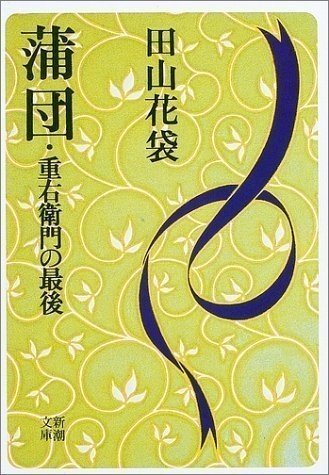
かれの経験にはこういう経験が幾度もあった。一歩の相違で運命の唯中に入ることが出来ずに、いつも圏外に立たせられた淋しい苦悶、その苦しい味をかれは常に味わった。
作者自身の体験を元に描かれる私小説の元祖にして、日本の自然主義文学を代表する問題作。
弟子として自分の家に下宿させている女学生に密かに想いを寄せる中年の作家(主人公)の心情に、気持ち悪さ半分、共感半分で読み進めていたのですが…
物語が加速する終盤で一気に惹きつけられ、そして何と言ってもあのラストシーンで完全にやられました。
最後のページの直前にタイトルからラストを予感し、そしてその予感がほぼ当たっていたにも関わらず、予想以上の気持ち悪さにどうしようも無く切なくなりました。
この作品はあのラストシーンが全てだと思っています。
実際に花袋が経験したことかどうかは関係なく、あの終わりを描くことができたことに関して自分は花袋を尊敬します。
3位:女生徒 / 太宰治

私は、いままで、自分が、よいしょなんて、げびた言葉を言い出す女だとは、思ってなかった。よいしょ、なんて、お婆さんの掛声みたいで、いやらしい。
「人間失格」はまだ読み終えていませんが、自分はこっちの太宰の方が好きだろうという謎の確信があります。
本作「女生徒」は、太宰へ送られてきた実在の女学生の日記を元にして書いた、太宰の少女独白体シリーズの代表作。
実際の日記からどの程度太宰が手を加えているか分かりませんが、とにかく年頃の少女の繊細でどうしようもない心理描写のリアリティが素晴らしい。(少女の心境なんて本当のところは分かりませんが)
思春期だからこそ気になってしまう、自分と世の中の歪みをこれ以上ないくらい素直に少女が独白しているその「語り」が本当に癖になってしまいます。
個人的に、本当の女性が読んでもこの語りにリアリティを認めるのか否かは非常に気になるところです。
2位:兎の眼 / 灰谷健次郎

小谷先生はおおきな声で読みはじめた。
「ぼくはじっとじっと見た。それから、はこの中までじっとじっと見た。赤いやつが出た。ぼくは鼻がずんとした。サイダーを飲んだみたい、ぼくは心がずんとした。ぼくはあかいやつがすき、小谷先生もすき」
小谷先生も好きというところまでくると、小谷先生の声はふるえた。
たちまち涙がたまった。たえかねて小谷先生はうしろを向いた。
子どもの誰かが拍手をたたいた。するとあっちからもこっちからも拍手がおこった。
教育者かつ児童文学作家である灰谷健次郎の処女作にして代表作。児童文学ということで、私の中の立ち位置としてはガイブン編の3位に挙げたケストナーの「飛ぶ教室」と近いところにいる作品。
「飛ぶ教室」も「兎の眼」も、教育現場がこうであったらいいのになぁという作者の痛切な理想が投影されている作品なので、言ってしまえばそれこそ「お話の中でしか有り得ない、いろいろあっても必ずハッピーエンドに綺麗に着地するおとぎ話」なわけです。
しかし、両者ともに、とりあえずハッピーエンドにしただけのお涙頂戴モノではないと私は強く思います。
「兎の眼」の世界に生きる人物たちからは、鉄三にしろ古谷先生にしろバクじいさんにしろ、それぞれの人生を責任を持って生きている、強烈な人間臭さが確かに伝わってきます。
このようにリアルな人間と時代を描写しているからこそ、児童文学という枠に関係なく、「兎の眼」は名作として読み継がれてきたのだと思います。
1位:春琴抄 / 谷崎潤一郎
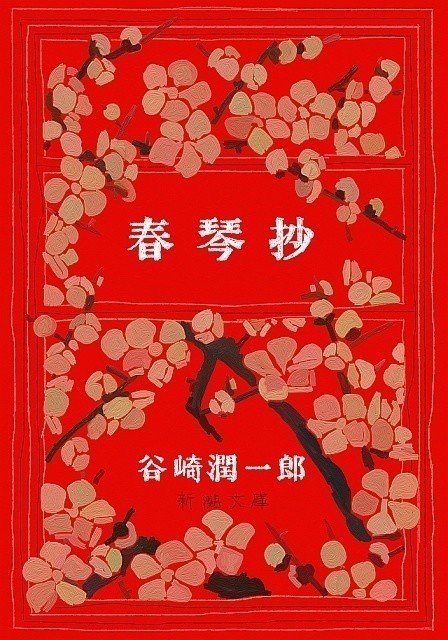
佐助もまたそれを苦役と感ぜずむしろ喜んだのであった彼女の特別な意地悪さを甘えられているように取り、一種の恩寵の如くに解したのでもあろう。
その世界的な評価の高さから“大谷崎”とも呼ばれる、谷崎潤一郎の代表作のひとつ。
この作品で初めて谷崎を読んだのですが、読んでみようと思った理由は単純です。
この話は「マゾヒズム」を描いている作品だと聞いたからです。
谷崎潤一郎の作風は耽美主義と呼ばれ、「官能的な愛欲をいかに恍惚的に書くか」が主題であったらしく、中でもこの「春琴抄」は、盲目の女性とそれに仕える男のかなりイレギュラーな主従関係を描いた話だと聞き、興味をそそられない訳にはいきませんでした。
「マゾヒズムを描いているらしいけれど、どれほど幻想的で官能的な話なんだろうか」とワクワクドキドキしながら読み始めたのを覚えています。
しかし読んでみた結果、抱いた印象はむしろ真逆でした。
どんなに現実離れした内容なんだと思っていたのに、「春琴抄」でのマゾヒズムは、あくまで日常的なところから地続きで繋がっていたのです。
谷崎の卓越した文章力の故なのかも知れませんが、ふと読み進めている最中、佐助が盲目的に春琴に支えていく様子に共感してしまい、そんな自分を発見して驚きました。
何かとても恐ろしく刺激的な世界でも、自分が暮らす現実とは離れた、どこか別の世界での話ならそれほど怖くないし心を動かされません。
しかし、そのような世界と今いる世界が実はそんなに遠くなく、繋がっているんだよ、ということを丁寧かつ天才的な鮮やかさで浮き彫りにしているのがこの「春琴抄」だと思います。
自分は、この話を読んで涙を流しました。
小説は虚構だけど虚構じゃなく、小説だからこそ与えられる現実への働きかけだってあるんだ、ということを本当の意味で教えてくれた作品です。
ランキングは以上です。
前回挙げさせていただいたよく見る書評系ブログの影響や、早いうちにラテンアメリカ文学に触れて世界の突拍子もない文学の世界を知ってしまったこともあり、自分は今は海外文学を中心に読んでいます。
しかしやはり日本文学にはそれなりの良さがあり、もちろんガイブンと共通するような普遍的な良さもあるというのは、今年いくつか有名どころの日本文学を読んで確認できたことです。
ただ、何と言っても日本文学のもっとも良いところは「作者が書いた原文そのままで読むことができる」点だと思います。
ガイブンはどうしても翻訳を介さなければ(少なくとも今の自分は)読めないので、原文ままで読めるという日本文学の利点は嫌というほど感じます。だからこそ、その特権を生かすためにも日本文学にはこれからも触れていきたいと思っています。(あくまで優先は海外文学ですが)
今回はここまでです。
実は、本記事のおまけとして前回の10選に入りきらなかったお気に入りの海外文学を数冊紹介しようと思っていたのですが、日本文学だけでかなりの長さになってしまったのでやめました。
※追記:2018年に読んだ文学作品の紹介記事はこちら↓
それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
