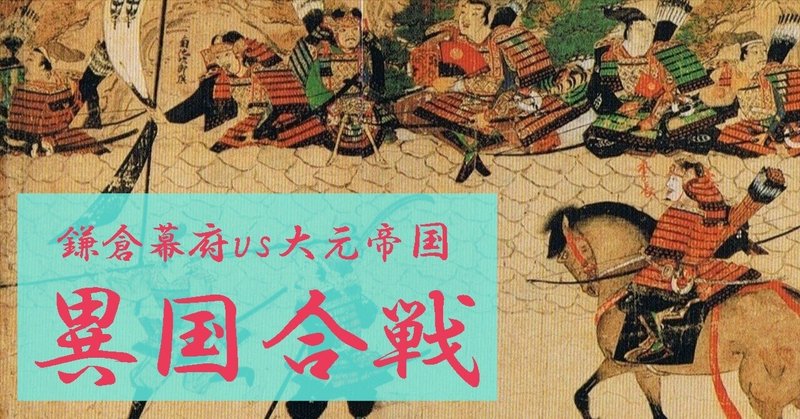
【異国合戦(20)】二月騒動
モンゴルからの使者・趙良弼が日本を離れ、12人の大宰府使節が燕京を訪れた文永9年(1272)2月、日本では大きな事件がありました。。
今回は蒙古襲来を前に執権・北条時宗が権力基盤を盤石なものとしたと評価される「二月騒動」を解説します。。
前回記事は下記のとおりです。
これまでの全記事は下記から読めます。
不可解な名越家襲撃
事件はまず鎌倉で起こった。2月11日朝、武装した武士たちが突如として名越時章・教時兄弟の屋敷を急襲したのである。
名越時章は幕府の最高議決機関である評定衆の一員で訴訟審理を司る引付の一番頭人。将軍権力が形骸化した幕府において執権、連署に次ぐ序列3位ともいえる立場にあった。弟の教時も評定衆の一員である。兄弟が襲撃されたのは弟・教時が謀反を企てたからだという。
結果、追い詰められた時章は自害し、教時は襲撃部隊によって討ち取られた。
名越教時は先代将軍・宗尊親王が鎌倉を追放される際に抗議のデモンストレーションを行った過去がある。反得宗家(反北条時宗)的な思いを持っていたことは間違いなかろう。
名越家が2代執権北条義時の正統な後継者として「我らこそが北条家の本流」という強い思いを持つ家であったことも確かである。
しかし、襲撃はあまりに唐突であり、事件はこの後、不可解な経緯をたどる。兄・名越時章は無実であったとし、襲撃を指揮した5人の大将が斬首に処されるのである。
この5人は4人が御内人(得宗家=北条時宗の直臣)、1人が連署・北条政村の家臣であった。
そして謀反人とされた弟・名越教時を討ち取ったものたちには賞罰がなく、人々の笑いものになったという。教時が謀反人とされた根拠が明らかになることはなかった。
この顛末は、強引な名越兄弟討伐に反発が強く、執権・北条時宗が火消しに走らざるを得なかった結果なのかもしれない。
後に名越時章の嫡子であった名越公時は評定衆となり二番引付頭人まで昇る。さらにその嫡子の名越時家は鎮西探題として対蒙古の最前線である九州に下向した。
時章・教時兄弟の弟の名越時基も評定衆から二番引付頭人まで昇り、時宗の嫡男・貞時の娘を妻とする。
このように名越家は幕府滅亡まで権勢を維持することに成功した。しかし、得宗家の対抗勢力としての地位は失い、他の北条一門と同様に得宗家の補完勢力としての道を歩むことになる。
結果的として、二月騒動により2代執権・北条義時の後継争いから続いた得宗家と名越家の北条一門本流争いは得宗家の勝利で確定することになった。
北条時輔の誅伐
幕府を揺るがす事変は名越兄弟の粛清だけでは終わらず、京へも飛び火する。
鎌倉の騒動から4日後の2月15日、六波羅北方探題の赤橋義宗が南方探題で執権・北条時宗の異母兄である北条時輔を謀反の疑いで攻め滅ぼしたのである。京で幕府の軍事動員と戦闘が行われたのは承久合戦以来のことで51年ぶりのことであった。六波羅探題が討ち取られるのは史上初の前代未聞のことである。
北条時輔は六波羅南方探題に在職すること7年3か月。京の貴族たちにとっては最も身近で縁の深い北条一門であり、その闘死が衝撃を与えたことは想像に難くない。
5代執権北条時頼は長男・時輔より次男・時宗を大事に扱い、後継者とした。これは時輔の母が側室、時宗の母が正室という母の身分による差であり、武家社会において特別異常なことではない。時輔にとって執権となり幕政を動かす弟・時宗の存在は面白くなかったかもしれないが、この点を謀反の根拠と強調しすぎるのも問題があろう。
結局、北条時輔についても名越兄弟同様に謀反の証拠を示す具体的な史料は存在していない。
挙国一致体制の確立
謀反の証拠は薄弱でありながら、なぜ名越兄弟と北条時輔は討たれねばならなかったのか。これは討つ側にこそ討たねばならない積極的理由があったと考えるべきだろう。モンゴルからの外交的圧迫と安全保障上の脅威が迫る中、権力基盤を確立させるために北条時宗は潜在的な国内のライバルを排除したかったと考える他ない。
名越兄弟にも北条時輔にも事変当時は謀反の意思は無かったかもしれない。しかし、対モンゴルの戦争指導を進める上で時宗の政策に反発をする者たちが現れた場合、名越家と時輔は謀反の結集点となりうる有力者ではあった。
北条時宗の狙いは未然にその結集点を排除することにあったと考えられる。そのためなら謀反の証拠は重要ではなかった。
同時に鎌倉と京、東西二か所における容赦ない武力発動と殺戮は時宗に反発する者の居場所が幕府内に存在しないことを示すだけでなく、朝廷にも幕府の方針に反対させない恫喝の効果を強烈に与えた。
二月騒動を経て、モンゴル帝国と戦争をするための北条時宗独裁体制は完成したと評価できよう。強引な手段ではあったが、対モンゴル挙国一致体制はこうして成った。
無実の誤殺であったと認定された名越時章が務めた筑後・肥後・大隅の九州三カ国の守護職は没収され、名越家に返還されることはなかった。言うまでもなく九州は対モンゴル防衛の要地である。
筑後は大友頼泰、肥後は安達泰盛、大隅は千葉宗胤という得宗家に近い御家人に守護職を与えることで対モンゴル防衛体制はより強固となった。
北条政村の死去
文永10年(1273)5月27日、7代執権を務め北条時宗にその地位を譲った後は連署として幕府ナンバー2の地位にあった北条政村が他界した。享年69歳であった
2代執権北条義時の五男として生まれ、父の死後、母・伊賀の方が政村を執権に据えようと陰謀を企む伊賀氏の変を起こした。計画は失敗に終わり、父の跡は兄の泰時が継いだが、政村が罪を問われることは無かった。
以後、政村は幕府内の政変において一貫して北条氏嫡流の得宗家を支持する立場に回り、幕府内の重鎮としての立場を揺るぎないものとした。幼き頃に自らが当事者となる内紛に巻き込まれ、罪を許されたことが「得宗家を支えて北条一門の結束を重視する」という政村の生き方を方向づけたように思われる。
時の執権・北条時宗にとっては後見人であり、その独裁的地位を用意したのが政村と言えよう。
摂家将軍、皇族将軍とともに幕府へやってきた関東伺候の廷臣とも交流を持ち、優れた和歌も残した教養人でもあった。京の貴族・吉田経長は政村の訃報を耳にして日記に「東方の遺老なり。惜しむべし、惜しむべし」と記し、その死を悼んだ。
モンゴルとの戦争を前に北条時宗は最も頼れる補佐役を失うことになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
