
きわダイアローグ01 芹沢高志×向井知子 4/4
4. 新しい旅と知覚
///
4-1. 見えること・イメージが生まれること
向井:例えば、新型コロナウイルスが収まったとしても、環境問題などで、移動ができなくなる時代が本当に訪れるかもしれません。実際に自分がある場所に赴くことなしに、世界との折り合い、向き合い方を考えないといけないときがくると思うんです。その際、記述や描写をして俯瞰的にものを見ることではなく、揺さぶりのなかで瞬間的に身体的にどうイメージするかという力が必要になってくると思います。人間が他の生物と違う進化を遂げている特徴として、「イメージする力が強かった」ということがあると思います。イメージというと視覚を思い浮かべますけれど、本来は脳のなかで起きていることですよね。もしかしたら他の動物も、人間とは別の形でイメージを生成しながら生態系と折り合いをつけているのかもしれないですし、わたしたちはこれから、視覚にこだわらず五感でイメージを持って、折り合いをつけていくことが大切になっているんじゃないかなと思うんです。
人間がこれだけ移動できるようになったのは、鉄道が出てきたことが大きいでしょうけれども、それはたかが100年くらいの話で、人間は長距離を移動できない時代のほうが長かった。それまでは、自分のいる場所で、天候や天体と対話し、世界を想像する力を育ててきていたと思うんです。今は、インターネットなどで世界の向こう側を見ることができるけれど、行ったことのない場所ですら見せられているなかで、その場所に実際に行くことと行かないことでは全然違うんだとを意識しつつ、想像力を育てていくことをどうやっていくのだろうと思っています。
芹沢:たぶん、それは社会全体としてすごく大きな問題なのではないかという気がしています。物理的な空間に自分が移動して、そこのランドスケープに入り込んでいくという体験を、基本的には置き換えによって、映像的テクニックや、匂いとか触覚とか、そういうものも総動員してVRなどで体験させようというわけでしょう? 古いかもしれないけれど、僕は、それでは置き換えられないものがあると思っています。
エドワード・T・ホール *1 という文化人類学者が『かくれた次元』のなかで、「予示的」を意味する「adumbrative」という言葉について語っています。

1970年、みすず書房
それは、日傘(アンブレラ)を差したら、その影が落ちるようなこと。我々がコミュニケーションを取るなかでも、自分が何かをすれば、相手がそれを見て、些細な反応をする。その応答は感知、論理といったことではなく、それを超えた何かだと思うんです。例えば、我々は視覚の影響を強く受けすぎていますが、そのほかにも音や匂い、距離などを知覚しています。いくら頑張って高精細の画像をつくったとしても、そこには画面までの距離しかありません。奥行きや影、さらに言えば空間の感覚が、我々の予兆や予感などに、強く影響しているのではないかと思います。アートは、影や予兆、ヴィジョン、幻影といったものと、ものすごく近しい関係にあると僕は思っています。先ほども申し上げましたが、ランドスケープの中にあって、自分が変わるから風景も変わる、風景が変わるから自分も変わる。それは、モノローグではなくて、通信であり、ダイアローグです。全身を使った対話であり、我々は、皮膚感覚とか鼻が利くとかいうように、視覚だけでなく空間全体を感知する力を、生物である以上、育んできた気がするのです。
向井:人間は、俗に言うと視覚の仕組みを外部化する、「うつす」ということを一生懸命やってきたと言われます。先ほども少しお話ししましたが、イメージは本来、脳のなかで思い描いているものですよね。もしかしたら脳のなかで行われていることと、人間が「目に見えること」だと思って外部化してきたものには隔たりがあるのかなと思ったりしています。例えば先天的な盲目の方が、手術によって急に目が見えるようになった場合、外界をちゃんと認識できないそうなんです。というのは、目の仕組みとしてできるのは、輪郭線を描くことなので、本当は立体視するための陰影の意味やそのことによる距離などの空間把握が、体験としてわからない。だから前後関係が全部同じ、輪郭線でしか見えてこないらしいんです。そもそも、子どもが安定的に立体視できて、大人と同じような仕組みをちゃんと持つまでには、小学校5、6年生までかかるらしいです。そのぐらい視覚というのは他の四感に支えられて、習得しないと成立しないものだということを考えると、人の四感を鍛え直さないと知覚できないというか、イメージするということのあり方、解釈ももしかしたら変わってくるのかなと。
現象学的地理学者のイーフー・トゥアン *2 が『トポフィリア』のなかで、視覚だけが唯一客観的な知覚であると書いています。
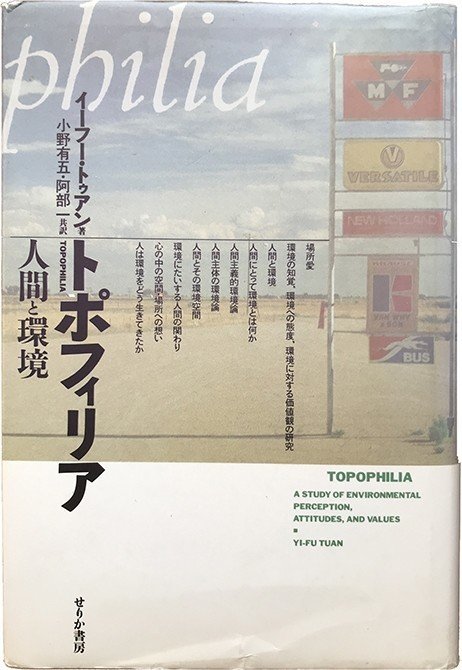
1992年、せりか書房
授業で学生に同書の話をする際に、トゥアンの例示にあるように、「スラムにバスで行ったとします。そのスラムについて話してみて」と聞くと、大抵はみな「汚い」とか「子どもたちが寄ってくる」と描写します。でも、「バスの窓を開けたらどう?」と言うと、「くさい」「騒音がすごい」「こわい」と、急に体験が主観的なものになっていくんです。トゥアンはそのように、視覚だけが「我々の感情に深く入りこまない」客観的なものだと、主体と直接繋がっている他の四感との違いについて言及しています。実際、人間がどのように空間を理解して、目が見えるようになるかというと、最初は母親を触るところから始まるわけです。そこから寝返りでX軸の方向を学んで、その次にハイハイによってX、Zができる。立つところで初めてX、Y、Zができるんですね。その過程には、おっぱいの匂いや声、母親への距離といった他の四感によって育まれてきた感情と理解があって、そこから得た想像力や身体の記憶から空間的な体験ができあがってきている。そこで初めて、視覚というものが成立するのです。そう考えたときに、わたしたちはこれだけ高精細な視覚情報の世界にいますが、イメージは、視覚から生まれるものではないのかもしれないと思うのです。それでもなぜわたしが映像を使っているのは、映像から触覚的なものを喚起できないかなと思っているからですが、映像を使っていないような映像がつくれるといいんだろうなと。映像をつくっているときに、どうやって余白をつくっていくかを考えているのですが、その余白というのは映像なのに映像ではないもの、そんなものがつくれるといいのかなと、思います。想像力って、やっぱり、視覚的ではないのかもしれない。
芹沢:目は進化の過程で、それ以外の感覚を統合していくための、一つのデバイスとして利用されていったのかもしれません。目の進化が、触覚や嗅覚などをまとめあげるうえで、すごく重要な役割を担ったのだろうなと思っています。
先日、東工大の伊藤亜紗 *3 という研究者が現代アーティストの目[mé]*4 と対談した映像を見たのですが、それがすごく面白くて、彼女の『目の見えない人は世界をどう見ているのか』という本も読みました。それもまた面白くて、立っている地平が、わりと近いなと感じました。

2015年、光文社
彼女は、もともと生物学に興味を持っていた人だからか、身体障がい者と言われる人たちへのアプローチが、全然違うんですね。その本について少しお話をしますと……。同じ「目が見えない」人でも、先天的に全く見えない人と、途中から視力がなくなってしまった人とでは、世界の感知の仕方が違いますよね。しかし晴眼者からすると、目という重要な機能が失われているわけだから、「手助けしなきゃならない」「かわいそう」といったような意識が勝ってしまう。手助けしなければ、世界を認知できないんじゃないかとさえ思ってしまう。しかし、個人差はもちろんあるにしても、彼らは彼らでちゃんと世界を認識して生活しています。また、目が見えない人は特異な能力を持っていると思ってしまうことも幻想というか、そうではないんだと彼女は言います。彼らの世界認識の方法と、我々がいつもやっている世界認識の方法はどこが違うのか。極端に言ってしまうと、多様性の一つくらいにつっぱねた感覚で「本当のところ、どんなふうにしているの?」と、インタビューを続けていく。福祉も重要ですが、福祉の枠組みのなかだけで「身体障がい者へのアプローチ」を考えていくと、歪みも出てくる。身体障がいということも多様なあり方の一つとして捉えることで、我々の世界認識の方法や思考モデルを根本から考え直すきっかけが生まれるかもしれません。
4-2. 自然の認識
向井:きわプロジェクトの「インクルーシブ・ピクニック」には、実はそういうところがあったんです。
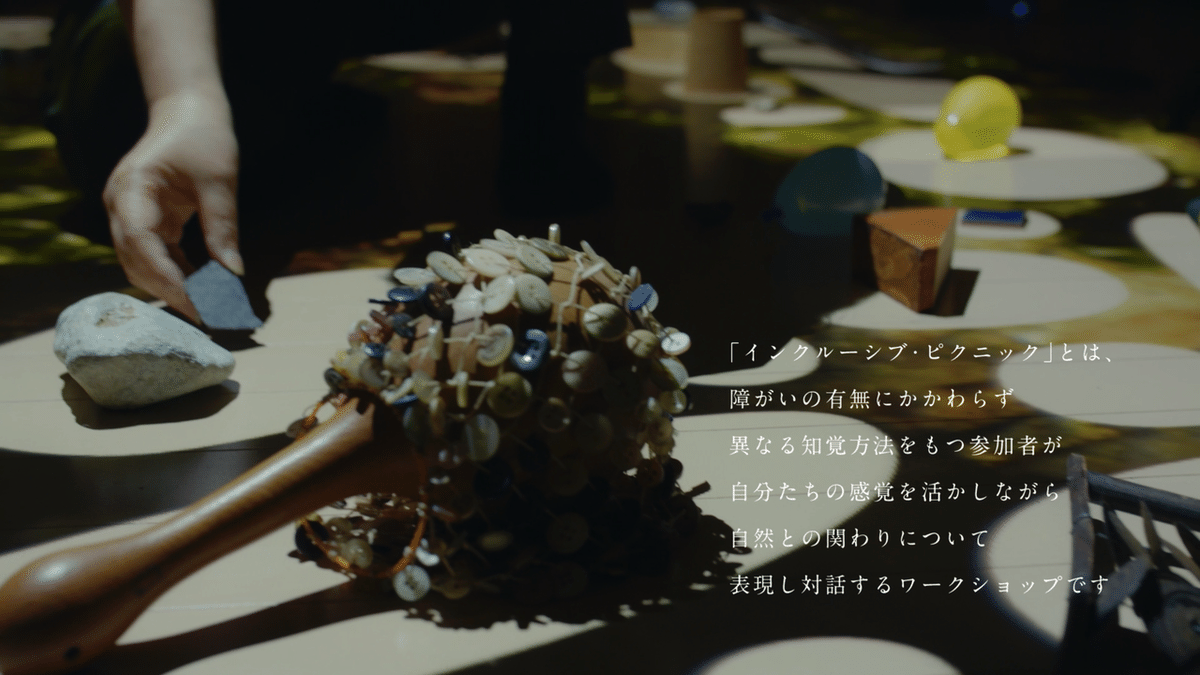

東長寺 水の苑
世界と個人のつなぎ方はそれぞれにしかなく、おそらく映像音響公演「きわにたつ」は、人間が折り合いをつけようとした場所を扱っていると思うんですが、それでは観る人が回路を持ち得ないこともたくさんある。もう少し主体に戻したときに、それぞれがどう感じているかということを、公演形式とワークショップ形式と両方でやってみたいと思ったのが「インクルーシブ・ピクニック」です。例えば、「自然」に対して、プロジェクトメンバーで話した際、東京育ちのメンバーは、東長寺の石のグリッドから生えている雑草を見て「自然だ」と言うのに対し、地方出身のメンバーは「自然にしては小さすぎますよ」と返したことがあったんです。「自然って汚いですよ」「森なんてだいたい整備されているでしょ」と。おそらく「wild」、「自然」と言っているものも所詮、その人の体験に近いところで判断しているんです。いわゆる障がいがないとされている人たちでも、こんなに感じ方が違うのだから、いろいろな知覚的な特性を持っている人が関わってきたら、わたしたちが自然と言っているものの捉え方、知覚の仕方、その人にしかわからない向き合い方や表現の仕方があるはずです。そのあたりの揺らぎ、感覚のきわを共有できるとよいなと思い、企画していたんです。企画当初には、「本公演の『きわにたつ』とプレイベントの『きわにふれる』『インクルーシブ・ピクニック』はどう関係しているんですか?』と、スタッフからも言われました。わたしのなかで説明できていることもできないこともあって、今、そこに完璧なフレームがあるわけではありません。でも、今回、こうして芹沢さんにお話を伺う際、双方向から向かわないと、揺さぶりとして何かが出てこないだろうなと思ったのと同じように、両方をやらないと、何かが見えてこない、体験できないことがあるのではないかとは思っています。
芹沢:僕は、きわプロジェクトの大きな方向性みたいなものに関して、共感というか、わかったような気になっているんです。P3ができた当時、新宿で考えれば都市的な中心は新宿三丁目くらいまでで、東長寺のロケーションは新宿でも四ツ谷でもない辺境と認識していました。しかし、辺境でしか新しいものは生まれない。境界であるからこその自由があったと思うんです。あそこで活動しながら、そんなことを感じていました。
4-3. 階段を降りる
向井:確かにそうですね。当時、東長寺の展示に対しては、行こうとする意思がすごく強かったです。アクセスが悪いわけではないのに、いわゆる美術館とはちょっと違うところにわざわざ行くという感覚がありました。話が飛びますが、ドイツに行ってから、あるゲイの友人が「ゲイカルチャーのある場所は、日常から、ある階段を降りて、別の空間のなかに入っていくようなものだ」というような話をしてくれたんですね。普段からその場所は実際にあるのに、昼間では見えない空間が広がっていると。その話を聞いてから、街にいて、どこかの階段を降りていった先には、日常の世界では見えていないけれど、実際にあるはずのものの光景が広がっている。現実とはつながっているけれど、階段を降りていくと、ふと切り替わり、異界のように存在している。わたしのなかで、東長寺が「光景」ということとすごくつながっているというお話をしましたが、今思えば、あのときの講堂もそういった場所だったと思います。日常からパサージュのように階段を降りていったときに、境界上の世界があった。それを残像的に自分のなかで体験として享受していたような感じがあります。
それから、もう一つお話ししたいエピソードとして、私のなかで、1990年ごろの東長寺での「MANDALA 天と地を結ぶ色とかたち」展というチベット仏教を紹介した展覧会がものすごく強烈に残っているんです。

1990年、P3、東長寺講堂
色鮮やかな五色の砂で繊細な形象を積み重ねていく「砂絵マンダラ」も展示されていて、その作法などもマルチスライドで紹介されていました。当時、展示の際に、芹沢さんがお話しくださったのか記憶が曖昧なのですが「お坊さまたちが新宿の街を見て『こんなにネオンがあって光を持っているのに、あなたたちは、なぜ我々を呼ぶ必要があるのか』とおっしゃった」というようなことを伺った記憶があるんです。東長寺の展示空間で、実際に観客やパフォーマンスをしている人の姿も見ていて多重に重なっているのですが、その場にいた人だけでなく、いなかった人もそこに「ある」というか……。人がいるときもあるし、インスタレーションや展示物だけのときにも、東長寺での光景のなかには、いつも人の影を多重に見たような、個人的体験があったんです。だから、お坊さまの話を聞いたときに、光や映像みたいなものというのは、何かを顕在化するための材料というか術なのかもしれないなと思いました。
4-4. 命がけの移動ー新しい旅の意識
芹沢:向井さんもおっしゃっていましたが、今、こういう世界になって、移動することが制限されてしまいましたよね。でもそれは本当に悪いことだけなのかと、考えてみたんです。例えば、飲みに行くときなんかでも、半分冗談ではあるものの、誰と面と向かって会おうかと選ぶわけです。僕は高齢者だし、タバコも吸うから、「命がけで飲みに来ている」「命がけでお前に会いに来ている」という感覚になる。旅をすることも、昔はみんな命がけの感覚だったんです。それが、あまりにもイージーに、インスタントに移動ができたり、人に会えたりできるようになりました。それはとても素敵な世界ではありましたが、今、その世界が制限され、そこにある種の貴重ささえ感じるようになりました。これは「命を張ってでもやるべきこと」なのか? こういう思考回路は、しばらく使ってこなかった。「止むに止まれず訪れたい」とか「死ぬまでに行ってみたい」と思う欲求や、「あの人には絶対に会っておきたい」と思う何か。そういう、今までの我々に欠けていたというか、忘れたふりをしていた命の危険とか死に対する意識が、日常のなかに現れる。このことが、創造的に働いていく可能性もあるような気もしているんですね。
「精神とランドスケープ」のシリーズにも選びましたが、アニー・ディラード *5 に『ティンカー・クリークのほとりで』という本があります。散歩をしながら、ティンカー・クリークのディテールや細部をディープな形で綴っていった一冊です。

1991年、めるくまーる社
僕は、これも一つの立派なトラベローグだと思うんです。ヘンリー・デイヴィッド・ソロー *6 のように、ある場所だけを歩き続けることで、世界との関係を深めていくこともできる。広く飛び回るんじゃなくて、深く潜っていく。たかだか、100年、200年前までは、みんなそういうことに長けていたはずなのに、今は不慣れになってしまった。でも、これからの世界では、そういう新しい旅の意識が生まれてくる可能性もあるのではないかと思っています。
///
*1 エドワード・T・ホール(Edward Twitchell Hall, Jr.、1914年~2009年)
アメリカ出身の文化人類学者。社会学、言語学、動物学等にも精通したコミュニケーション論で知られる。著書『かくれた次元』では、人間の「密接距離」「個体距離」「社会距離」「公衆距離」について論じている。
*2 イーフー・トゥアン(Yi-Fu Tuan、1930年~2022年)
中国系アメリカ人の地理学者。70年代を中心に現象地理学の分野で活躍し、第一人者として知られる。
*3 伊藤亜紗(1979年~)
東京都出身の美学者。2013年より東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授を務め、障害を通して、人間の身体のあり方を研究している。
*4 目[mé]
アーティストの荒神明香とディレクターの南川憲二、インストーラーの増井宏文を中心に、2012年に結成された現代アートチーム。主に、インスタレーションの形態をとった作品を発表している。
*5 アニー・ディラード(Aniie Dillard、1945年~)
アメリカ出身のエッセイスト。代表作『ティンカー・クリークのほとりで』は、自然環境をめぐるノンフィクション文学であり、ピュリッツァー賞を受賞している。
*6 ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(Henry David Thoreau、1817年~1862年5月6日)
アメリカ出身の作家・思想家。代表作である『ウォールデン 森の生活』は160年以上前に刊行されたにもかかわらず、今なお世界中で読まれ続けている。
///
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
