
きわダイアローグ01 芹沢高志×向井知子 1/4
1.
対話的な旅ー「精神とランドスケープ」の背景
自分が変わるから環境も変わるし、環境が変わるから自分も変わっていく
///
向井:芹沢さんは元々、建築やランドスケープといった分野を専門とされていますよね。P3 art and environment(以下P3)が東長寺にできた当初、ご自身の専門の枠に収まらない、専門領域の境界上のことをやっている方がいると、芹沢さんのことを知りました。そして、その方が設立に関わられた「アートとサイエンスを横断する」、いわゆる狭義のアートではないものを発信するP3というスペースは、強い印象として残りました。とても個人的なことになりますが、1989年にP3が立ち上がったとき、わたし自身は空間の勉強をしており、大学3年生でした。そのあとドイツに留学してしまったので、P3の企画を見ていたのは、設立初期と後期にあたります。ドイツではデジタルバウハウスとよばれたケルン・メディア芸術大学 大学院 *1 に入りましたけれど、ここは、アート、サイエンス、テクノロジーの横断を理念として、1990年に創立されたドイツ最初のメディア芸術大学でした。

13世紀に建てられたオーバーシュトルツェンハウス内の様子
学生も教員もみなが横断性やデジタルの意味を手探りしていた頃で、わたし自身、「境界」「はざま」「間」といった概念を意識しながら、映像メディアを通して、空間と身体的体験を探り始めた時期でした。その前後に、P3での展示や企画を体験していたということになります。P3は、自分がものをつくっていく上で、自覚未満だったものを自分の中でいろいろ経験しているときに、見ていた、体験していた場所でした。きわプロジェクトのメンバーの一人であるスヴェン・ヒルシュは、在学時期は重ならないですが、物理学を修めたあとに同大学院に入学しており、サイエンスとアートの狭間で、揺さぶられていた人です。我々は90年代、デジタルというものが生まれてきた頃に大学院に通っていたのですが、あの頃を起点に変化していった身体性や思考方法について、当時は感ずることはあってもまだ言語化できなかった感触といったものが、今の自分たち自身のなかでもう少し明確に自覚できるようになった部分があります。今日、アートとサイエンスの横断みたいなことは、あたりまえのように言いますけれども、改めて、芹沢さんに、当時のお話を伺うとともに、今の時代をどう考えていらっしゃるのか、世代を超えてブリッジし、今についてを考えたいと思っています。
芹沢:では、P3がどういうふうにつくられていったのかということから、話を始めようと思います。P3が開かれたのは、1989年。そもそもは、「東長寺の新伽藍を建てるプロジェクトに加わってほしい」と言われたことがきっかけです。1985年くらいから4、5年かけて設計や、一体そこで何をやっていくのかを考えていきました。
当時、僕はいくつかの洋書を読んでおり、出版してくれるところがあった場合には、翻訳出版という形を取らせてもらっていました。翻訳を始めたのは、正直に言うと、英語が堪能だからではなく、自分の勉強のためだったんですね。翻訳ほど、一冊の本を最初から熟読していくという経験というのはそんなにないじゃないですか。今思えば、自分の人生の中期に、そういう形を取って本を熟読していったことはすごく重要なことだったと思います。そんなことをしているなか、めるくまーるという出版社と、「新しい翻訳シリーズをつくってみよう」という話になりました。それが実は、P3をつくっていく時期、過程とダブっているんですね。そこで、戦略的な意味も含め、P3のコンセプトと同じ「精神とランドスケープ」という名前のシリーズにしました。いざ具体的な空間ができたときにも基本テーマとして「精神とランドスケープ」と置けば、自分のやっていこうとしている関心みたいなものが一本通るというか、求心力が得られると思ったんです。
ではなぜ「精神とランドスケープ」というふうに考えてきたか。80年代の後半頃は、日本もバブル経済で、社会全体が浮かれて熱を持って進んでいったと思うんです。バブル時代に、世界中を飛び回る「ジェット族」という言い方があったことからもわかるように、とにかくジェット機に乗って、物理的に世界を飛び回ることが先端を行っているイメージがあったような気がします。即物的と言えば失礼だけれど、あまり精神性といったこととは関係なく、移動によって新しい世界が切り拓かれていくんだという力ずくの旅みたいなことができるようになった。それで、パリやニューヨークへ行き、「こんなおしゃれな場所があった」とか「こんなおいしいレストランがあった」というような旅行記や旅行案内、ルポみたいなものをいろんな人が書いていました。
僕自身が学生だった60年代から70年代の始め頃は、世界的には、ニューエイジものやヒッピー文化などの影響が大きかったんです。その頃の日本は、80〜90年代に比べると、貧しいというか、そんなにお金があるわけではありませんでした。だから、当時は、世界中を飛び回るというより、バックパック一つで世界を放浪したり、あるいは、ヒッピーのようなライフスタイルをとったり。60年代の終わりくらいだと政治はラディカルで、芸術ではさまざまなアヴァンギャルドなものが一気に出てくるような時代でした。その頃の旅行記は、ややもすると極端かもしれないけれど、精神世界ものというか、ニューエイジ的な文脈で書かれているものが多く、あらかたは辺境、チベットやインド、アフリカ、アメリカン・ネイティブの世界を旅して、記述していくようなものが多かったんです。旅に出かける前から、ある種の精神的な見方で世界を見ていて、聖地のようなところに出かけていって、自分の内面の世界を「やっぱりそうだったじゃないか」と確認していくような旅の仕方でした。そういった「精神的な旅」には、80〜90年代の「物理的な旅」と、正反対の同じさがあると思うんです。80〜90年代には、物理的な移動によって、ニューヨークってこんなところ、パリってこんなところという確認作業を行なっている。あるいは、南米の珍しい街など、初めて見る風景に肉体を運んで行って、冒険とまでは言わないけれど、かなりマッチョな旅をしていたわけです。60〜70年代も、80〜90年代もそういった内容の旅行記的な本が多く、僕自身の旅を思い出すと、ちょっと違うんじゃないかという感覚がすごくありました。自分とランドスケープというか、自分以外の外界との関係は、自分の内面世界から一方的に外界を見るとか、外界が絶対的に確立していて一方的に享受していくとか、そういうものではないと感じたんです(ここでの「ランドスケープ」は「環境」「社会」とも言えると思います)。やはり、対話みたいなものが、旅の一番の醍醐味なのではないか?と。旅というのは、自分が変われれば環境も変わるし、環境が変わることで自分も変わっていくという、終わりのないエンドレスな活動。自分の見方が変わることで風景の意味も変わってくるし、そうやって解釈した風景がまた自分にこだまして、自分がさらに考え方を変えたり、見方を変えたり……という、キャッチボールのようなものが、旅の歓びだったり、驚きだったり、価値であるように思ったんです。そういった旅行記はあるのだろうかと話をしていたタイミングで、今も仲の良い編集者の女性が、ピーター・マシーセン*2 。の『雪豹』という本がまだ訳されていないと教えてくれた。
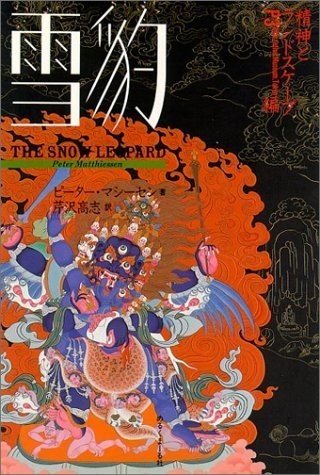
1988年、めるくまーる社
この本はヒッピー・ジェネレーションの頃のもので、チベットの宿には必ず誰かの読み古しが置いてあるくらい、世界的なベストセラーでした。その本について、僕は、ゴリゴリに固まった精神世界ものの旅行記だろうと思っていたので、彼女に「名前はよく聞くけれど、そんなにいい本なの?」と聞いたわけです。そうしたら「すごくいい、気に入ると思うよ」と言われました。
『雪豹』は、奥さんであるデボラを癌で亡くしたマシーセンが、旅に出るところから始まります。奥さんとの思い出や悲しみを背負い込んでいるマシーセンに、世界的な動物学者・動物行動学者である親友のジョージ・B・シャラー*3 が、ブルーシープの生態調査のためチベットへ行くので一緒に行こうと誘います。マシーセンはチベット仏教などにも興味を持っており、当時ではまだ行くのが難しかったネパールやチベットへの旅ということで魅了されたんですね。特に彼の心を動かしたのは、幻の雪豹(スノーレオパード)というネコ科の動物が住んでおり、それを野生で見られるかもしれないということ。そこで、シャラーに同行して、クリスタル・マウンテンという聖なる山へ向かう過酷な旅を延々としていくわけです。『雪豹』では、風景や動植物、先住民たちとの会話や、そこで感じた驚き、同行したシェルパとのやり取り、それからブルーシープの生態などが淡々と記述されていく。別に推理小説ではないから、物語の最後まで話しますが、最終的に、雪豹の足跡までは発見したものの、雪豹を見ることはできなかったんです。つまり、マシーセンは、自分が追い求めていた目標には行き着かないまま帰ってくるわけです。この本に書かれていることは、ドキュメンタリーだったのか、創作的な要素も入っているのかは全くわからないけれど、夢と幻の要素がスーッと入りつつも、体裁としてはものすごく淡々と書かれた山歩きの日記です。ただ、例えば、すごく青い空とか、珍しい植物や動物といったものに出会うことで、ふっと心が洗われるようになった瞬間、マシーセンの心には急にデボラとの思い出が浮かんできたりする。きれいに、リニアに、何かことが進んでいくわけではなく、その旅自体が行ったり来たり、揺れ動きつつ、風景と出会っていくことで自分の気持ちもどんどんどんどん変わっていく。日々変わっていく風景に呼応して、気持ちが変化し、元々の最大の目標であった雪豹に出会えなくても、最終的に彼はそれを受容してしまうんですね。この本を読んで、「僕の旅の仕方は、こんなふうな感じだよなあ」と思ったんです。
めるくまーる社では、当時、ロバート・M・パーシグ *4 という人の『禅とオートバイ修理技術』という、これもヒッピー世代にとってはバイブルのような本を新訳で出すという話が進んでいました。
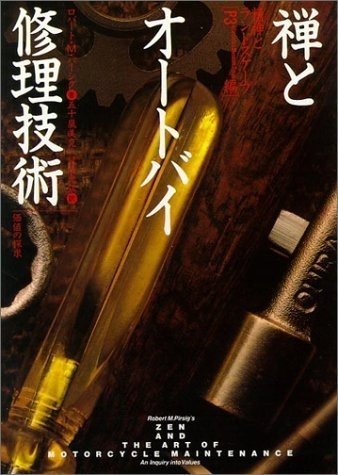
1990年、めるくまーる社
それで、『禅とオートバイ修理技術』と、この『雪豹』を中核に、精神と物理的なランドスケープとをつないでいくような旅の本が集められるのではないかという構想を持って、本をセレクトしていきました。そうして、「精神とランドスケープ」というシリーズをつくる作業と、P3の設計を同時進行で進めていったんです。このシリーズをつくることによって、旅を通して、精神と外界との間の絶え間ない揺らぎを記述していく「トラベローグ」のような形式の、大きな可能性を知りました。自分の手法というと大げさですが、そのトラベローグ的な手法が、後年、ビエンナーレやトリエンナーレなど、地域で開かれるアートプロジェクトをつくっていく上でも基本になっていきました。ランドスケープと自分の精神のダイアローグを、どのようなかたちでプロジェクトに反映させていくのかということが、この頃から自分の主要な活動テーマになっていったのです。
///
*1 ケルン・メディア芸術大学
すべてのオーディオ・ビジュアル・メディア領域を専門とする、ドイツで最初のメディア芸術大学。アート、サイエンス、デジタルテクノロジーを横断する、21世紀のデジタル・バウハウスとして、1990年、ドイツ・ケルン市に創立。
*2 ピーター・マシーセン
1927年生まれ、アメリカ出身の小説家・ナチュラリスト。代表作である『雪豹』は、全米図書賞を受賞している。
*3 ジョージ・B・シャラー
1933年生まれ、ドイツ系アメリカ人の哺乳類学者・生物学者。野生動物の生活を研究し続け、それらをまとめた論文や著書は世界中で翻訳されている。
*4 ロバート・M・パーシグ
1929年生まれ、アメリカ出身の小説家・哲学者。代表作として『禅とオートバイ技術』、‟Lila: An Inquiry into Morals”(未翻訳)など。
///
芹沢高志(せりざわたかし)
P3 art and environment統合ディレクター
1989年、P3 art and environmentを設立。現代美術、環境計画分野で数々のプロジェクトを展開。「横浜トリエンナーレ2005」、「混浴温泉世界」、「さいたまトリエンナーレ2016」など、様々な地域のアートプロジェクトに関わる。
向井知子(むかいともこ)
きわプロジェクト・クリエイティブディレクター、映像空間演出
日々の暮らしの延長上に、思索の空間づくりを展開。国内外の歴史文化的拠点での映像空間演出、美術館等の映像展示デザイン、舞台の映像制作等に従事。公共空間の演出に、東京国立博物館、谷中「柏湯通り」、防府天満宮、一の坂川(山口)、聖ゲルトゥルトゥ教会(ドイツ)他。
///
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
