
アイスランド旅行記㉖さらば、愛しきStöðvarfjörður
前回までのあらすじ
「10代のうちにオーロラを見る」という夢を叶えた夜。アイスランドに来るまでに色々な葛藤があって、着いてからもハプニングに見舞われたけれど、一番の目的を果たすことが出来た。
今回は、もうすぐ終わりを迎えるワークキャンプの愛しい日常を振り返りたい。
幻の温水プールと、私達の幸せ
ある日の朝、リーダーから「今日は近くにある温水プールに連れて行ってもらえる」という情報がもたらされた。
以前書いた通り、ここではシャワーが2日に一度しか浴びられなかった(1日に出るお湯の量が決まっているため)こともあり、みんなとても喜んでいた。アイスランドには、地熱を利用した温水プールがあちこちにある。中でもブルーラグーンという世界最大の露天風呂はレイキャビクからアクセス出来る場所にあり、とても有名だが、私は日程や予算の関係で諦めていた。ブルーラグーンと比べればもちろん小規模だが、「アイスランドの温泉がここで体験出来るなんてラッキー!」と思った。
しかし、時間になって家の前に到着したのは、バスというには小さすぎる車で、全員乗ることが出来なかった。何人かに絞れば行くことも出来たはずだが、私たちは全員行かないという選択をしたのだった。
今振り返ってみると、せっかく手段があるのに全員諦めたのはナンセンスな気がするし、日本にいる両親にこの話をしたら「えー?なにそれ。」と言われてしまった。だけど、当時の私達は「全員で行けないなら別に良いや、それより家の中でみんなで楽しいことをしていたい。」という気持ちに、自然となっていたのだ。
これは、すごく特別なことだと思う。
「とにかく色々な場所に出かけて、様々な経験をして、知見を広げたい。」という意気込みで各々参加した私達が、「みんなで一緒にいられるだけで楽しいし幸せ」という価値を見出していたということだからだ。


「sequence(シークエンス)」。
暇な時間は、みんなでトランプをしたり、お喋りをしたりして過ごしていた。そんな時間が、とてつもなく愛おしくて。


(私は未成年だったのでお酒は飲めず)

海外組にも「Demon Killer!」と喜ばれた。


オーシャンビューならぬレイクビューの窓からは、心地よい日光。

朝サッカー⚽️
またある日は、朝食の後、リーダーの一声でサッカーコートに出かけた。

子供がたくさん住んでいるようには見えないこの村だが、結構立派なサッカーコートが近くにあったので驚いた。もちろん、ちゃんとした試合が出来るような物ではないが、遊びでやるには十分の広さだった。特に申請などは要らないようだった(定かではない)。

私は、サッカーボールを蹴るなんて小学校の体育以来だったが、上手も下手も関係なくただただ楽しい時間を過ごした。
少年サッカーなど、サッカーチームの練習のためではなく、娯楽のためのサッカーコートがあるというのも、海外らしいなと感じた。


ペンキ塗りとちょっとした事件簿
さて、本業のボランティア活動はどうなっているのか。
キャンプ前半は家の大掃除に時間を費やしてしまったが、後半はリノベーション的なことも行った。
これからも、各国からのボランティア参加者が活動の拠点として寝泊まりする家。彼らのために、この家をより素敵な場所にするのが私たちの「ボランティア活動」だ。


この頃、もう一軒で生活していたチームから、フランス人の女性が一人こちらの家に来ることになった。
「途中で移ることも出来る」と言われていたが、実際に移動して作業をしたのは彼女だけだったと記憶している。
彼女は、タフなメンバーが揃った別チームの中でも小柄だったので、こちらのチームに移ってきたのもなんとなくわかるような気がした。別チームの方に行った日本人の友達とLINEで情報交換していたのだが、初日から「床の木を剥がした」と言っていたので、かなりハードだったのだろう。
しかし彼女は、日本人と韓国人で構成されたこちらのチームのワークもあまり合わないようだった。ペンキ塗りをしていても、「あなたの担当はここからここまで」と言われたエリアをやり終える前に飽きて辞めてしまう。周りのメンバーが黙々と作業をしていても、飽きたら放置。単純作業が嫌だったのか、お国柄なのかは分からないが、真面目とは言えなかった。
「任されたことは自分で最後までやり遂げる」という意識が強かった日本人の私達も、途中から参加した彼女がもっと居心地良く過ごせるように努力をするべきだったと今は思う。彼女は終始不満げな顔をして、1日で戻ってしまった。苦い記憶である。



最終日
最後の夜は、家の周りを動画と写真に収めた。
たった10日間の滞在だったけれど、食事を作って洗濯機を回して…この家はアイスランドでの生活の全てだった。

洗濯といえば、この家の洗濯機は地下にあった。海外ドラマでよく見る、地下室というやつだ。
一度外に出て、この庭の横にある小さな階段を降りていく。洗濯の時間というのは特に設けられておらず、各自好きな時に洗濯機を回していた。
私は、以前紹介した同い年の日本人の女の子、アナと2人で使うことが多かった。持参した洗濯ネットに自分の服を入れ、旅行用の粉末洗剤を入れてスイッチオン。そして、また外に出る。

他愛もない話をしながら、外の階段を上る。家に戻ると、お姉さん・お兄さん達がソファでくつろいでいて、「あ、洗濯機回してきたんだね〜」「終わったら次使わせて〜」というような会話が始まる。
最年少の私たちは、何かと可愛がってもらっていたし、もう大家族のような感覚になっていた。当然、別れが寂しい。



私は二段ベッドの上で寝ていたが、ちょうどその高さに小さな窓があった。この窓をぼんやり眺めながら眠りにつくのが好きだった。
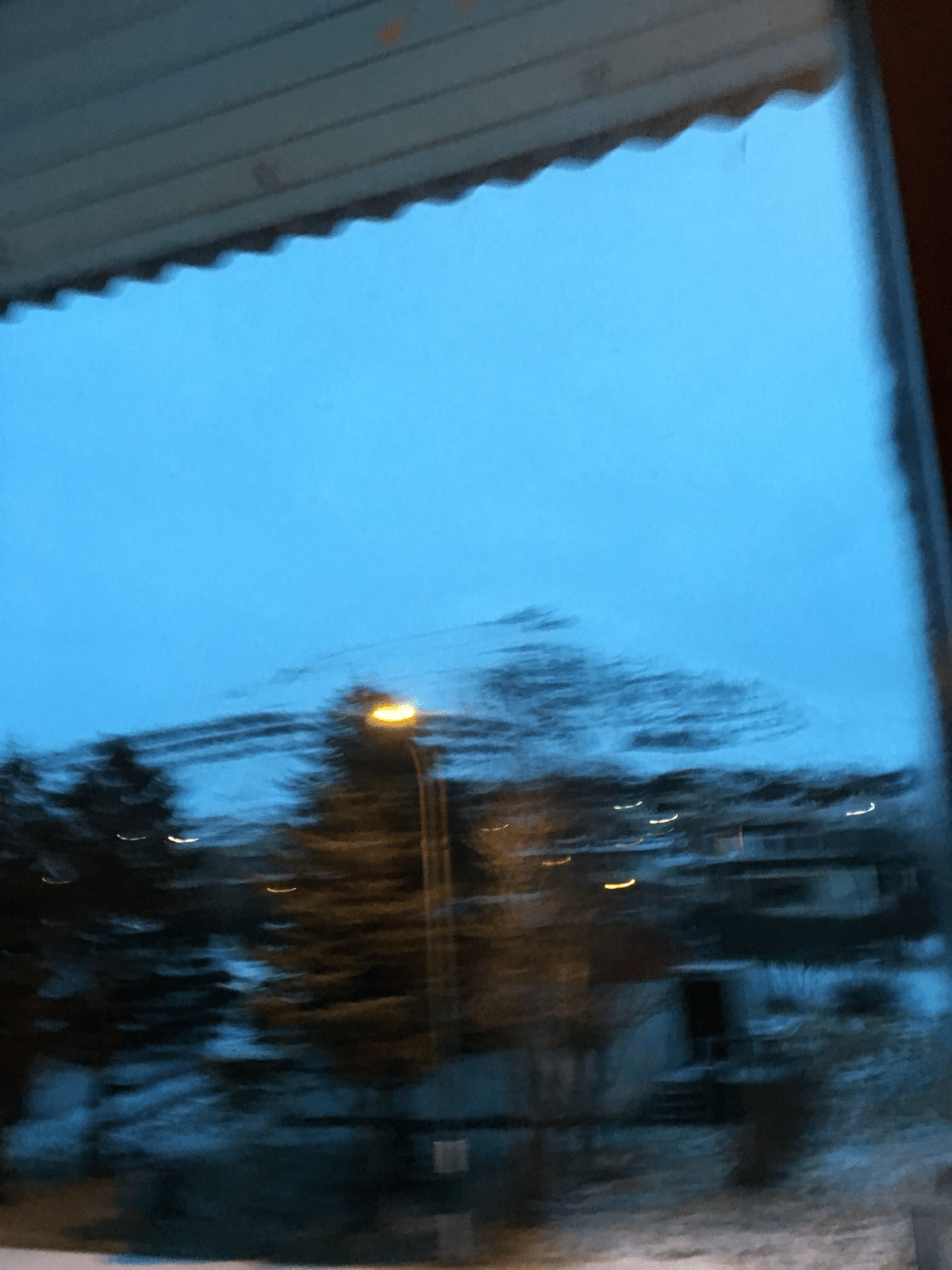
この旅でよく聴いていたのは、スピッツの「三日月ロックその3」という曲。共同生活では、イヤホンで音楽を聴くという時間は無かったけれど、唯一1人の時間となる寝る直前のベッドの上で、一日一回くらい聴いていた。
この曲は別に旅がテーマの曲でも何でもないが、なんとなくこの時の感情にハマる曲だった。歌詞がどうとか、背中を押されるとかでは全然なく、単純にハマったというだけ。
今もこの曲を聴くと、アイスランドでの生活が蘇る。
三日月ロック その3を聴きながら、夜空に浮かぶ月を見て、「あの月は日本でも同じなんだよな。」と思った。この素晴らしい日々が終わって日常に戻っても、アイスランドと同じ月が浮かんでいると思えばなんとかやっていけそうな気がした。
次回、Stöðvarfjörðurに別れを告げて、再びリングロードへ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
