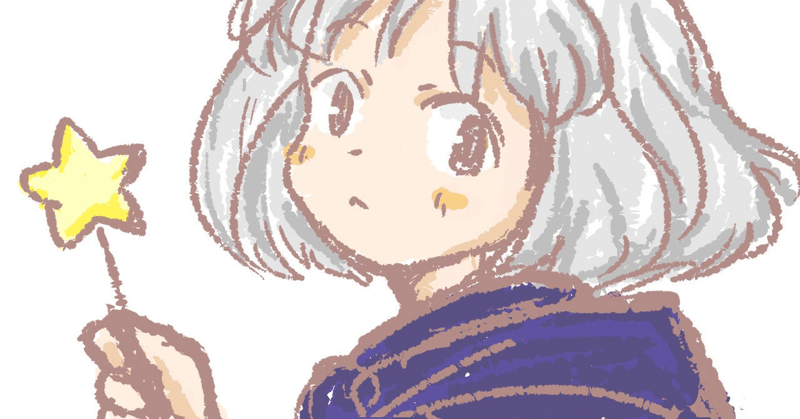
ガーリーな魔法少女
創作短編(8182字)。お読みいただける全ての読者様に幸あれ。
その風は、ヒラヒラのスカート1枚では身を守れない程に冷たかった。6チャンネルの可愛い気象予報士は予想最高気温が17℃だと陽気な声で伝えていたが、流石に朝はまだ寒い。買ったばかりのミルクティーで右手の暖を取り、左手でお尻を押さえながら学校前の歩道橋を昇る。
「おっはよー。こりゃまた攻めたねえ」
私の気分と真逆のテンションで話しかける夏美。今日もマスタード色のライトダウンジャケットとロールアップされたデニムパンツ、履き古したスニーカーが真っ先に目に留まる。
「当然よ。私は1軍になりたいんだから」
「でも寒いっしょ? 3月でミニスカはまだ早いって」
“おしゃれは我慢”とは言い得て妙で、自分を可愛く見せる為なら寒さに耐えるなど造作もないことだ。暖かくなるまでロングスカートやパンツスタイルで凌ぐ夏美のような人は3軍に落ちぶれる運命にある。まあ、私も人のことを言えないのだが。
***
女性のファッションセンスが天井までインフレした20XX年。大学、特に女子大には『おしゃれカースト』なるピラミッドがどのキャンパスにも存在していた。1軍は読者モデルやインスタグラマー、アパレル店員などのおしゃれステータスを当たり前のように持っており、2軍はコミュニケーションを巧みに駆使して1軍と戦略的に仲良くなり、必要以上に褒めたりコーデを丸パクリする質の悪い奴ら。
私はそのどちらにも入れない最下層の3軍だが、約1年もの間、毎日私服で通学しているうちにコーデの組み方の基本は身に付いていた。まず、何でも良いからベースとなる服を1点決める。春の訪れを感じるので淡い色のフレアスカートはどうか。パステルピンクの42センチ丈か、ライトベージュの56センチ丈の二択まで絞る。今日の気温なら1軍の奴らはきっと攻めてくる。思い切ってミニ丈にしよう。
次に、そのベース服に最適なトップスを合わせる。スカートが横に広がるので、トップスは逆に締まるアイテムでAラインを強調させるべきだろう。いつも悩まされるのがカラーバランス。ミニスカのピンクを目立たせるにはトップスは白系の地味目にすべきなのだろうが、締まる白のトップスとなるとタートルネックのニットか、Tシャツしか持っていない。前者は冬物だし、後者はカジュアルすぎる。どうしよう、なかなか決まらない。まだ靴下と靴と鞄、そしてアクセサリーの選定が残っているというのに。やばたにえん、ぴえん。
1時間にも及ぶ100着以上との格闘の末、ようやく着る服が決まる。冷蔵庫から水素水のパウチを取り出し、三口含んで疲弊しきった心身を癒す。これが毎朝待っているのだ。制服通学だった中学・高校がいかに生温かったかを思い知る。
***
「流石にそこまでやったらあざとすぎじゃね?」
「いや、デコルテは目立たせてナンボでしょ」
歩道橋からキャンパスまでの100m、私と夏美は鎖骨にチークを塗るか否かで軽く議論を交わしながら歩いていた。話しながらも目は慌ただしく左右を向け、登校する女子たちのファッションをチェックする。今のところミニ丈は一人も見当たらないし、黒か暖色系のビビッドばかりでパステルカラーすら皆無。3軍の中では上位だと自分に言い聞かせつつ、1限の教室に到着。前列左を陣取る数少ない1軍と、取り囲むように立って彼女らに媚びへつらう2軍の面々を後列から遠目で観察する。
「なんか1軍、手を抜いてね?」
夏美がボソッと言った。ジャケットとパンツのセットアップを着る者や、オールインワン1着で済ませる者、黒ワンピだけでレイヤードすらしない者。私は愕然とした。これは手を抜いているのではなく、むしろ『引き算の美学』だ。セットアップはトレンドのくすみグリーンだし、オールインワンは世界的に有名なブランドの新作だし、ワンピースはベルトで締めているのでより綺麗なAラインを作れる。シンプルでもポイントをしっかり押さえれば大人のおしゃれになる。いつもこうだ。私がいくら時間をかけて悩みまくったコーデも、1軍のレベチなセンスには到底敵わない。
***
家に帰るなりインスタのマイページをチェックする。67から一向に増えないフォロワー数。いいねが36しか付いていない今朝UPしたミニスカ。この調子ではインフルエンサーもブランドプロデューサーも夢のまた夢だ。
『明日だけど、5時に品川駅中央改札で良い?』
腹筋52回目、スポブラとメディキュットが汗で蒸れ始める頃に山内君からLINEが来た。ホワイトデーの明日、水族館に行く約束をしていたことを思い出す。また1時間もかけて着る服を選ばなければならないのか。一番の苦痛は、悩みに悩んでコーデを決めたところで、山内君は何の反応も示さないということ。「似合っているね」なんて褒めてくれたのは昨年夏のおうちデートでのTシャツ、短パン姿が最後だ。別にイルカやクラゲが好きなわけでも無いし、明日のデートに全く価値を見いだせない自分が居る。
いや、そもそもこの人生とは何なのか。おしゃれ戦争に敗北しっぱなしのキャンパスライフ。フォロワーの増えないインスタ。誰にも認めてもらえない私のファッション。洋服を買いまくり薄くなる財布。報われない努力。
……もういいや。何も考えず加湿器のスイッチを入れ、ホットアイマスクを装着し眠りにつく。
***
目を覚ますと、私は魔法少女になっていた。
白とピンクのフリル付きワンピース。大きいリボンで2箇所結われた髪。そして極めつけは右手に持っているステッキ。これが私? 嘘だ。もこもこの部屋着で寝ていたはずなのに。
「春香ちゃんにファッションの危機を救って欲しいピヨ!」
すぐ横で見知らぬ妖精が宙を舞い、普通にしゃべっている。妖精というかヒヨコにしか見えないのだが。いずれにせよ今の状況を何一つ理解できない。
***
そもそもファッションの流行はどこから始まっているのかと、疑問に思ったことは無いだろうか。実は、世界中の魔法少女が集まるトレンド会議で決定、魔法で発信することで即座に流行らせていたのである。
「純粋な乙女心で常に可愛いを追求し続ける女の子だけが魔法少女になれるピヨ!」
だからと言って私は別に魔法少女になりたいとは思っていない。貴方が勝手に変身させただけである。
アイボリーと名乗る妖精は、そんな私のツッコミも無視して説明を続ける。おしゃれな魔法少女がファッションの流行を生み出すという完成されたシステムが「魔女」の存在によって狂い始めているのだと言う。可愛いとは対極の思考を持つ魔女は、カジュアルやキレイめな洋服を魔法で全世界に発信してしまう。魔法少女がフリフリのスカートを永続的に流行らせ続けた一方で、2004年頃のデニムパンツや2008年前後のレギンス・トレンカ、2010年以降の黒タイツ、そして近年のロングスカートは魔女の仕業によるブームだったのである。
「ガーリーとカジュアルとキレイめが混在する現代のファッションはカオスだピヨ! 女の子は皆、可愛くなりたい気持ちを持っているのに、それを邪魔する魔女を絶対に許さないピヨ!」
アイボリーの訴えに私は共感し、考えを改めた。昨日の1軍のセットアップやオールインワンは、単に流行っているから受け入れられただけなのかもしれない。やはりミニスカを履いている私のセンスの方が正しい。そうとしか思えなくなってきた。
一緒に魔女を倒して欲しいというアイボリーのお願いに私は二つ返事でOKした。この世から魔女が居なくなり、カジュアルやキレイめな洋服が廃れてガーリー一辺倒の時代になれば、大学のおしゃれ戦争に勝利し1軍入りを果たすことも、その先のインフルエンサーになる夢さえも叶うかもしれない。
***
クローゼットから洋服を選ぶ作業がこんなにワクワクするのはいつ以来だろうか。私はアイボリーの眼差しを受けながら“ファッションの危機を救う”為の行動に出ていた。
「じゃあこれにしようかな」
ピンク色のフレアスカートが真っ白なローテーブルの上に置かれる。花柄と前面に付いた2つの大きなリボンが特徴である。
「可愛いピヨ! やっぱり春香ちゃん、センスあるピヨ!」
褒められるのも久しぶりの感覚だ。大学の奴らはレベルが高すぎて誰も私のファッションを評価してくれない。
「キラリ、シフォン、ペプラム、アントワープ!」
私はステッキをピンクのスカートに向けつつ、アイボリーに教わったばかりの呪文を唱える。
「これでOK。世界中のバイヤーがこのスカートを仕入れるようになるピヨ!」
3日後。私は大学の講義をサボり、開店直後のH&M、GU、グレイルを梯子した。どの店のマネキンも私の選んだスカートを履いてくれている。アイボリーの話は本当だった。
そのスカートを履く女子は日に日に増えていった。これが“魔法で流行らせる”現代の流行システム。魔女の作り出すカジュアル・キレイめブームをかき消すほどのガーリーアイテムを流行らせることが今の私の使命だ。それを永続的に実現できれば、魔女のほうから降参する未来が待っているかもしれない。
「まあ、最初から上手くは行かないピヨ」
リボン付きフレアスカートのブームはものの3週間で終焉を迎えた。時期を同じくして魔女が水色のパーカーを流行らせていたのは誤算だった。水色にピンクが合わないのは猿でも分かる。
私はめげずに、今度は袖レースの白いブラウスを選択。
「リボンが付いていないけど大丈夫ピヨ?」
アイボリーも積極的に意見を出してくれるが、引き算の美学も意識して選んだので、迷わずこれに魔法をかける。
しかし、数日後に流行り始めたのは白は白でもテーパードパンツのほうだった。無論これも魔女の仕業。
その後もグレンチェックのワンピースやニットのフード付きポンチョ、紐ではなくピンクのリボンで結ばれたスニーカー、ハートビジューの付いたポシェットなど、洋服から小物までありとあらゆる可愛いアイテムを発信し続けるも、どの流行も長く続くことはなく、カジュアルとキレイめの二大勢力がガーリーを凌駕する現状は変わらなかった。
私はそれに屈することなく可愛い洋服を着続けた。インスタのフォロワー数は2桁のままだし、1軍から見た私は浮いているらしく、学内で悪目立ちもし始めた。それでも自分の思うおしゃれを貫き通した。
***
「このままだと、魔女と戦うことになるかもしれないピヨ……」
木の葉に含まれるクロロフィルがアントシアニンに変わり、空が移ろいやすくなる頃、アイボリーは最悪の事態を危惧し始めた。世界に点在する魔法少女たちの中には、ガーリーアイテムの流行を阻止する魔女の勢いが増してきていることに苛立ちを覚える者も少なくないという。紀元前から続く魔法の歴史において、魔法少女と魔女の衝突は珍しいことではなかった。
「戦争は絶対にダメだよ!」
その時の私はいつになく力強い言葉を発していたと思う。しかしこの半年間、私の信じる“可愛い”を発信し続けた結果、現状を打破できていないのも事実。かくなる上は――。
***
「赤いランプの下でお待ち下さい」
タートルネックの白いニットにミントグリーンのエプロン。「お姉さん」と呼びたくなるほど大人びた佇まいの女性店員が笑顔でそう言った。
「チャイティーラテのアイスをグランデ、シロップ少なめオールミルク氷少なめ」
バーカウンターで出来上がりを待つ私の耳に入る呪文のようなカスタマイズ。この声はと思い目を右に向けると案の定、夏美だった。
「おっはよー。春香は何頼んだの?」
私の次の次の順番を待つ夏美が少し大きめの声で聞いてくる。間に挟まれたスーツ姿の男性客に申し訳ないと思いつつ「アイスココアにホワイトモカシロップ追加した」と、聞こえる程度の小声で答える。
「それで、話って何?」
席に着くなり夏美は本題に入ろうとする。飲むのは二の次で、通ぶった注文をするのがメインの彼女らしい。
「トレンド会議に魔女を呼ぼうと思うの」
notデュエル、butディスカッション。単純かつ平和的な方法だと思った。
「魔女に諦めさせるの?」
「女の子の可愛くなりたい気持ちと、ガーリーファッションの魅力を精一杯伝えれば、分かってくれると思う」
「“可愛い”を理解してくれるかな。だって魔女でしょ?」
「意地でも分からせる。もうこれ以上、カジュアルやキレイめの洋服を流行らせないようにしてやる。世界中の女の子を洋服で可愛くしちゃうんだから」
打倒魔女に燃え、ボルテージが上昇していく私。
「春香、最近笑わなくなったよね」
心配の眼差しを私に向けながら夏美は言った。
「私も魔法戦争になるのは反対だよ。でも、今大学で春香たちがやっていることも『おしゃれ戦争』だよね」
ハッと我に返った。またしても私はおしゃれに対する快楽を失っていた。
「そういえば夏美って、どうして普段着はカジュアルなの? 撮影会では短いスカートばかり履いているじゃん」
ふと、コスプレが趣味の夏美に、素朴な疑問をぶつけた。
「……単純に恥ずかしいのと、過去のトラウマかな。小学校の時、男子にスカートめくられたことあるのよ」
スカートや生足を性的な目で見て、あまつさえ下着にまで興味を抱くなんて言語道断。子どもの悪戯も例外ではない。可愛いとエロの区別も付けられない男どものせいで、夏美のような“可愛いを我慢する”女子が増えているような気がする。
「でも、コスのイベントでは堂々と可愛く居られるのよ。同じようにフリフリの衣装を着ている子がたくさん居るし、写真を撮る男の人たちも節度を守ってくれるからね」
夏美を見て思うのは、女の子は総じて可愛くなりたい気持ちを潜在的に持っているのではないかということ。ミニスカを履く私のように分かりやすい人も居れば、夏美のように限られた環境下でのみ可愛くなれる女子、洋服よりも髪やメイクで可愛さをアピールする女子、アクセサリーや小物で部分的に可愛くするのが精一杯の女子、あるいは憧れるだけで一歩を踏み出せない女子。この世の全ての女子たちが安心しておしゃれに挑戦できるように、それを後押しする洋服を流行らせたい。やはり私の夢はインフルエンサーなのだと改めて気付く。
「いつか春香も、私みたいに心からおしゃれを楽しめるようになると良いね」
***
80まで数えて息を切らす。腹筋の自己最高記録を更新できたのは、とにかく無心でやったからだろうか。夜も深いが、会議に出すアイテムは一向に決まらない。机に向かい頭を抱えても何も思いつかないからとりあえず身体を動かしていた。
ファッション雑誌を5冊は読破したし、インスタグラマーのコーデもざっと100人は見たと思う。それでも分からない。魔法戦争を阻止できるか否かは、私の選ぶ洋服にかかっている。そのプレッシャーが余計に悩ませる。魔女を納得させる、世間が認める可愛いとは何なのか。
『明日なんだけど、5時に池袋駅中央改札で良い?』
山内君のLINEを既読無視してから3時間は経っただろうか。
『私の服で、今までで一番可愛いと思ったのは何?』
デートの待ち合わせ場所そっちのけで、質問を打ち込んだ。男性の意見も聞いてみたくなったのだ。
***
「いよいよピヨ。覚悟は出来ているピヨ?」
粉雪の舞い降りる渋谷。その上空にパステルピンクの結界を張ったアイボリーは神妙な面持ちで皆に問いかけた。
「私は大丈夫。みんなは?」
世界中から集められた魔法少女と妖精たちが頷く。
「深淵の森より生まれしものよ。汝の真なる力、目覚めよ……」
私はアイボリーに教えてもらった可愛くない呪文を唱える。半期に一度のトレンド会議は召喚の儀式から始まった。
「混沌とする衣の世界に一時の光を。召喚・魔女!」
私のステッキから放つ眩しい光線が、出現した魔女から沸き出る漆黒のオーラに包まれる。光と闇が共存する奇妙な光景だった。
「私を見て下さい。この服を流行らせたいです!」
自分の中では最上級の“可愛い”を身に纏った私は、圧に押されながらも精一杯の笑顔を魔女に見せた。
***
パステルピンクの壁とクッション、カラフルな5本のガーベラ、自分よりも大きな熊のぬいぐるみ。物心ついた時から部屋は可愛いもので溢れていたが、私の容姿はそれに見合わなかった。
7歳で既にトングみたいなアイロンで前髪をカールしていた。少しだけ可愛くなれたような気がした。
初めて母親のメイクポーチに手を出したのは小5の時。ローズ色に染まる頬と、マキアージュで塗った唇は今でも忘れられない。
洋服は元アイドルの母親が、オフショルのシャツやチュールスカートなど、ガーリーなものばかりを選んだ。スキニージーンズは一度も履かせてくれなかったが、今思えばお尻の大きめな私を気遣ってのことだった。そういえば水着もスカートタイプだった。
中学に入り自分でコーデをするようになってからも、母親のセンスをそのまま受け継いだ。友達の誰もが私の私服を褒めてくれた。顔の良し悪しは関係ない。洋服だけで“可愛い”を作れるのだ。
毎月家に届く『Seventeen』でマルキューの存在を知った。夏休み、初めてスクランブル交差点を渡った。憧れだった白いワンピースと麦わら帽子を身に纏って。川島海荷バージョンの『MK5』を聴きながら店内に入ると、夢の世界が広がっていた。
しかし、大学生になるとおしゃれで初めて敗北を知った。渋谷でガーリーアイテムを買えば頂点に立てると信じ続けた私はカルチャーショックを受けた。以後、洋服を買う際に渋谷だけは避けるようになったが、それで改善される問題でもなかった。私はおしゃれの迷子になっていた。
***
「こ、これは……」
目を丸くする魔女。眼前には初めて渋谷に行った日のコーデをそのまま再現する私の姿があった。3ヶ月前の山内君の返信も『白ワンピに麦わら帽子』だった。シンプルでありながら多くの女子が一度は着てみたいと憧れる定番のおしゃれは、男子にも確実に受けるものだった。
「時にはカジュアルでラフに、キレイめで背伸びすることも必要かもしれません。でもそれは着る人の気分やTPOの問題であって、わざわざ画一的に流行らせるメリットを私は感じないのです。どうか女の子の可愛くなりたい気持ちを邪魔しないで下さい」
***
「おっはよー。おお、パンツとは珍しいねえ」
今日も歩道橋の上でマスタード色の夏美が手を振る。
「だって寒いから下にレギンス履いているもん」
別にスカートに固執しなくてもワイドパンツとロングコートでヒップラインは隠せると知った2021年の冬。魔女と対峙した会議からもう2年も経過していた。
確かに私はあの時、魔法戦争を阻止した。魔女は金輪際、カジュアルもキレイめも流行らせないと誓ってくれた。しかしその後、白ワンピースと麦わら帽子が流行ることはただの一度も無かった。年明けに世界中に蔓延した未曽有のウイルスによって、私を含む全ての魔法少女が魔力を失ったのである。魔法に頼らず普通の女の子たちが自ら流行を作り出す、新しい時代の幕開けとなった。
どこの大学も『おしゃれカースト』は消滅していた。授業はオンラインがデフォになり、おしゃれを極める意味を失ったからである。そもそもおしゃれで競い合うという概念が、辛いことの多い今の時代に合わなくなった。かつて1軍や2軍だった女子たちは、私や夏美の居る3軍とLINEグループを作り、ファッションの情報交換をしてくれるようになった。
“おしゃれは我慢”は死語と化していた。特に冬は誰もが“健康第一”を意識し、おしゃれは機能性が重視され、暖かい洋服で身を守るのが当たり前になった。
そして私はカジュアルダウンや甘辛MIXなど、ガーリー過ぎずカジュアル過ぎずキレイ過ぎずという丁度良いラインを覚えた。それを意識したコーデをインスタにUPしてからはフォロワーも4桁に増えた。夢のインフルエンサーにまた一歩近付いた。
また渋谷にも度々行くようになった。今日はマルキューとヒカリエで買い物すると、山内君にLINEした。俺も付き合いたいと返ってきた。どういうわけか、カジュアルやキレイめな洋服を着ることが多くなってからは「似合っているね」と褒めてくれる回数も増えた。本当に変わっているよ、私の彼氏は。両親指でフリック入力する私の小さい胸は躍っていた。
『じゃあ5時にハチ公前で』
(Fin.)
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
