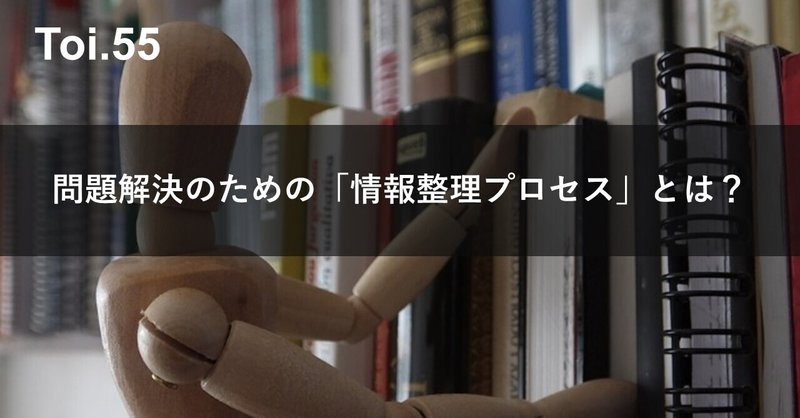
問題解決のための「情報整理プロセス」とは?
こんにちは。Kid.iAです。
突然ですが皆さんは「整理すること」は好きですか?(または苦手だったりしますか?)
以下のnote初投稿でも書いたのですが、自分の性格上複雑なこと(状況)というのがどうも苦手なようです。
それゆえに、複雑な情報を「分かりやすくすること」や「シンプルに整理すること」に強く興味を持っています。(複雑なことは複雑なまま扱った方がいいときもあるということは理解しています)
そんな私なのですが、10年以上前に読んでから大変参考にさせて頂いている「整理術」をテーマにした一冊の書籍があります。
その一冊とは、当時からアートディレクターとして多方面で活躍されていた佐藤可士和さんの書籍です。(書籍タイトル:佐藤可士和の超整理術)
毎回情報を軸とした問いを立て考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回の問いは「問題解決のための『情報整理プロセス』とは?」です。
佐藤氏は当該書籍の中で、問題を解決するためには大きく分けて「3つのプロセス」を踏む必要があると述べています。
今回はその3つのプロセスとは何なのかを、図を用いながら自分なりにまとめていければと思います。
1. 状況把握
一つ目は「状況把握」です。

問題の本質を突き止めるため、顧客がいる場合はヒアリングから始めます。
何かを考えるためには「情報」が不可欠ですよね。まずは情報を引き出して〇△□というふうに並べてみます。
情報が顧客の頭の中にしかないケースもあると思いますが、その場合は「見えないものを見えるようにする」というプロセス、つまり相手の「思考を情報化する」ところから始めます。
2. 視点導入
二つ目は「視点導入」です。

たくさんある情報を並び替える中で、重要度の低いものや重複しているものがあれば捨てていきます。結果、情報にプライオリティがつき重要なものだけを扱えるようになります。
さらに視点を導入することで情報の因果関係をはっきりさせます。誰かが問題と思っていたこともよくよく「その問題は何故起こるのか?」というような問いを続けていくと、その問題を起こす別の要因(≒真因)浮かび上がってきたりします。
そうすることで問題の本質=△が見えてきます。
3. 課題設定
三つ目は「課題設定」です。

見つけた問題の本質である△に、課題を設定して最終的に解決に導きます。
本質がポジティブなものである場合はそれを磨いて光らせたり、組み合わせたりして、埋もれていたものをアピールできるようにします。
ネガティブな本質が出てくるときもありますが、その場合は反転させるなどの発想の転換を行いネガティブをポジティブに変えることで問題解決に繋げることができます。
まとめ
最後に3つのプロセスをまとめて書きます。

個人的には上記プロセス内の
・情報の見える化を行うこと
・因果関係から本質を見つけること
この2点がプロセスを実行していく上でより大事な点なのではと日々の業務経験から思います。
見える化を行うことで共通言語化ができミスコミュニケーションが減らせますし、因果関係をしっかり押さえておけば見当違いのことに時間を割くことも防げます。
10年経った今でも本当に役に立つプロセスだと、まとめる中で改めて思いました。
もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️
今後の創作の活力になります。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
