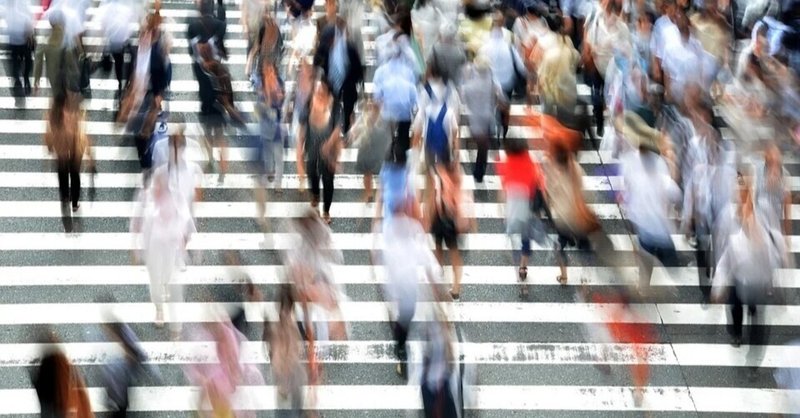
結局、行き着く先は「人」なのです。
今回は仕事の話となります。
一見さんに説明すると、現在の私は障害者福祉施設で障害を抱える方々の社会参加をお手伝いする仕事をしています。
ちょうど去年の5月1日に転職したので、丸一年、障害者福祉の現場で勤務したことになります。
…早いものです(・∀・)。
毎日、何かの壁にぶち当たっては、問題解決の手立てを考える日々で、「福祉は専門職」だということを痛感します。
…ですが。
どんな職業であっても、仕事とは人が行うことなので、結局のところ、行き着く先は人としての成長であり、それは人財育成の課題と同義であると私は考えています。
ということで、今回は「人」について書いてみようと思います。
最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
障害を抱える方々の社会参加をお手伝いする仕事というのは、簡単に言うと二つの点に集約されると思います。
一つは「働くとは何か?」であり、もう一つは「自分という人間とは何か?」です。
つまりは職業理解と自己理解をつなげるインセンティブとして「生きがい」や「やりがい」を見出してもらうということでしょう。
…「でしょう」としたのは、まだまだ若輩者なので、今後も考える視点や方向性が変化すると思うからです。
ともあれ、今の私としての考えを述べていこうと思います。
まずは障害を抱える方々への人財育成の話から。
現在の職務として、比較的軽度の知的障害者の方と精神障害者の方を支援することが多いのですが、彼らには共通のコンプレックスがあると考えています。
それは、「自分は人よりも劣っている」という思考です。
一見すると、横柄な態度で敬語も使わず、唯我独尊的な人もいますが、それはコンプレックスの裏返しであることが多く、それゆえに人を観察する能力に突出している方も多くいらっしゃいます。
よくよくヒアリングしてみると、彼らにとって働くことは「やらされていること」であることが多いということが分かります。
これは支援者側の思想や態度が、彼らに悪しき影響を与えていると私は推測しています。
どういうことかというと、障害を抱える方々に対して、支援をする人間が意識的か無意識的かに関わらず、上下関係を強いていると感じられるということです。

ーーーーーーーーーー
ところで、あなたは「自主的」と「主体的」の違いを説明できますか?
私なりの解釈で恐縮なのですが、「自主的」とは自ら行動することで、一度言われたり教えられたことを他人から、率先して行動できることだと定義づけします。
「自主的に宿題を片付ける」といった感じでしょうか。
一方の「主体的」とは、自分で考え、判断して行動することです。
「教科書だけでは理解できなかった部分を主体的に調べた」と例示できると思います。
微々たる違いかもしれませんが、行動に置き換えると大きな差になります。
例えば、「掃除をする」を例に挙げてみましょう。
自主的に作業してもらえるように指導するということは、作業工程を説明することです。
最初に大きなゴミを手で拾い、ほうきで掃き、掃除機をかけ、雑巾で磨く…などですね。
説明をした工程に従い、作業することができるようになりますが、極論、言われたことしか出来ません。
主体的に作業してもらうには、「働くとは何か?」を説く必要があります。
「掃除をする」とは、キレイな状態を保つことで気持ちよく生活できる、とても大切な役目であり、誰もが出来るけど誰もがやりたがらない作業かもしれない、だからこそ「ありがとう」と感謝される仕事なのだと。
すると、彼らは自身の中にある「キレイとは?」の価値観に従い、こちらの想定した工程以上の作業をすることがあるのです。
…支援者がどう伝え、障害を抱える方々にどう伝わるかが、いかに大切なのかを痛感します。
このあたりは「三人のレンガ職人」の寓話にも通ずる話かもしれませんね。

ーーーーーーーーーー
私は福祉経験一年の身ではありますが、福祉未経験の後進指導も仰せつかっています。
あるとき、こんなことを言われました。
「私は障害者の支援に興味はありますが、彼らとともに作業することには懐疑的です。支援者として彼らの作業を見守り、支援するのが仕事であって、彼らの行う作業を手伝うのなら、自分がその仕事に就きます。なぜなら、その方が稼げるからです。」
つまり、支援者とは障害を抱える方々を支援するのが仕事であって、一線を画すことが大切なのではないか?という問いかけでした。
これは「自分という人間とは何か?」への回答と同義だと私は思います。
上記の発言をした後輩は、無意識であっても障害を抱える方々を下に見ているのでしょう。
だからこそ、「出来ない部分を指導する」ことに意識が向いていると思うのです。
障害を抱える方々は、障害者である前に一人の人間です。
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」とは福沢諭吉の名著「学問のすすめ」の冒頭の言葉です。
そして何より、支援者に必要なのは、人であって人を育てるという大変に大きな責任感だと私は思います。

ーーーーーーーーーー
よく引用される言葉ですが、山本五十六の言葉を用いたいと思います。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。 話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。
支援者と障害者、先輩と後輩、上司と部下…。
さまざまな人間関係が社会には存在していますが、先述の「支援者とは見守ること」と位置付けるには、いろいろと不足している要素があると私は感じていますし、後進にも諭しています。
「では、あなたは後ろから指摘をしてくるだけの上司の下で、気持ち良く働けますか?」と。
上でも下でもなく、隣にいるからこそ伝えられるし、伝わってくれる。
まずはそこから始めることが肝要であり、人を育てるとは決して一方的ではないことを知ることが大切なのではないでしょうか?
ともに成長できる関係を構築すること。
人財育成とは、自分も育成される側だという姿勢で、相手を敬い、行動で示すところがスタートだと思うのですが、あなたはどうお考えでしょうか?
ーーーーーーーーーー
ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
