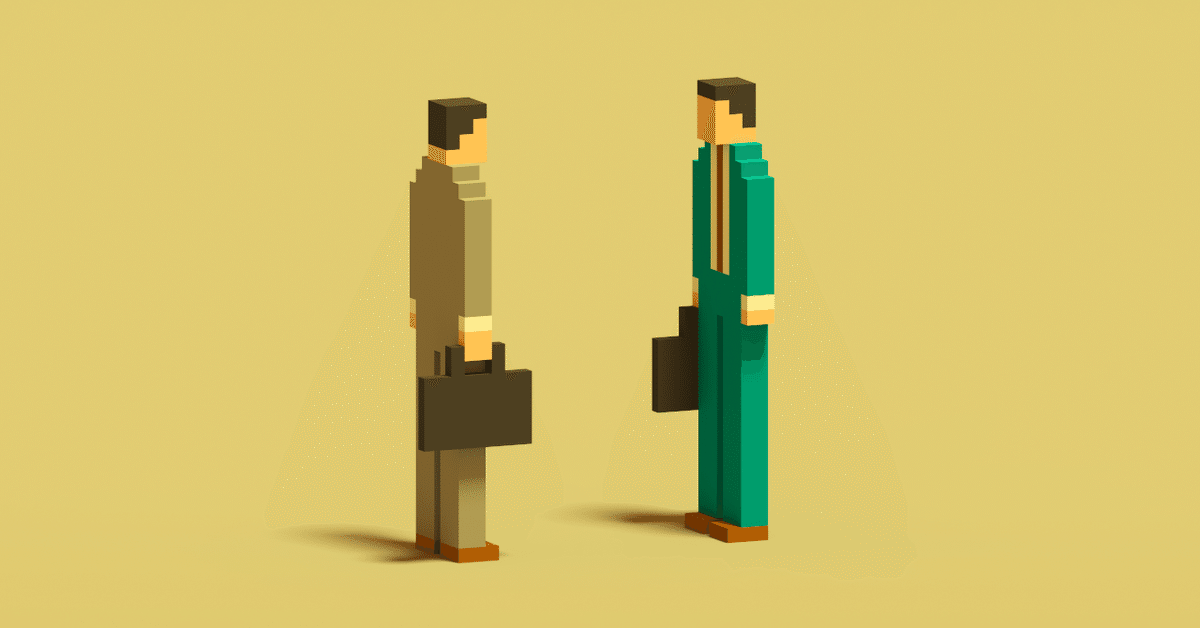
ひとに教えてもらうことが得意
以前noteで自分の強みについて書いたことがある。
上記の記事に書かれていることは、週に2回行っているパーソナルトレーニング中に、ふと思いついたのだけれど、最近別の強みもあることに気がついた。
それはひとに教えてもらう能力が他のひとよりもあるんじゃないか?ということ。
教えてもらう能力というよりは、いろんなひとにすぐに聞ける能力かな。
例えばぼくは、数字の分析に関してはほとんど知識がない。集計をしてある程度の仮説を立てることなら少しはできるかもしれない。
しかし、細かな分析に関してはさっぱりだ。
こういうとき、詳しい先輩や後輩がいたら真っ先に相談する。まず最初に自分で調べて知識をつけよう。とはならない。
こうする理由は、自分が調べたとしても的外れなことをする可能性が非常に高いからだ。
経験したことのある分野であれば当然別だが、踏み込んだことのない領域に関して、誰のアドバイスを聞くこともなく自分ひとりで突き進むのはかなりリスクがあると思う。
はじめての富士登山でガイドさんをつけないのと同じ。下手すると死ぬ可能性だってある。
仕事は登山ではないので、死ぬことはないけれど、多くの時間を無駄にすることになると思う。
なので、詳しいひとがいれば真っ先に聞きに行く。
これって案外できないひとがいるんじゃないかとふと思った。誰かに何かを聞くとき、気軽に聞けるひとと聞けないひとがいる。
それは普段のコミュニケーションによって決まると思う。
例えば同じチームに所属していて、なおかつ隣の席にいるひとに相談する場合、そこまで気を遣わずに相談することができるだろう。
しかし、まったく別部署のしかも歳の離れたひとの場合はどうだろう。なかなか話をする機会もないし、1日に1回あいさつを交わす程度の関係だったら、たぶん気軽に相談はできないと思う。
ぼくだってそんな状況だったら、気軽に相談できないと思う。
だから、できるだけ別部署のひととも小さなコミュニケーションをたくさん取るようにしている。
例えば、すれ違いざまに相手が髪を切っていることが分かれば、「あれ?イメチェンしました?」とか、「今日の服ブランドで固めすぎじゃないっすか?」みたいな感じで。
こういう積み重ねって結構重要で、関係値を作る基盤になっていると思う。
コミュニケーション量が大切なんじゃなくて、コミュニケーション機会が多い方が大切だということ。
いろんなひととコミュニケーション機会を多く作ることで、何か困ったときにすぐに相談できるような環境を作ることができる。
ここまで書いてあれですけど、ひとに教えてもらうことが得意なんじゃなくて、コミュニケーションの取り方がうまいってことになるのかな?
まあ、どっちでもいいや。
ひとつ言えることは気軽に相談できるひとが周りにたくさんいる環境は、仕事をするうえで、非常に優位に働く。
一番のメリットは自分ひとりで考えて抱え込むような時間が減ることだと思う。そうすることで精神的な負担を減らすことができる。
とはいっても、コミュニケーションって難しくて、向き不向きもあると思う。
別にこれをしなくても問題なく仕事が進められるひとだってたくさんいると思うので、社会人の必須能力ではないかもしれない。
が、身につけて損する能力ではないと思う。
<<<本日の一曲>>>
よき感じにゆるい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
