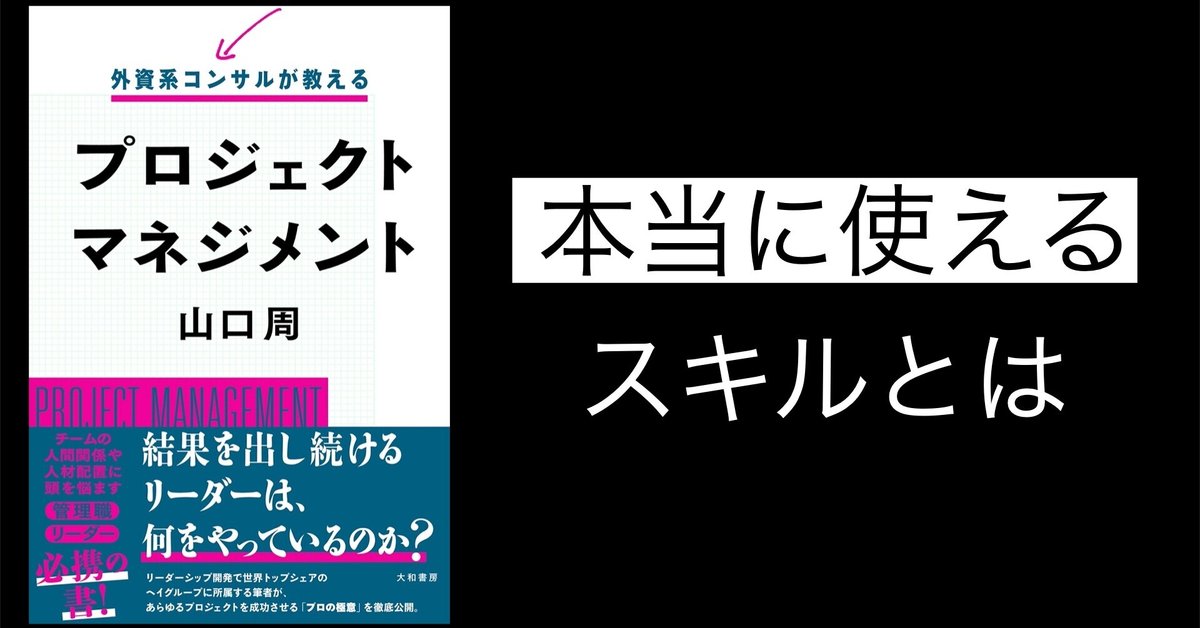
【本要約】外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント -どの業界でも通用するスキル
本記事は、2016年4月に刊行されました「外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント」(山口周著・大和書房)の要約・解説の記事になります。本書では、ベストセラー作家である山口周氏が広告代理店、外資系コンサルの経験で培ったプロジェクトマネジメントのノウハウを紹介しています。職種としてプロジェクトマネジメントの方はもちろん、様々な職種にも適用できるノウハウです。
▼本記事の概要
著者の山口周氏は「世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?」や「武器になる哲学」など、ベストセラーを連発している注目の著作家です。
ファーストキャリアを電通で10年ほど過ごされ、その後、20年近く外資系コンサルを渡り歩いてきました。著者がこれまで関わってきた仕事は「プロジェクト型」の仕事で、そこで得た現場の生きた知恵を、学術的な根拠や歴史なども紐解きながら、余すことなく、解説してくれているのが本書になります。
以前「文系AI人材になる―統計・プログラム知識は不要」を解説しましたが、「プロジェクトマネジャー」が文系AI人材として目指せるキャリアとして紹介されていました。また、私が人材エージェントをやっていた経験からも、プロジェクトマネジャーが需要として伸びていることも知っていました。
しかし、プロジェクトマネジャーがどういう仕事なのか、どんなことが求められるのかということがいまいちピンときていませんでした。
そこで、プロジェクトマネジメントの本を調べていると、本書が「本当に役立つ本」として非常に高い評価を受けていたため、ピックアップしました。
先に本書の結論です。
・変化の激しい現代は「官僚組織型」から「プロジェクト型」への変化が必要
・今後、全てのビジネスマンにプロジェクトマネジメントスキルが必要になる
・プロジェクトマネジメントには「すべき」と「すべからず」の考え、行動がある
・プロジェクトマネジメントスキルは最も業界横断的に活用が可能なスキルである
この本のポイントは以下です。
・著者の経験、学術的な根拠、歴史などあらゆる角度から考察されている点
・多数の実績を残してきた著者ならではの生きた知恵が具体的に紹介されている点
・本として構造がしっかりしているのでシンプルに読みやすい点
こんな方におすすめの本です。
・何かしらのプロジェクトに関わることになった全ての方
・チームの人間関係や人材配置に頭を悩ます管理職、リーダーの方
・他業種、他業界でも通用するスキルを身につけたい方
読んで分かったこととしては、プロジェクトマネジャーという職種、役割でなくても、今後「プロジェクトマネジメント」のスキルは必須になってくるであろうということでした。また、汎用性が高く、総合力の必要なスキルのため、身につけることができれば、今すぐに仕事に活かせるスキルだとも思います。
本書では網羅的に、現場で活かせるスキルが解説されているのですが、本記事ではその中でも以下を重点的に解説したいと思います。
・今後プロジェクトマネジメントスキルが求められる理由
・プロジェクトの進め方
・プロジェクトマネジメントスキルを磨くためには
▼今後プロジェクトマネジメントスキルが求められる理由
本書では、「はじめに」と「おわりに」に、今、なぜ、プロジェクトマネジメントスキルが必要なのか、また、身につけるとなぜ良いのかが解説されています。
【プロジェクトマネジメントスキルが必要な理由】
著者は今後全てのビジネスパーソンにプロジェクトマネジャーとしての力量が求められるようになるだろうと主張とします。
理由としては、ここ数年で起きている劇的な変化によって、”従来の仕組み”が破綻してきていることにあります。
ここで言及している”従来の仕組み”とは、階級を設けて上から順に意思決定の連鎖をしていく「官僚型組織」を指しています。この官僚型組織では「ルールの規定と権限委譲」が運営の基本になり、この組織体系は高度経済成長時には非常によく機能しておりました。
しかし、現代は状況の変化が早すぎるため、ルールでは対応できないことが多くなっています。そのため、ルールに判断基準を置いて処理していく「官僚型組織」では対処ができません。
そこで必要となったのが、目的と価値観に立脚して、自分の判断で物事を進めていく「プロジェクトマネジメント」の能力です。
【プロジェクトマネジメントは組織で成果を出すスキル】
著者は、「身につけるスキルには三種類あって、本当に自分を助けてくれるのは三番目のスキル」だと主張します。
一番目のスキル…「その会社で評価されるスキル」(例)伝票処理や受発注など
二番目のスキル…「その業界で評価されるスキル」(例)業界特化の商品企画など
三番目のスキル…「どの業種であっても評価されるスキル」
(例)論理的思考、ファシリテーション、プレゼンテーションなど
もちろん、プロジェクトマネジメントは三番目のスキルに当たります。
今後、人間そのものの寿命は伸びていき、働く期間も長くなりますが、会社や業界の寿命は短くなっていく傾向があります。そんな中で、異業種への転職などが増えていくことが予測されております。
この辺りはベストセラーとなった「LIFE SHIFT」(リンダ・グラットン著)などでご存知の方も多いかと思います。
そんな世の中で、業界横断的に活用可能なスキルを身につけることは必須になってくると思われます。また、三番目のスキルの中でも「プロジェクトマネジメント」のスキルは、「持つ者」と「持たざる者」の格差が一番大きいスキルだと著者は指摘します。
理由としては、論理的思考やプレゼン能力などが「個人として成果を出すためのスキル」であるのに対して、プロジェクトマネジメントは「組織として成果を出すためのスキル」であるからです。
そのため、「プロジェクトマネジメント」のスキルは、今後必須になるし、身につけることで大きなインパクトを人生やキャリアに与えると指摘しています。
▼プロジェクトの進め方
本書では以下フェーズで「すべき」「すべからず」のポイントを解説しています。
・プロジェクトを始める前(第1章)
・プロジェクト序盤(第2章)
・プロジェクトの着地(第3章)
この中でも、特に重要なのはプロジェクトを始める前の段階です。
読むとわかるのですが、それ以降の序盤、着地については始める前の前提を元に進められるため、この段階で躓いてしまうと以降の修正が難しくなります。
そのため、ここでは始める前について重点的に解説して参ります。
【勝てるプロジェクトを見極める】
プロジェクトをうまく進めていくポイントとして、著者が最初に挙げているポイントとしては、「勝てるプロジェクトを見極める」です。
著者曰く、勝ち続けているマネジャーは「確実に勝ちが見込めるプロジェクトだけをやってきた」ことがポイントだと述べています。つまり、プロジェクトの目利きが効くかどうかがプロジェクトマネジャーとしての成功を決めると言います。
本書では例としてナポレオンを挙げており、ナポレオンは「勝てる」かつ「意味がある」戦場を見つけることができたからこそ、戦果を上げることができたと言います。
また、勝てないプロジェクトの特徴として「目的が不明確なプロジェクト」を挙げています。特に気をつけなくてはいけないのが「目的」のフリをした「手段」です。例えば、「AIを導入する」「ジョブ型人事評価を導入する」などがプロジェクトの目的になっている場合は危険です。なぜなら、AIの導入も、ジョブ型人事評価も手段でしかないためです。これを避けるためには「そもそも何のために」を問い、目的を明確化することが重要としています。そして、それらを早い段階でメンバーに共有することも、モチベーションや判断基準の観点から大事であるとされています。
【成否の半分は人選で決まる】
成功した事業は「良い計画が立てられ、計画に適した人材が選ばれ、成功した」のではなく、「優秀な人材が集まり、その後議論によって計画が生まれ、成功した」という順番であると本書では指摘しています。つまり、「人材が先、計画が後」ということです。
この教訓を踏まえて、プロジェクトマネジャーが気を付けなければいけないのが、「プロジェクトに必要な人材の質と量に対して、ちょうど100%のチーム体制では必ず破綻する」ということです。なぜなら、想定の100%だと余裕がないため、危機対応ができないためです。そのため、最初の段階でメンバーの質・量に不安があるのであれば、然るべき人に訴えて、人員の増員や入れ替えを必ず交渉しておくべきと主張しています。
【期待値をコントロールする】
本書では、プロジェクトの開始時に各方面の期待値をコントロールすることが重要だと述べられています。
特に期待値を上げすぎないコミュニケーションが重要としています。成果と期待値の関係をまとめると以下になります。(P71)

同じ成果の水準でも、初期の期待値が高いと相対的な満足度は下がります。そのため、各方面の期待値は適切に設定(できれば低めに)することが重要です。
期待値をコントロールする要素としては「期間」「リソース」「成果」の3つがり、コントロールの仕方としては具体的には以下を挙げています。
・3つの要素に関して必要な見積もりに対し、1.5倍程度を提示する
・「プロジェクトの難度に関する見通し」を関係者で共有する
【その他】
このプロジェクト前の段階では、その他にも、適切なリスク管理の方法や、メンバーの力量の把握の仕方、人事配置の仕方などが説明されています。
また、プロジェクト序盤では、報連相の具体的なタイミングや方法論、心理的安全性の作り方、強い組織を作るために「情報流通量」を不安などが解説されています。
着地では、聞くことの重要性、フィードバックの適切なやり方、一貫性と柔軟性のバランスなどについて解説されています。
【プロジェクトマネジャーとは】
先ほどはプロジェクトの進め方についてのポイントを見ていきましたが、そもそもプロジェクトマネジャーの仕事とはなんなのかについて触れておきます。
本書ではプロジェクトマネジャーの仕事は「資源配分である」と言います。資源(人やお金や時間など)を調達し、最適な管理を行い、プロジェクトを成功に導くのがプロジェクトマネジャーの役割です。
ここで考えなければいけないのが、「時間」「コスト」「品質」にはトレードオフの関係があることです。例えば、プロジェクトの「品質」を高めようとすれば、「時間を長くする」か「コストをあげる」のどちらか、もしくはどちらともが必要になります。このトレードオフをコントロールすることがプロジェクトマネジャーの役割だといえます。
▼プロジェクトマネジメントスキルを磨くためには
本書では最後の第4章で成功に導くリーダーシップに求められる資質や心構えについて書かれています。
成功に導くリーダーシップについて、具体的な解説は本書を確認頂ければと思うのですが、要素を抽出すると、以下になります。
・バランス感覚を持つ
・いつも上機嫌でいる(感情をコントロールする)
・自責思考
・目的を立てて、目的にフォーカスする
リーダーになる方は先天的にこれらを身につけているかというとそういうわけではありません。それでは、これらはどのように身につけていくことができるのでしょうか。
【リーダーシップを身につけるためには】
まずは小さくてもリーダーシップを持つことが重要であるとしています。
世の中の大きな変化は、初めから大きなリーダーシップを持っていただけでなく、小さなリーダーシップから始まることが多いと言います。例えば、米国の公民権運動は、バスで白人専用席に座った黒人女性が立つことを拒んだことから始まりました。このように自身の価値観を持って世の中に対して、アンチテーゼを提案していくことが第一歩になるとしています。
また、ビーイングではなく、ドゥーイングが大切であるとしています。
リーダーとしてあるべき姿、要素は以下です。
・正直
・未来志向
・情熱的
・有能
・フェア
これらが必要なことは納得できると思いますが、これら条件が必要とわかっていても、明日からすぐにこれらの要素を満たした人間になれるかというと難しいと思います。
そのため、まずはドゥーイング(行動)を意識することが大切になります。
生まれつきのリーダーシップというのは幻想です。偉大なリーダーになった人は、誰もが、与えられた場所の中で、最初は戸惑いながら「リーダープレイ」を実施、その中からリーダーとしての振る舞い方、考え方を学びとっていったのです。(P195)
▼まとめ
本記事では以下について解説して参りました。
・今後プロジェクトマネジメントスキルが求められる理由
・プロジェクトの進め方
・プロジェクトマネジメントスキルを磨くためには
最後に、総括した感想と補足としては
【AIプロジェクトにおいて期待値コントロールはめちゃくちゃ重要】
【日々の業務も時間軸を区切ってプロジェクトとして取り組む】
ということを挙げさせていただきます。
【AIプロジェクトにおいて期待値コントロールはめちゃくちゃ重要】
AIの導入はほぼ間違いなく、プロジェクト型になります。また、そのプロジェクトはトップダウンで行われることが多く、経営陣からのAIに対する期待値が過剰に高いことがよくあります。そして、期待値が高ければ高いほど、プロジェクトがうまくいかなくなります。
これはAIに限ったことではないと思いますが、その時々でバズワードのように取り扱われているものは、その実態も分からないまま、過度な期待をされることが多いです。しかし、最新の技術というのは成果が安定しないことも多くあり、大体のケースで期待値を下回る結果となります。こうして、プロジェクトはうまくいかなくなります。そのため、プロジェクトマネジャーには上がりすぎた期待値を下げることが求められます。
とはいえ、新しいことを取り組むとなった際に、やたらと期待値を下げても、必要なリソースが確保できなくなるなどの問題も発生します。そのため、プロジェクトに関わる人間は期待値の適切なコントロールが必要になります。
私の経験上ですが、上記のバランスを取るには、短期と長期の視点に分けて、期待値を設定することが重要かと思います。短期的には今の技術でできることのギリギリ100%で設定するのではなく、やや余裕をもった期待値を設定します。そうすることで、初期段階でうまくいった際にプロジェクトに対する満足度の貯金ができます。
逆に長期的には少し高めの期待値を設定しておき、最初の段階から未来を感じてもらうことで、予算などの適切なリソースを割いてもらうことができる可能性が高くります。この短期と長期のバランスが大切ではないかと思います。
【日々の業務も時間軸を区切ってプロジェクトとして取り組む】
ここまで、前提としてプロジェクト型の仕事について解説してきましたが、多くの人は現状の仕事がプロジェクト単位ではないことが多いのではないかと思います。しかし、時間軸を区切って、目的などを明確に持てば、プロジェクトのような働き方ができるのではないかと思います。
私の所属する現職でも、ずば抜けた結果を出すチームは1年間を一つのプロジェクトのように捉え、目的を明確にし、その目的に向かってまさにプロジェクトを進めていくように仕事をしているチームが多いと感じます。
時間軸を区切ることで、一つの目安ができるので、その目安ごとに目的をたて、プロジェクトのように管理していくことで高い成果を残すチームができるのでないかと思いました。
冒頭でも述べた通り、プロジェクトマネジメントは今後必須のスキルとなり、スキルの有無が大きな格差になると思います。また、”今後のため”ではなく、”今すぐ”成果を上げるためにも身につけておきべきスキルでもあると思います。
個人的には会社の管理職の方々とこの本を読んでディスカッションし、定期的に本の内容を確認する場を設けるだけでも相当組織として強くなるのではないかとも感じました。本当に有用な本だと思いますので、ぜひご興味のある方はご覧ください。
今回の記事は以上になります。
ご一読いただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
