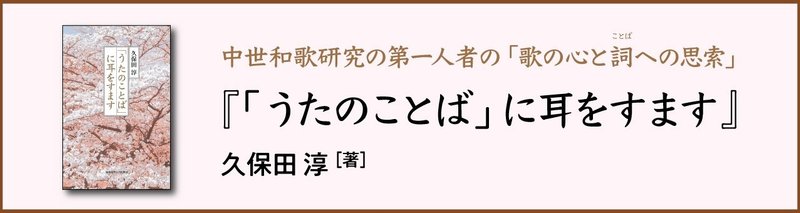【試し読み】『「うたのことば」に耳をすます』
『「うたのことば」に耳をすます』(久保田淳 著)が9月に刊行されました。この本は中世和歌研究の第一人者・久保田淳氏が研究のかたわらでつれづれに書き記したエッセイをまとめた一冊です。
万葉集、古今集から、西行、藤原定家といった中世の歌人、正岡子規ら近代、そして現代に至るまでの、さまざまな「うたのことば」を通して、日本人が何を思い、感じてきたのか。ことばがどのように人々の生活に入り込み、流行りすたりが生まれたのか。著者の思索が凝縮されています。
今回は本書の中から二つのエッセイを紹介します。「古典詩歌の勧め」ではうたに込められる愛や悲しみについて、「すがる 蜂と鹿」ではことばの解釈を巡る研究について紐解いています。
***
古典詩歌の勧め
よくみれば薺(なづな)花さく垣ねかな 芭蕉
なずなは春の七草の一つである。冬を越したその葉を正月七日、七草がゆにして食べる。春、すみれやたんぽぽが咲くころになると、なずなも白いこまかな花を咲かせる。菜の花の仲間だから、花びらは四枚だ。しかし、とても小さいから、よほど注意しないと気づかない。芭蕉は垣根をのぞきこんで、その下に咲いているこの小さな花を見つめている。芭蕉の目は小さな存在を見過ごさず、そこにも備わる美しさを見いだす目である。
あかあかやあかあかあかやあかあかやあかあかあかやあかあかや月
「あかあかや」とは、明るいなあという驚きのことばだ。「明るい」という形容詞を昔は「あかし」といった。この歌は「明るいなあ、明るいなあ」という感嘆の声をくりかえして、月の明るさを讃えているのである。月はきっと満月であろう。
この歌の作者は明恵上人である。平安時代の末に生れて鎌倉時代の初め、日本の歴史の激動期を生きた。その間源平動乱や承久の乱などの内戦があったが、彼はひたすら信仰に励んだ。修行の合間に歌を詠んでいる。
それらは身のまわりの自然に対して有情な存在に対すると同じような態度で接したものが多い。おそらくこの歌でも、明恵は夜空にくまなく満ち満ちているまどかな月の光に、仏の慈悲の光を感じているのであろう。すなおな心で自然と向かいあう時、自然は思いがけない神秘な顔を見せてくれる。
うつそみの人なる我や明日よりは二上山(ふたがみやま)をいろせと我(あ)が見む
「うつそみ」は「うつせみ」と同じで、「うつそみの人」はこの世の人という意味、「いろせ」とは母親が同じ兄弟のことをいうことばである。「この世の人であるわたしは、明日からは、弟の葬られた二上山を弟として見るのだろうか」。
この歌は突如弟を失った姉の悲しみの歌である。弟というのは天武天皇の皇子である大津皇子(おおつのみこ)、歌の作者である姉は大伯皇女(おおくのひめみこ)という。
大津皇子は謀反を企てたとされてみずから命を絶ち、二上山に葬られた。死に際して、
ももづたふ磐余(いはれ)の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠(くもがく)りなむ
と詠んだと伝えられる。あるいは皇子の死を悼んだ人々が歌ったものかもしれない。
この皇子は山の中で恋人の石川郎女(いらつめ)を待って、
あしひきの山のしづくに妹待つとわれ立ち濡れぬ山のしづくに
とも歌っている。堂々とした体格で、文才もあった。人望も高かったという。
二上山は頂が二つに分かれている、変った形の山で、大和平野のあちこちからよく見える、美しい山だ。
これらの歌を収めている万葉集をひもとくと、古代の人々の愛や悲しみ、そしてまた喜びがいきいきと伝わってくる。
いろいろな花が咲く。さまざまな鳥が囀(さえず)る。日本の自然は美しい。古(いにしえ)の歌人や俳人は三十一字や十七字という短いことばでその美しさを的確に表現してきた。それらの和歌や俳句を読むことによって、わたくしたちは改めて自然の美しさに気付かされ、自然の中で生きることの有難さを知るであろう。
いろいろな人がいる。一人として同じ人はいない。しかしまた、だれしもが他を愛し、また愛されることを願い、喜びを求め、愛する者の死を悲しむ。そのような人の心は、昔から今まで変ることはない。そのことも昔の人々の残した和歌や歌謡などを読むことによって、確かめられ、納得されるのである。そしてそういう経験は励ましとなり、慰めとなって、わたくしたちに生きる力を与えるであろう。
古典を読むこと、それは自然の不思議さを知ること、人間の心を知ること、そして人間として生きることを意味するのである。
古典の詩歌を読もう。
(久保田淳・室伏信助編『角川全訳古語辞典』巻初、二〇〇二年十月、角川書店)
***
すがる 蜂と鹿
古今和歌集・巻第八離別歌に、題しらず、よみ人しらずの、次のような歌がある
すがる鳴く秋の萩原朝立ちて旅行く人をいつとか待たむ(三六六)
この歌に見える「すがる」はじが蜂(似我蜂・細腰蜂)をさすとされている。たとえば、岩波文庫本『古今和歌集』の脚注では「ジガバチの古名」という。じが蜂というのは土に穴を掘って産卵し、卵が孵化した時の餌に虫を捕らえてその穴に引き入れたのちに土でふさぐのだという。「じが」というのはその羽音の擬音にもとづくのであろう。この蜂は万葉集に、
春さればすがるなす野のほととぎすほとほと妹に逢はず来にけり(巻十・一九七九)
……わたつみの 殿の甍(いらか)に 飛び翔る すがるのごとき 腰細に 取り飾らひ……(巻十六・三七九一・竹取翁の長歌)
と歌われ、
しなが鳥 安房に継ぎたる 梓弓 末の珠名(たまな)は 胸別(むなわけ)の 広き我妹(わぎも) 腰細の すがる娘子(をとめ)の……(春九・一七三八、高橋虫麻呂歌集)
と、腰のくびれた美女に喩えられている。
けれども、平安時代後期には、古今集・離別歌の「すがる」は鹿のこととされていた。それは源俊頼あたりの考えていたことだろうか。彼の歌学書『俊頼髄脳』ではこの歌を引いて、「すがるとは鹿を申すなめり」という。そして、自身、「原の上の鹿」という題で、
秋来ればしめぢが原に咲きそむる萩の初枝にすがる鳴くなり(散木奇歌集・秋部)
と詠んでいる。しかし、俊頼よりは先輩格の大江匡房(まさふさ)も『堀河百首』の「野」の題で、
すがる臥す野中の草や深からん行(ゆき)かふ人の笠の見えぬは
と詠んでいるから、院政期頃の歌人の間では、すがる=鹿の異名というのはおそらく共通理解であったのであろう。俊頼の同世代の藤原仲実も、その著『綺語抄』の動物部で同じ古今の歌を引いて、「すがる わかきしか」と釈している。また源忠房も『永久百首』の「秋風」の題で、次のように歌う。
色見えで身にもしむかなすがる鳴く小萩が原の秋の夕暮
やや遅れて、藤原清輔は『奥義抄』下で、古今集の歌を釈して、「すがるとは鹿をいふ也。或物にはわかきしかとぞ申したる。又、さそりといふ虫をもすがるといふ。万葉云」として、前引の「春されば」という万葉歌を「春なればすがるなく野の」という訓みで引いて、「是はさそりなり」という。清輔の義弟の顕昭は『袖中抄(しゅうちゅうしょう)』第十で「スガルナル野」という項を立て、「或人ノ関東ヘクダリテ侍シハ、アヅマニハ蜂ヲスガルト申(まうす)トゾ。サヽリ蜂トマウセバ、ハチ・サヽリハ同物也」と記し、清輔の右の万葉歌での釈については「イカヾトキコユ」と疑問を投げかけている。
そして、晩年の藤原定家が著した歌学書『僻案抄(へきあんしょう)』では、問題の古今歌につき、「すがる、少年の昔、古今の説受け侍りし時、すがるは鹿の別名なりとぞ申されし」という。定家にそう教えたのは、父の俊成であったことが知られる。定家は次いで前引の万葉歌をも引いて「春の野になるといへる、鹿に叶はねば、さゝり蜂など申すめり」としながら、「この歌(古今の「すがる鳴くの歌」)にとりては、秋の萩原に鳴かむ、鹿疑ひなきか」と結論した。そしておそらく、これが中世においても定説に近い解釈だったのであろう。
だから、西行の、
すがる臥す木暗(こぐれ)が下の葛巻きを吹き裏返す秋の初風(山家集・中)
でも、慈円の、
奥山にかき籠りなんのちはさはすがるましらや友となるべき(拾玉集・第一・述懐百首)
すがる鳴く野辺の夕暮あはれなり尾花が末に風をまかせて(同・同・賦百字百首)
でも、式子内親王の、
露寒み分くれば風にたぐひつゝすがる鳴くなり小野の萩原(式子内親王集・第二百首)
でも、「すがる」は鹿のことと解する他なさそうである。
古今歌の注釈の問題に戻ると、近世に至って契沖の『古今余材抄』が、『日本書紀』巻第十四雄略紀にいう、養蚕にかかわった小子部栖軽(ちいさこべのすがる)についての注「須我屢」をも引いて、すがる=じが蜂説を強く提唱する。「鹿をすがると心得きたれるは、日本紀万葉集をかむがへあはせずして、萩は鹿の花妻にて、まじはりてなく物なれば、おしあてに鹿ぞとつたへ来れるなるべし。日本紀に鹿をばかせぎとこそ点じたれ。それだに和名(『和名抄』のこと)には見えず。ましてすがるといへる事は、物にもすべて見えぬ事なり」。
このような注釈史を経て、今日の古今集の注釈書では「すがる鳴く」の歌での「すがる」はじが蜂を意味するというところに落ち着いたのであろう。そして、多分それで正しいのであろう。
ただ、古今集の時代の歌人たちが万葉歌人と同じように、じが蜂の羽音に耳を傾けたのかどうか、それほど鋭敏な聴覚を持ち続けていたのかどうか、いささか気になるのである。少なくとも、すがる=鹿と決めてかかっていたらしい院政期以降の歌人の聴覚は、かなり鈍ってきていたのであろう。
さて、現代ではどうであろうか。我々はさまざまな騒音に堪えながら、歌を詠んだり、また読んだりしなければならないのである。
(「礫」二〇〇七年十一月)

***
さて、本書のタイトルにある「耳をすます」とはどんな行為なのでしょうか。現代の人々が和歌や短歌を読むとき、文字で読む、つまり視覚的に情報を受け取りますが、かつては宮廷で実際に歌を詠みあげたり、聴いたりして耳で楽しむものでした。ことばの向こう側に広がっている世界に耳をすましてみると、うたがまた違って感じられるのではないか、というメッセージを「耳をすます」に込めました。皆さんもぜひ、耳をすまして読んでみてください。
下のバナーから弊社HPの書籍紹介にリンクしています。ぜひご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?