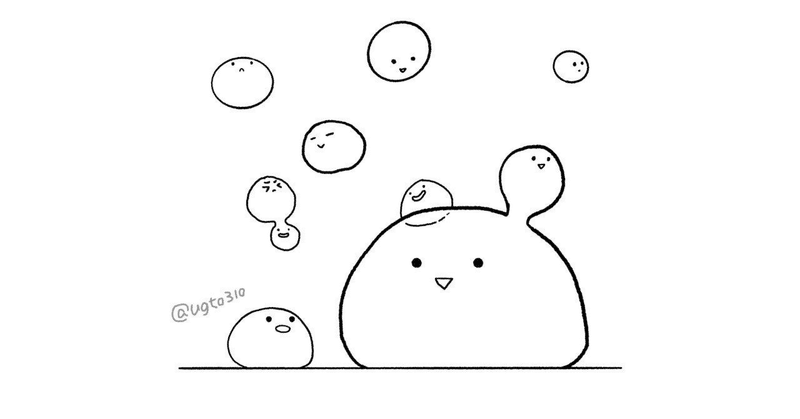
20231023_戦乱から安定期、王朝の滅亡までの流れを学び考えたこと_覇権で読み解けば世界史がわかる_紹介と感想17
はじめに
こんにちは、Keiです。
今まで私にとって"元気が出た"と思ったコンテンツや"役に立つかもな"と思ったコンテンツや考え方を紹介してきました。今回も良い人生にするために"役に立つかもな"と思った考え方を紹介していきます。
参考書
この度、参考にした本は
『「覇権」で読み解けば世界史がわかる』神野正史
です。
内容と感想
前回の記事では"外戚vs宦官"までの部分を読んで感じた事を書いきました。
今回の記事では"漢帝国以降の中国史"までの部分を読んで感じた事を書いていきます。
内容
長い戦乱時代→短期政権→長期政権というパターンは歴史上随所に現れる。
●中国の例
・春秋戦国時代(約500年)→秦帝国(約15年)→漢帝国(約400年)
・魏晋南北朝(約400年)→隋帝国(30年未満)→唐帝国(約300年)
●ローマの例
・内乱の一世紀→カエサル→帝政
●日本の例
・戦国時代→織豊政権→徳川幕府
ひとつひとつの王朝は
・戦乱の時代で全国の国土が荒廃し、人口が激減
→統一王朝が生まれ社会が安定し、農業生産力が向上
→人口が増え、農地が足らなくなり対外膨張戦争が国庫を圧迫
→増税による農民の窮乏で反乱が起こり、混乱のうちに滅亡
というパターンを繰り返している。
戦乱時代では人口の多さで国力が定まるため人口増加に躍起になるが、統一王朝となると、爆発的に増えた人口を支えきれなくなり、崩壊していく。荒廃の時代は人口を増やすことが国を安全に向かわせるが、安定の時代になると、増えすぎた人口が国を亡ぼす。
感想
歴史を俯瞰して見ると大まかな流れを把握でき、その中から共通点を見つけることができる点は純粋に面白いと思います。戦乱の時代に争い合う単位の規模も時代と共に大きくなっているように見えます。将来的には地球単位の政権が誕生するかもしれません。そして(現在も含むかもしれませんが)その前には長い戦乱の時代があると思います。統一したとしても、制度が噛み合わずに短期に終わり、統一前の制度を上手く取り入れた者たちが長期政権を築くことができるのだと思います。歴史から将来を予測することは今後も続けていこうと思いました。
統一王朝の流れからも、何度も似たような過ちを繰り返しているという点を学ぶことができると思います。対外膨張戦争の実施が、滅亡への一歩になるように見えます。対外膨張戦争を行わずに国をまとめ、運営できる国は長い間繁栄することができると思います。このような工夫ができる人を政治の中心に置くことができると良いと思いました。また専守防衛の考え方は長く繁栄するという観点で見ても良い考え方だと思いました。
安定の時代になると人口の増加が国を滅ぼすことに繋がるという点は、人口増加に伴う対応ができなくなってしまうからだと思います。食料、経済、意思決定など人口増加に伴い多くの問題が発生すると思います。どれも難しい問題ですが、これらの問題の解決策を考えられないと国が滅亡に向かうと思います。解決策を考えながら人口増加のメリットを得られるように運営できると良いと思いました。
最後に
歴史を俯瞰して見ることで、時代変化の経緯の共通点を得ることができると思います。共通点を見つけることで今後の大まかな流れを予測する事にも繋がると思います。また、歴史から失敗例を学ぶことにより、少なくとも過去の人類と同じ失敗を避ける事に繋がると思います。
歴史を利用し、今後の大まかな流れの予測や失敗の回避を意識する事で、より良い手段を選択できるように過ごしていきましょう!
どなたかの参考になれば幸いです。
以下、私の記事一覧ページと自己紹介ページです。
ご興味ございましたら、ご覧いただけると嬉しいです。
Xの紹介です。
よろしければご覧ください。
"応援したい"と思って下さった方はサポート頂けると嬉しいです。
