
都農ワイン28年の奮闘記から学ぶ、地域資源を活かすビジネス術。
4年前に移住してから、ぼくが都農町で最も尊敬し続ける経営者が都農ワイン前社長の小畑暁さん。
現社長の赤尾さんとともに、台風が多く高温多湿でワイン不適地といわれた宮崎県都農町で、年間20万本以上ものワインを毎年作り続けています。
今年に入って、ぼくらが経営するHOSTEL ALAで、僭越ながら都農ワイン提携ホステルとして、試飲セットをおかせてもらったり。
4月から毎月開催しているALAガーデンは、「都農ワインガーデン」として、町内外問わず、気軽に屋外でワインを楽しんでもらえる場づくりを進めています。


小畑さんは、今年の6月に社長を赤尾さんに譲り、相談役に。
これまでの奮闘記が宮崎日日新聞でも連載記事として綴られました。
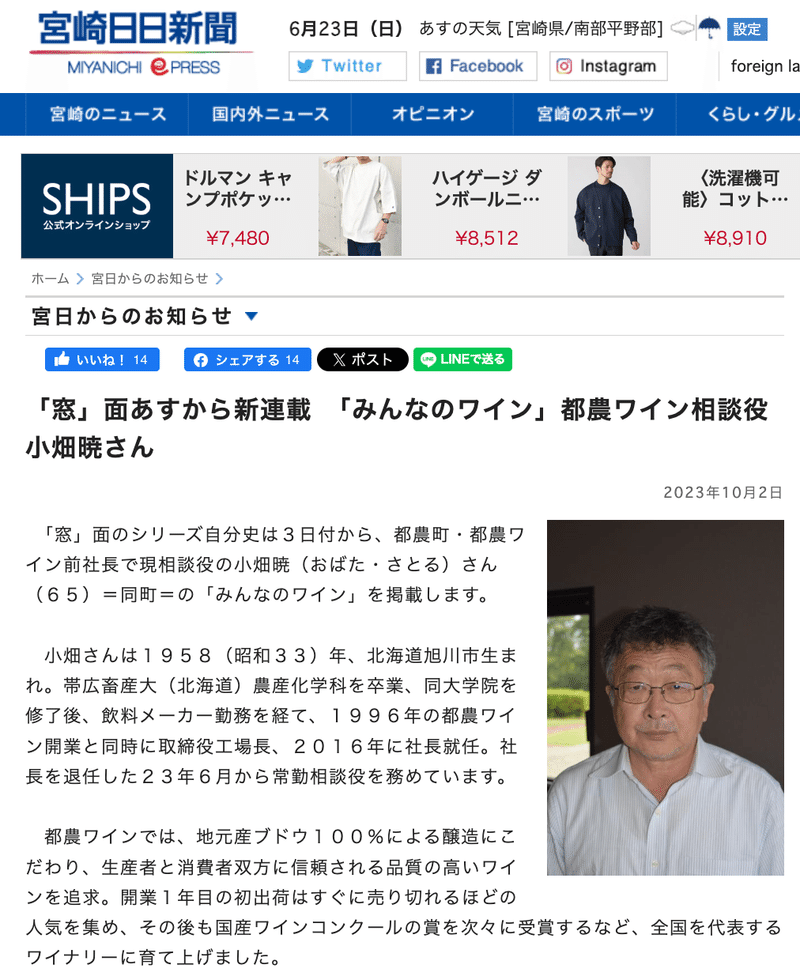
7月20日は、ALAガーデンのメインプログラム「まちづくりカレッジ」第4回のゲストに小畑さんをお招きし、新しいコトを起こす、地域資源を活かすビジネスという観点から、じっくりとお話を聞き出そうと、いまから準備しながら楽しみにしています。

これまでの都農ワインの奮闘記を、ざくっとご紹介します
1.いいワインはいいブドウから

都農ワインの歴史は、10代の若手農家、永友百二さんが稲作に頼らず果樹栽培にチャレンジ、19歳で梨園を開園させ、終戦直後からぶどうの栽培に着手したことから始まります。
年間降雨量4,000ミリ以上、世界のぶどう産地の5〜8倍もの雨が降り、収穫期には台風、火山灰性でミネラル分の不足の土壌など、ぶどうの栽培には適さない不利な条件だらけでした。
「田んぼに木を植えるなんて」との非難にもめげず、土の基礎研究から土壌改良を行い、排水対策や防風林の植樹、ビニールトンネルの栽培など研鑽を重ねながら対策を講じて昭和28年に県内で初めて巨峰を植え付けに成功しています。

昭和43年には都農町ぶどう協議会が発足し、昭和60年代にはぶどう農家は300軒を超えました。
その後、供給過多になった際の生産調整や、町としての産業化を目指し、平成元年にワイナリー構想が立ち上がりました。
地元産のぶどうのみを使って、都農ならではの風味豊かなワインづくりを実現しようと、第三セクターで設立されたのが、現在の株式会社都農ワインです。

現場で都農ワインをつくり続ける小畑さんと赤尾さんの話を聞いていると、血縁がなく、出身も異なるのに永友百二さんのチャレンジスピリットを継承していることを強く感じます。
2.世界に通じるワインをつくる

立ち上げを託された小畑さんは、帯広畜産大学の大学院を卒業後、青年海外協力隊でボリビア、ブラジルに駐在しワイン醸造に携わってきました。
相棒の赤尾さんは隣の川南町出身、高卒で都農町役場史上初のワイン技師として入庁し、以来2人で町役場とともに、都農ワインを創り上げてきました。
小畑さんは最初に都農町長と面談した際、「世界に通じるワインをつくる」と宣言したんだそうです!
明確な根拠はなかったものの、若いうちから世界でワインをつくってきたからこそ、ごく自然に抱いたビジョンだったとともに、永友百二から連なる不可能を可能にする、新たなチャレンジの始まりとなりました。

創業以来、長年、小畑さんと赤尾さんの2人でぶどうの栽培から醸造、そして販売と完結してきました。まさに六次化の体現。2人だけで。
話を聞いていて感じるのは、「いいぶどうがいいワインをつくる」との永友百二スピリットです。ワインづくりは農業であり、小手先のプロモーションやネットワークづくりに依存しないところに魅力を感じます。
3.設備の先行投資

南米を始め長年、海外でワイン市場を見てきた小畑さんだからわかる、グローバル市場でのワインのトレンド。
1万人の町のワイナリーだから小さくまとまるつもりはない、都農町でワインをつくると決めた時から当時の町長に「世界に通じるワインをつくる」と宣言して始めてから考え方にブレはありません。
都農ワインの名を知らしめたキャンベル・アーリーのスティールワインの伸びにいち早く限界を感じた小畑は、当時、国内に先例の少なかったスパークリングワインの開発を構想しました。
2004年前後のこと、専用で炭酸充填の設備が必要であり当時で50,000千円近くの投資になりました。

第3セクターの都農ワインは、新たな投資をする際、町議会の承認を得る必要があり、金融機関を含めて利害関係者の理解を得るのは並大抵のことではなかったと思います。
小畑さんのブレない軸としては「つくりたいものがある」が先、そのためにどういう設備が必要かを考え、自ら資金調達に走る。経営はその繰り返し。

もちろん、利益を出して確実に返済していくことは言うまでもありません。
醸造家というと職人気質でつくることに集中し他のことに興味を持てないイメージがあったのですが、2人ともお金が好き?だからか、必ず収支計算と資金調達が頭の片側にあります。
「すぐ、やる」「チャレンジ」が都農ワイン最大の競争優位性であることを改めて実感しました。
自分の給料は自分で稼ぐという意識の強さ、技術者ながらPLやBSの管理を大切にしているところも都農ワインの強みです。
小畑さん曰く「本当のクリエイティビティは収支を考える」。
4.まちのみんなでつくるワイナリー
ここまで来るには、町役場を始め、町のみんなの協力なくしては得られなかったと小畑さんは感謝の気持ちとともに述懐します。
当然、立場の異なる関係者間での軋轢は生じました。ただし、目指す方向は一緒、少子高齢化で人口減少が加速する都農町における厳しさは言わずとも共通の危機感として一体感を持ってきました。
2010年の口蹄疫をみんなで乗り越えたことを糧に、今またコロナに立ち向かおうとするポジティブなエネルギーにも繋がっています。

もともと、小畑さんが目指していたワインは、特定のお金持ちに飲んでもらうワインではなく、町のみんなに飲んでもらえるワイン。
年に一度のハーベストフェスティバルを始め、収穫祭や町の花火大会など、これまでも積極的に都農ワインとして地域貢献を実施してきました。
5.地方創生とはテロワール
最後に、これからの都農ワインの展望について聞いてみたところ、「若い醸造家の育成」との答えがかえってきました。
単なる醸造技術の伝承にとどまらず、ワインづくりは農業であり、ワインは地酒であるいう確固たる信念と、常にチャレンジを続けてきた伝統のバトンを渡していきたいと願っています。
町とともにつくってきた都農ワインですが、人口減少、少子高齢化、若者流出など、地方創生の背景にある課題が山積する中でのコロナショックで、一企業だけでは解決できず、町全体として、生き残り策を考え、実行していかなければなりません。
小畑さんが考える地方創生とは、まさにテロワールであり、その土地、風土、人からしかつくりだせない固有のものです。

どこかの地方の成功事例を真似てもうまくいくはずがなく、都農町ならではの価値を見出し、深めていくべきとの考えを持っています。
物質的な豊かさには限度がありますが、精神的な豊かさには限度がありません。これからも町の人に豊かさを感じてもらえるよう、強みである畑と醸造の一体化を武器に、都農ワイン独自の品種づくりにチャレンジし続けていくことは確かです。
(参考)
ぼくらが取材・編集した都農町公式YouTubeつのTV
「都農ワイン醸造家|終わらない、答え合わせ」


7月20日、ALAガーデンのご予約はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
