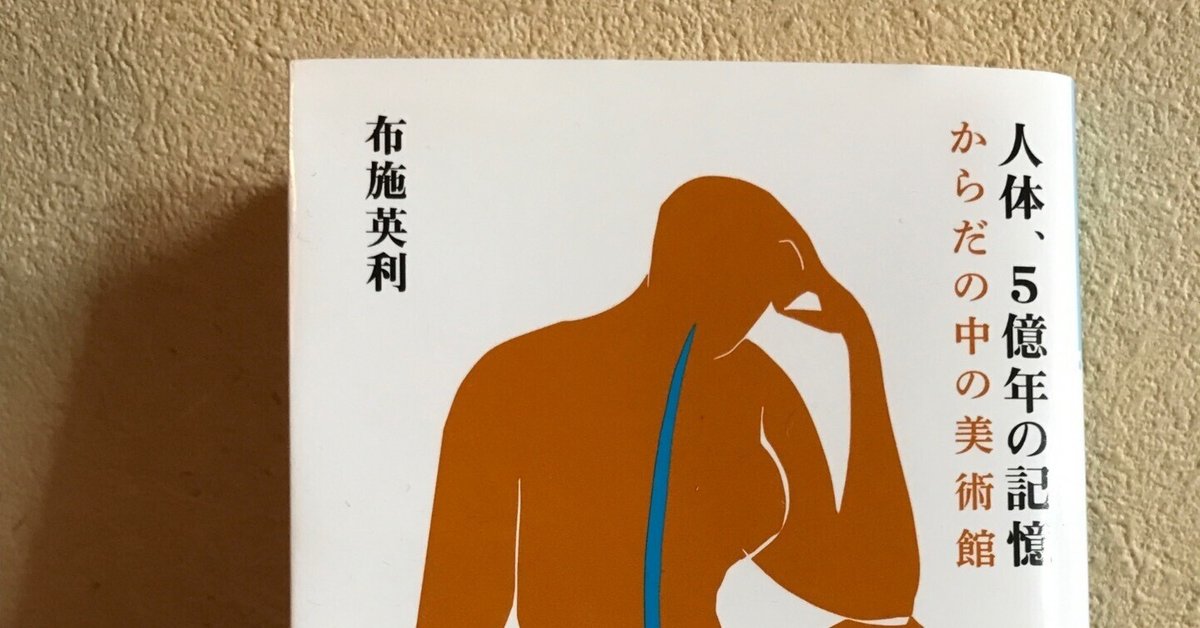
人体、5億年の記憶 からだの中の美術館 - 布施英利 を読んで vol.2
p.257 胎児の成長の章 受精してから十月十日(トツキトウカ)で出産する。赤子になって。それまでに子宮の中で生命の5億年の進化を辿って生まれてくる。特に30日を過ぎた1週間がめざましく進化する過程だという。受胎32日は魚のよう、35日に両生類の顔、36日が爬虫類、38日には犬のような哺乳類の顔。この数日間に約1億数千年の時を駆け巡るという。その絵を見る。なるほど。
引用:
p.223「受精卵の発生にあたって、この生命進化のドラマを必ず走馬灯のごとく再現させていく.......、いわば母親の体内で十月十日、こうした遠い祖先の悠久の歩みを”からだを張って”なぞり、復習し続けてきた」生命とリズム三木成夫)
なるほどね。
p.223 三木は胎児の顔の変化をビジュアルで提示することでそれを証明しようと思う。絵に書いたわけだ。上記の1週間の間に海から上陸する。そして爬虫類の時期から心臓も左右に壁ができて、肺循環、血液循環すなわち、肺呼吸に対応した陸の生物に変化する。
引用:
p.229「三木はこの時期の変化を生命の進化、あるいは地質時代で言うと中生代末期から新生代にかけてのアルプス造山運動の時代と重ね合わせる。そもそも生物の上陸への進化についても、それをバリスカン造山運動と重ねる見方がある。」
抜粋「天変地異に対して、海の生物が陸で暮らすようになった ー 何も生物は新しいフロンティアを求めて、、、人類のように世界を広げようとしたわけではない。造山運動というやむに止まれに理由によって、生き延びるために進化をした」「ともあれ、アルプス造山運動という天変地異も、生物に苦難をもたらしただろう。ちょうどその頃にあたる胎児の顔に、苦行僧のような悩める顔を見て、三木がいう「秋霜烈日,しゅうそうれつじつ,秋の冷たい霜と夏の烈(はげ)しい日光。権威・刑罰などが非常にきびしいたとえ。」が、そのような地質時代と合致することもなくはないだろう。」ともあれ胎児はそのようにして受精卵から大ききう変貌し、新生児として生まれてくる。」
この胎児の成長を地球の変化、特に地質学的要素と組み合わせる見方を始めて知った。驚きと共になるほどと納得する。
引用、抜粋:
「三木の判断を支えている根拠は、顔の相貌の印象である。三木はそれを「面影」という言い方で説明している。」
以上のことを読んで胎児期に地球の中で生き抜いた生命の記憶を辿っていっている神秘のようなものを感じた。そしてなんとそれが顔の表情にも見て取れるのではないかというのことにもびっくり、納得してしまう。生命とは神秘。 最近の関心ごとといえば、このような人体の不思議と心のつながり、自然の流れのつながり。
この第一章を読んで基本的な体内器官の働きや連携、そして心とのつながりを知れた。改めて自分という人間はなまざまな臓器や神経の働き連携、微生物の働きが相互に絡み合い生命として生きていることに驚く。この驚いている自我?意識?だけが自分ではないことを知る。当たり前すぎて考えていなかったことを思い出す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
