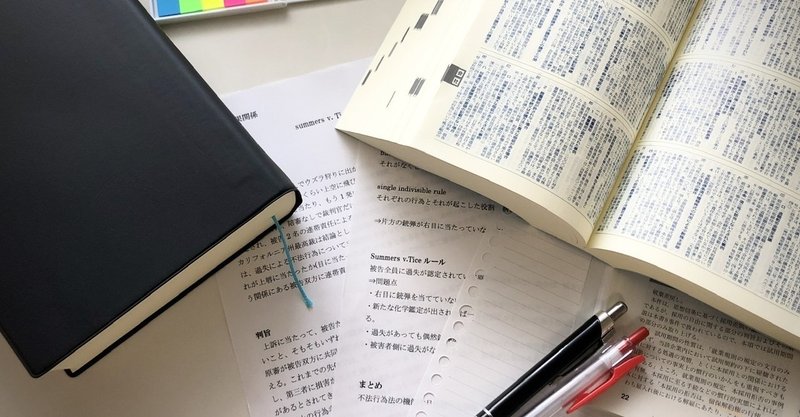
「国家公務員離れ」なぜ?若者世代が重視する働く価値観を発達的に捉えてみる
今回の気になった記事はこちら。
本文にもありますが国会公務員「総合職」、いわゆるキャリア官僚の今年度の採用試験の申込者数ですが、現行制度の試験になって以降過去最少の人数になったそう。
女性の申し込み者比率は過去最大となったものの、減少は4年連続となりました。
以前の記事でも紹介しましたが、公務員志望者の減少している職種で言えば教員の採用試験倍率も深刻な問題です。
今回は教員の倍率低下問題について言及しませんが、気になる方は妹尾昌俊さんのこちらの記事もぜひご覧になってください。
さて。
キャリア官僚と教員。どちらもとてもやりがいがあり、社会的地位のある仕事ですが、なぜ近年の若者から敬遠されているのでしょう。
この要因については大きく分けて2つあると考えています。
1つはブラックな労働環境がメディアやSNSによって明るみとなったったことに加え、清廉潔白であらねばならないといった社会からの期待やイメージ...そして何かあったときの強い風当り。
年功序列で旧態依然とした組織文化。自己裁量が少なく、なかなか若いうちから大きな仕事をさせてもらうことができないこともあると思います。
そして2つめですが、今回のテーマである若者の働く価値観の変化に起因していると考えられます。
それでは考察していきます。
若者世代のキャリア観を捉える、発達度合いの3タイプ
タイプの話をはじめる前に言葉の定義を揃えておきましょう。
私が若者世代という言葉を使う際は、ミレニアム世代からZ世代を指しています。以下、各世代の特徴です。
「ミレニアム世代]
1981~1995年生まれまでの2000年代の初頭に成年期を迎えた世代のことをいい、M世代、ミレニアルズ(Millennials)とも呼ばれる。PCや携帯電話が社会インフラとなっていくのも目の当たりにして育ったデジタルパイオニア世代であり、金融危機や格差の拡大、気候変動問題などが深刻化する厳しい社会情勢のなかで育ったことから過去の世代とは異なる価値観や経済感覚、職業観などを有する。現在25~34歳くらいの世代。
[Z世代]
1996年~2012年生まれの現在16~24歳くらいの世代。高速インターネット、スマホ、YouTube、そしてSNSが子どもの頃から身近にあり、手足のように使いこなすデジタルネイティブ世代。リアルとオンラインの垣根がなく、SNSで世界各国の様々な人と繋がり情報を得てきたことでダイバーシティや異文化への高い理解を示し、社会課題にも関心が高い。一方「自分らしさ」という個性や価値観を大事にし、ミレニアム世代以上にプライベート重視の傾向が強い。
ちなみに、筆者はミレニアム世代のど真ん中であり、仕事がらZ世代の方々とも接点を多く持っています。
この若者世代の価値観。特に就職や進学に関わるキャリア観ですが、これまでの肌感覚として大きく三つに分けてみました。山本のなかのイメージ図です。ちょっとキャズムっぽいですね。

自己実現・目標追及タイプ(発達上位20%くらい)
明確な目標を求めて生まれ育った地元を積極的に出ていく層。
社会課題にも関心があり、成長機会を欲し生半可な安定や環境を求めず、意志を持って都市・海外へ。進学ならたとえ家計が厳しくても奨学金という未来への先行投資をしていく。ワークライフバランスも大事だが、それ以上に自己実現を追い求める層。
ワークライフバランス・環境左右タイプ(発達中位60%くらい)
親が学費出してくれるなら県外進学し、家計厳しいなら残ってそこそこ頑張る。成長機会あればあったでいいけど、ガツガツ働くよりはワークライフバランスを重視する安定重視層。
やりたいことが明確に決まっている訳ではないけど、興味をそそられるものがあれば「自分探し」をするように地域を離れていく。環境に左右されやすく、家族・友人・恋人など身近な人によって上位下位どちらの層にも行く可能性あり。
プライベート重視・未成熟タイプ(発達下位20%くらい)
進路は基本的に受動的・消去法的に地元に残ることを選んでおり、やりたいことがなかなか定まらず、人によっては特定の職に就くことも回避。交友関係や活動範囲がずっと変わらず、短期的な視点で物事を考え、好き嫌いや楽しいかどうかで判断。行き当りばったり。仕事は生活の糧、趣味のためというプライベートが一番な未成熟層。
ここでは発達段階になぞらえてざっくり分類しており、学力といった知能ではなく精神性や知性という観点で判断しています。ただ、若いうちは主体性や学ぶということに対する姿勢と学力は相関がありそうなので、結果として学力も関係あるかもしれませんね。
これまでたくさんの学生に対してキャリア教育を行ったり、面談してきて感じた山本の感覚的な分析のためエビデンスはありません。
そこまで皆さんの実感とかけ離れてはいないと思いますが、いかがでしょうか。
若者世代が重視する働く価値観とは?
先ほどの3タイプを下敷きにすると、地域の人口動態のからくりもちょっと見えきます。
地域を積極的に出ていく方々の受け皿になっているのはやはり首都圏のベンチャー企業や外資系企業、進学でもいわゆる難関大学といわれるところに行く人はほぼほぼ上位タイプですから、卒業しても新卒で戻るケースは稀。Uターンどころか残った方が成長機会がたくさんあります。
地域に積極的に残っているのは?というと、そこが発達中位~下位です。
上位層が残りたいと思えるような環境ではない、地域の組織の多くは生産性の意識が希薄であり、正直素行さえ悪くなければ”何となくでも働けてしまう”ような環境。仕事をしないおじさんが蔓延ってます。
地域にあるこの典型的な中小企業が、図らずも中位下位の子たちにとってはちょうどよい。つまり需給バランスが取れているんですね。
加えてどこも人手不足ですから、中位下位の若者に振りむいてもらうために、研修やスキルアップといった人への投資より休暇の取りやすさや残業無しという鼻先人参のようなインセンティブを売りにするから、結果として若手がなかなか育たないという連鎖。
これが地域の企業の生産性がなかなか上がらず、イノベーションが起きにくい要因だと考えています。
タイプによって優先順位も変わってきますが、そんな若者たちの価値観を捉えるファクターが以下の4つです。
衛生要因・動機づけ要因と環境要因・個人要因のマトリクスです。

衛生要因や動機づけ要因はハーズバーグの二要因理論で言われているもので、衛生要因は給与待遇、福利厚生、休日、人間関係などが該当し、高まることで不快や不満を減らす効果があると考えられていますが、一定以上になるとその効果は弱まります。
動機づけ要因はやりがいや仕事の意味意義、社会的影響、承認や達成感などで、高まることでその人の仕事に対するやる気や愛着に繋がります。
簡単に言えば、衛生要因はマイナス(不快不満)を減らす方向に作用し、動機づけ要因はプラス(仕事のモチベーション)を増やす方向に左右するということですね。
先述の2要因に掛け合わせたものが、環境要因と個人要因です。
環境要因は職場で働く人を取り巻く環境で、一個人の意思ではコントロールが困難なシステムや制度、雰囲気も入ってきます。
いくら経営者であっても、給与や休みは変更できても人間関係や成長機会は簡単には変えられません。
個人要因は個人の内面的なものに起因するもので、意識の発達段階やライフステージに左右されます。発達段階が未熟な下位層にとって、やりがいや意味意義はそれほど重きを置きませんが、自己実現を意識する上位層は特にここが重要です。
この4要因を少し補足すると、意味意義は自分の仕事が社会の役に立っていると感じられるかどうか。成長機会は文字通り若いうちにダイナミックな仕事に挑戦できるかであり、成長実感とは「この組織にいて自分は成長できている、○○ができるようになった」という感覚を感じられるかを表します。
この4つの働く価値観が今の若者を読み解く上で手掛かりになると思います。
発達段階が上位の層は動機づけ要因が重要になってきますが、どんなに動機づけ要因が高くとも衛生要因が劣悪なところは敬遠したくなるでしょう。
生活に対する不安や不満が少ない状態にあるからこそ、仕事で失敗を恐れずチャレンジも出来るというものです。
中位下位層も衛生要因がきっかけとなって最初は働きはじめると思いますが、動機づけ要因が弱ければたとえ不満は抱かなくとも充実感を得られず、モチベーションが湧かずに次第に飽きが生まれ、離職を誘発します。
長い回り道をしてきましたが、ここまで話してようやく冒頭の話です。
国会公務員や教員がなぜ志願者が減っているかについて仮説が浮かんできます。
国会公務員はかつては上位もしくは上位に近い中位の方々が多かったと想像できますが、若者世代の価値観からすれば衛生要因についてミスマッチが生まれています。
やりがい搾取は以ての外。給与が高いからといって酷使してよい、国のために働くという大義名分のもとで滅私奉公せよというのは時代遅れかもしれません。
ベンチャー企業や外資系企業といった企業は能力主義が主。成長機会も若いうちからたくさありますし、株式会社といえど利益だけでなく社会課題解決に力を注いでいる企業も少なくありません。
国という実態ない概念のために働く国家公務員と違い、顧客と直接やり取りをするなかで仕事の手応えも感じやすいでしょう。
個人的には、国家公務員はPRをどれだけ頑張っても今の組織構造や文化にメスを入れない限りはなかなか変わらないと思います。教員も然りですね。
衛生要因と動機づけ要因への視点を持ちながら、いまの組織を見直すこと。そして若者世代の価値観の特徴、発達段階を踏まえたアプローチをぜひ考えてみてください。
数多あるnoteのなか、お読みいただきありがとうございました。いただいたご支援を糧に、皆さんの生き方や働き方を見直すヒントになるような記事を書いていきたいと思います。
