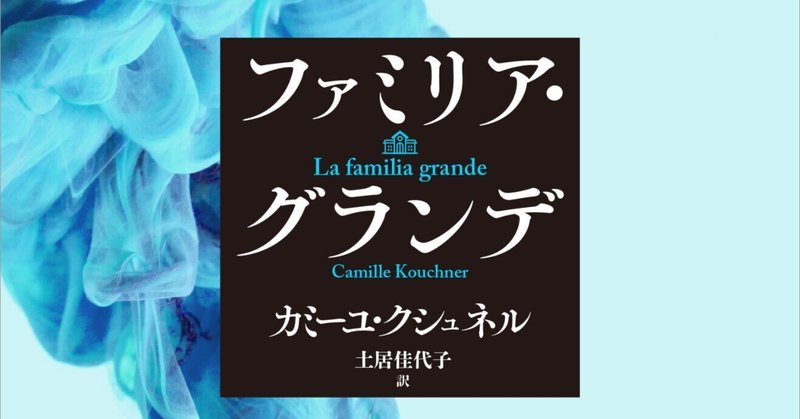
沈黙が破られるまでの30年|ファミリア・グランデ|土居佳代子【訳者まえがき】
加害者告発に加え、否認した母と傍観者だった自分も性虐待に加担していたという自責から書かれた本は他に類を見ない。まさに震撼の書である。――信田さよ子
2022年3月29日、カミーユ・クシュネル 著『ファミリア・グランデ』(土居佳代子 訳)が発売されました。

本書では、性虐待される双子の弟を見ていることしかできなかった「私」の、30年にわたる苦悩が一人称で綴られます。
著者の実父は「国境なき医師団」創設者のひとり、叔母はトリュフォー監督も認めた有名女優、母も継父も著名な言論人ということもあり、2021年1月の原書出版時にはフランス中に激震が走りました(現在32万部突破)。出版された1週間後には、#MeTooIncesteというハッシュタグで8万件ものツイートが流れ、マクロン大統領が「子どもに対する性犯罪」の対応に関して声明を発するまでに至ったといいます。
傍観者としての、小さな加担者としての罪悪感を見つめ直し、苦悩の記憶を掘り起こしながら、文学的努力を払い、その経験を言語化した著者。本書には「告発」という性質がありますが、本質的には、被害がなかったことにされる構造と、沈黙にともなう罪悪感をありありと表現した一冊といえます。
冒頭に掲げた臨床心理士・信田さよ子さんの推薦以外にも、発売前から応援コメントが届いています。
数時間で読み通すなんていつぶりだろう。誤解を恐れず言えば、めちゃくちゃ面白い外国文学を読むような感覚で私はこの本を読んだ。
──紀伊國屋書店ゆめタウン下松店・池田匡隆
子を持つ親として、またひとりの女性として、そしてかつて子どもだった者として、この本は私に、過ちを断罪するための言葉を手渡そうとしているのだ、と読み終えて気がついた。そしてこの言葉を、未来に届けなくてはいけないのだと。いまいるこの場所で、私なりのやり方で。
──三省堂書店成城店・大塚真祐子
ひとりでも多くの読者、特に著者と同じように悩み、沈黙させられている方に本書が届くことを願い、本稿では特別に「訳者まえがき」を公開します。
訳者まえがき(土居佳代子)
本書『ファミリア・グランデ(La familia grande)』は、2021年1月に出版されると同時に、大きな反響を呼んだ。激震を起こした、という言い方さえされている。それまでにも未成年に対する性的暴行、特に近親者による性虐待に関する本は少なからず出ていた。だが今回は、特にフランスではよく知られた、非常に影響力のある人物が関わっていたことがあった。これでもう見てみないふり、自分とは関係がないからということはできなくなった、と言うべきだろう。
昔から家庭内で性虐待がおこなわれてきたことは、たいていの人が知っていた。しかし、それは秘密にすべきことである、取り立てて言うことでもない、あるいは、特殊な環境における、特別の変態的行為に違いないなどといって、表立って取り上げられることはほとんどなかったようだ。ここ20年ほどの間にも、社会の認識は行きつ戻りつしていた。そうした経緯については、本書のあとに出版された、シャルロット・パドロウスキのOu peut-être une nuit(『それとも夜だったかもしれない』)に詳しい(同じ内容が出版前にポッドキャストでも配信されている)。
パドロウスキの本は、自身の家庭の事情とともに、多くの犠牲者たちの声を集めているため、どんなに多くの子どもや大人が悩まされ、傷を負っているかがわかる。アンケートでは把握しきれない性質のものではあるが、フランスの10人に1人がそうした経験を持つと推定されている。その題名の由来からして――シャンソン好きならきっとご存じの――バルバラ「黒い鷲」の冒頭の詩句であり、これはこの歌手が父親による近親姦を歌ったものだった、という衝撃的な事実が作中で明かされている。
未成年者に対する性的暴行に加えて、インセストについての法律がフランスでできたのは、やっと2010年。その後、2015年、2018年と改正が続いて、被害者が成人となってから20年だった時効期間が、30年と延ばされた。フランスでの成人年齢は18歳なので、48歳まで告訴が可能となったのだ。実際、被害者本人が自覚するまで、訴えようと思えるまでにはずいぶん時間がかかるようで、時効なしにすべきだという声も多い。また、2018年の改正では、レイプの定義も変わった。
カミーユ・クシュネルによる本書が出てから、さらに力を入れた法律改正の検討が続けられ、採択された新法では、近親者と18歳未満の未成年者の間では互いの同意の有無にかかわらずインセストと判断されることとなった。これに対しても、18歳未満に限定すべきでないとの批判がある。
さて、著者のカミーユ・クシュネルは1975年生まれ、私法を専門とする大学准教授。母は著名な公法学者で作家のエヴリーヌ・ピジエ、実父は医師で政治家、「国境なき医師団」の創設者の一人であるベルナール・クシュネルだ。さらに母の妹は、特にトリュフォーの映画や舞台で多くのファンを持つ女優マリー゠フランス・ピジエ。また本書には決して名前が出てこないが、問題となった母の再婚相手(「継父」)は、テレビ・ラジオ出演も多い著名な政治学者で憲法学者。実父の再婚相手もテレビの人気キャスターである。
このような知的で華やかな家庭環境において、先に述べた「秘密にしておくべき、珍しくもないこと」が起こっていた。著者には5歳上の兄コランと、著者と双子の弟ヴィクトール、母が再婚してからの養子である妹ルースと弟パブロがいる。継父による被害にあったのは、当時13歳のヴィクトールだった。
母はフランスで公法の教授資格をとった初めての女性の一人であり、筋金入りのフェミニストで左派、一時はキューバのカストロの恋人だったこともある。その母方の祖母ポーラも、離婚を勝ち取ったあと、自由と独立を何よりも大切にしていた人物だった。
母が再婚してから一家は、毎年、南仏サナリ=シュル=メールにある継父の広大な別荘へ行くようになる。ここには左派のインテリで、自由を愛する仲間たちが集まり、大人も子どもも混ざった「大家族(ラ・ファミリア・グランデ)」が形成される。
子どもたちの大寝室の壁には、1968年5月革命のポスターが貼りめぐらされていた。そのような環境で、議論し、ゲームをし、踊り……、そのころの風潮とはいえ、裸でプールに入ることも日常茶飯事だった。性的にも解放された雰囲気では、それがよしとされていた。その中で問題は起きていた。そして大人たちは――フェミニズムの闘士であった母さえも――沈黙した。
著者はこの物語を、子どもとして見ていたこと、当時はよくわからず、違和感を覚えながらもそのまま受け入れていたさまざまなことを、つらい記憶を掘り起こし、大人の言葉で再構成したという。もちろんそれは、母の愛情に包まれた記憶でもあり、太陽の輝きとラベンダーの香りに満ちた、サナリでの幸福な時間でもあった。継父も、著者が心から愛し、いろいろなことを教えてくれる、信頼できる存在だった。そう信じていた。
だが、事件が起こって、著者は罪悪感と沈黙の中に閉じ込められることになる。
#MeToo運動が高まり、聖職者による未成年の性虐待が明るみに出たり、2020年1月にはヴァネッサ・スプリンゴラの『同意(Le Consentement)』(内山奈緒美 訳、中央公論新社、2020年11月)が出版され、未成年者に対するレイプが問題になったりした。『同意』は、いかに美しい恋愛に見えても、いかに多くの文化人がかつてそれを弁護したとしても、14歳の少女の同意は、本当の同意とはいえないことを、社会に知らしめた。
また、父親とのインセストを描いたクリスチーヌ・アンゴのLe Voyage dans l’Est(『東の旅』)は、これがいかに本当の愛情とは異なるものかを暴き、2021年のメディシス賞を受賞する。そのほかにも前掲のパドロウスキなど、本書と前後していくつもの重要な本が出ている。
素地はできていた。とはいえ、本書が大きな契機となり、いつもテレビで見かける人物、政界にも顔が利き、学生の間でも偶像的教授だった人物の犯罪が明らかになったことで、社会の関心が一気に高まったのは間違いない。
本書の中でヴィクトールが言う。「彼らは僕を信じるとは思うけれど、完全に無視するだろう」――確かにそうだった。けれどこれが書かれることによって、それは許されないことであるという声が、より多くの人の耳に届いたに違いない。
継父についてはすでに時効が成立していたが、その後も事情聴取がおこなわれ、すべての公職を退くことになった。そして問題を知りながら沈黙していた法曹界・政界の要人や大学人数名も退職を余儀なくされた。
本が出版された約1週間後には、#MeTooinceste(#MeTooインセスト)というハッシュタグで約8万件ものツイートが流れた。そしてその数日後には、同じくツイッターで、マクロン大統領が「子どもに対する性犯罪」の対応に関する声明を発するまでに至ったのだ。
最後に、研究書を別として、本書が少しほかと違うのは、性虐待の直接の被害者によるものではないことだ。だが、そのためにかえって、黙認されがちなこうした行為のひとつひとつがどれだけ多くの人を傷つけ、しかも長い年月苦しめ続けるかが、そのメカニズムが、よく理解できる。著者が「あれは許されないことだった」とはっきり認識し、母親や継父から自由になるのに30年もかかった。その重みを嚙みしめたい。
「Inceste」についても触れておこう。臨床心理士の信田さよ子氏などの著書によると、日本では、親族による未成年者に対する性虐待に「同意」は意味をなさず、一方は完全な被害者であるとして、「近親相姦」ではなく「近親姦」と呼ばれるようになってきた経緯があるという。さらに近年では、「近親(相)姦」概念や「姦」という文字に潜む女性蔑視、偏見、歴史的な抑圧への問い直しが進んだこともあり、「性虐待」「性暴力」あるいはそのまま「インセスト」が使われるようになっている。本稿はそうした経緯を踏まえながら書いたが、この本が書かれるに至った時代背景や法改正の時期、著者のバックグラウンド等を鑑みて、本編では基本的に「近親姦」を訳語としてあてている。
なお、途中に散りばめられたシャンソンや詩句、小説からの引用が、ある意味ノスタルジックに時代の空気を伝えるとともに、巧みに配置された言葉やそこから生まれるイメージによって、作品の深みと魅力を増している。土地の名前や人名も同様だが、日本の読者、特に若い世代には馴染みの薄いものもあるだろうとの老婆心から、簡単な注を付した。ほとんどの歌はネットで聴けるので、ご興味があれば、検索してみていただければと思う。
2021年12月
プロフィール
著者:カミーユ・クシュネル(Camille Kouchner)
1975年生まれ。私法を専門とする大学准教授。本書が初の著書となる。
訳者:土居佳代子(どい・かよこ)
翻訳家。青山学院大学文学部卒。訳書に、アントワーヌ・レリス『ぼくは君たちを憎まないことにした』(ポプラ社)、ベルナール・ミニエ『氷結』(ハーパーBOOKS)、エマニュエル・ド ヴァレスキエル『マリー・アントワネットの最期の日々』(原書房)など。
参考記事
※リンクは2022年4月6日現在のものです。
