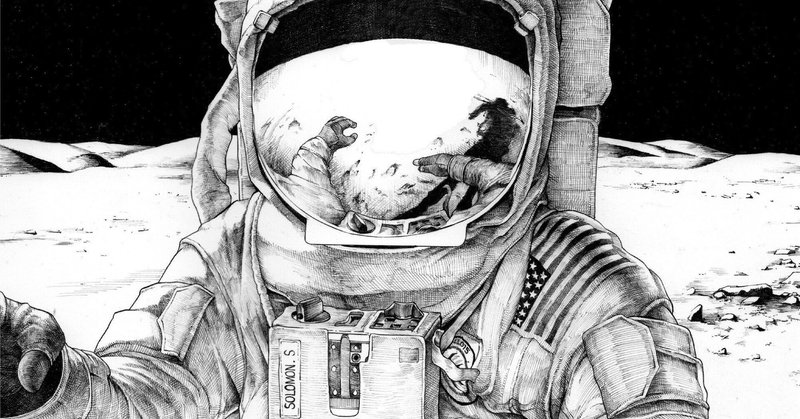
科学を楽しく学んで楽しく生活しよう!
ご無沙汰しています。仕事や健康などのことなど色々ありまして、しばらく更新が途絶えておりました。今後定期的に更新できるように、科学ニュースの紹介以外にも記載しようと思っております。
そこで今回は、「科学を勉強する意義と方法」について、自分なりの考えをまとめましたのでここで紹介しようと思います。
なぜ科学を学ぶ必要があるの?
人によって答えは色々あると思います。私の答えは、以下の通りです。
「現代の世の中が科学で成り立っているから」
みなさんはわたしの書いたこの記事を、パソコンやスマホで見てくださっていると思います。その目の前にある機械は科学と技術で作られたものです。一日の生活を通しても、朝起きてから夜寝るまで、現在の我々の生活には、ほとんどの場面で科学によって成り立っています。現代社会は、人類が解明・発展してきた科学によって作り上げたものです!
「科学なんてしらなくても生きていけるよ!」
もちろんこういう意見もあるでしょう。はい、そのとおりです。しかしちょっとだけ考えてみませんか?例えば、最近よく言われている「手を洗うということ」や「アルコール消毒すること」について考えてみましょう。なぜ手を洗うことが、ウィルス感染から身を守るかわかりますか?なぜアルコール消毒が重要か考えたことはありますか?
この花王の記事にもありますが、エタノールは、ウィルスの破壊(※正しくは、エンベロープの破壊および膜たんぱく質の変性)に関わっているとされています。またアルコール類のたんぱく質変性作用(ウィルスや細菌を壊す能力)は、水と一緒の方がより強くなることが知られています。市販の消毒用エタノールが70%前後なのはこれが理由です。
さてウィルスにはアルコール消毒が効くと思いますが、実はアルコール消毒が効きづらいウィルスもいるのです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html
科学を知らなくてもアルコール消毒はできますが、知っていれば消毒の仕方が変わってきますよね。
その一方で、実際に科学的な根拠がないにもかかわらず科学という言葉を使い、人の不安につけこんで、人をだます商品なども売られています。こういった商品を避けるためには、科学を知る必要があります。このような無駄な商品を買わないことで、そのお金は運動や家族との時間などもっと有意義なものに使えます。
このように科学を知れば自分の生活の役に立ってきますし、より豊かな生活に結びつきます。しかし「知る」ためには「学ぶ」ことが必要となります。そこで今回は、学校の授業以外で科学を大人が学ぶ方法を紹介してみます。
私が考える科学を学ぶ10の方法を挙げてみました
私が思いつく限り、以下の10個になるかなと思います。もしこれ以外にも、「こんなのはどうか?」と思った方は教えて下さい!
1)本−1:簡単に書かれた本(例:漫画)
最近で言えば、「はたらく細胞」や「Dr. STONE」でしょうか。「もやしもん」の絵本バージョンも結構気に入っています。ちょっとデフォルメしすぎかな、と感じるところもありますが、子供の導入には非常に良いですね!何事も学び始めは、「わかりやすい」が一番です!
https://hataraku-saibou.com
https://www.shonenjump.com/j/rensai/drstone.html
https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000004820
2)本−2:科学ジャーナリストの方たちや専門家が書いた雑誌、本
いわゆる科学ジャーナリストの方や専門家が書いた本です。ジャーナリストの方なので文章が読みやすい上に、専門家も編集者などの協力で読む易い文章になっていることが多いです。私の大好きな本を一冊ご紹介します。
https://www.amazon.co.jp/病の皇帝「がん」に挑む-―-人類4000年の苦闘-上-シッダールタ・ムカジー/dp/4152093951
この本の著者も、医者であり研究者でもあります。私の研究テーマである「がん」の歴史についてスリリングに書いてあります。この本の書評は大阪大学教授の仲野徹先生のが素晴らしいので紹介します。
https://honz.jp/articles/-/30560
また科学雑誌も大変素晴らしいのが揃っております。
https://www.newtonpress.co.jp
https://www.nikkei-science.com
科学雑誌は、ニュートンなどの非常に読みやすいもの、日経サイエンスのような中級程度のもの、そして専門家が読むような雑誌など(例えば実験医学など)、様々な難易度のものがあります。自分の読みたいレベルに合わせて読むといいですね!私も、高校、大学、研究者時代にこういった科学雑誌を読むことがあり、とても勉強になりました!
ここで気をつけないといけないのは、医者や科学者、科学ジャーナリスト、医療ジャーナリストであっても、明らかに科学的に間違えている本が多く出版されています。自分の科学リテラシーを上げて選別するしかないですね。
3)研究者のアウトリーチ活動
研究者は「アウトリーチ活動」というのをやっております。詳しくは以下の論文ナビが詳しいです!
https://rnavi.org/3380/
科学者が一般人向けに自分たちの研究を紹介する活動のことです。なぜこんな活動をする必要があるかというと、一つには研究費の存在があります。科学者が研究する上で大事なものとして「研究費」があります。多くの研究費は国民の税金が使われています。税金を使っている以上は、税金の使いみちの説明責任がある、と考えているからです。もう一つは、研究者の社会への関わりを積極的に増やすことで、よりよい社会をつくるための双方向の対話を重要視しているからです。双方向の対話によって、一般の方々がどのように自分の研究を捉えているか、どのようなニーズがあるか、研究者が知ることができます。また一般の方々には、もっと科学に興味を持ってもらい、サポートをしてもらったり、科学を目指す人口を増やすなど、いろいろな効果が期待されます。
様々なものがありますが、おすすめは研究所、大学の研究室に遊びに行くことです!こういうご時世ですので、去年や今年は中止しているようですが、理化学研究所や国立がんセンター、そして大学の研究所なども積極的に活動しています。研究者と直に話すチャンスです!
https://openday.riken.jp
https://www.ncc.go.jp/jp/information/event/index.html#general
私もアカデミアの研究者だったころは、積極的にアウトリーチ活動に参加していました。自分の研究を一般の人に説明するのに四苦八苦した覚えがあります。
4)科学博物館
有名なのでいえば国立科学博物館や科学未来館などでしょうか。こういった科学博物館の存在は、その国の科学教育のレベルの高さを示していると、個人的には思っています。根拠もデータもない、完全な私見です。
https://www.kahaku.go.jp
https://www.miraikan.jst.go.jp
ただ大人も子供も、本当に見て体験してほしいと思っています。またそれぞれの地方にもこういった科学博物館が存在するようです。科学博物館の存在は今後の日本の科学教育のためにも重要なのでどんどん発展していってほしいです。
5)ドキュメンタリー
ネットフリックスなどで見ることのできるドキュメンタリー番組が良いですね!また日本ではNHKスペシャルのシリーズ人体などが有名です。わたしもネットフリックスやNHKでドキュメンタリーをよくみます。ちょっと悲しいのが、民放ではあまり科学ドキュメンタリーがないことです。民放のほうが若い世代が見ることが多いと思うので、もっと制作してほしいと思っています。
6)YouTube
正直、YouTubeは苦手で(完全におじさんですね・・・)、科学関連のYouTubeはまだしっかりと見たことがありません。しかし軽く検索しても色々出てきますね。大学教授の講義などの動画も公開されており、大学に行かなくても色々と勉強できそうです。ただ2)の本のところでもありましたが、こちらも正しい科学の知識を説明しているものとそうでないものがありそうで、注意が必要ですね。
7)専門書
いわゆる研究者の卵と呼ばれる大学生や大学院生の教科書です。以前、ヨーロッパの非英語圏で少しだけ仕事をしていたことがありました。そのとき、私が日本語の教科書を読んでいると、周りの研究者たちが興味深そうに見ていました。彼ら/彼女らの国には母国語で書かれた生物の教科書はないからです!このように、教科書が母国語で書かれておらず、英語で教科書を読むしかない国は結構あるようです。日本の本の文化は非常に素晴らしく、翻訳のレベルも高いです。ハードルが少し高いですが、外国に比べて恵まれているこの状況を活かして、頑張ってチャレンジしてみるのも良いかもしれません。
8)論文
研究者の研究の成果、そして最先端の科学がつまっているのが、論文です。論文を読むのはかなりハードルが高いです。その理由として以下の3つがあります。
①英語で書かれていることが多い。
科学の世界では共通言語として英語を使います。そのためほとんどの論文は英語で書かれてあります。しかも論文に書かれている英語はあまり普段しゃべるような書き方ではないので、ビジネス英語が得意な人でも中身を理解するのは難しいかもしれません。
しかし最近ではGoogle翻訳やDeepLといったAI技術を用いた翻訳システムが無料で使えます。これを使えば少しは内容を理解することができるかもしれません。
②専門用語が難しい。
専門用語はどこにでもあると思いますが、科学の世界は専門用語だらけです。さらに言うと、言葉の意味から推測するのが難しい専門用語が多いです。例えば、皮膚の組織内にあるランゲルハンス細胞(Langerhans cell)というものがあります。ランゲルハンス??となりますよね?これは人の名前なんです。またT細胞、B細胞のように文字を短くしたものなど(T: thymus 胸腺、B: bone marrrow 骨髄)、専門用語には様々な種類があって名前だけから意味を予想するのは無理です。ただインターネットが発達した時代です。Googleで調べればすぐに意味がわかりますので、こちらは根気次第でしょうか。
③値段が高い。
論文を読むのにはお金がかかることもあります。しかし最近は、科学の成果を多くの人に見てもらうことを目的にして、無料の論文というのが多く見ることができます。有名なのでいえば、eLifeやPLoSジャーナル、Scientific reportsなどでしょうか。以下にリンクを貼っておきますので、適当に論文を選んでみてください。意味がわからなくても全文は表示されるはずです。
https://plos.org
https://elifesciences.org
https://www.nature.com/srep/
科学は不思議を殺すものではなく、
不思議を生み出すものである。
明治の文豪で科学者でもあった寺田寅彦の名言の一つに「科学は不思議を殺すものではなく、不思議を生み出すものである。」があります。普段から科学を知り、知った科学で普段の生活を理解して、そしてまた普段の生活から不思議が生まれます。わたしたちは普段の生活から科学者になれるのです。
いかがだったでしょうか?それぞれの項目は、また時間を見つけてみなさんに紹介できればと思っています。
たまには家族でネットフリックスでも立ち上げて、ドキュメンタリー番組を見ながら科学を一緒に楽しく学んでもいいですし、はたらく細胞の主題歌を合唱しながら「うしろまえちゃん」を応援してあげることも、立派な科学教育だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
