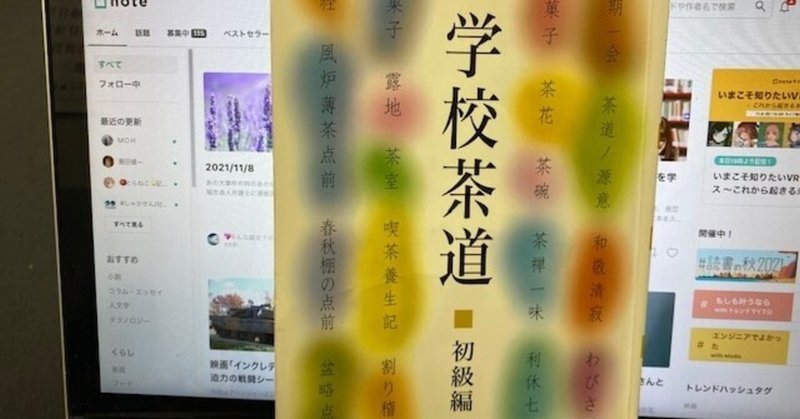
「天下一のお点前でした」と、利休の言葉の意味した事 -⑩
私が隔週で通っている銀座の歌舞伎座の側にある茶道教室。そこの先生は、多分、特別講師のような事をしていて地域の小中学校や、もしくは大学で、授業の枠を持っているのだろうと思われる。
先日、先生から「蜻蛉さん。よかったら、これをお貸しします。蜻蛉さんには、特にこの辺りがピッタリかも知れませんね」と、教科書を渡された。しかも、欄外のあちこちに書き込みがされている。どうも、どこかの高校あたりで、授業で使ったものらしい。
家に帰って早速読んでみた。「利休の逸話」といいうページで、こんな話が紹介されていた。かいつまんで紹介したい。
堺の商人から利休を自分の茶室に招待したい、との誘いがあった。利休は弟子を連れて、商人の茶室に向かった。華麗に準備の整えられた茶室に入って、主人のお点前が始まった。主人は利休の前でのお手前とあって、緊張の極みだった。遂には茶杓をおとしたり茶筅を転がしたりと、失敗が何度も続いた。弟子たちはお互いに目配せをして、クスリと笑いあっていた。
利休も弟子たちも茶を飲み干した後、商人が言った。「今日は誠に申し訳ありませんでした。失敗続きでとんだ失礼をいたしました」と、自分の無作法を利休と弟子たちに詫びた。商人の言葉に対して利休は、「いえ、いえ。ご主人のお手前は天下一でしたよ」と、褒め称えた。
帰り道、弟子の一人が利休に、どうして商人のお点前が天下一だったのか、と問うた。利休は答えた。「彼の心は、なんとしても私たちに最高のおもてなしをしたいと思っていた。それが緊張のあまり、あのように度重なる失敗となって現れたのです。その心根は天下一です」と。
私は、書き込みだらけで付箋だらけの教科書を前にして、不覚にも涙を流していた。『さすが、利休殿!』と。
この時、『等伯と利休』は、歳こそ20歳近く離れているものの、二人は師弟愛にも似た硬い友情で結ばれていたに違いない、と深く思った。次の小説の主要なテーマにするのは、これだと決めた。生活の全ての事は、小説に通じている。
先日の掛け軸を思いだした。「月落不離天」の禅語。「悟りとは、どこか別のところにあるものではなく、身近な所にあるのです」と教えた、中国の禅師の言葉である。
創作活動が円滑になるように、取材費をサポートしていただければ、幸いです。
