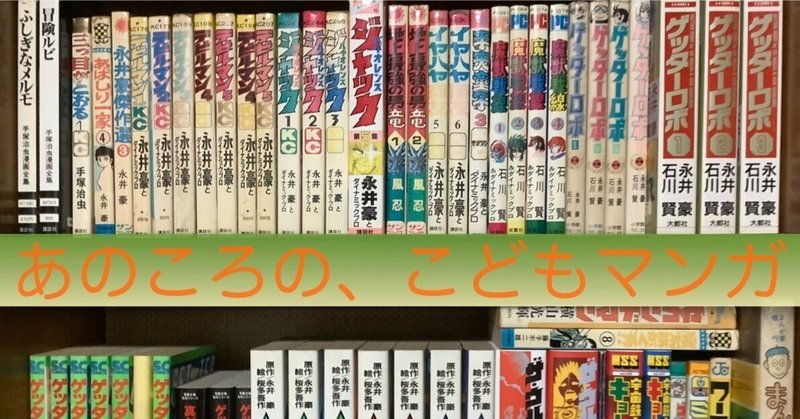
時間SF初体験?
記録をひもといてみると、『ドラえもん』の小学館学習雑誌での開始は1970年1月号から、だったようだ(※1)。
自分が小学校に入学したのは1971年4月なので、本当の連載開始からは1年ちょっと経っていたことになるが、記憶の中では、ちゃんとドラえもんが未来からやってくる話から読み始めて、未来に帰る話まで読み、しみじみとしていたら、翌月、あっさり帰ってきちゃったところまでがひと続きになっている。
……なっていたのだが(笑)、こどもの頃の記憶なんてものはだいぶいい加減なので(笑)、実際の学習雑誌での掲載順を調べてみた(※1)。
そうしたところ、自分の学年は、「さようならドラえもん」と「帰ってきたドラえもん」(※2)を、小学三年生3月号と小学四年生4月号とで、まさにリアルタイムで読んでいたということがわかった(コミックスでは6巻、7巻に収録)。
一方で、この学年が読んだはずの学習雑誌を遡ると、ドラえもんが未来からやってくる話は、入学した時の小学一年生では読めなかったようだ。
ちょうど2学年上の世代が新連載にジャストミートのようなので、2学年上だった姉の世代の小学一年生が家にあって、それで読んだ、という可能性が高そうである。
さて、『ドラえもん』の基本設定は今さら説明するまでもないが、幼稚園の頃に『ドラえもん』を読み始めていたとすると、自分が「タイムマシン」「タイムトラベル」などの設定に触れたのは『ドラえもん』が初めて、ということになると思う。
中でも、印象に残っているのはのび太の宿題をドラえもんが代わりにやってあげる話(「ドラえもんだらけ」(※2))だ。(コミックス5巻収録)
宿題の量が多すぎるので、一計を案じたドラえもんは、「2時間後の自分」「4時間後の自分」「6時間後の自分」「8時間後の自分」を連れてくるのだが、なぜかみんな誰かに袋叩きに遭ったようなボロボロの姿。なぜかと思っていると、宿題が終わったところで、連れてきた未来の自分たちに袋叩きにされるのだ。
ボロボロになりつつも、やれやれ宿題も終わったことだし、と、ドラえもんが眠りにつくと、当然ながら(笑)、2時間ごとに過去の自分がタイムマシンでやってくる…(笑)。
よくよく考えれば、普通に徹夜すればよかったのに、なまじタイムマシンがあったのでこんな事態に。
最初に未来の自分を連れてこようと思ったのも、眠りを邪魔されて過去の自分を袋叩きにしたくなるのも、同じドラえもんなのがおかしい。
普段は未来から持ってきた道具が巻き起こす騒動を描く『ドラえもん』の中で、変わった道具も出てこず、タイムマシンがあることで起こるループ構造をギャグにした一編。
まだ「タイムマシン」「タイムトラベル」が出てくる小説とかを読む前のことなので(※3)、自分にとっての時間SF初体験は『ドラえもん』だったのだろう。
因みに、この「同じ時間に同一人物が同時存在できる」というゆるい時間SF設定は、『涼宮ハルヒ』シリーズには受け継がれていると思う。
引用した3冊で描かれる「笹の葉ラプソディ」と『消失』がらみのエピソードがその代表例だろう。
未来からやってきたみくるちゃんがちょっと抜けているのも、ドラえもんの伝統なのかもしれない(笑)。
さて、今回、こどもの頃の記憶を検証していて、実はひとつ謎が残ってしまった。
上記の時間SFギャグの傑作「ドラえもんだらけ」の掲載号は、姉より一学年上だったようだ(姉が小学2年の時の小学三年生の1971年2月号)。
「さようならドラえもん」より前に、「ドラえもんだらけ」の話を読んだ記憶はあるのだ。
その頃、まだ『ドラえもん』のコミックスは出ていないし、雑誌に載っていたのを読んだという覚えもある。
はてさて、ぼくは小学三年生のその号をどこでどうやって読んだのだろうか。
おしえて、ドラえもん!?
<参考>
※1 『ドラえもん』の学習雑誌への掲載号・掲載順、サブタイトル等は以下のサイトを参考にした。
◆「ドラえもん」作品総覧
◆藤子・F・不二雄大全集 収録作品リスト
※2 本文中、『ドラえもん』のサブタイトルは現在のコミックス版に準拠した。
※3 当時、子供に向けた時間SFの映像作品としては、少年ドラマシリーズの『タイムトラベラー』などもあった。
少年ドラマシリーズは1972年に始まってはいたが、自分の記憶にあるのは『怪人オヨヨ』以降で、残念ながら、第一作の『タイムトラベラー』は本放映も再放送も観れていなかった。
『続・タイムトラベラー』の方は再放送を何度も観て、鶴書房の小説版『続・時をかける少女』もだいぶ読み返したものだが、これは小学3年以降に読んだものだったと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
