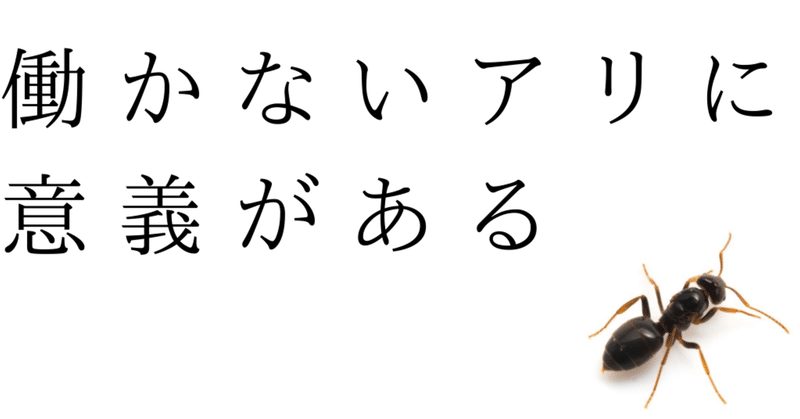
働かないアリに意義がある
こんにちは。「アリとキリギリス」の話は、もともと「アリとセミ」の話だったとか。たけぶち(@k_takebuchii)です。
さて、今回はこちら。「働かないアリに意義がある」を紹介します!
表紙の雰囲気から「怠け者に優しい本なのかなあ」と考えていたら、予想外にアカデミックな内容でした。
できるだけかみ砕きつつ、紹介していきます!
意外と知らない「ムシの社会」とは?
「働かないアリ」について語る前に、そもそもムシの社会がどう回っているかを把握しておく必要があります。
ムシの社会は「能力差のない(が、個性はある)個体の集まりが、必要に応じて局所的に勝手に対応していく」ことで最適化されています。
一言でいえばムシの社会は、仕事が生じたときに全体の情報伝達や共有なしにコロニーの部分部分が局所的に反応して処理してしまう、というスタイルなのです。(p.36)
脳が小さく高度な知能的判断ができないムシは、仕事の大きさに応じて単純な判断を積み重ねていき、局所的に対応します。個体の能力差がないため、中央集権的に管理する個体もいません。
社会性昆虫の個体のあいだに特定の仕事に対する「才能」の違いがあるとすると、才能のある者を向いた仕事に振り向ける別のメカニズムがあったほうが、有利になるはずです。しかしムシの場合はこのような複雑な制御をするよりも、能力差のない個体の集まりとしてコロニーがあり、誰がどの仕事をやろうともコロニーとしての効率に差が出ないようなシステムのほうが、コストがかさまないのかもしれません。(p.41)
能力の差を前提とする人間社会とは、そもそも社会構造が全く違うということだけおさえておけばOKです!
働かないアリに意義がある
ムシ社会では、必要な個体数を必要な場所に配置する管理システムがない代わりに、個体ごとに「反応閾値」があります。
「反応閾値」=「仕事に対する腰の軽さの個体差」を指します。
仕事が発生した際には「反応閾値が低い(=すぐ仕事にとりかかる)」ムシが仕事を担当します。逆に「反応閾値が高い(=仕事にとりかかるまでのハードルが高い)」ムシは、なかなか働き始めません。
しかしながら、「反応閾値が低い(=すぐ仕事にとりかかる)」ムシが優秀で、「反応閾値が高い(=仕事にとりかかるまでのハードルが高い)」ムシがダメというわけではありません。
「反応閾値が低い(=すぐ仕事にとりかかる)」ムシもずっと仕事をし続けられるわけではないので、その時には「反応閾値が高い(=仕事にとりかかるまでのハードルが高い)」ムシが必要なわけです。
ムシの社会が指令系統なしにうまくいくためには、メンバーのあいだに様々な個性がなければありません。個性があるので、必要なときに必要な数を必要な仕事に配置することが可能になっているのです。
このときの「個性が必要」とは、すなわち能力の高さを求めているわけではないのが面白いところです。仕事をすぐにやるやつ、なかなかやらないやつ、性能のいいやつ、悪いやつ。優れたものだけではなく、劣ったものも交じっていることが大事なのです。(p.76)
効率性を求める組織のリスク
企業は能力の高い人間を求め、効率のよさを追求しています。勝ち組や負け組という言葉を定着し、みな勝ち組になろうと必死です。しかし、世の中にいる人間の平均的能力というものはいつの時代もあまり変わらないのではないでしょうか。それでも組織のために最大限の能力を出せ!と尻を叩かれ続けているわけです。昨今の経済におけるグローバルリズムの進行がその傾向に拍車をかけています。(p.77)
効率化を求める組織は、「優秀」な人を雇い「無駄」を徹底に省く方向に進んでいきます。
ところが、「優秀」「無駄」の基準は、どんどん変化していくし、変化していく中で特定の基準において「優秀」な人だけでは対応していけません。逆に、今は「無駄」とされることに価値がついていく可能性もあるわけです。
昨今では「個性が大事」という風潮も広まりつつありますが、それは「特定の分野で優れている」ことを前提としているように感じます。
「優れるな異なれ」とは人間社会でもよく言われていますが、こうしてムシ社会を見ていても、やはり「特定の基準で優れるよりも、異なっていることの方が重要である」といえそうです。
「アリとキリギリス」において、アリは働き者として描かれていますが、キリギリスのような存在も必要なのかもしれませんね。
頂いたサポートは書籍代の一部として利用しています🙇♂️ ※たけぶちは、Amazon.co.jp アソシエイトメンバーです。
