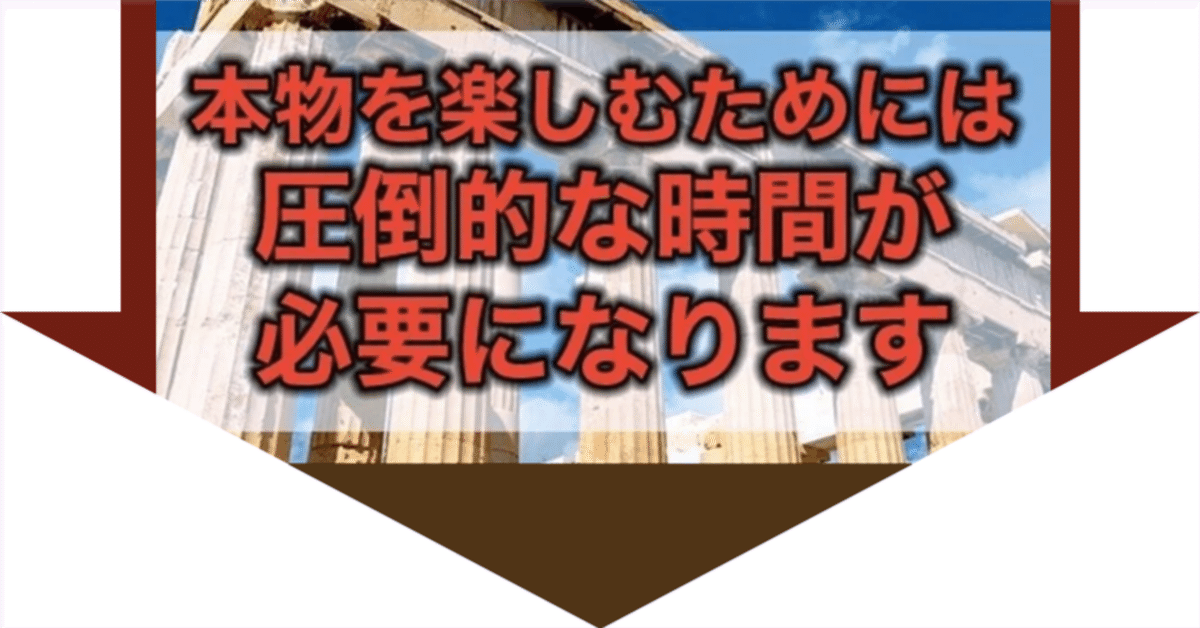
32/何故、偽物の方が好かれるのか?
第4章 キッチュ
<3,233文字>
【記事のポイント】『キッチュ』という名称は、『アヴァンギャルド』や『デカダンス』に比べると認知度はグッと落ちるはずですが、近代的な時間意識を考える上では、とても大切なキーワードです。
1. 悲しい本物と楽しい偽物
この章では、キッチュの考察とあわせて、第二次世界対戦以降の時代を徐々に見ていきます。
第5章では、1970年代を1年ごとに見ていきますが、その助走です。
第二次世界大戦が終ってしばらくすると、ペギー・グッゲンハイムは大好きな街ヴェネチアへと帰っていきました。
その行動は、まさしくヨーロッパ生まれの前衛芸術家と同じでした。
ニューヨークは、ペギーが生まれ育った街でしたが、彼女にとっては終生異郷だったのかも知れません。
ヴェネチアに移る時には、二人目の夫マックス・エルンストとも離婚していました。
ニューヨークの美術状況も様変わりしたので、あまり思い残すこともなかったのでしょう。
ペギーは、ヨーロッパの前衛芸術をアメリカに紹介し、それによって刺激されたアメリカ人の若手芸術家たち、中でもジャクスン・ポロックを大切に育てました。
しかし、価値が認められるやいなや、現代美術の作品はまたたくまに投資の対象になり、状況は一変してしまったのです。
作品の内容ではなく、値段の変動が人々を引きつけました。
ペギーはその状況を嘆きながらも、そうなる前に自分の大切なコレクションが形成できたことを、喜びとともに回想しています。
文化的な価値判断は、元来細やかな違いを認識できることでした。
絵画に隠された意味を丹念に追いかけたワーブルク研究所のモットー「神は細部に宿る」は、その信念のあらわれです。
ここから先は

文化史的セルフイメージ・アップ
マインドブロックをつくり出しているのは、自分自身です。それが腑に落ちると、すべては一気に好転し始めます。ただし、つくり出す過程は『自分一人…

モダンの5つの仮面/日本人が歩いてきた道
日本人の意識が、なぜ1970年代に大きく変わったのか? それは、ビデオの登場によって映像の視聴体験がまったく別の形になったからです。 ビデ…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
