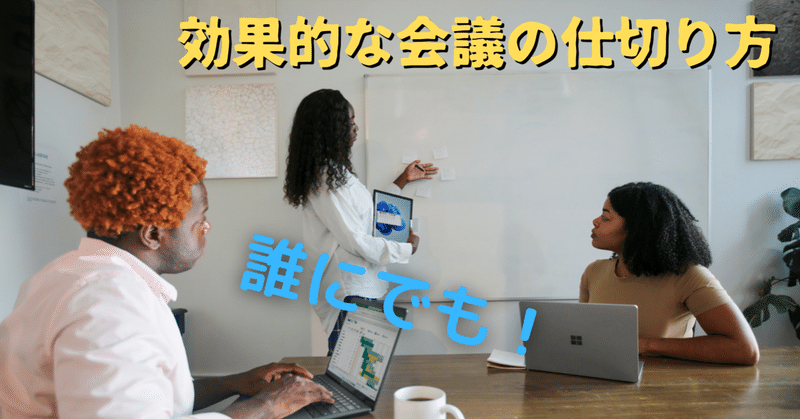
【時は金なり】効果的な会議の仕切り方
皆さんこんにちは!じゅんです!
今日も僕の記事にアクセスしていただきありがとうございます!
今回は僕の大っ嫌いな会議についてお話ししようと思います。
僕は民間企業での勤務経験がないので、一般的な会議がどのようなものなのかよく分かっていません。ですが、少なくとも学校の会議はもはや会議ではないと思っています。あれは朗読会だと。
そんな僕は1秒でも会議を短くしたいと思っているわけです。
ただ、そのためには単純に短くしようと発言を早くしたりすればいいというわけではないのです。その前の準備段階が大事だということを連続で紹介しているこちらの本から学びました!
ではどういうふうにすれば会議が短く、そして効果的になるのか、一緒に見ていきましょう!
大前提
まず理解しておかなければならないことは、不要な会議を減らすという前提です。そもそも会議を開く必要があるのかどうか、そこをあらためて見直す必要があるということです。
人間は与えられた時間はいっぱいに使おうとする心理を備えています(パーキンソンの法則)。ですので、たとえ開く必要のない会議であったとしても何かと話をしてしまうのです。
そうなると本来必要のない会議を開き、さらに必要のない仕事が生まれる可能性もあります。まさに悪循環ですね。
そういうことから大前提として不要な会議を開かないということを念頭に入れておきましょう。
会議の分割

その前提の上で、会議を3つの役割に分担することで短時間かつ効果的なものにすることができます。その3つというのが、
・情報共有
・アイディア出し
・意思決定
です。ではそれぞれでどんなことに注意すべきか見ていきましょう!
・情報共有

僕自身、会議は情報共有の場ではない、というスタンスです。
ただ、情報共有を会議の場ですることのメリットも承知しているので完全否定はしないようになってきました。
ただし絶対にやめなければならないことは、資料の読み上げです。
これだけは絶対ダメです。なぜなら口頭で読み上げる時間よりも黙読で目で字を追っていく時間の方が短いからです。
だからこそ情報共有する側の人は資料を読んだらわかる状態に体裁を整えて、会議の場では「◯分資料を読んでください・・・<◯分後>・・・何か質問はありますか?」という形にすべきなのです。
・アイディア出し

ということでまずは情報共有を会議から少し取り出した形にしたところで、いよいよ会議らしい役割に入っていきましょう。
その1つがアイディア出しです。ブレインストーミングなどと言い換えることもできますね。
ここで大事なことは、質よりも量だということです。
そしてなぜアイディア出しという役割を抽出するのかというと、その量をたくさん生み出すためです。
後述する意思決定と役割がごちゃ混ぜになっているとどうなるでしょうか?
「予算を100万円上げる」というアイディアが出たとしてそこに、「じゃあそれはどの部署から捻出するんだ」という反対意見が出たとしましょう。
そうなると、なかなか斬新さや突飛さのある新しいアイディアは生まれにくいでしょう。
これが意思決定とアイディア出しが分割できていないことによるデメリットです。
アイディアを出すときに重要なのは、どんな意見でも肯定的に受け入れること、そして誰でもどんな意見でも言いやすい雰囲気を作ることです。
そのための具体的アクションとしては最初に出てきたアイディアを称賛すること、それもできるだけ大したことのないアイディアであれば好ましいでしょう。
そうすれば周りの人たちは「こんな意見でも言っていいんだ!」という前向きな気持ちになりますので。
・意思決定

そのアイディア出しが終われば最後に選別も含めて意思決定の役割があります。
これはアイディア出しの流れで始まるものでもあれば、それまでにやってきた成果をもとに今後どうしていくか、というものでもあるでしょう。
ここで気をつけるべきことは全て会議に始まる前にあります。
1つは人員。
意思決定の場では必ず各部署のリーダーなどの出席すべき人が出席するようにすることです。いわば僕のようなペーペーが出席すべきではないということです。
言い換えれば必要最低限の人数で開催することとも言えますね。
多過ぎたところで先ほどのアイディア出しの時のようなメリットはありませんので。
適切な人員が出席すれば、次にすべきことは冒頭で評価軸を明確にして、どのように決定するかを決めることです。
意思決定の場ではやはりそれぞれの部署や役割によって意見が割れたりするものです。そこで不毛な議論にならないようにまずは何をもって決断するか、その判断基準を決めるのです。
言わば根拠のようなものですね。
組織が何を大切にしているか、それを表すものとも言えるでしょう。
そして多数決なのか、推薦制なのか、といったどのように決めるかということも含めて本題に入る前に決めておきましょう。
この時点で決定方法に全員が合意をしていればのちに不要なわだかまりを生まなくてすみますので。
下々の人たちは?

そんなこんなで偉そうに語ってきましたが、結局これは会議をファシリテートする立場の人ができることなんですよね。
じゃあ、下々の僕たちには一体何ができるのでしょうか?
・資料準備
・アイディア出し
・少しの勇気と行動
これら3つが僕たちにできることだと考えます。それぞれ簡単に述べていきますね!
・資料準備
先ほどの情報共有のところで述べましたように、読めばわかる資料作りを徹底すべきです。
作りが甘いのに「黙読してください」と言ったところで「読んでもわからんわ!」と突き返されるかもしれません。
そうならないようにしっかりとわかりやすい資料を作るようにしましょう。
・アイディア出し
次にアイディア出しでは言いやすい雰囲気ならばどんどん意見を言いましょう。
正直これに関しては環境に大きく影響されると思います。何か言ったら咎められそうな雰囲気ならば黙っておくのがいいかもしれませんね。
ですがそうではなく何でも言える雰囲気ならどんなアイディアでも言ってみることに価値があるかもしれません!
・少しの勇気と行動
最後に少し精神論の話をします。
それが少しの勇気を持って行動をしようということです。
具体的には資料を口頭で読まずに「僕が読むよりもみなさんそれぞれに読んでいただいた方が早いと思うので、3分でざっと目を通してみてください」という発言をすることが挙げられます。
他にも、誰かの発言の後に「確認なんですけど、僕と田中さんはこういう動きをすればいいですよね?」と質問してみることもありです。
そんな風に何でもいいから会議でちょっとした勇気を持って行動をしてみること。これがなぜいいのかというと会議に向き合う姿勢が主体的になるからです。
僕自身2年前までは適当に会議に参加していましたが、少しの発言をするようになってからはもっと前向きに取り組むようになりました。
そんな中でもっといい会議にしようという提案をお偉いさん方だけの会議にに出席して提案することもありました。
そんな小さい勇気と行動をするだけで少し大きなことができるようになったんです。そんな経験から小さな勇気を持って行動をすることが大切なんだと言えます。
まとめ
さて、いかがだったでしょうか?
今回は短時間かつ効果的な会議にするための方法についての記事でした。
では、振り返りをしていきましょう!
大前提
そもそも不要な会議を開かないという前提を持っておくこと。
会議の分割
・情報共有
会議では基本必要ないとは思っているが、するとすれば資料を読み上げず黙読してもらう。
・アイディア出し
どんなアイディアでも歓迎し、質より量にこだわること。
否定的な意見は全て排除し、誰でも何でも言える雰囲気が大切。
・意思決定
重要なのは会議の前。出席すべき人のみが出席し、どのような評価軸でどのように決定するのか、これらを本題に入る前に決定しておく必要がある。
下々の人たちは?
会議を仕切るわけでもない人にとってできることは以下の3つ。
・資料準備
・アイディア出し
・少しの勇気と行動
特に勇気を持って行動すればその後に成長と大きな挑戦が待っている。
ぜひほんの少しでもいいからやってみてほしい!
今回の記事があなたの生活向上の一助となれば幸いです!
ではまた!
↓今回の参考文献はコチラ!↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
