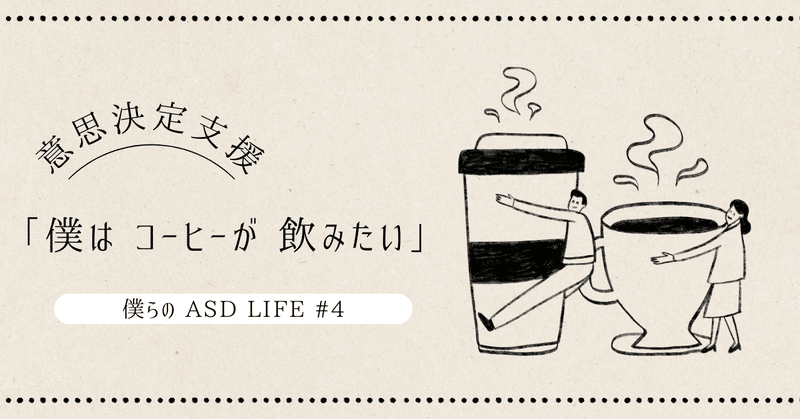
「僕は コーヒーが 飲みたい」
トライフルは、ASDの方の就労や生活を支援している。今日は彼らとの関わりの中でいくつか、印象に残るエピソードを紹介していきたい。
①いつもついてない電気がついていて、気持ちが悪い
Aさんは知的障がいのあるASDの男性だ。ある日、入浴時に何かを私に訴えてきた。よく見ると「風呂だき」というボタンを指差している。最初私も「お風呂入ったね、どうぞ」など、応えたりしていた。しかし、何か腑に落ちない表情を浮かべるAさん。よく見ると「風呂だき」のボタンの上の電気がついている。とっさに私はその電気を消した。するとAさんは満足気にいつものルーチンワークに戻っていった。
なぜか。この日は「風呂だき」ボタンを押して自動で湯張りをしたのだが、いつもは水道の蛇口を捻って湯張りしていたため、電気がついていたのは、この日が初めてだったのだ。「いつもついていない電気がついている」という状況は、私たちにとっては本当に些細なことであるが、彼らにとっては「大きな変化」なのだ。ASDのある方は、シングルフォーカスといって、全体よりも細部へ注目する特性がある。また、関係性を捉えることが苦手で、モノトラックといって、一度走り始めるとなかなか自分の行動を変更するのが苦手な特性がある。上記のエピソードはそういったASDの特性を物語るものであり、本人にとっては大きな意味を持ち、そのことが生活の困難さにつながっている可能性があることを感じた。だからこそ、ASDの方を支援する際にはしっかりとアセスメントすることが大切なのだ、とあらためて感じた。
②「僕は コーヒーが 飲みたい」
ある朝、グループホームで牛乳を飲んでいた私をみたBさん。なにかものありげな顔でこちらをみた後、自室へ戻っていった。なんだったんだろうと思った矢先、ご自身のお話ブックからカードをバーに張り替えて、そのバーを私の元へやってきて手渡した。そのバーには、「僕は コーヒーが 飲みたい」という3枚のカードが貼られていた。嬉しくてすぐにコーヒーを入れて彼に手渡すと、嬉しそうにそのコーヒーを飲んでいた。
Bさんもいわゆる重度の知的障がいがあるASDの男性だ。表出言語はない。しかし、このようにコミュニケーションをとることはできるから興味深い。なぜこのようなことができるのか。それは、これまでの「療育の積み重ね」があったからだと思う。お話ブックは確かに優れた支援ツールではあるが、療育なしに、初見でこのツールを使いこなすことは到底できない。「カードを張り替えて」ということもポイントだ。ASDのある方は視覚的にものを考えることが得意だという特性を活かして、Bさんなりにカスタマイズしたカードを用意してあったため、表出言語を持たないBさんであっても、こうしてコミュニケーションをとることが可能なのだ。あらためて、成人期の支援現場では、幼少期や学齢期の積み重ねが生活に活きるということを感じた。早期から適切な療育を積み重ねることが大切であり、どんな些細な療育の積み重ねであってもそれは必ず将来に活きると確信した。
ASDのある方との生活は、新しい発見の連続で、とてもおもしろい!
これが僕らのASD LIFE。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
