
【試し読み】斜線堂有紀の恋愛小説『君の地球が平らになりますように』
恋愛小説の新作短編を斜線堂有紀さんから頂きました。……仮に、昔好きだった人と再会したとして。もしかしたらまた恋がはじまるかも? 期待は膨らむけれど、もしその好きだった人が、以前とずいぶん変わってしまっていたら……たとえば、『陰謀論』にどっぷりはまっていたとしたら……。斜線堂有紀のおくる恋愛地獄篇、開帳。12月にはnoteで掲載された作品+書き下ろしを加えた単行本が発売予定です。
斜線堂有紀(しゃせんどうゆうき)
第23回電撃小説大賞《メディアワークス文庫賞》を『キネマ探偵カレイドミステリー』にて受賞、同作でデビュー。『コール・ミー・バイ・ノーネーム』『恋に至る病』『楽園とは探偵の不在なり』『廃遊園地の殺人』など、ミステリ作品を中心に著作多数。恋愛小説集『愛じゃないならこれは何』絶賛発売中。
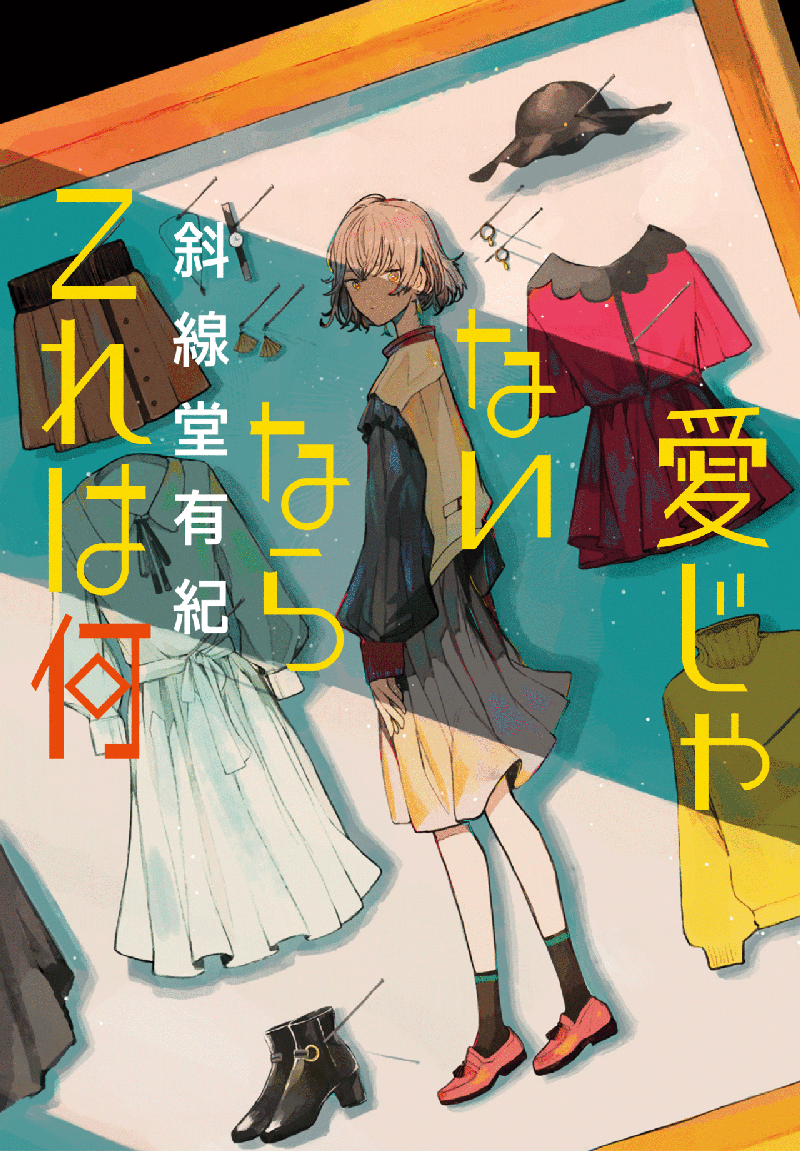
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-790068-2
君の地球が平らになりますように
辛くなった時、悲しくなった時、待﨑小町(まつざきこまち)は東壱船(あずまかずふね)が断頭台に立たされるところを想像する。
東は大勢の人間に石を投げられ、刑場に引き立てられていく状況でもなお美しく、凜としている。だが、彼を今までのように扱う人は誰もいない。薄情なものだ。みんな、あれだけ東くん、東くんと群がっていたというのに。仕方ない。だって、東は変わってしまった。罪人だから。もう誰も東のことを好きじゃない。
そんな中で、小町だけは颯爽と彼の前に躍り出るのだ。驚いた東は、小町だけを見つめる。群衆の投げる石は小町にも当たり、額から血が流れるけれど気にしない。投げるなら投げればいい、と彼女は思い、東のことを見つめ返す。刑吏が小町を引き離そうとするが、彼女は必死に抵抗する。
やがて小町はぞんざいに引き剥がされ、ごろごろと地面に転がるだろう。群衆はどうしてあんな男を、と吐き捨てるように言う。でも、小町は諦めない。最後の最後まで、東を救う為に走ろうとする。東は後ろ髪を引かれるように、小町のことを何度も振り返る。
──みんなに嫌われてしまった、蔑まれるようになってしまった可哀想な東くん。それでも私は、貴方が好き。みんなが見ていた上っ面じゃなく、貴方そのものが好き。
小町は諦めず、断頭台に共に立つ。東はどうしてそこまで、と思いながら彼女を見つめる。世界中の人間に嫌われているのに、どうして小町だけが自分を愛し続けていてくれるのだろう、と困惑する。
そこで初めて、彼は自分が選ぶべきだったのは誰かなのか、本当の愛がどこにあるのかを知るだろう。確かに、少しだけ遅かったかもしれない。けれど、小町はそれを責めたりなんかしない。だって、最後の最後に、東は小町を見つけてくれた。
それだけで、小町は充分だった。幸せだ、と心の底から思う。
自分が真に報われる場所は、この孤立無援の断頭台だった。そんな状況があるはずもなくても、小町は幾度となく夢を見た。
英知大学二年、東壱船はボランティアサークル『猫の手』の中で二番目に人気の男だった。
あまり飲み会が得意なタイプでもないし、わざわざ自分から会話を切り回す方でもない。けれど、さりげない気遣いは出来るし、サークルの運営は殆ど東がやっていた。しかも、大変そうな素振りを見せない。真面目な好青年、という言葉を体現したような大学生。それが東壱船だった。
黒髪に眼鏡のビジュアルも、大変に受けが良かった。だって、素材が良くなければ良いと言えない要素ですし? その通り、東壱船は素材が良かった。
一方の小町は、どこか浮いたところのある冴えない女だった。
ただ地味であるというだけならまだいいのだが、なんというか、全体的に垢抜けなさが滲み出ているのである。極度に悪い顔立ちをしているわけじゃない。目立つ外見的欠点があるわけじゃない。それでも、小動物を思わせる彼女には、おどおどした印象が濡れたビニール袋のように纏わり付いているのだった。
それなのに、小町は不幸にも東に恋をしてしまった。何か好きになるきっかけがあったわけではない。強いて言うなら外見が好みだったから。あの、いかにも理知的な、綺麗な顔つきが好きだ。それだけで、小町はいとも簡単に彼のことを好きになってしまった。
恋なんてそのくらいで構わないだろう。
とはいえ、小町と東が接近することはなかった。東はそもそもがそんなに社交的なタイプではないし、サークルの飲み会でも、彼は学部の同じ男友達と固まって話しているか、サークル幹部の女子と話しているのが常だった。
小町は三つほど離れた、聞き耳を立てられる限界の席で、にこにこと東のことを見つめていた。直接の会話は無くても、それで小町は充分幸せだった。
「てかさ、東はどういうのがタイプなわけ?」
とある先輩の一人が、飲み会の最中に不意に尋ねる。小町の心臓がぐうと爪を立てられたように痛んだ。息すら詰めて彼の返答を待っていると、ややあって東は言った。
「うーん……食べ方が綺麗な人かな。やっぱり、そういう生活の仕方が現れてるところに育ちとか、考え方とかが出るんじゃないかな、と思うし」
途端に、小町は自分の皿に盛られたサラダが恐ろしくなる。こんもりと盛られたそれは、切り崩されるのを待っていた。東はこのサラダをどう食べるのを正解だと見做すだろうか。もし正解を出せたら、私のことを気にしてくれるだろうか?
小町の動揺を余所に、同級生の一人が「東っていかにもそういう大和撫子っぽいの好きそうだよなー。なんか逆にポリコレ的にどうなんそれ」と笑う。すると、東は心外だと言わんばかりの表情を浮かべた。
「ポリコレと食べるのが綺麗な人が好きっていうのはは関係ない。女性はそうあるべき、とか考えているわけじゃない。単に、生活がちゃんとしてる人が好きなんだ。自分で食べるものを自分で管理出来るような」
「つまりは料理上手ってこと? やっぱおしとやかな黒髪系が好きなんじゃん」
雑な理解で纏められて、東は更に不服そうな表情を浮かべた。けれど、それ以上何を言っても無駄だと思ったのだろう。溜息を吐いてビールを一口飲む。隣に座っている女の子が「えーでも、そういうところで人を見る東くんってかっこいいよね」とさりげなく盛り立てた。
強くなった鼓動は鳴り止まなかった。小町は出来るだけ綺麗な箸使いで、ミニトマトを摘まみ上げる。東は来年の学祭をどうするか、冬の合宿は何をするかに話題を変えていた。対して、周りの女の子達は恋バナに話を戻したがっている。東壱船の恋愛に、みんなが興味津々なのだ。
小町はミニトマトを奥歯でゆっくりと噛む。東は一度も小町の方を見なかった。
程なくして、小町の恋は終わった。ごく自然に、東に恋人が出来たのだ。
恋人の座を射止めたのは一個上の代の先輩で、いかにも大和撫子というような綺麗な女だった。料理が趣味で、食べ方が綺麗。飲み会で確認出来た箸使いは確かに美しかった。東はとても正直に自分の好みを語っていたのだな、と小町は思った。
あれから小町は綺麗な箸使いを練習し、料理もYouTubeを使って一から学び直した。だが、それをアピールする機会には恵まれなかった。件の先輩はきっと、東にそれらの美点を見つけてもらえたのだろう。
小町はチャンスを与えられなかった自分を悔やんだ。もっと何か機会があれば、東はきっと自分のいいところに気がついてくれたはずなのに。料理だって味わってくれたはずなのに。自分が待っているだけだったから、この恋が叶わなかったのだ。
やり方を間違えた。時間が戻せるなら、と小町は本気で思った。時間が戻せたらもっと上手くやれる、と本気で思ったのだ。
だが、その彼女と東は半年後に別れた。
理由はよく分からなかった。だが、生真面目な東が美人の先輩と別れたことはサークル内でも面白がられ、なんと『フラれた東壱船を慰める会』まで催されることになった。場所は、とあるサークル部員の自宅だった。
開催の旨はサークルのグループLINEで報された。──一人一品は差し入れを持ち込むこと。酒代は割り勘で別途徴収のこと。参加自由。
この『参加自由』の後ろには、仲の良い面子なら、という見えない括弧書きが入っている。それでも、小町はすぐさま送った。
『私も行っていいかな。国分寺なら家から近いんだ』
小町の家から国分寺は、五十六分の距離だった。
主賓である東はそこまでへこんだ様子でもなく、とはいえ完全にどうでも良さそうな雰囲気を纏っているわけでもなく、とても良い塩梅だった。健全で理想的なお付き合いが、スマートに終わった気配。
男女比は七対三だった。もっと来ると思っていたのに、と小町は意外に思う。東のことを狙っている人間なんて他にもいくらでもいそうなのに。きっと別れたばかりの東に気後れしたのだろう。
つまり、ここに来ているのは形振り構っていられない側の人間なのだ。
狭い折りたたみテーブル二台の上には、所狭しと食べ物が並んでいる。チーズやサラミなどの定番のおつまみの他に、明らかに駅ナカで買ってきたのであろう高級そうな惣菜や、タッパーに入った手作りの料理が載っていた。みんな考えていることは同じだ。
小町も、チータラを除けて自分のタッパーを載せた。祈るような気持ちで捧げ物を置いた後は、部屋の隅でただジンジャーエールを飲んでいた。この規模の宅飲みになると、何人かはテーブルから弾き出されることになる。別に文句を言うつもりじゃない。そういうことはままある。
東は延々と人に囲まれている。この狭い部屋だと、逆に彼の会話が聞こえない。小町はただチャンスを窺った。
そうして、酔い潰れて眠る人数が増えた頃合を見計らって立ち上がった。空いたグラスやタッパーを持って、台所に向かう。スポンジに洗剤を含ませたところで、東がやってきた。
「洗うの?」
「うん。ある程度まで洗っておけば楽かなって。ほら、野口くんの家だし。みんなが帰ってから野口くんが一人で洗うの大変だろうから。私こういうの好きだから、やっておくから気にしないで」
訊かれてから答えればいいのに、小町は早口でそう言った。予想は当たっていた。東はこういうことを率先してやる相手のところにやって来る。何しろ真面目だし、気がつくから。
「俺もやろうと思ってたんだけど、待﨑さんに先を越されちゃったな。ありがとう。損な役回りやらせちゃったな」
「ううん。本当に……私が気になるだけだから」
それに、損な役回りだなんてご冗談がきつい。リビングに取り残された何人かの女の子は、眠たげな目の奥でこちらを注視している。そして、いち早く動き出した小町のことを妬ましく思っているはずだ。立場が逆だったら、小町もそうしていた。
「東くんも戻っていいよ。ここは私がやっちゃうから」
「あーいや……酔い冷ましたいし。ちょっとここにいる」
東がゆるく首を振る。そう言うと思った、と小町は心の中で思った。誰かが雑用を引き受けていたら。それを見守ってくれるのが東だ。彼の真面目な性質は、先読みを楽にする。ややあって、小町は皿を洗いながら尋ねた。
「東くん、三木先輩とどうして別れたの?」
三木先輩というのは、例の美しい彼女のことだ。
東と三木先輩がどうして別れたのかは、この飲み会でもはぐらかされてきたところだ。みんなの前でする話じゃない、とのことだったが、東はゆっくりと溜息を吐いて言った。
「ああ、……うんまあ、付き合ってみたらあんまり話とか考え方とか合わなくて」
「そうなんだ」
「顔合わせて険悪になるくらいなら、離れた方がいい友達になれるのかもしれないって話し合ったんだ。最近は本当に顔合わせるとすぐに言い合いになるっていうか」
東がぽつぽつと理由を話してくれるのが嬉しかった。少なくとも小町は、二人の破局を茶化したりしないと判断されたのだろう。指先を冷たい水が伝う。
「そういうこともあるよね。……うん」
「でも、別に葉子先輩のことが嫌いになったわけじゃないんだけど。別れたというよりは、関係の名前を変えるって意識かな。建設的な二人でいる為に、敢えて選んだことなんだよ」
さりげなく差し挟まれた名前呼びに、小町の心がぎゅうと抉られる。だが、それはもう終わった話だ。これからには関係が無い。小町は意を決して口を開く。
「あの……今日出てきた昆布巻きどうだった?」
「あー……あれ? 豚肉と……あと、海老しんじょのやつ」
そう言われただけで、小町の心臓が跳ねた。ちゃんと、認識されていたのだ。
「もしかして、あれ作ったのって待﨑さん?」
「うん。そうなんだ。どうだった?」
「なんか一人だけしっかりしてるもの作ってる子いるんだなーって感心したわ」
「じゃなくて、味……」
「味は勿論美味しかったよ。味つけが俺好みで」
「……そうなんだ。良かった」
「ああいう丁寧な和食が作れるのは凄いよ。出汁も出来合いのものじゃないんだろ」
「あ、うん……ちゃんと……取って……」
バリエーションに欠けた返答をしながら、小町は密かに震える。
地味だけど丁寧に作ってある料理は、小町が一生懸命考えた『東の好きそうな料理』だった。ここに来ている他の全員を無視して、東の為だけに作ったものだ。それを、東がちゃんと喜んでくれている。
駅ナカで買ったローストビーフやカルパッチョの方が、周りのみんなが喜んで食べていた。けれど、東が求めているのは──本当に大切にしているものは、こちらであるはずだった。
「こういう会あんまり来ないんだけど、会場が近かったし、何かパッと作って持ってくの好きだから来たんだ」
「待﨑さんって料理上手いんだね。知らなかった」
「料理はそんなに上手なわけじゃないけど……外食とか買ったものとかだと栄養が偏るから、必要な分はちゃんと自分で作ろうとしてるだけ」
「へえ、偉いね。やっぱり外で食べるよりも自分で作った方が何を食べるか自分でコントロール出来るしね」
東は一層嬉しそうな顔をして、楽しそうに言った。もしかしたら東自身も料理が好きなのかもしれない、と小町は思う。このままずっと話をしていたかった。三木先輩よりもずっと、私の方が話が合うでしょう? と言いたかった。これはいつか選んでもらう為の布石なのだ。
無情にも皿が洗い終わって、東は元の位置に戻ってしまった。小町も部屋の隅に落ち着く。終電の時間まで、小町はぼんやりと東のことを見つめていた。
ところで、この飲み会が功を奏したとは言い難い。東は二ヶ月も経たない内に、三輪桃華と付き合い出した。サークルで書記をやっている可愛い顔立ちをした女で、件の飲み会には自分で作ったエビチリを持ち込んでいた人間だった。
そのエビチリは市販の中華調味料の味がしたのだけれど、東にはそんなことは分からなかったのかもしれなかった。
そこで小町は悟った。
『料理上手な女』も『食べ方が綺麗な女』も、全部第二段階の話だった。東の恋人になる為には、美しく目を惹く女であることが必要なのだ。それが第一段階で、クリアしていなければそもそも土俵に上がれない。
東壱船と三輪桃華との交際は長く続いた。小町と東の接点が無くなるまで、自分達が卒業してしまうまで、二人は付き合い続けた。そこになってようやく、小町は東を諦めることが出来たのだった。そこから先を観測出来るほど、小町は東と親しくなかったからだ。
顔が熱くなる。何が海老のしんじょだ。しっかりしている味が何だっていうんだ。
認められてなかった。あの言葉には、何の意味もなかった。
出汁を取った待﨑小町は、中華調味料を使った三輪桃華に負けるのだ。
それから五年が経った。
卒業した小町はとある銀行で働いていた。受付の業務はストレスが溜まることも多かったが、やるべきことがはっきりしているというのが向いていた。それに、休みがしっかりと定まっているところもいい。
たまに、東壱船の夢を見た。現実に即した夢だ。東はみんなから惜しまれ、隣に三輪桃華を置きながら卒業していく。綺麗になった小町の箸使いも、あれからすっかり上手くなってしまった料理も置き去りにして。
あるいはこんな夢を見た。三輪桃華に手酷く裏切られ、もう誰も信じられないと思った東の前に現れて、手を差し伸べる。東はその手を取ってくれて、本当は誰を選ぶべきだったかを悟る。
五年も会っていない東のことを定期的に思い出してしまうのは、執着というよりは惰性だった。あるいは、揺らぐ復讐心だろうか。この五年、小町の世界には恋が無い。勿論、機会はあっただろう。けれど、それは小町の恋ではなかった。
打算的になれるほどの愛情が無ければ、それは恋とは呼べなかった。孤立してほしいのは、東壱船ただ一人だった。卒業した東壱船はコンサルという業界外の人間にはいまいち何をやっているのか分からない職業に就いていた。卒業してから、一度も会っていない。
『ボランティアサークル・猫の手/第八期同窓会』の知らせがLINEグループに投稿されたのは、その時だった。場所は赤坂にあるダイニングバーだ。添えるように投稿された『運営手伝ってくれる人募集します!』の文字に、小町の目が引きつけられた。
「ひっさしぶりー、元気してた? 待﨑さん全然変わらないねー」
五年ぶりにあった戸練こよりは、大きな目を輝かせて笑っていた。カフェラテ入りの小さなコーヒーカップを持つ手には、やたら幾何学的な模様のジェルネイルが張り付いている。
「マジでやること多くてさ。しっかりしてる待﨑さんに手伝ってもらえるのはありがたいわー。えっと、今何してるんだっけ?」
「NNC銀行で働いてる。……総合職とかじゃないけど」
「えー大手じゃん。やっぱり真面目な子が最後は勝つんだね」
戸練は何が面白いのかくっくっと引き笑いを漏らした。彼女自身は今、大手の広告代理店に勤めているらしかった。
「基本的に私が面子は集めてて、会場も押さえてるから。あとは、この会場との打ち合わせを待﨑さんに頼もうかなって」
さりげなく負担が重いところを任せられたな、と思ったが、背に腹は代えられなかった。自分の考えていることを実現させる為には、これしか方法が無かったのである。ややあって、小町は言った。
「あの……東くんは呼ばないの?」
「え?」
「ほら、サークルの副代表だった……東壱船くん、だっけ? 下の名前は怪しいんだけど、名前が無いなって」
忘れるはずもない名前をさりげなく口にしながら、様子を窺う。
「まだ参加したいって連絡が来てないのかもしれないけど、もう〆切間近だし……こっちから声を掛けてみるのはどうかなって思ったんだよね」
「あー……もしかして待﨑さん、知らない側か」
今度は小町が「え、」と言う番だった。そんな小町の様子を見て、戸練は更に笑みを深めた。
「東、東ねえ……うん。マジで? 呼びたい?」
からかうように言われた言葉に対し、小町は食い気味に頷く。何しろ、東はこういう場に必須の人間じゃないか。招待しないでどうする、呼べ。だが、戸練はニヤつきながら続ける。
「ここだけの話、東マジでヤバいんだよ。どんどん悪化しててさ」
「もしかして、何か病気とか……?」
「ある意味で病気だよ。てか、声掛けてもいいけど、その場合待﨑さんに相手してもらうことになるけどいいの? ま、他にも待﨑さんみたいに事情知らない人いるかもだから、呼ぶのもアリかー……」
戸練は困ったように笑ったが、そこには確かな優越感も滲んでいた。そんなことも知らないの? という暗い喜び。大人しく優越感の餌になっていると、彼女は囁くように答えを告げた。
「あいつ、めちゃくちゃ病んじゃってさ。陰謀論? っていうのかよくわかんないけど。あいつのアカウント教えてあげようか? 見たらわかると思う」
そう言って、戸練は薄ら笑いながらスマホの画面を見せてきた。
そこには、東の顔写真をアイコンに使ったアカウントが映っていた。
東壱船@自葎会
自葎会東京Fサブリーダー。自然を愛する医食同源伝道師。本氣で日本をよくしたい。未来のために、子どもたちを毒から守ろう!利権の為に輸入される毒食品にNOを。気づき2020/6/9
「本名でこれやってんだよ。ヤバくない?」
「自……なんて読むの? これ」
「りつ。自分で立つって意味の自立を、漢字変えてんだよ。何か知らないけど、草冠には自然のパワーが含まれてるんだってさ」
「どういうこと……?」
小町はいかにもしおらしく、教えを乞うような顔つきで言う。
「意味、分っかんないでしょ。みんな分かってないよ。自然のパワーって何? 怖いよね」
「東くんがこの自葎会っていうのに入ったから、同窓会呼ばないってこと?」
「呼ばないっていうか、あっちが来たがらないだろうなってこと。だってさ、前に東と会った時、輸入食品には毒が入ってるだの、水は一度煮沸しなくちゃ飲めないだの言ってさ。カフェに自分で沸かした白湯入った水筒持参して……んで杉田と揉めたんだよ」
今度はいかにもうんざりとした表情だった。被害が自分の友人に及んだからか、ただ笑っていられなくなったのだろう。
「またあんなことになったら気まずいじゃん。だから、声わざわざ掛けるのもなって。反応無いっていうのはそういうことでしょ」
「ああ、じゃあ……声、掛けない方がいい?」
小町がそう言うと、戸練は微妙な表情で言う。
「や、待﨑さんが相手出来るって思うなら呼んでもいいんじゃない? 揉めなきゃいいわけだから。……てか、待﨑さんの他にも東について聞いてくる人いたし。会いたい需要はそれなりにあるってことでしょ」
なら、呼んじゃって現実見せた方がいいんじゃない? と、まるで腫れ物でも扱うかのように戸練が言う。
「待﨑さんが呼んだら来るんじゃない? ほら、待﨑さんは私らと違って、あいつと揉めたわけじゃないし。うん、それがいいよ。私が待﨑さんっぽくして誘うわ。ね、いいでしょそれで」
「えっ、それ、いいのかな。だって……ほら、東くんは三輪さんと付き合ってるのに」
果たして、戸練は言った。
「別れたに決まってんじゃん。あんなのと付き合いたいやつなんかいないよ」
この作品の続きは12月5日発売の『君の地球が平らになりますように』にてお楽しみください。
