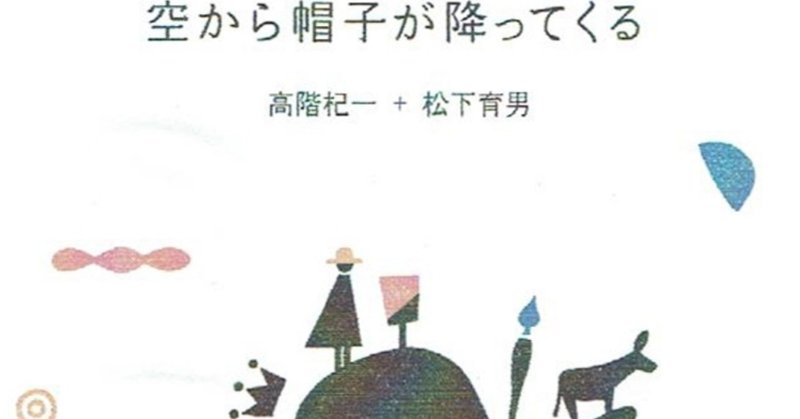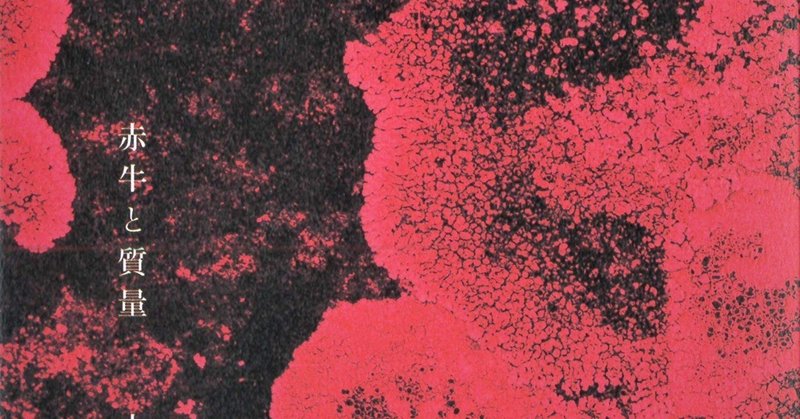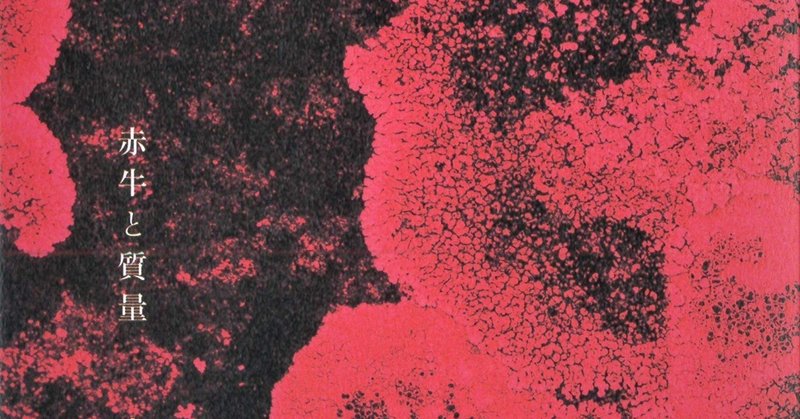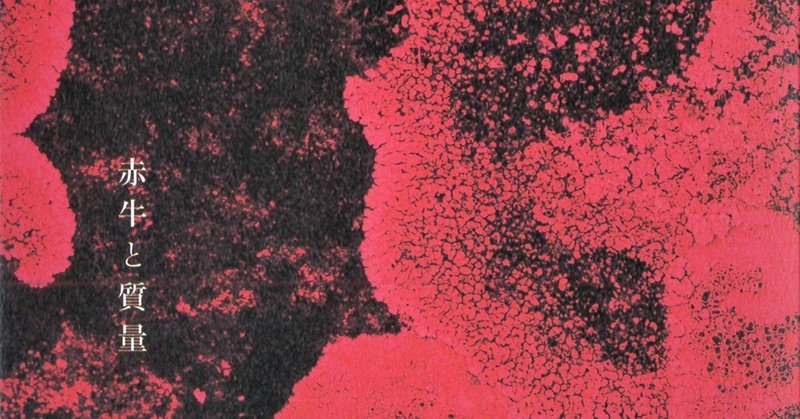記事一覧
中原中也「朝鮮女」を読む
朝鮮女
朝鮮女の服の紐
秋の風にや縒れたらん
街道を往くをりをりは
子供の手をば無理に引き
額顰めし汝が面ぞ
肌赤銅の乾物にて
なにを思へるその顔ぞ ―― まことやわれもうらぶれし
こころに呆け見ゐたりけむ
われを打見ていぶかりて
子供うながし去りゆけり……
軽く立ちたる埃かも
何をかわれに思へとや
軽く立ちたる埃かも
何をかわれに思へとや……
……………………………
高階杞一 + 松下育男 『共詩・空から帽子が降ってくる』
高階さんから「新しい詩集を送るよ」とメールがあって、楽しみに待っていたら、届いた詩集には高階さんの他に、松下さんの名前もあった。しかもそのふたつが「+」で繋がれていて、題名には「共詩」と謳われている。おまけに帯には「ライト兄弟」(!)とあるではないか。
共同で書く詩と言えば、昔は連歌や連句、最近では連詩がある。連詩でもふたりだけで行う場合は「対詩」と呼んだりする。僕も小池昌代さんや田口犬男さん(
小池昌代の〈詩と小説〉: 『赤牛と質量』を読む その4
あともうひとつだけ、どうしても論じてみたい詩があるとすれば、「釣りをした一日」で、それは詩集の4番目に配されているのだった。困っちゃうな。これじゃきりがないよ。
実際、この詩集の最初の4作品には、異様な力が込められている。登板早々、いきなり連続三振を奪うベテラン投手の迫力である。選手生命を賭けて投げているのだ。『赤牛と質量』は、きっと小池さんの代表作になるだろう。(ここで前言撤回。どうしても論
小池昌代の〈詩と小説〉:『赤牛と質量』を読む その3
この詩集に収められている詩を、片っ端から網羅していこうというわけではないが、三番目の詩「香水瓶」もどうしても外せない。現代詩における〈自由〉を問いかける作品だからだ。それは僕が詩集『単調にぼたぼたと、がさつで粗暴に』で取り組んだ問題でもある。
20年前に詩の賞の副賞として貰った6本の香水瓶から詩は始まる。
それぞれの瓶にアルファベットが刻まれ
普通に並べれば poetry ぽぅえっとりぃー
小池昌代の〈詩と小説〉:『赤牛と質量』を読む その2
詩集の二番目に置かれている「ジュリオ・ホセ・サネトモ」という作品には、見覚えがあった。以前雑誌で読んだ時の、冒頭の印象が強烈だったからだ。
妻とはセックスしない
妻だけでなく
もうだれとも
韓国で出会ったスペイン人
ジュリオ・ホセ・マルティネス・ピエオラは言った
韓国で開かれていた詩祭の席で飛び出した発言らしい。「一座は湧いた」「韓国ではまだ/みんな妻と性交をしている/日本ではーー」などと言っ
小池昌代の〈詩と小説〉: 『赤牛と質量』を読む その1
小池さんの最新詩集『赤牛と質量』の特徴は、自由自在な重層性だ。
冒頭に置かれた「とぎ汁」を見てみよう。
死ぬときも
こぎれいにしておかなくちゃいけない なんて言って
ハサミ、シャキシャキ
せっせと他人の
髪の毛を切ったり 顔を剃ったり
(中国では みみたぶにも剃刀をあてるの)
そして百二歳まで生きた
胡同(ふーとん)の床屋さん
出だしの部分だが、いわゆる口語自由詩の典型的なスタイルだ。カッコ
小池昌代の〈詩と小説〉: 『影を歩く』を読む その3
『影を歩く』では、小説と小説の間に詩が挿入され、小説の中にも詩があるのだが、その一方、詩の中に小説の素が編み込まれてもいる。たとえば第二章の冒頭に置かれた「二重婚」という詩(それにしてもすごいタイトルをつけたものです)のこんな一節。
すでに十分老いたあなたは
新しいことができなくなった
しかしかすかに残る
性欲をもえたたせ
小鳥とともに歌う
タクトを振り
あの第二バイオリンの若い女を
欲しいと思
小池昌代の〈詩と小説〉: 『影を歩く』を読む その2
生活から出ていかなければならない。その感覚は、小池さんの作品のなかではいつも突然の不意打ちとしてやってくる。『影を歩く』の第三章に入っている「水鏡」(短編小説)はその典型だ。
荒れている高校生の娘の部屋に『土佐日記』が投げ出されているのを「わたし」は見つける。拾い上げて、頁を捲り、貫之の「影見れば波の底なるひさかたの……」の歌を読みながら海の底を思う。「わたし」は夫を船の事故で亡くしているのだ。
小池昌代の〈詩と小説〉:『影を歩く』を読む
昨年末、小池昌代さんと公開トークを行う機会があった。それぞれの新刊を持ち寄って話し合うという企画。僕の本は『前立腺歌日記』、そして彼女の本が『影を歩く』だった。もっとも僕がドイツを出発する時点で『影を歩く』はまだ手元に届いていなかった。いま奥付をみると発行日は2018年12月11日となっている。最終ゲラをPDFで送ってもらい、僕はそれをiPadで読みながら日本行の飛行機に乗ったのだった。
『前立
フランク・オハラを飯野友幸さんと読む
飯野友幸さんから待望のオハラ論が届いた。『フランク・オハラ 冷戦初期の詩人の芸術』(水声社)だ。
フランク・オハラは以前から気になる詩人だった。彼の書く詩が自分の好みだということははっきりと分かるのだが、その理由を言い当てることができない。そもそもほとんどの作品が、読んでいて心地よいのだけれど、何を言っているのか分からない、実にもどかしい存在だった。そのもどかしさを解きほぐしてくれる導き手の到来
平出隆『私のティーアガルテン行』を読む(その4)
本書には実に多彩な人物たちが登場する。
前項に引いた水仙先生こと鳥山晴代先生のほか、小学校すら退学していながら五カ国語を操り植物学動物学に通じた博学の祖父・平出種作、音楽の時間にはてんで歌えないのに、休み時間になると初夏の蜂のような小さく、かつ力強い歌声を響かせる黒本君、平出少年が思わずそのまばらな顎髭に手を伸ばして触ってしまった(そしてそれを自若としていやがる風も見せず、触られるままに笑みを絶
平出隆『私のティーアガルテン行』を読む(その3)
若い頃から詩人の書いた散文が好きだった。散文詩はむしろ苦手なのである。詩人の書いたれっきとした散文を読むのが好きなのだ。
高校生の頃は田村隆一の『詩人のノート』を(授業中にこっそり)読んでいた。リルケの『マルテの手記』を読んだのはいつだっただろう。辻邦生の初期の小説(たとえば『回廊にて』)にも、同じような匂いがあった。金関寿夫さんが訳したヨシフ・ブロツキーの『ヴェネツィア 水の迷宮の夢』は、散文