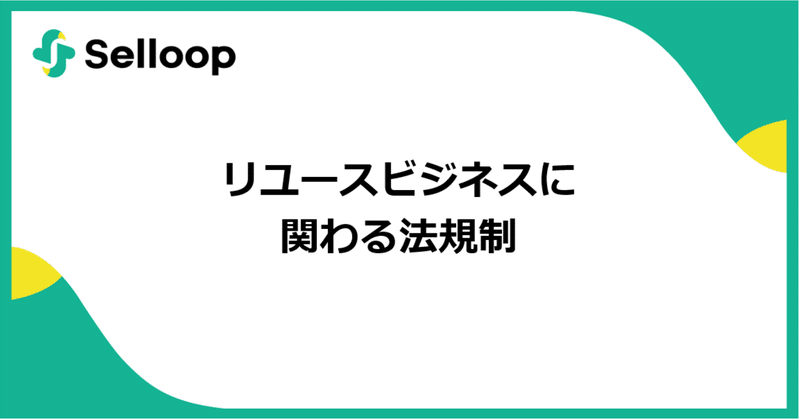
リユースビジネスに関わる法規制
導入
こんにちは。二次流通で顧客とのつながりをつくる『Selloop』Managerの長谷川です。この記事は、二次流通ビジネスの導入や立ち上げを検討している方や興味がある方にとって、「リユースビジネスに関係してくる法規制ってどんなものがあるのか」、「どういったポイントに注意すべきか」といった点でご参考になる内容かと思います。二次流通ビジネスについて具体的なイメージを持っていただくお役に立てば幸いです。
1.リユースビジネスにおける法規制上の注意点 - 古物営業法と環境関連法
リユースビジネスとはその名の通り、リユース品(=中古品)を取り扱うビジネスのことを指し、一般的には個人や法人からの使用済製品の「買取」、買い取った製品の「再商品化」、再商品化した製品の「再販売」等を行うビジネスモデルです。
例えばサーキュラーコマースを導入する施策として買取プログラムや新品販売時の下取りプログラム等を実装する等の場合には、リユースビジネスに関わる法規制に注意が必要で、しっかりと法やコンプライアンスに適合した仕組みにすることが必要です。
まず第一に、リユース品の売買には古物営業法に基づく許可が必要です。古物商許可に関する記事は下記をご確認ください。
第二に、リユースビジネスの性質上、廃棄物処理法や家電リサイクル法等のいわゆる環境関連法にも注意が必要です。
消費者向けにサービスを展開する等の場合には、消費者保護等の観点で「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」、「個人情報保護法」なども当然関わってくる重要な法規制ですが、本記事では特にリユースビジネスとの関わりが大きい環境関連法について取り上げてみたいと思います。
2.環境関連法の全体像
リユースビジネスに関わる法規制はその性質上、大きく環境関連法とそれ以外に分かれ、環境関連法としては主に「循環型社会形成推進基本法」、「廃棄物処理法」、「家電リサイクル法」、「小型家電リサイクル法」、その他廃棄物の多い個別物品に対する各種リサイクル法(家電以外には、容器包装リサイクル法、自動車リサイクル法、建設資材リサイクル法、食品リサイクル法がこれに当たります。また2022年4月にはプラスチック資源循環促進法が施行されました。これら個別物品に関わってくる場合には確認しておいた方がよいでしょう。)等があります。ちなみに環境関連法以外では前述のように「古物営業法」の他、「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」などが関わってくる可能性があります。
リユースを行うにあたって特に守るべき環境関連法の全体像については、環境省が「リユース業界を取り巻く環境関連法の法的環境の整理」にて整理をしており、下記がその一覧表です。本記事も基本的にこの資料をもとに作成しておりますので、詳細は本資料及び環境省のHP等をご参照いただければと思います。

本記事では全体の枠組みとなる「循環型社会形成推進基本法」、そして特に義務的な規定があり注意が必要な「廃棄物処理法」、「家電リサイクル法」、「小型家電リサイクル法」、「バーゼル法」について主に取り上げます。
3.各環境関連法の具体的内容
3-1 リユースビジネス全体に関わる基本法(循環型社会形成推進基本法)
リユースビジネス全体に関わる基本法として、日本が循環型社会を目指すうえでの基本的な枠組みを整備した循環型社会形成推進基本法があります。目指すべき循環型社会の概念を明示し、そのような社会形成に向けた国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化しました。また第 7 条で定める基本原則では、リユースがリサイクルよりも上位に位置付けられており、環境への負荷低減に有効であると認められる場合には、①リデュース(発生抑制)、②リユース(再使用)、③リサイクル(再生利用)、④熱回収、⑤適正処分の順に優先するとされています。
(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)
第七条
循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。
一 循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。
二 循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。
三 循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない。
四 循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行われないものについては、処分されなければならない。
同基本法に基づき2018年に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」でも、リデュース・リユースの機能をもつ2R 型ビジネスモデルの普及が循環型社会にもたらす影響の評価を進めることや、そうしたビジネスモデルの確立・普及を促進すること等が課題として挙げられています。
このように循環型社会を形成するための基盤となる法律や計画において、リユースを推進することが求められていることが分かります。
リユースビジネスの種類やそのポテンシャルについては下記の各記事をご覧ください。
3-2 買取・回収する不要物が廃棄物に当たる場合
使用済製品、つまり中古品はその状態に応じて、リユース品としての価値がある製品(リユース可能な製品)と廃棄せざるを得ない製品(リユースできない製品=廃棄物)のいずれも発生するため、注意が必要になります。
一般消費者や法人から不要な使用済製品等を買い取ったり回収したりする場面において、その不要物が「廃棄物」に当たる場合、原則としてその収集・運搬・保管・処分をするためには廃棄物処理業や産業廃棄物収集運搬業の許可を得なければいけません。
よって、その不要物が「有価物」なのか「廃棄物」なのかをはっきりと
「査定」する仕組がまず非常に重要だと言えるでしょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)において、廃棄物の定義とその処理方法について定められており、全ての廃棄物は廃棄物処理法に従って処理する必要があります。
なお廃棄物処理の許可はその性質により様々な区分があり、それに応じた許可が必要となります。
一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の区分
産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の品目の区分
処理の内容の区分(収集運搬、積み替え保管、処分の区分)
許可取得地域(一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は都道府県)の区分
許可取得処理業者は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」で検索できます。
3-3 廃棄物の該当性
では法律上の「廃棄物」とは何でしょうか?(廃棄物の該当性)
この点、平成 11 年の最高裁判例において総合判断説が採用されています。また、同主旨のことが、「行政処分の指針につ いて(通知)」(平成 25 年3月 29 日付け環廃産発第 1303299 号)においても示されていま す。
(2) 廃棄物該当性の判断について
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
つまり単純に有償取引がされているから有価物、そうでないから廃棄物という基準ではなく、5つの要素を総合的に勘案して判断されます。同通知の指針によれば、これら5つの要素についてより具体的には下記のような観点で判断されます。
①物の性状
・利用用途に合った品質か
-JIS 規格等の基準があればそれに適合しているか
-品質管理がなされているか
・飛散、流出、悪臭等がないか
-環境基準は満たしているか
②排出の状況
・計画的に排出しているか
・適切な保管、品質管理がなされているか
③通常の取扱い形態
・製品としての市場があるか
④取引価値の有無
・取引の相手方に有償譲渡されているか
-名目を問わず処理料金に相当する金品の受渡しがないこと
-譲渡価格が輸送費等の諸経費を考慮しても、引渡し側・引取り側の双方にとって営利活動として合理的な額であること
⑤占有者の意思
・占有者の意思として適切に利用、又は他人に有償譲渡する意思が認められること
-「占有者の意思」とは、客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる意思であること
特に④の取引価値の有無に関しては、モノの代金だけでなく輸送費等の諸経費を考慮しても合理的な額であることが示されており、例えば(モノの代金を無料や1円で引き取り)輸送費がモノの代金を上回る場合は廃棄物としてみなされる可能性があります。
廃棄物の該当性については各自治体に相談することが重要です。
3-4 例外的に廃棄物処理法の許可が不要となる場合(下取りの取り扱い)
新しい製品を販売する際に、商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引き取り収集運搬する、いわゆる下取り行為については、新品を販売した者が自ら収集運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。 ただし、具体的どのような行為が商慣習に該当するかは自治体に確認が必要です。
なおあくまで「無償」であり、例えば処理料金をもらって引き取ることは廃棄物処理の許可が無ければできません。また、収集運搬を他社に委託する場合には、委託先には廃掃法上の許可が必要です。
その他、いわゆる専ら物の回収や、引っ越し業務と同時に発生した転居廃棄物の回収等についても特定の条件を満たせば廃掃法の許可が例外的に不要になる場合があります。
3-5 家電リサイクル法の引取義務
家電リサイクル法の対象品目(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の小売業者でもあるリユース事業者は、家電リサイクル法対象品目が廃棄物になった場合、「過去に自ら小売販売したもの」、または、「新たに小売販売をするのと引替えに引取りを求められた際」には、引取る義務があります。
なお、製造業者等または指定法人に引き渡すために行う収集及び運搬に関する料金を顧客 に請求することができます。(家電リサイクル法 第 11 条)
また、家電リサイクル法の対象品目の買取りの際には、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日付け環廃産発第 120319001 号)の「リユース・リサイクル仕分 け基準の作成に係るガイドライン」のガイドラインAに照らして判断し、家電リサイクル法を遵守することが必要です。
加えて、家電リサイクル法の対象品目を販売するリユース事業者がこれら対象品目の廃棄物を引取る際、破損防止やエアコン等の冷媒として使用されていたフロン類の漏出防止に努めて収集・運搬を行う必要があります。
3-6 リユース品の輸出、輸出業者への販売時には関係する法規制の確認が必要
日本は「有害廃棄物の越境移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下、バー ゼル条約)の国内担保法として「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下、 「バーゼル法」)と廃棄物処理法が施行されています。バーゼル法の規制対象物(バーゼル物) を輸出する場合には、バーゼル法に基づく手続きを行う必要があります。また、廃棄物処理法の規制対象物(廃棄物)を輸出する場合は、廃棄物処理法に基づき環境大臣の確認を得る必要があります。
正当なリユース品の輸出は、バーゼル法、廃棄物処理法の規制対象とはなりませんが、 規制対象物に該当しないことを確認し、求めに応じてこれを証明する必要があります。
そのため輸出の際は、輸出先で確実にリユースされることを確認し(例えば実際には資源としてのリサイクル等のリユース以外の行為が行われていないか)、行政機関等の求めがあった際に説明ができるようにしておく必要があります。(この点、環境省は事前の相談窓口を設けています)
また、自らが輸出しない場合であっても、「リユース品の販売先の事業者が不適切な輸出を行っていないか?」という点も確認することが推奨されています。
なお電気・電子機器の場合は環境省作成の「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」を確認しましょう。
3-7 家電リサイクル法対象品目の保管
使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)において、家電リサイクル法の対象品目は
「(中略)雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等の再使用の目的に適さない粗雑な取扱いがなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えない」とされています。 これら品目を倉庫等で保管する時は、屋根がある場所や屋内で保管するなど、「リユース品である」、「商品である」ことが分かるよう、適切な保管をする必要があります。
3-8 売れ残りの廃棄
当然、売れ残り等を産業廃棄物として廃棄する際には、産業廃棄物収集運搬事業者、産業廃棄物処分業者のぞれぞれと直接契約を締結した上で、当該産業廃棄物の引渡しの際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。
なお契約書とマニフェストは5年間の保管義務があるので注意が必要です。
家電リサイクル法の対象品目(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、 冷 蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)が売れ残った場合は、家電リサイクル券を貼付し て自ら指定引取場所へ運搬するか、廃棄物収集運搬業者に運搬を委託し、家電リサイクル法のルールで処理が必要です。
売れ残ってしまった使用済小型電子機器等を廃棄する場合は、小型家電リサイクル法によって認定された事業者(認定事業者)その他再資源化を適正に実施できるものに引 き渡すことが責務となっています。
4.おわりに
以上、リユースビジネスに関係してくる、特に注意が必要な環境関連の法規制について簡単にご紹介させていただきました。なお詳細や最新の情報については必ず環境省のHP等をご確認ください。
このように、しっかりと法やコンプライアンスに適合したリユースの仕組みを構築・導入するためにはいくつか重要なポイントがあり、相応の専門知識やノウハウが要求されることもあります。例えば、有価物か廃棄物か否かを査定する仕組みを構築する際は、商品の状態別に二次流通の市場でどの程度の価値・価格を持つのかといった情報が一つ基準となります。きちんと検査や保管を行うファシリティも必要になるでしょう。
二次流通支援サービス「Selloop」では、上記のような法・コンプライアンスへの対応含め、PoC実施やクイックかつローリスクなリユースビジネスの立ち上げを、ビジネス設計のコンサルティングや各種開発・制作の代行、業務BPOによって実現します。
ご興味のある方は、Selloop webサイトよりお気軽にご相談ください。

