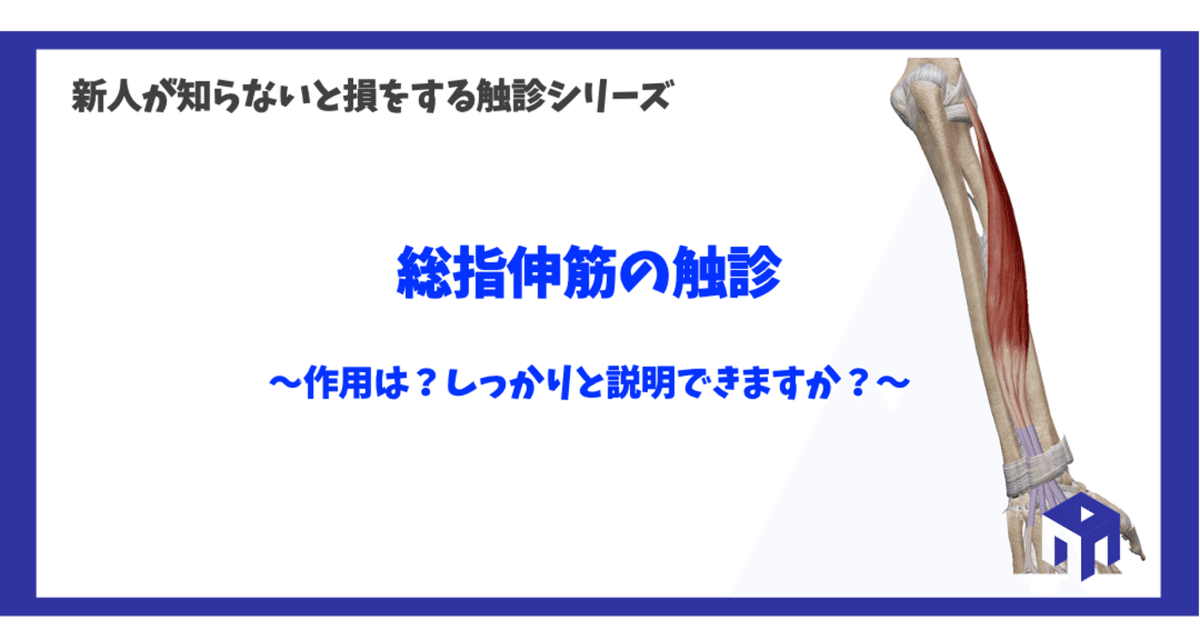
総指伸筋の触診
前回までは手関節の運動に関係する筋の触診について整理していきました。機能解剖を整理すると、なぜその筋に触診するべきか?と目的が明確になり、臨床と結びつきますね。
前回までの内容はこちら
臨床1年目の教科書
今回からテーマは手指の運動に関係する筋となります。
初回は総指伸筋です。
1 触れることの臨床意義
総指伸筋の機能としては示指から小指までのMP関節を伸展させます。
臨床において、この機能は脳卒中後のリハビリを担当する際にはしっかりと確認しておきたいポイントです。
脳卒中患者では選択的に伸筋が障害を受けやすい傾向にあります。そのため、まずは手指の集団伸展の主動作筋となる総指伸筋は臨床で治療ターゲットとなります。
総指伸筋の随意運動が得られない場合は、電気刺激も有効とされています。
そのためにはしっかりと触診できる様になっておきたいですね。
2 特徴
総指伸筋で最も意識しておきたい特徴が、外側束には、虫様筋、掌側骨間筋、背側骨間骨の腱が合流し、PIP、DIPの伸展運動に関与する点です。

(引用:基礎運動学 第6版)
この外側束に停止している手内在筋の協同作用によりPIP関節、DIP関節の伸展はされます。
PIP関節、DIP関節の伸展には総指伸筋が優位に関わるのは、MP関節が屈曲位にあるときであり、MP関節が伸展位では、中心束、外側束が弛緩し、その機能を失うとされています。
そのため、手指の伸展に関して、総指伸筋だけでなく、手内在筋も一緒に評価しておきたいポイントとなります。
3 実際の触診方法
では、実際に触れていきましょう。
① 示指・小指を屈曲させる
② 中指・環指を伸展してもらい腱を確認
③ 腱をたどり、筋腹まで触診していく
④ 筋腹を確認したら、もう一度中指・環指を伸展してもらい収縮を確認

4 まとめ
触診と一緒に周囲の解剖を学ぶと、それが臨床でどう評価していき、どう介入につながっていくのか?の理解が深まります。
ぜひ触診する際には機能解剖も確認していきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。
------------------------------------------------
追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪
【リハカレ公式HP】https://iairjapan.jp/rehacollege/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
