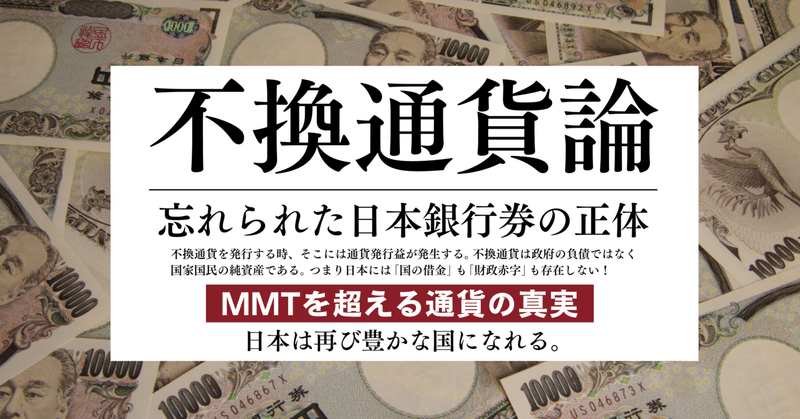
不換通貨論 ~忘れられた日本銀行券の正体~ #005(1章-05) 兌換通貨は「物品の預かり証書」/不換通貨は「物品の預かり証書」ではない
兌換通貨は「物品の預かり証書」
ここでもう一度、兌換通貨とはいったい何なのか考えてみよう。
兌換通貨は基本的には「物品の預かり証書」のことだ。たとえば日本銀行兌換券は、準備金である正貨が日本銀行に保管されているが、その所有者は日本銀行ではなく兌換紙幣の所有者である。そのため日本銀行にとって、金庫にある「金(きん)」は所有者からの預り金、いわば借り物に過ぎない。そのため、兌換紙幣は日本銀行が発行した借用証書であり、利用者はこれを自己が所有する「金」と同様に扱うことが出来た。
10世紀に宋(そう)国で流通していた「交子(こうし)」や、マルコ・ポーロの『東方見聞録』(1298)にて紹介された東洋の紙幣を真似てつくられた「ノタ・ディ・バンコ(ノート・デ・バンク)(銀行の書類)」と呼ばれる紙幣は「この券と引き換えに預かっている金貨を渡します」という「預かり証書」であった。
現代人は、通貨と言えば中央政府や中央銀行が国家権力で発行しているものを想像してしまうが、貨幣の歴史を見渡せば、取引の利便性のために私企業や金商人が発行していたものが数多く存在している。
金貨や金塊をやり取りするのは持ち運びや防犯面で不都合だったからだ。
また、紙を使った証文・紙幣は西洋と比べて日本や中国で早く普及しているが、これは西洋では高価な羊皮紙が主流であったためであろう。
(※西暦105年に中国で植物繊維を砕いて作る紙が発明され、日本に伝わったのは610年とされる。1150年にスペインに伝わるまでには大きな隔たりがある。高価な羊皮紙は、貴族たちによる重要な契約書や聖職者たちの聖書に多く用いられていた)
兌換通貨(預かり証書)に求められる財務の信頼性
持ち運びに便利な兌換紙幣であるが、市場でやり取りされるときには「この預かり証書を発行者に持っていくと本当に金貨と交換してもらえるのだろうか?」という疑いが生じることになる。
これは発行者が私企業であっても、政府または中央銀行であっても同じことだ。
兌換通貨の価値の正体は、交換用に準備されている財産、つまり「準備金」なのだ。
たとえば「日本銀行兌換銀券」の1圓紙幣は1圓銀貨と交換できた。
この1圓銀貨は、銀90%、銅10%、重さ26・96グラムの貴金属である。つまり1圓紙幣は銀24・264グラム、銅2・696グラムの価値が約束されていたというわけだ。
そのため兌換通貨時代には、日本銀行は交換用の金銀の保有が義務付けられていた。
「銀貨の価値」と「兌換紙幣の価値」は法律によって一致させられている。銀行に行けば銀貨と交換してくれるのだから、それは銀貨の権利書・預かり証書である。
反対に、不換通貨の場合には、この交換の約束が存在していない。
先ほどと同じく銀24・264グラム、銅2・696グラムを購入しようとするとき、不換通貨では何円を支払えばよいか決まっていない。「銀の価値」と「不換通貨の価値」にはまったく関係がないため、銀の購買量が常に変わり続けるのが不換通貨である。
喫茶店のチケットに例えてみよう。
「コーヒー1杯無料券」はコーヒーの価格に関わらず1杯と交換してもらえるので、コーヒーの『兌換通貨』、兌換コーヒー券と言える。
反対に「一〇〇円券」は、コーヒーが一〇〇円以下なら1杯と交換できるが、コーヒーが二〇〇円なら2枚、三〇〇円になったら3枚必要になる。このように、具体的な交換の約束がない場合は、『不換通貨』だと言える。
不換通貨は「物品の預かり証書」ではない
兌換通貨は結局のところ、持ち運びしやすく証券化された「物品貨幣」の一種であるから、物品の仲間であった。しかし不換通貨は、物品の裏付けがないので物品ではない。
そのため、世の中のものは「不換通貨」と「それ以外のもの」に分けることができる。これを言い換えると「不換通貨」と「物品」になる。
つまり兌換通貨は物品である。これは通貨のことを考えるうえで非常に重要な点だ。
現在でもインターネットで金地金(きんじがね)取引をしても、いつも実際に金塊を送り付けるわけではない。その金塊は保管場所に置かれたままで、所有権だけが移っていくことがほとんどだ。ヤップ島にある持ち運びのできない巨大な石のコイン「石貨(せっか)」も同様で、所有権が移転しても実際に対象となった商品を移動させる必要はない。海に沈んだままの石貨もあるそうだが、通貨は、その「所有権」を移譲すればよく、売買は、実際の受け渡しを必要とする訳ではない。
金貨や、金貨との交換を約束された兌換通貨をやり取りするときには、本質的にはゴールドという「物品」をやり取りしている。つまりこれはある種の物々交換なので、理解するのも容易い。それ自体には物品としての価値がない「不換通貨」を介した取引とは性質が大きく異なる。
不換通貨にあるのは、書き込まれて変わらない「価格(額面価格)」のみである。
不換通貨を無限に発行できるのは何とも交換する約束をしていないから
「通貨を無限に発行できるはずがない」と言う人は「通貨」と「物品」を切り離すことができていない。つまり「不換通貨」と「兌換通貨(商品引換券)」の違いを理解できていないか、不換通貨という概念をまだ知らない人だろう。
彼らは通貨に「金」などの物品による裏付けが必要だった「兌換通貨」の感覚で話をしている。その感覚は、金本位制時代には間違いではなかった。たしかに「金」の引換券である兌換通貨をいくら印刷したところで、実際に「金」がなければ、それは裏付けのない紙きれに過ぎない。
ではこの金という「物品」を物々交換しているだけの兌換通貨に対して、もう一方の「不換通貨」とはいったい何だろうか。
それは商品やサービスを取引するための道具であり、そのための単位・数字である。そして不換通貨は兌換通貨とは異なり「資産による裏付け」を必要としないため、際限なく、つまり無限に発行できるのである。
いくら不換通貨を印刷・作成しても、その瞬間においては金やその他の物品(資源)が増えるわけではない。しかしモノやサービスを仲介するための通貨が増えて市場の取引を活発にすること、そして流通している通貨の価値を減らすことができるのだ。
通貨が増えると通貨の価値が減っていく
不換通貨には、裏付けとなっている「商品の価値」はなく、1通貨単位の価値は、通貨の総量分の1、つまり【1円の市場価値=1/円の総量】である。
だから通貨の流通量を2倍にすれば、流通している不換通貨の希少価値は、半分に下がる。
このような価値の減少は「インフレ税」や「通貨滞留税」とでも呼ぶべきもので、その効果など詳細は次章で説明する。
このように不換通貨は「通貨でしかない通貨」、「純粋な通貨」だといえる。物としての価値が極めて小さいものを使用するため、その流通量を自由に管理することができる。そのため、これを「管理通貨制度」と呼んでいる。
余談だが、どの種の通貨でも管理は可能なのだから、何を管理しているのかが判る名称、たとえば「通貨『流通量』管理制度」や、「無限発行可能通貨制度」または「不換通貨制度」などと改めるべきではないだろうか。正しい名前がつけられれば、正しい理解が進むだろう。
#経済 #通貨 #紙幣 #MMT #財務省 #日本銀行 #財政破綻 #積極財政 #緊縮財政 #氷河期 #財政赤字 #財政規律 #少子化 #インフレ #デフレ #不換紙幣
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
