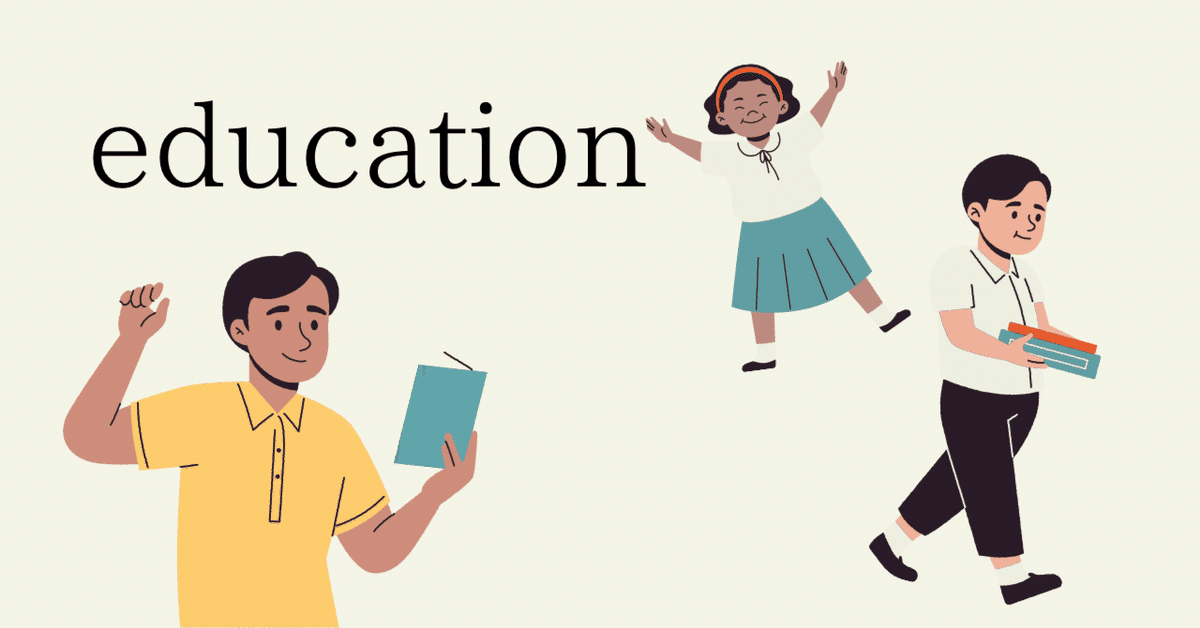
生徒が教員の言うことを聞かないのは正しい
教員になってから「どうして生徒は言うことを聞いてくれないのだろう」と悩むときが来る。しかし、この問いは実は成立していなくて、生徒は言うことを聞かない。というか、人間は他者の言うことを聞かない。だから、生徒が教員の言うことを聞かないということは当たり前であり、ある意味正しいコミュニケーションである。その悩みは「教員は生徒に言うことを聞かせなければならない」という使命感が前提にあるはずだが、その前提は成立しない。
むしろ、もしあなたの近くに、あなたの言うことをすべて聞いてくれる生徒がいるのであれば、そっちの方が大問題である。「THE WAVE」という映画の中で、教員が教室を全体主義化していく中で、その教員を妄信する生徒が現れた。映画の最後に、教員はここまで教室を全体主義化してきたのは、全体主義の恐ろしさを生徒に体験してもらうためだった、と明かすものの、その教員を妄信していた生徒は「だましたのか」と逆上。自分の身を捧げて仕えていた主君からの背信行為によって、その生徒は結局自殺する。自己の実存を完全に他者の言葉にゆだねるということがどれだけ怖いか。だから、目の前の生徒が言うことを聞かないのであれば、それは至極正しい。
生徒が言うことを聞かないからといって、じゃあ何もしないかと言うとそうではない。言うことは聞かないまでも、言うことを聞かせようとする教員と、意識的・無意識的問わず教員の言うことを聞かない生徒の間にある緊張関係は常に持ち続けなければならない。昨日の記事も書いたが、この緊張関係の中から創造的な営みが発生するはずである。例えば、教員が発信する論理の綻びを生徒が発見し、その綻びを押し広げ、新しい価値観を生み出したり。批評の授業では、教員が想定する生徒の論があって、その課題を設定する。しかし、その教員の想定よりもはるかに質の高い論が提出されることがある。しかし、その想定外の論は、教員の想定という天井が設定されていなければ、発生しない。
生徒が完全に言うことを聞くようになるのが最悪。生徒が言うことを聞いてくれなくて悩むのは第一歩。生徒が言うことを聞かなくてほっとするのが次の一歩。教員の言うことの想定を超えて、生徒が新しい何かを提出することができたらさらに次の一歩。教室・学校における創造的営みは、この緊張関係の裂け目から生じるはず。非対称だからこそ、生まれる創造。学校は生徒が教員の言うことを聞くようになることが目的なのではない。異なる他者と対話を繰り広げながら新しいものを創っていく、もしくは創る実地訓練をするのが学校という場のはずだ。
もどかしいけど、日々生徒と対話を繰り返し、逸脱を積み重ね、創造を繰り広げる。体力と忍耐が必要だけど、やってみよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
