
アジア論研究会【第2期・発展編】
この研究会について
現代のアジア人が考えていることはそうではなくて、西欧的な優れた文化価値を、より大規模に実現するために、西洋をもう一度東洋によって包み直す、逆に西洋自身をこちらから変容する。(中略)その巻き返す時に、自分の中に独自なものがなければならない。それは何かというと、おそらくそういうものが実体としてあるとは思わない。しかし方法としては、つまり主体形成の過程としては、ありうるのではないかと思ったので、「方法としてのアジア」という題をつけたわけですが、それを明確に規定することは私にもできないのです。
《方法》日本の近現代に書かれた文学作品や批評的なテキストを、「アジア」という観点から考察する。近代文学/批評読書会から派生した企画。こちらは、報告者を輪番制で立て、レジュメを用意して討論形式で行う。
《テキスト・頻度・場所》報告者のテーマによって、その都度次回のテキストを選択する。頻度はだいたい二ヶ月〜三ヶ月に1回ほどで、オンライン(zoom)で開催。
《参加者》神戸大学、そのOB、皇學館、立教大、大阪公立大、チューリヒ大など様々な所属の者がいる。参加希望の際は、私松田(matsudaitsuki@gmail.com)に連絡ください。
この読書会は、2020年11月に始めた。22年12月現在、2年間にわたって続けてきたことになる。以前は「第1期・入門編」と題して、参加者間の合意を作ることを目指してきた。以下が、その「第1期」のリンク。
上記の末尾には、赤井浩太が総括記事を書いているので、もし興味があれば参照していただきたい。神戸大学の院生を中心に創設したが、国内外(立教大、皇學館大、チューリヒ大など)の院生が参加希望を寄せてくれ、次第に規模も拡大し始めた。
そのような2年の準備期間を経たのち、「第2期」を開始した。2022年11月からは参加者の合意を前提に、ここで出てきた意見を論集・シンポ・企画へとまとめ上げてゆくために、より明確なテーマを設定し進めてゆくことを目指している。
◎第0回(22/9/4)
◆【日時・参加者】
2022年9月4日、オンラインにて開催。参加者12人。
あらためて、新規参加者を含めて、合意を形成するための準備会。
◆【主要テキスト】
参加者の松田樹、トーマス・ブルックが22年3月に博士論文を提出し、その末尾にていずれも「アジア」がテーマとなっていること、またそれぞれの研究対象の中上健次とリービ英雄が「アジア」を共通の問題関心としていることから、その博士論文を検討した。
●松田樹「中上健次作品研究――「政治と文学」の終わりから「近代文学の終り」まで――(神戸大学大学院人文学研究科、22年3月)
●トーマス・ブルック「越境作家」に関する言語横断的研究――リービ英雄を中心に――(神戸大学大学院人文学研究科、22年3月)
いずれの博士論文も刊行準備中であるため、その詳細はここには記載しない。中上とリービの共通点が明らかになったとともに、第二期からの新規参加者を含めて議論の土台を共有することができた。
◎第1回(22/11/12)
◆【日時・参加者】
2022年11月12日、オンライン開催、参加者10人、発表:キム・スギ
◆【テキスト】
●メイン:金石範「鴉の死」(『文芸首都』1957年12月号発表)
後に連なる大長編『火山島』の原型作品とも言える実質的デビュー作
●サブ:文京洙『済州島四・三事件――「島のくに」の死と再生の物語』(岩波現代文庫)

◆【時代】
舞台は、1948年勃発の済州島四・三事件。
とりわけ、「鴉の死」で描かれるのは1949年2月から3月である。
◆【議論の要点メモ】
・雑誌『季刊 人間として』との関わりなど、金石範の日本における立ち位置
・〈在日〉文学紹介者である野間宏の全体小説論(サルトル論)との関わり
・〈在日〉文学に対する金の評価(私小説批判)
・ 金石範の「全体」観と日韓の「戦後」(アメリカ極東戦略の評価)
・話し言葉と書き言葉の分裂(ディアスポラ文学)などなど
◆【報告者コメント】
今回の研究会では、まず来歴も含めた作家の〈日本文学〉における立ち位置が検討され、その後「鴉の死」において金石範がいかに表象の臨界にある四・三事件(の忘却)に対して抵抗したか、またし得ていないかが小説の内在的読解から追究された。


まず、立ち位置については、野間宏・小田実・鶴見俊輔・『新日本文学』との関わりが指摘され、その接続(と断絶)が指摘された。
また、テクストの根本性格として
①官憲の目が意識されていること
②資料や証言がほぼない中で作品が書かれたこと
に注意が促され、この小説を読むべき布置が準備された。
②に関しては、そもそも四・三事件が近年まで公式にはない(あるいはただの暴挙であった)とされていたことを留意する必要がある(文京洙『済州島四・三事件――「島のくに」の死と再生の物語』)。
そして、そのように忘却されたものが、「空洞」や「不気味なもの」として滞留し続けることが、小説の中で示唆されていることに注意を促したい。
例えば、「鴉の死」には以下のような描写がある。
ともかく白昼の村落に一人の人間もいないというこのふしぎな現象は、死にたえたように不気味であった。廃墟ではない。廃墟には乾燥した明朗さもあるが、これはまだどこかに血が生きていて陰湿で陰険であった。海底に沈んだ村のようにここには何かがこもっていた。家々は無傷のまま空洞のように無数に存在していた。しかもその冷たく暗い空洞にまだ生温かい人間の息吹が漂っていて、なおさら不気味な印象を与えた。
死に絶えたものは「乾燥」して「明朗」であり、清潔でさえあるだろう。しかし歴史の廃墟には「何かがこもって」おり、「陰湿」で「陰険」でさえある。敗残者の歴史を救済するとはこの「不気味さ」に積極的に対面しようとすることであり、その「空洞」に「息吹」を感知し続けることである。そして、それは何より金石範文学を読む〈方法〉であるだろう。
そしてこの〈方法〉は、すぐさま日本列島と韓半島(朝鮮半島)における「戦後」という歴史的=政治的布置を照射する。往々にして日本国内だけの視点から論及される「戦後」が、「大東亜戦争」の反省を言うサイドからさえ言われるこの戦後観がいかに日本一国主義的な、旧宗主国的なものでしかないかが暴露されるのである。

さらにそれは、〈マイナー文学〉においては一体のものである文学=政治が、「政治と文学」と分-接して語りまたその接続と分離を文芸としたこの国の文学の虚偽をも暴き出すだろう。金石範の文学はもはや政治と文学を区別できない地点で書かれている。
したがって、金石範を対象とする「文学研究」、小説の構造分析や技術分析もそこに差し向けられなければならない。そこに寄与しない作品分析はどれほど精緻であろうと空転するほかないだろう。四・三事件は、大阪に在日コリアンが多い直接の原因でもある(金石範・金時鐘・梁石日らは大阪にいた)。いわば在日問題の一起源と言える。そして、その「起源」には日帝の影がある。米帝の協力がある。韓国は「解放」されてなおいまだ植民地主義を脱し切れていない。金石範文学はそのような問題圏への志向性を孕んでいる。
韓国政府が四・三事件を忘却しただけではない。日本精神史も韓半島を隠蔽したのである。金石範文学は抵抗としてある。我々はその可能性と限界を見定めなければならない。
【文責】キム・スギ(チューリヒ大学哲学部博士課程)
◎第2回(23/1/21)
◆【日時・参加者】
2023年1月21日、対面、参加者10人 発表:西田正慶
◆【時代】
・1970年代、直木賞作家とアジア
◆【主要テキスト】
・結城昌治『軍旗はためく下に』(中央公論社、70・7)
・深作欣二監督:「軍旗はためく下に」(1972)
◆【議論の要点メモ】
大岡昇平と結城昌治/70年代以降の戦争小説のナラティヴ/戦争を忘却する意思/架空の場所としての戦地アジア/近代日本と「人肉食」表象
◆【報告者コメント】
今回の報告では、結城昌治『軍旗はためく下に』(中央公論社、70・7)と72年公開の結城作品を原作とする深作欣二監督の同名映画を取り上げ、1970年代の戦争小説・映画について検討を行った。


結城昌治『軍旗はためく下に』(中央公論社、70・7)は、1969年11月から70年4月にかけて『中央公論』に連載された五篇の短篇をもとに構成される。戦後、東京地検に勤務した作家は、サンフランシスコ講和条約に際しての恩赦手続きのなかで軍法会議の判決書を読み漁った体験をもとに本作の着想を得たという。戦後25年を経て発表された本作は、「旧軍隊の最も暗い面を描いたものであるが、従来のそれをあばきたてるという手法でなく、冷静に寧ろ悲しんでいるようであった」(源氏鶏太)、「軍隊物の常道を踏まず、自己の土俵にもち来たって、重い記録を完了している」(水上勉)といった評価を得て、この年の直木賞を獲ている。また、かつての「”聖戦”のかげには、多くの傷痕がかくされている」とする尾崎秀樹は、本作を「その傷痕を執拗にえぐった連作」であると書評を寄せた(「”聖戦”の傷痕を執拗にえぐる」『週刊朝日』70・8・14)。
一方で、『中央公論』における結城の連載が開始される以前に同誌の創作欄を占めていたのは、67年1月から69年7月にかけて連載された大岡昇平『レイテ戦記』(中央公論社、71・9)であった。72年4月に同誌上では両者の対談が催され、中国やフィリピンに対する加害の忘却を危惧する大岡に、戦後処理を「戦中世代のおそらく最後の義務」として結城が応じている。
周知のように、圧倒的な調査量に基づき構成された⾧編小説である『レイテ戦記』は、「近代小説の仕組みをこの作品は採用せぬが、しかし現代小説の到達したもっとも大きい小説として完全である」と述べる大江健三郎によれば、「戦記の文体を「異化」した文体として、独自」性を有するとされる(『大岡昇平集10』岩波書店、83・9)。一般に、『レイテ戦記』の完成は戦地アジアにおける死者に対する「鎮魂」の意がこめられたものとして受け入れられた。

なるほど、『レイテ戦記』がアジア・太平洋戦争における戦死者たちへの弔意を示すための歴史のパースペクティヴを提示しえた小説であるとすれば、『軍旗はためく下に』は戦争およびアジアをいかなるナラティヴにおいて、またどのように表した作品であるのかが問われねばならないだろう。尾崎がいうような「傷痕」の現在性とはいかなるものであるのかも、こうした問いによって可視化されるはずである。
本作の特色はタイトルごとによって変化する語りのシステムに顕著である。第一話「敵前逃亡・奔敵」冒頭では、話者である「私」がインタビュイー「中尾」に対して、戦友会内で「回想録」の作成を計画していることを語る。
回想録を思いたった私たちには、これを私たち自身の青春の形見にすると同時に、このような青春が存在したことを次ぎの世代の青春に伝えたい気持がありました。戦争の善悪を問うのではなく、軍隊の功罪を問うつもりもありません。だから勇ましい手柄話や美談も結構ですが、編集委員はまた手分けをして、私は軍法会議で処断された戦友の話を聞いてまわる役を受持たされました。
「回想録」の編集委員を任されたという「私」は戦友会に顔を出さない「中尾」に聞き取りを行う。「私」によれば、「軍隊の功罪を問うつもり」はなく「自身の青春の形見にすると同時に、このような青春が存在したことを次ぎの世代の青春に伝えたい気持があ」ったというが、この「回想録」は「住所の分っている戦友と遺族に配るだけ」であるとされる。戦友会のなかには「今さら軍隊のことなど思い出したくない」人々も含まれており、戦時の経験を一種の「青春」であったととらえる「私たち」と彼らの間には溝が生じていることが窺える。彼らの「青春」を次世代に残したいという希望は、戦争を過去として忘却してしまいたいという「戦友」の意思との間で、その実現に苦悩することとなる。こうした「私」の説明が示すのは、本作にあらわれる語りや発言は、一般の「回想録」には収められることなく抜け落ちるような声であり、戦争の記憶であるということにほかならない。
次いで、「敵前逃亡」によって処罰された「小松伍長」の話を伺いに来た「私」と「中尾」のやり取りの間には、「中尾」の記憶に基づいた三人称形式の叙述が挟まれる。中尾の視点を借り受ける地の文のごとき叙述は、中尾の心理も小説の記述に表面化させるが、一方でこの語り手は戦地での中尾の心理を現在時制で語るなど時間的な立ち位置に揺らぎが見られる。次の条はその様子を示したものである。
小松伍長の逃亡について、倉田軍曹は臆病風に吹かれたせいだと言っていたが、中尾はひそかに別の仮説をたてていた。
確かに、小松は臆病だったに違いない。しかし、その臆病が急に彼を大胆にさせたのではなかったのか。誰だって命が惜しいし、一日も早く内地に還りたいと思っている。敵に遭遇すれば、もちろん怖い。そういうことは、軍人の禁忌としてなかなか口に出せないでいるだけだ。死はつねに彼を脅しつづけたはずだった。ある程度までは戦場に馴れるということもあるが、恐怖が全て消え去るということはない。中尾が自分をかえりみても、度胸の半ば以上は諦めを伴った自棄である。だから小松伍長の場合は、その自棄が極端に烈しかったのではないのか。臆病のあまり、緊張に耐えきれなくなった末に、その反動作用で死に向って居直ったのではないか。
中尾の「小松」の内面を推測する思考を語り手は三人称の叙述に置き直すが、ここで注目すべきは、「中尾が自分をかえりみて」いるのが、中尾の戦地における思考であるのか、現在時における思考であるのかが断定されていない点である。
続くパラグラフには、小松が「たとえ軍隊生活に馴染まず、いかに臆病だったにしても、彼はごく平凡な考えの兵士であり、国のために死ぬということを当然のように受取っていたはずである。中尾自身も、当時は尽忠国難に殉じるということをいささかの疑いもなく信じていた」との語りが読まれる。「当時は」という時制を示す句は、相対的にこの語りが現在の中尾が「私」に向かって語ったと思われる個人の記憶の内容を客観形式に変換したものであることを確実にする。その一方で、中尾の小松を語る記憶と思考は戦地と現在を分かちがたく往還するものであることが時制表現の揺らぎというかたちをとって表れている。中尾における戦地に向けられる思考は「当時」から「敗戦後二十四年以上」の時間のなかで決して完結することなく続くものであることを、三人称の語り手は個人的な体験にとどめることなく物語として提示する。このとき中尾が語ったとみられる彼の発話は「回想録」としての戦争体験者の語りとしてではなく、不特定多数に放たれた物語のナラティヴに置き換えられるのである。
それでは、『軍旗はためく下に』におけるアジアの問題はどのようなものだろうか。報告では第四話「敵前党与逃亡」に基づいて検討した。この小説には実際の裁判が行われた事件がモデルとして存在している。結城は自作解説にて本作のなかで「誤解を避けるため架空の地名を随所に用いた」と明かしている(「著者ノート」『結城昌治著作集5』朝日新聞社、73・11)。その地名の一つに当たるのが「敵前党与逃亡」に登場する「バースランド島」である。この島は作中にて「面積は四国の半分くらいでしょうか。三千メートルを越える嶮しい山もありますが、海岸線の砂地のほかは、湿地帯を含めて殆どジャングルです」と説明される。

第四話「敵前党与逃亡」は、「私」が表題の罪名によって「バースランド島」で「死刑」に処されたとされる「馬淵軍曹」の死について同じ中隊に属していた上官や兵士の刑罰をつかさどっていた憲兵らに尋ねてまわることで真相を明らかにしようとする筋を持つ。馬淵軍曹の死は多数の人物のそれぞれ食い違う証言によって判然としないが、彼らの証言のなかでは同じく「バースランド島」の原住民に関する記憶が語られる。
バースランド島にはカナカ族の土民が約四万人いると聞いていました。日本軍は陸海合せて当初約三万五千ですから、それより多かったわけです。海岸近くの土民は多少ひらけていて、華僑がたまに椰子の実などと物々交換にきていたせいらしいのですが、男も女も短い腰巻みたいな物をつけていました。山岳部では、女は三角形の葉っぱで局部の辺を隠す程度、男は全裸です。肌の色は本当に真っ黒で、アメリカン・ニグロの黒さなど比較になりません。全身に入墨をしていますが、黒い肌に黒一色の入墨ですから、余計穢く見えるだけで模様などは分らない。
『ブリタニカ国際大百科事典』の説明によれば、「カナカ族」は実際に存在する語ではあるが、「文化的,社会的に多様な人々が含まれており,学術上の用語としても使われていない」「差別的用語」であるとされる。
本作の証言者たちは「カナカ族」を「土民」と称し、主にその「人肉食」文化をまことしやかに「私」に語る。
そこでわたしなどは専ら土民と接触させられたわけですが、おそらく、あの島で土民にいちばん多く殺されたのは憲兵だったと思います。何しろ兇暴な奴らで、殺したら首から上以外は全部食ってしまう。足の裏が最高にうまいと言ってましたが、その取り合いで猛烈な喧嘩をしているところを見たこともあります。(略)奴らは人肉を食うとき、きれいに腑分けしてからバナナの葉にくるんで石焼きにする。そういうことを知っているのでなおのこと怖い。いったん怖いと思い始めたら、気が遠くなりそうになります。
作中では「バースランド島」の先住民は日本軍にとって怯えをもたらす存在であったことが幾人もの証言から浮かび上がる。しかし、彼らの証言が切り落としているのは、先住民族に対する彼ら自身の加害性であり、先住民たちの攻撃はこうした加害に対する反発であるが、軍隊内の証言者は「いったん怖いと思い始めたら、気が遠くなりそうにな」ると、自らの疚しさを押し隠しつつ、その被害者としての立場を強調する。

作品の終盤で馬淵軍曹の同僚であった「寺島継夫」が自身の馬淵の殺害を告白しようとするが、「私」はこれを遮る。
――馬淵さんはクリスチャンだったそうですね。
――そういうことは聞いていません。
――人間が人間の肉を食うでしょうか。
――食うでしょう。わたしは食うと思います。
――きょうの話は忘れることにします。
――なぜですか。
――忘れたいからです。あなたも早くお忘れになった方がいい。バースランドは遠い島です。
――でも、わたしは夢を見たわけではありません。なぜもっと正直に話せと言わないんですか。
なぜもっと率直に、人間の味はどうだったかと聞かないんですか。
――それが愉しい思い出なら伺います。
こうして戦地「バースランド島」の記憶は誰によっても語りえない記憶として表象される。それは「バースランド島」の先住民族の人肉食文化という日本軍にとっての他者性を強調することによって、である。しかし、架空の地である「バースランド島」における先住民族たちとの関係は作品においてのみスキャンダラスな体験としてあらわれているのであり、実際にモデルを持つ「馬淵軍曹」の判決書事件とは異なり、解答不能な謎として読み手には届けられるのである。
「敵前党与逃亡」の謎はしばしば「藪の中」に消失したと語られるが、軍隊内の証言の杜撰さが前面に押したされたことのみによるのではなく、作品に設定された近代日本の他者としての先住民族を虚構として用いることによって可能となっている。本作においては、実際に係争中の事件と戦地における虚構を綯い交ぜにすることで、戦後日本における戦争の現在性と「藪の中」という闇に消えながらも時に浮かび上がる未来に回帰する問題を提示することで、その現在性を確保したと言えるだろう。
深作欣二監督『軍旗はためく下に』は「敵前党与逃亡」をベースに全5話からなる原作のそれぞれの中心エピソードを組み合わせた作品構成であるが、映画内においてもこの原住民の描写は極めて短いごくわずかなカットにしかおさめられず、およそイメージ不可能なものとしてスクリーンに映される。原作・映画ともにこの先住民族はアジアにおける近代日本の想像力の範囲外に置かれるのである。

議論に際してはこうした作品の検討から、接続可能な問題として戦後文学における表象不可能なものとしての「人肉食」を描いた作品との関連の指摘もなされた。たとえば、大岡昇平「野火」や武田泰淳「ひかりごけ」に代表される小説がそれにあたる。これらの作品は戦後まもなく発表されたものであるが、『軍旗はためく下に』がこうした作品に描かれたイメージとどのように差異化されているのかについては今後も検討の余地を残した問題であろうと思われる。
◆文責・西田正慶(神戸大学博士後期課程)
◎第3回(23/4/2)
◆【日時・参加者】
2023年4月2日、対面、参加者10人 発表:秀島希望
◆【時代】
・1950年代、堀田善衞とアジア・アフリカ
◆【主要テキスト】
・ 堀田善衞『河』(『中央公論文芸特集号』1959・1)
・ 堀田善衞『インドで考えたこと』(岩波書店、1957・12)
◆【議論の要点メモ】
安保闘争前夜の文壇状況と『河』の同時代的な評価/ナショナリズムと「文学」/堀田善衞の歴史認識と小説形式の関わり/冷戦を捉える視点―竹内好と堀田善衞の差異
◆【報告者コメント】
今回の報告では、堀田善衞『河』(『中央公論文芸特集号』1959・1)を取り上げ、1940年代から1950年代のアジア・アフリカが如何に表象されているのか検討した。


堀田善衞『河』は、『中央公論文芸特集号』1959・1月号に発表され、同年4月に中央公論社より単行本『河』として上梓された作者による中編小説である。
『河』の執筆に関して堀田は後年、アジア・アフリカ作家会議の運動の事務局員として「第三世界のあちこちを廻った」経験が『河』の執筆につながったと振り返っている(堀田善衞「著者あとがき 無常観の克服」(『堀田善衞全集』第3巻、筑摩書房、1993)。堀田の上海体験、及び「第三世界」との関りは以下の通り。
1945年3月、東京大空襲の後に上海に渡った堀田は、国際文化振興会の上海資料室に勤め、1947年1月に引き揚げられるまでの約2年間を上海で過ごす。
その後、1957年10月に中国作家協会、及び中国人民対外文化協会に招かれ、山本健吉を団長として、本多秋五、井上靖、十返肇、多田裕計らとともに北京、上海、重慶、広州などを旅する。それら上海における体験は、後に随筆『上海にて』(筑摩書房、1959・7)にまとめられる。
一方、堀田と「第三世界」のかかわりは、1956年の晩秋から57年の年初にかけて、アジア作家会議への参加のためにインドのニューデリーに滞在したことに端を発し、1958年6月には、アジア・アフリカ作家会議国際準備会議出席のためモスクワへ渡る。
そこでの体験は、『インドで考えたこと』(岩波書店、1957・12)、『後進国の未来像』(新潮社、59・10)にそれぞれまとめられる。各随筆と『河』には、同様のモチーフの連なりや、引用がみられ、『河』は各随筆との関係のなかで成り立つテクストである。
『河』では、1946年から1958年までの12年間のアジア・アフリカ、ヨーロッパにおける「私」の体験が語られる。本作に章番号は付されていないが、本コメントでは、テクスト内に設けられた空白に基づき本文を6つに分節、各節を第1章などと称することとする。本作の特色は、「河」を媒介に出来事が反復、回想される点にある。
第4章では、アラスカのアンカレージからコーペンハーゲンへ向かう道中において、グリーンランドの「直線曲線のジグザグ」の氷原から、「支離滅裂」に流れるカナダのユーコン河が喚起され、そこから東アジアに流れる様々な河が連想される様子が語られる。その際、「私」が最初に想起するのは、黄河の風景である。

彼が決潰口を閉じに行った黄河の、その決潰は、かつて蒋介石の命によって日本軍の進撃を食い止めるために行われたものであったが、そのために、日本軍だけではなく、中国の軍隊も、大いに水死した。私はこの溢水地帯を低空で飛んだことがあった。(中略)そのときで既に七年もの歳月、昆虫のようなものも箱のようなものも、敵味方、農民ともどもに、水のなかにつかり放しだったのである。
ここでの現在時は明確には語られないが、第2章において「1958年の初夏、私はコーペンハーゲンにいた」(615)とあることから、1958年に12年前に中国で知り合ったディルクセン、及び「彼が決潰口を閉じに行った黄河」を想起していることがわかる。それとともに、「七年」という時間の経過が語られているが、これは、蒋介石の命によって黄河の決潰が行われた1938年から「七年」後の1945年を指すと推察される。このように、既に語られた話題や風景が別の場面で反復され、かつ、そこに新たな回想が付加されるのは、複数の時間軸の回想を幾度も繰返しながら進行していく『河』という物語全体の特徴である。
今回の議論では、上記のような『河』の時間的な特徴から、同時代の文壇内部における小説の評価軸に話が展開した。
同時代評では、新年号の創作欄から窺える文学の転換のなかに『河』を置き、本作の「非小説」性を逆説的に評価する傾向がみられる。
たとえば、各誌の新年号の特徴を老大家の欠落と長編小説の連載とする平野謙は、1959年1月を「過渡の年」と表現し、老大家の存在や短編小説にかわる「新しい文学上の試み」がなされているとは言い難い点を「現代小説の問題」とする。
そのうえで、平野は、『河』を「日本人との会話からはじまるこの作品は、最近のフットウする国際情勢を背景とする作者自身の見聞にもとづいているらしいだけに、まだ十分に芸術作品にまで結晶していない」と述べるも、「小説の非芸術性を意識的に発展させる点に、現代小説のゆきづまりを打開する一血路があるとすれば「河」は1959年度の初頭をかざるにたる作品というべきだろう」と評価する(平野謙「今月の小説ベスト3」『毎日新聞』1958・12・20)。
このような評価をもとに、議論では、安保闘争前夜の機運のなかで、安定的に構築された時間(歴史)を小説化するのとは異なった小説の定型が模索されており、たんなる政治評論のような本作が好評を博した可能性が指摘された。それは、「中間小説」論や「国民文学」論に連なる問題でもある。

それに関連して、『河』では、第二次世界大戦後のアジア・アフリカのナショナリズムの形成が肯定的に語られる一方で、エジプト人やカメルーン人、デンマーク人等の人々と何語で会話しているのかがぼかされる、すなわち言語の対立が奇妙に等閑視されていることが問題化された。 言語を規定しないことは、アジア・アフリカの奇妙な連帯を生むとともに、実体化されないものとしてアジア・アフリカを語ることである。議論では、そこから堀田善衞と竹内好との距離にまで話が展開した。
◆文責・秀島希望(立教大学大学院博士後期課程)
◎第4回(23/7/1)
◆【日時・参加者】
2023/06/04、オンライン開催、参加者10人 発表:星住優太
◆【時代】
1950年代前半、従軍体験者による加害告白
◆【主要テキスト】
・田村泰次郎「裸女のゐる隊列」(『別冊文藝春秋』1954・10)
・家永三郎『太平洋戦争』(岩波現代文庫、2002・7)
◆【議論の要点メモ】
国策映画と講和条約以後のナショナリズム/戦争小説と文壇の関係/被害者である中国人への眼差しの欠如/従軍体験者と銃後の戦争体験者の戦後意識の相違
◆【報告者コメント】
今回の報告では、1950年代前半に従軍体験を持ち、なおかつ戦争犯罪を体験している作家が、そのことを戦後どのように語ったのか、という問題意識のもと、田村泰次郎「裸女のゐる隊列」を分析した。

本作はアジア・太平洋戦争中に山西省で行われた戦争犯罪を題材としている。よく知られるように、そこで描かれた内容が事実であると家永三郎は『太平洋戦争』の中で田村に照会を取り言及している。
歴史学者の笠原十九司も田村と同じ部隊であった近藤一の証言と住岡義一の供述から、本作はほとんど事実に基づいていると明らかにした。このような、事実を書く文体と小説の文体の差異について成田龍一は次のように述べている。
成田 (前略)歴史学には、「全体」を明らかにするという目的のために、文学とは違ったかたちで文体を規定していった過程があります。フィクションである文学に対して、歴史学は「事実」を語るとして、そのスタイルを模索したのです。(中略)
一九八一年に森村さんの『悪魔の飽食』が出たときに歴史家は、小説家の作品ではあるが、「事実」の調査に基づいているようだから、歴史の叙述として「認定」し、受け入れてゆこうという立場をとった。田村泰次郎の『蝗』は家永三郎さんの『太平洋戦争』で言及されていますけれども、そのために家永さんはわざわざ田村泰次郎に手紙を出して、「あれは事実ですか」と訊ね、「事実です」という返信を得て引用する、という手続きを経ています。(上野千鶴子、川村湊、成田龍一「戦争はどのように語られてきたか」『小説 TRIPPER』1998夏季号→『戦争はどのように語られてきたか』朝日新聞社、1999・8)
アジア・太平洋戦争以後の戦争文学は「加害の現場、加害の行為を記述する言語を持ちえなかった」と語る上野に、成田は森村誠一や田村泰次郎の作品を提示しながら、それらが調査や体験による「事実」に基づいているために「歴史の叙述」として受け入れられた経緯を提示している。


ここでは、小説=被害、歴史=加害という対立が用いられているが、事態はそう単純に分けられるものではないだろう。
武田泰淳「審判」(1947)や大岡昇平「野火」(1951)、小島信夫「小銃」(1952)など、戦争小説には加害を描いた作品がいくつかある。そもそも、田村の「裸女のゐる隊列」も家永が照会するまでは戦争証言ではなく小説として読まれていた。以上のような状況から問題とすべきなのは、戦争小説と歴史言説をその内容によって区別することではなく、「事実」に基づくような戦争証言と加害を描いた戦争小説の文体はどのように異なっているのかということであろう。言い換えるならば、戦争小説の固有性はどこにあるのか。
本作は、戦後から約10年の年月が経たある日に、「私」と妻が戦中に撮られた国策映画を見に行く場面から始まる。山西省の戦闘を中心に写したらしい映画に対して、「私」はまず画面に映る景色に心を奪われる。映画を見ながら「私」が想起するのは、戦時中の行軍や山西省の住民である。
その風物のなかに、画面には、ほとんど姿を見せない土地の住民たちの顔を、私は思ひだしてゐた。(中略)
その顔の深いしはのなかには、長いあひだに、吹きつけてくる黄塵がたまって、黄いろい皮膚の色と見分けがつかなくなり、乾いた仮面のやうに、表情のない顔になってゐる。その仮面の下にあるなまの顔を、私たちは気がつかずに、表情のない仮面だけを見て、相手を軽蔑したのである。感情の動きのすくない、動物のやうに愚鈍な連中だと思ひこみ、私たちはのろまな動物をでもあつかふやうに、彼らをあつかったのだ。
山西省の住民の顔は「表情のない仮面」であり、「私」たちは彼らを動物のように扱っていた。議論では、この点に中国人への視線の欠如が指摘された。しかし、「愚鈍な連中だと思ひこみ」という反省が述べられていることには留保する必要があるだろう。また、「私」はこのような山西省の記憶を妻にさえ告げることはできずにいる。戦争体験者が加害告白のアポリアを抱えていることが明示されながら、「私」は部隊のことについて思い出してゆく。
「私」の所属した部隊には山脇隊長という人物がいた。山脇は山西省の住民を捕え「新兵に一名づつの男を刺殺させ」たり、討伐で強姦を繰り返すような人物である。山脇の戦争犯罪は、笠原が指摘するように田村と同じ部隊であった住岡義一の証言と重なる点が多い(「住岡義一的筆供"原文"」『日本侵華戦犯筆供』中國檔案出版社、2005・6)。本作が証言と異なるのは、「そのときからすでに、私はさういふ考へ方をうたがはずにはゐられなかった」と、戦争犯罪への批判の意識が書かれることである。
本作では、さらに題名となる戦争犯罪の場面が次のように描かれる。
そのとき、なにか白い色が、隊列のなかに、まじってゐるのを、私は見た。
白い色は、うす暗さを増してきてゐる山の暮色に、一際きはだってゐるが、とっさには、それがなんであるか、私には見当がつかなかった。
けれども、近づくにつれて、まもなく、私にはわかった。それは全裸の女なのだ。一個分隊くらゐの間隔をおいて、その裸の女体は配置されてゐる。あまりの唐突さに、私にはこの場面の意味が、すぐには判断出来なかった。「貴様たち、この姑娘たちが抱きたかったら、へたばるんぢゃないぞっ――いいか、姑娘の裸をにらみながら、それっ、頑張るんだっ、――」
下士官がどなってゐる声が、聞えてくる。隊列は、私のそばにきた。 眼の前をすぎて行く女の肌は、はっきりと鳥肌だってゐるのが見え、蝋人形のやうに透きとほってきてゐて、むしろ、妖しい艶めかしさを帯びてさへ見えた。
この裸女を連れ歩く場面も、田村と同じ部隊であった近藤一の証言と重なる(青木茂「近藤一の体験した中国の日本軍」二、『日本軍兵士・近藤一 忘れえぬ戦争を生きる』風媒社、2006・3、p20)。「事実」である出来事を田村は、戦争証言とは異なり小説の一場面として描いている。ここで「私」は「その裸の女体は配置されてゐる」と語り、「この場面の意味が、すぐには判断出来」ない。「私」の記憶では、戦争犯罪はあくまで一つの場面なのである。このような加害行為を場面として眺める態度は、本作の冒頭で映画を見る行為に重なっている。要するに、本作において「私」は常に傍観者として戦争犯罪にかかわる人物なのである。
そのことは、本作の最後の一文である「そんな話を、私は家内にも話さないが、人間であることをみづから拒否したやうな、その隊列のなかに加はってゐた一人として、私はさうせずにはゐられなかった」にも表れている。「私」はあくまで隊列の一員であり、主体的に戦争犯罪に加担した加害者として描かれてはいない。この映画的に加害行為を描く手法こそ、戦争小説として戦争加害を告白する田村の方法だと言えるだろう。
◆文責・星住優太(神戸大学人文学研究科博士後期課程)
◎第5回(23/8/9)
◆【日時・参加者】
2023/08/19、オンライン開催、参加者7人 発表:金善泰
◆【時代】
1940年代、日本帝国支配下の朝鮮
◆【主要テキスト】
・ 金史良「ムルオリ島」(『國民文學』1942年1月)
◆【議論の要点メモ】
1940年代の朝鮮の平壌の時代的状況/植民地朝鮮の雑誌『國民文學』/朝鮮の地名と日本語の表記の問題/主人公の欲望とメルヘンの問題、ロマンティシズム/物語における「ユートピア」/登場人物の階級問題/紀行文と説話
◆【報告者コメント】
今回の報告では、在日朝鮮人文学の金史良の「ムルオリ島」(『國民文學』一九四二年一月)の物語のナラティブに着目した議論を行った。
本作は、金史良が朝鮮で発表した作品であり、一九四二年という太平洋戦争期に書かれたが、戦争の表現とは距離を置いた物語である。これは、金史良が日本の文壇で活動していた時期に、一九四一年に検挙された後、朝鮮に帰国するといった経緯と関係がある。
本作が当時の時代的状況を物語内容に表現しなかったことに対して、郭炯徳「「大東亜戦争」前後の金史良文学――「外地文学」から「地方文学」への変容」(『早稲田大学大学院文学研究科紀要』早稲田大学大学院文学研究科、二〇〇九年二月)は、「非現実」への志向を見せる作品であると指摘している。このような評価は、同時代評で言われる金史良のロマンティシズム的な傾向の影響であり、彼のロマンティシズム的な変遷には、植民地支配の外部的抑圧による挫折であると安宇植は述べている。そのほか、「ムルオリ島」が発表された『國民文學』は、植民地朝鮮における唯一の文芸雑誌であり、本誌に関わった人々は、京城帝国大学と朝鮮の親日派の知識人などの既存の金史良の文学の方向性と相違することも注目する必要がある。

作品内部においては、物語の全体像についての議論が行われた。本作は主人公の烺の視点に沿った語りとムルオリ島の住人である彌勒の視点に沿った語りで構成されている。人物の間には、知識人と朝鮮の下層農民という階級性として描かれているが、烺による語りは、紀行文的な叙述を展開している。
いつも間にか船はポプラの木立鮮かな半角島に沿ふ狭い灘を機關の音刻むやうにして通り抜け、平壌舊城内を後に見るやうになつた。猩岩島や蓬莱島に半角島などの繪のやうな小島を眺めながら、平川里の楊柳に烟る長堤の前を三十分程も下つて行けば、今度は右岸に玉硯山や牛鼻岩などが勾配や崖をなして疎らな松林を點綴し、まるで北畵の山水屏風でも徐々にひろげて行くやうである。江流には左手に細長い豆老島が流れる如く横はり、パカチの蔓草に、おほはれた黄色い屋根屋根が田圃の中にところどころ固つて見える。畑には白い着物の百姓たちの姿がくぐまつて見え、江べりの緑なす草原には牝牛や仔牛がのどかに草を喰みながら、時々思ひ出したやうに尾を振つてゐた。
ここから窺えるように、烺の紀行文的な語りは、朝鮮の平壌と近郊の田園の生活を大同江の島々の名前を列挙しながら、風景をリアルスティックに描写する。
しかし対照的に、彌勒の語りは「悲しいかな、われわれはこの際あの昭和×年の怖ろしい大同江の氾濫を思ひ浮かべねばならない」(第四節)から窺えるように、語り手により編集され、彌勒の声は読者から消えていくのである。このような人物の声は、彼等が駆使する言語の問題に関わっている。
「ムルオリ島」に登場する人物たちは当時の生活においても現実には朝鮮語でしかしゃべらない農民たちなのだが、ここではじかに日本語でしゃべっている。金史良がこの作品を書いたのはおそらく朝鮮でであり、日常生活ではほとんど朝鮮語しかしゃべらない人々のあいだに自分を置きながら書いたにちがいない、そのあいだのプロセスのことが私を妙な気持ちにさそう。もちろん当時は朝鮮人が「日本人」だということで、公けには朝鮮語が奪われて「国語(日本語)常用」を強制され、いままでの朝鮮語作家たちまでが日本語で小説を書くという趨勢にあったから、朝鮮で日本語の小説を書いて発表したとしてもそれは不思議ではない。しかしじっさいは土着の人間のあいだで、それは農村に限らず都市においても依然として朝鮮語が使われていた。公的機関や表通りからいったん裏通りに入れば、日常生活のいたるところ家庭ではもちろんのこと、そこでは朝鮮語が支配していた。
金石範は、当時の朝鮮の国語(日本語)であるにもかかわらず、日常生活においては朝鮮語が使われていることを注目し、「ムルオリ島」の登場人物の中で、彌勒を含めた農村の人々が日本語話者として描かれていることに違和感があると指摘している。

金石範が指摘する違和感とは、本作の彌勒の「それが雨霧の下に海のやうに擴がり、鵾遊島、ベルチヤンソムのやうな小さな島々は、青い木藪の水面の上にちらつかせてゐるだけで、中流には白いあぶくが嘔吐のやうに泡立ち、筏から切れた木材が時々生物のやうに頭を突き上げながら無數に流れる」(第四節)という語りから現れる「やうに」の繰り返し使われる描写の異質さであるだろう。 それから議論は、신희교「金史良의「물오리섬(ムルオリ島)」연구」、シン・ヒギョ「金史良の「ムルオリ島」研究」(『国語文学』国語文学会、一九九八年一月)が指摘した本作の「説話」的な性格に発展していった。「説話」は現実の問題を描くことに至っては、適していないのにもかかわらず、朝鮮の農民の悲惨な生活を描くために「説話」的要素をとりれたこととともに、作中にムルオリ島で、「どんなお伽噺を聞かしてくれる?」(第二節)という童話を欲望する子供たちの登場により、物語が全体的にメルヘンティックになっていく。このように異なる物語世界が混在する本作は、朝鮮の文学者の林和が指摘する朝鮮文学の特徴であった。
外向と内省は本来対立される方向であるにもかかわらず、同じ時代に両傾向が一つで発生する時はその種子が抱くある基礎の単一性を考えねばならない。私はこれを作家の内部における「語ろうとすること」、「知ろうとすること」の分裂にあるのではないかと考えている。(中略)従って、作家の思想を活かそうとすると作品の事実性が排除され、作品の事実性を活かそうとすると作家の思想が排除されなければならないジレンマに陥るのである。
引用は報告者の拙訳による
林和が指摘する一九三〇年代後半の朝鮮文学の特徴は、作家の思想と作品のリアリティのジレンマである。「ムルオリ島」においても、作品の内容が植民地支配への抵抗という民族主義的なリアル性が欠如されたことで、ロマンティシズムへ傾いたと評価された。
つまり、これは「ムルオリ島」は作家の思想性を表すが、現実性が欠如されていることを意味する。しかし、「老船頭はその時片方の帆網を引いて方角を斜めに取りながら、ひとりにたつと笑つた。『さあ、もう城内だぜ』」(第四節)という結末を確認すると、説話の幻想世界であった島からリアリズム的語りを展開していた平壌へ回帰することで物語が閉ざされる。この点から考えると、物語における思想性と作品の現実への回帰による現実性の結合が窺えるのではないだろうか。
また、金史良の作品が朝鮮人に向けられた問題への現実的なアプローチとするなら、「ムルオリ島」から確認できるスタイルの変化はさまざまな意味を持つ。しかし、本作を作家の挫折によるロマンティシズムへの転回として分析することは、不十分であると言える。特に、金史良が佐賀高校時代に、同人誌で書いた「土城廊」(『文藝首都』一九四〇年二月)と本作には、作品の舞台と題材において、共通点が見られる。こういう点において「ムルオリ島」は、金史良の転換期の初期作品との影響関係を検討する上で、金史良の日本と朝鮮での文学活動を探るキーとなる作品である。
◆文責・金善泰(神戸大学博士前期課程)
◎第6回(23/10/15)
◆【日時・参加者】
2023年10月15日、オンライン、参加者9人 発表:丸山栞和
◆【時代】
・1920年代初頭、「支那趣味」と怪奇探偵小説
◆【主要テキスト】
・芥川龍之介「奇怪な再会」(『大阪毎日新聞』1921 年1月5日〜2月2日)
・同「アグニの神」(『赤い鳥』1921 年1月)
・同「妖婆」(1919 年9〜10 月『中央公論』)
本稿における芥川作品の引用は全て『芥川龍之介全集』(筑摩書房 昭和 49 年)によった。
◆【議論の要点メモ】
大正 10 年前後作家の「支那趣味」/中国各地を旅する作家たち/ポー風の怪奇小説の流行/「野性」の発露としての「支那人の狂女」/大正の東京と「怪奇」
◆【報告者コメント】
今回の報告では、芥川「奇怪な再会」(『大阪毎日新聞』1921 ・1・5〜2・2)を取り上げ、1920年代に作家たちの関心を引きつけた「中国」的な表象と「怪奇」との結びつきを検討した。
芥川は本作発表のわずか1月後に渡中を控えており、「中国」への関心が最も高まった時期の作品と言ってよい。また同時に本作は、数年にわたり試みていた現代(大正期)日本を舞台にしたポー的な怪奇小説の内の一作としても読むことができる。そのため同様の怪奇小説として「妖婆」、またそれを改編した童話「アグニの神」を合わせて検討した。


「妖婆」は「失敗作」としての評価が定着してしまった作品である。
すべての話は(小道具は別として)寧ろ大時代的なものであつて、私には新鮮な興味を一つも起こさせないのである。仮りに作者が新時代の―大正の東京の怪譚を我々に与へようと試みられたものとしたな ら作者は妖婆の住家を寧ろ活動写真小屋の隣りにし、乃至は妖婆の言葉を普通我々の聞きなれた現代語にする用意をも多分必要としたらう。
ここで佐藤に指摘されたように、芥川は大正期東京に怪奇を描き出すことには失敗し、「大時代的」にならざるをえず、結末に至っては通俗小説に陥るしかなかった。その失敗を乗り越えるべくして構想されたであろう、同じく東京本所を舞台とした「奇怪な再会」において、主役に「支那人の狂女」選んだことに着目した。
本作品は多くの先行研究が指摘する通り、「雇婆さん」の語りを聞いた医師 K の語りを記述する「私」という多重の語り構造になっている。今は「お蓮」と呼ばれ日本軍の主計の妾となっている元娼婦の女性「孟惠蓮」が、占いをきっかけにかつての恋人「金」と威海衛に残してきた犬の幻覚を見るようになり、ついにはアイデンティティの分裂により発狂してしまうまでの出来事について、お蓮の視点から描かれているように見える。
が、途中で「雇婆さん」の言葉が挿入され、読者は初めて、これまでのお蓮の視点が「私」によって勝手に補完され、勝手に代理されたものであったと分かるというのが、本作の最大の特徴である。
お蓮が発狂していくまでに最も大きく話が転換するのは、自分を囲う牧野が金を殺害したことがほのめかされた後の場面である。
お蓮が床を抜け出したのは、その夜の三時過ぎだった。彼女は二階の寝間を後に、そっと暗い梯子を下りると、手さぐりに鏡台の前へ行った。そうしてその抽斗から、剃刀の箱を取り出した。
「牧野め。牧野の畜生め。」
お蓮はそう呟きながら、静に箱の中の物を抜いた。その拍子に剃刀のにおいが、磨ぎ澄ました鋼のにおいが、かすかに彼女の鼻を打った。いつか彼女の心の中には、狂暴な野性が動いていた。それは彼女が身を売るまでに、邪慳な継母との争いから、荒むままに任せた野性だった。白粉が地肌を隠したように、この数年間の生活が押し隠していた野性だった。………
「牧野め。鬼め。二度の日の目は見せないから、――」
お蓮の「野性」について書かれているのはこの一か所のみである。「野性」について、芥川は後に「文芸的な、余りに文芸的な」(『改造』昭和2年6月号)にて、「ゴオガンの『タイチの女』について、「橙色の人間獣の牝は何か僕を引き寄せようとしてゐる。かう云ふ「野性の呼び声」を僕等の中に感ずるものは僕一人に限つてゐるのであらうか?」と述べており、「近代」に対抗しうるものとしての「野性」を芥川が称揚しようとしていたことは間違いない。ただ、これはプリミティヴィズムの発想でもある。

また、お蓮発狂のきっかけとなる玄象道人の占いは(道人曰く)「漢の京房」に始まるという擲銭卜、つまり「易」である。大正 10 年前後には大本教の弾圧事件が起こるなど、新興宗教の活発化を背景に占いや霊能が流行していた。お蓮の幻覚を支配していく「東京が森になる」も、この道人の発言に端を発するものであり、ここにお蓮の「野性」を呼び覚ます契機として中国的な占いが機能しているといえる。ただ、占いの方法や道人の言葉には注意が必要だろう。「妖婆」や「アグニの神」では少女を依り代とした神降ろしのような様子が描かれ、物語の結末においても非合理的な「神」の存在がほのめかされる。

一方で、「奇怪な再会」では占いは完全に「易」を利用したものとなっており、体系的な理論に基づいたもので、非近代的ではあるが、非合理的なものとまでは断じることはできない。
また、占いの結果として玄象道人が述べる「雷水解」だが、本来は行動による問題の解決を意味する卦であるが、道人は「諸事思うようにはならぬ」と真逆の解釈をお蓮に伝えてしまう。芥川が単に誤ったとは考えづらい。お蓮にとって最も望んだ金との再会が狂気の中においてのみ叶うという結末にふさわしく、周囲の人々とお蓮の主観とによって結末が問題の解決とも「諸事思うようにならな」かったとも読めるように、わざと道人にほぼ真逆の解説をさせているのではないだろうか。
「私は昔の惠蓮じゃない。今はお蓮と云う日本人だもの。金さんも会いに来ない筈だ。けれども金さんさえ来てくれれば、――」
ふと頭かしらを擡げたお蓮は、もう一度驚きの声を洩らした。見ると小犬のいた所には、横になった支那人が一人、四角な枕へ肘をのせながら、悠々と鴉片を燻らせている! 迫った額、長い睫毛、それから左の目尻の黒子。――すべてが金に違いなかった。のみならず彼はお蓮を見ると、やはり煙管を啣えたまま、昔の通り涼しい眼に、ちらりと微笑を浮べたではないか?
「御覧。東京はもうあの通り、どこを見ても森ばかりだよ。」
成程二階の亜字欄の外には、見慣ない樹木が枝を張った上に、刺繍の模様にありそうな鳥が、何羽も気軽そうに囀っている、――そんな景色を眺めながら、お蓮は懐しい金の側に、一夜中恍惚と坐っていた。………
お蓮の「野性」は牧野の殺害という方向では発露しなかったが、最終局面において意外な形で発露したといえるのではないか。白い子犬との「再会」を経てついに完全に狂気の世界に入りこんでしまった惠蓮の姿は一見すると悲劇であるが、惠蓮自身の意識からすれば、金との「再会」という最も望んだことを成し遂げたともいえる。
つまり惠蓮の「野性」は(その狂った意識下に限ってではあるが)金との「再会」のために東京を森に変え、昔の惠蓮に戻るという望みをも叶える力を発揮したのである。またそのことが結果として、牧野から「お蓮」を奪うことにも繋がっている。軍人でありながら「帝国万歳」と叫ぶ連中からは距離を取り、商人へと転身を図る牧野は近代日本の合理性を象徴するような存在といえ、彼に対し、惠蓮の「野性」が復讐を遂げる物語としてこの作品を読むことが可能だろう。つまりは、近代日本に揺さぶりをかける「野性」の威力を描くことを目的として、芥川が本作品の舞台を「現代」の東京に設定したのだと考えられる。
ただ、「惠蓮自身の意識」とは言っても、それ自体が「私」によって補完的に描写されたものであり、ここでもやはり近代人である「私」から「惠蓮」への同情的な寄り添いと表裏一体となった日本版オリエンタリズムの視線が確認できるだろう。
*
しかしこのプリミティヴな「野性」の象徴としての「支那人の女」とは別の角度から、「中国」的な描写を検討できないかという方向で今回は議論が進んだ。
まず「お蓮」の設定の曖昧さについて指摘があった。娼婦になるまでの「孟惠蓮」の経歴について「それは彼女が身を売るまでに、邪慳な継母との争いから、荒むままに任せた野性だった」と語られる場面があるのみで、詳細は全く不明のままである。また威海衛の娼婦として日露戦争前後に日本人の客を取っていたことがほのめかされるのみで、どのようにして日本語を身につけたのかも全く語られない。そればかりか、「金」やかつての惠蓮の同僚「一枝」が惠蓮の幻覚(幻聴)として登場する場面では、注釈なく日本語を話させている。このように惠蓮の設定も、「中国」的な描写も正確さや詳細さを欠いている。
一方で、最後の幻覚の場面においてのみ、取ってつけたように「中国」的な風物とともに「金」を登場させ、発狂し入院した「孟惠蓮」が「支那服」を脱がなかったという設定が加えられている。
ここで大正期の画壇における画題としての「中国服の女」の流行に議論が及んだ。藤島武二「匂い」(1915年)をはじめ、岸田劉生も妹(日本人である)に中国服を着せモデルとした「輝子像」(1920年)を描いている。作中では「孟惠蓮」のアイデンティティの回復やその狂気的病態として描かれている「支那服」であるが、そこには同時代の「中国服の女」への興味や多様な欲望が作用していることが指摘できるだろう。


最後に、作品の怪奇性について議論が進んだ。3匹目の「白い犬」つまり、弥勒寺橋でお蓮が「再会」する「子犬」である。お蓮は狂気の中でその犬が威海衛に残してきた犬だと考えるが、「現実」にはあり得ないことである。ただし最後の場面で「私」がKから見せてもらう写真にも犬が写っていることから、犬は幻覚上ではなく「現実」のものではある。3匹目の犬が何ものなのかは判然としないことが、この作品の怪奇性を読者に感じさせるよう機能している。
また、「犬」や「金」(の幻覚)が現れる場面やお蓮の狂気が増していく場面では、雨や鼻の濡れた犬など水に関係する描写や、橋など境界を象徴するものが出てくる。古典的な怪異の描写を用いて、作品の怪奇性が高められている。
お蓮が入院することになる「脳病院」や精神病的についても、大正期においては、狂気に陥った人に対する前近代的な怪奇現象(狐憑きなど)としての見方から科学的な治療を要する疾患としての見方へと社会が変化していく過渡期であったという指摘があった。医師KやK脳病院という近代医療による狂気への対処を描きながらも、3匹目の「白い犬」の存在を怪奇的要素として残したところはまさに過渡期的時代の空気を表現しているといえるだろう。
従来、芥川自身の怪奇小説の試みとして言及されることの多かった本作品だが、大正10年前後の時代背景の中に位置づけて検討することで、当時の文壇のみならず社会全体の流行を反映し、時代の感覚を切り取った作品であるということが指摘できるだろう。
(文責:丸山栞和、神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了生)
◎第7回(24/2/12)
◆【日時・参加者】
第7回、2024年2月12日、オンライン開催、8人
◆【時代】
・1960年代、戦後日本と引き揚げ(担当:白井)
◆【主要テキスト】
・五木寛之「私刑の夏」(『小説現代』、一九六七年七月→『海を見ていたジョニー』、講談社、一九六七年)
・平岡正明『魔界転生 クロスオーバー作家論』(TBデザイン研究出版部、一九七七年)
◆【議論の要点メモ】
小説を説明するエッセイ/ハードボイルド的文体と時計の時刻を使った物語構造/男女表象の紋切型/ホモソーシャルな主人公と敵/外国語が見られない引き揚げ小説の閉鎖性
◆【報告者コメント】
今回の報告では、五木寛之の引き揚げ小説「私刑の夏」を取り上げ、そのハードボイルド的文体と時計の時刻との関係からその物語の構造を論じた。
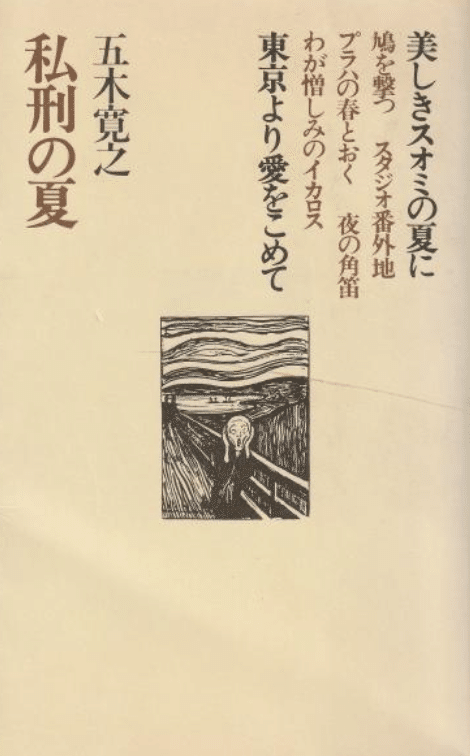
五木は、一九四六年に平壌から南下して日本に引き揚げた。七〇年頃のエッセイ「平壌からの脱出」に記されたその体験について、五木は「前に短い小説に書いたことがある」と明かした。それが今回の「私刑の夏」である。
どこかで銃声がした。一発きりで、後は静かになった。街は暗かった。通行人の足音もとだえ、街灯も消えていた。夜の舗道を、時おり何かが通り過ぎる気配があった。近ごろ急に増えた野犬の群か、保安隊の警邏班にちがいない。このH市では、一般人の十時以後の夜間外出は禁止されていた。
(中略)
「二十分前よ」
結城の肩を、うしろから陽子が手で押さえた。
報告者がまず注目したのは、「―た」という語尾で短く区切られる文体である。「―た」が連続する現在形の文体は、急くような切迫感を演出している。
そして本作では、「夜間外出禁止」であるにもかかわらず、主人公の結城らが秘密裡にソ連軍の輸送トラックに乗り込んでH市から脱出を試みるために時刻が重要となる。スミルノフ大尉とソ連軍を買収した星賀悟郎の指揮で走りだす輸送トラックに乗った結城は、夜光時計でくりかえし時刻を確認する。しかし最終的には、ソ連軍の裏切りによって出発地のH市に戻ってきてしまい、日本人たちはスミルノフ大尉と星賀をリンチにかける。
スミルノフ大尉をとりかこんだ男たちの、細長い影が静止した。
乾いた銃声が二発鳴った。しばらく間をおいて、変にこもった一発がきこえた。
結城は無意識に腕時計に目をやった。時計のガラス板は破れて、長針が飛んでいた。
結城は、膝を抱えるように倒れている星賀の体と、黒い血の河を眺め、樹にしばりつけられたままうなだれているスミルノフ大尉の影を眺めた。
輸送トラックがじつはH市の周りをぐるぐると回っていたように、時計の針も進んでいたはずなのに、最後には時計の「長針」が飛んでしまっている。本作の物語は、時計の針に対応してこうした円環状の構造を有している。

参加者の議論では、主人公・結城と悪者・星賀悟郎がある種のホモソーシャルな鏡像的関係になっていることが指摘された。結城は、元・中学国語教師であり、引き揚げ者の女子どもらを連れているリーダーである。他方で、星賀は元・満鉄調査部で、現在はロシア軍と渡りをつけながら南鮮への脱出の手引きをしている。結城は星賀を次のように見ている。
星賀はすぐにわかった。くたびれた半袖シャツ姿の連中の間に、たった一人だけリュウとした背広の男がいた。目にしみるような白麻のスーツを着て、草色のネクタイを結んでいる。引き緊った敏捷そうな体つきで、背が高かった。良く陽に灼けた浅黒い肌と、強く光る目と、やや厚目の唇をもっていた。美しい青年だった。
星賀がこうして描かれるのは、主に結城の回想の中においてであり、また引用部のように思い出されるという仕方でその姿は視覚的に美化されている。星賀もまた初めは「慈善事業」ではなく「金もうけ」の目的で引き揚げ者の密輸を行なっていたが、しかし時間が経つと「慈善道楽」と言って結城らを脱出させる計画を立てるようになる。
また参加者の議論では、引き揚げ小説であるにもかかわらず、本作の日本人らが外国語に触れることがないということが指摘された。例えば結城は、トラック輸送隊のメンバーの朝鮮人を日本人だと勘違いするが、それは「日本語がうますぎたので間違えた」とされる。あるいは、ソ連軍のスミルノフ大尉さえ日本語を話す。
すでに三時間ちかく走っている。まだ一度も検問所にぶつからないのだが不思議だった。
結城は、その事をスミルノフ大尉にきいてみた。大尉は正確な日本語でゆっくりと答えた。
「最初の検問所は避けて通ったね。自分はこの辺の地理は、何度も通ってよく知っているから。それに、大きな街はみんな迂回している。少し遠回りになってもそれの方が安全だと思う」
こうした外国語に触れない日本語のみの引き揚げ空間では、最後に書かれる「おれたちはどこからきて、どこへ行くのだろう」という言葉も意味を成さない。すなわち、本作においては「異国」から「故郷」へという図式が成立せず、物語においても結城たち日本人は結局のところ元のH市に戻ってきてしまうのである。
このように、今回の発表ではハードボイルド的なエンタメ作品の問題点や引き揚げ小説という前提自体への疑念が提出された。今後は、他の作品も視野に入れた上で、あらためて引き揚げ小説とエンターテインメントについて検討するべきだと考えている。
(文責:白井耕平、神戸大学博士後期課程)
◎第8回(24/4/13)
◆【日時・参加者】
2024年4月13日、オンライン開催、参加者7人
◆【時代】
・1900年代・日露戦後〜韓国併合期(担当:都田)
◆【主要テキスト】
・ 夏目漱石『満韓ところどころ』(『東京朝日新聞』1909・10・21~12・30/『大阪朝日新聞』1909・10・22~12・29)
・川村湊『作文のなかの大日本帝国』(岩波書店、2000年2月
◆【議論の要点メモ】
アジアにおける「小説」の発生/青春の回帰/平面化/紀行文のスタイル/労働者の描き方
◆【報告者コメント】
今回の報告では、夏目漱石「満韓ところどころ」における文学的方法に焦点を当てた。「満韓ところどころ」は、漱石が南満洲鉄道株式会社総裁の中村是公の誘いに応じて1909年9月2日〜10月17日の間に満洲・韓国へと赴いた際の体験をもとにしている。

この紀行文の評価は大きく二つに分かれる。一つは、中野重治をはじめとして朴裕河に代表されるような、漱石の帝国主義・植民地主義的側面を見出すものである。いま一つは、差別的表現を含む本作の語りを『吾輩は猫である』や『坊っちゃん』と同様な「写生文」としてのユーモアだと見なし、そこに植民地主義への相対化を見るものである。
大杉重男「「友」と「供」のポリティクス──夏目漱石の「満韓」表象における「友愛」の構造──」(『論樹』2015・12)は以上の状況をふまえ、「この時未だ十分に明らかにされていないのは、当時の一般の日本人の偏見に還元されるだけではない漱石文学固有の盲目的構造である」と指摘し、日本の植民地支配の構造を肯定しかつ隠蔽する語りの手法を問題化している。問われるべきは、写生文という概念を前提にせずに本作から抽出できる文学的方法である。
風呂から出て砂の中に立ちながら、河の上流を見渡すと、河がぐるりと緩く折れ曲っている。その向う側に五六本の大きな柳が見える。奥には村があるらしい。牛と馬が五六頭水を渉って来た。距離が遠いので小さく動いているが、色だけは判然分る。皆茶褐色をして柳の下に近づいて行く。牛追は牛よりもなお小さかった。すべてが世間で云う南画と称するものに髣髴として面白かった。中にも高い柳が細い葉をことごとく枝に収めて、静まり返っているところは、全く支那めいていた。
「余」はしばしば、眼に入る満洲の現在の光景を過去の中国像に収束させようとする。この認識方法については、これまでにも現実の問題を回避する仕草として多くの批判がなされてきた。
(前略)余は石段の上に立って、玄関から一直線に日本橋まで続いている、広い往来を眺めた。大連の日は日本の日よりもたしかに明るく眼の前を照らした。日は遠くに見える、けれども光は近くにある、とでも評したらよかろうと思うほど空気が透き徹って、路も樹も屋根も煉瓦も、それぞれ鮮やかに眸の中に浮き出した。
注目すべきは、「余」が南画的・漢文的に光景を捉える箇所以外でも、「日は遠くに見える、けれども光は近くにある」ような土地であることを強調している点である。つまり満洲の地を、遠くにあるものも目の前に見えるように認識される空間として描き出しているのである。
南画的ともいえる遠近法を持たないこの空間認識は、「南画」を直接言及しない箇所においても行われているのである。「この辺の空気は内地よりも遥に澄んでいるから、遠くのものが、つい鼻の先にあるように鮮である」(二十五)という箇所のように、「内地」との差も強調されている。このことをどう捉えるべきか。


漱石は、この旅行中に「物の関係と三様の人間」と題する講演を行っていた。そこでは人間を「物と物との関係を明める人」と「物と物との関係を変化せしむる人」、「物と物との関係を味ふ人」の三種に分類する。
講演の聴衆である満鉄の人々や満洲に来ている人々は「物と物との関係を変化せしむる」ために「転転循環して進んで居る」。対して、「物と物との関係を味ふ人」としての文学者は「単調なる生活を趣味多く多角形に変化せしめて味ふ」。
この講演の内容を鑑みたとき、「満韓ところどころ」において「余」が行う南画的・平面的認識は、「趣味多く多角形に変化せしめて味ふ」ために「単調」を自ら作り出す文学的行為だと見做せるのではないだろうか。
(前略)旅順の港は袋の口を括ったように狭くなって外洋に続いている。袋の中はいつ見ても油を注したと思われるほど平らかである。始めてこの色を遠くから眺めたときは嬉しかった。しかし水の光が強く照り返して、湾内がただ一枚に堅く見えたので、あの上を舟で漕ぎ廻って見たいと云う気は少しも起らなかった。
旅順の港に言及する箇所においても、その平面性を強調する語りが見られる。「余」はその平面性に「嬉し」さを覚える。だが、「余」を案内する軍人たちは、その港にポンプで空気を送り込み、そこにいる人々を「波に揺られて上ったり下ったり」させ、「余」は胸が悪くなる。
ここには「単調」を語りの上で作り出してそこに嬉しさを覚える文学者と、「物と物との関係を変化せしむる」軍人との相剋が見出せる。これに続く章では、「閑静な寂れた屋敷町に過ぎない」新市街の中で「女」に囲まれてすき焼きを食べることになる。「森閑として人の気合のない往来をホテルまで、影のように歩いて来て、今までの派出なスキ焼を眼前に浮かべると、やはり小説じみた心持がした」(二十九)と、この矛盾は「小説じみた心持」を生む。単調さを、軍人ではなく「女」が破るとき、そこに「小説」の契機が生じるのである。
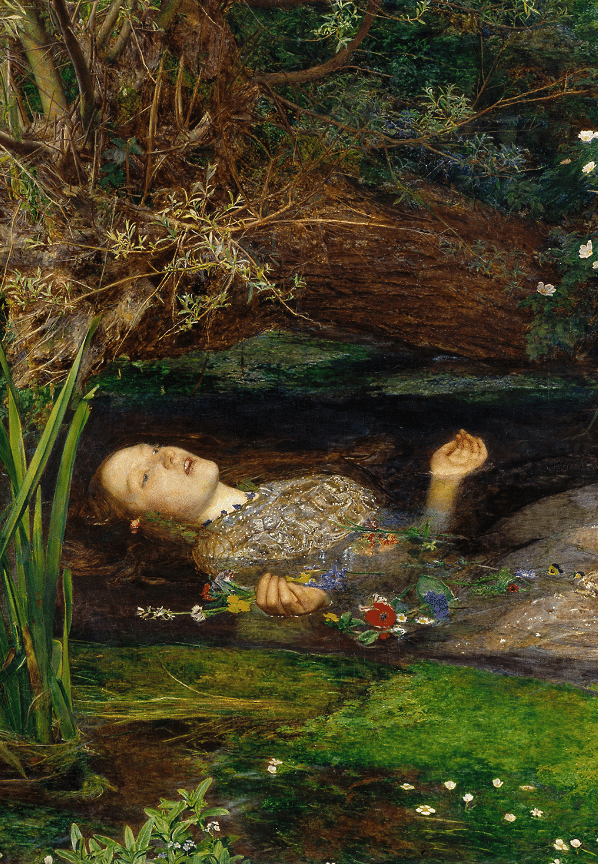
漱石の「女」のイメージを取り上げる際にしばしば参照されるものである。
1901年の「倫敦消息」でも、下宿をめぐる出来事を語るにあたって「小説的」という語が用いられている。だが、その金銭的な事情による出来事は「すこぶる平凡」で「色気」のないものであるために、「小説」性は否定され「運命」の「廻転」として片付けられる。異国の地における随筆的作品という点で共通点を持ちながらも、両作は「小説」を生む満洲と生まないイギリスという差異を有している。
本作ではこの後も不思議な「女」がしばしば登場する。単調さを強調し、そこから「小説」という「女」を登場させる本作のこの過程は、オリエンタリズムの発生の過程なのである。満洲の土地から単調な光景を見出し、そこから「小説」の生成をほのめかす本作の語りを、作家自身に還元し現実を無視するオリエンタリズムとして退けるのではなく、その操作の過程自体を問わなければならない。
本作は、軍人や満鉄による近代化=植民化と同時並行する、アジアにおける「小説」生成のための文学的整備として見做すことができる。
漱石の言葉で換言すれば、本作が描き出すのは「物と物との関係を変化せしむる人」と「物と物との関係を味ふ人」とが同じ構造のもとに開拓を進める姿である。このとき、想像力の源として扱われてゆくアジアという概念をめぐる文学史の見通しが開けよう。
議論のなかでは、旧友たちとの交流を中心に据える本作には、明治20年代の日本における社会全体としての青春の反復としての性格があるという指摘があった。高浜虚子『朝鮮』回(第1期・第8回)においても、韓国併合時期前後における政治小説の時代の反復について言及した。「満韓ところどころ」をアジアにおける小説の発生の条件を描いたものとしてみたとき、より広く明治10〜20年代の日本における近代化と小説の発生との相似的関係について検討することができるだろう。
「満韓ところどころ」とそれ以前の作品、たとえば日清戦争、日露戦争の時期の従軍記と取り結ぶ関係性については課題が残っている。また、本作は紀行文集や漱石文集、旅行案内などの中に収録されることになるが、どれほどの影響力を同時代以降の作家にもたらしたのかは、今後検討を重ねていきたい。
(文責:都田康仁、神戸大学博士後期課程)
◎【次回】第9回(24/6/29)13時〜
・蓮田善明『陣中日記』『陣中詩集』(『蓮田善明全集』、島津書房、平成元年)
・蓮田善明『応召日記』(同上)
・佐藤春夫『陣中の竪琴』(『定本佐藤春夫全集』第20巻、臨川書店、平成十一年)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
