
アジア論研究会【第1期・入門編】
この研究会について
現代のアジア人が考えていることはそうではなくて、西欧的な優れた文化価値を、より大規模に実現するために、西洋をもう一度東洋によって包み直す、逆に西洋自身をこちらから変容する。(中略)その巻き返す時に、自分の中に独自なものがなければならない。それは何かというと、おそらくそういうものが実体としてあるとは思わない。しかし方法としては、つまり主体形成の過程としては、ありうるのではないかと思ったので、「方法としてのアジア」という題をつけたわけですが、それを明確に規定することは私にもできないのです。(竹内好「方法としてのアジア」)
《方法》日本の近現代に書かれた文学作品や批評的なテキストを、「アジア」という観点から考察する。近代文学/批評読書会から派生した企画。こちらは、報告者を輪番制で立て、レジュメを用意して討論形式で行う。
《テキスト・頻度・場所》報告者のテーマによって、その都度次回のテキストを選択する。頻度はだいたい二ヶ月〜三ヶ月に1回ほどで、神戸大学の読書室+オンライン(google meet)で開催。
《参加者》神戸大学の院生を中心としているが、OBにも参加してもらっている。参加希望の際は、私松田(matsudaitsuki@gmail.com)に連絡ください。
◎第1回(20/11/3)
◆【日時・場所・参加者】
2020年11月3日、オンラインにて開催。参加者7人。
◆【時代】
1990年代、冷戦体制崩壊期における「アジア」(担当:松田樹)
◆【主要テキスト】
・柄谷行人『終焉をめぐって』
・中上健次『南回帰船』『異族』
・梶谷懐『日本と中国、「脱近代」の誘惑―アジア的なものを再考する」』
◆【議論の要点メモ】
冷戦体制の崩壊=「近代の超克」論の再興/竹内好テーゼに対する柄谷の評価/中上のサブカルチャー化/映画『ラストエンペラー』/戦後における「満州」=偽史の脈流/福田和也の保田與重郎/武田泰淳の再導入
◆【報告者コメント】
今回の報告では、中上健次に関してすでに発表した論文「 大東亜共栄圏とサブカルチャーへの欲望―中上健次後期作品・『異族』『南回帰船』をめぐって」(『マンガ/漫画/MANGA 人文学の視点から』)での議論を、より広い文脈へと開いてゆくことを試みた。
カギとなるのは、中上の盟友・柄谷行人が同時期に近代日本における「アジア」の思想史的な意義や「大東亜共栄圏」の問題に繰り返し言及している点である。とりわけ興味深いのは、『終焉をめぐって』(福武書店、90・5)に掲載された以下のような見取り図である。柄谷によれば、「近代日本」は「国権」と「民権」、「西洋」と「アジア」という二つの軸の中で揺れ動いてきた(「一九七〇年=昭和四十五年」)。

続く「大江健三郎のアレゴリー」でも柄谷は、この図式を敷衍して、大江の作品では「アジア」に関わる左側(Ⅱ、Ⅲ象限)が「暴力」や「無意識」として現れる、と議論を展開してゆく。
ここで柄谷が論を進める際に参照しているのは、竹内好「近代の超克」(59・11)である。そこで竹内は「「近代の超克」は、いわば日本近代史のアポリア(難関)の凝縮であった」とする有名なテーゼ――すなわち「大東亜戦争」には「アジア」に対する侵略/解放の二重性が絡み合っており、そこには「復古と維新、鎖国と開国、国粋と文明開化、東洋と西洋」等々の矛盾が集積している――を提起する。だが、時期的に先行する竹内の論考「近代主義と民族の問題」(『文学』51・9)では、次のようにも述べられていたのであった。
文学の創造の根元によこたわる暗いひろがりを、隈なく照らし出すためには、ただ一つの照明だけでは不十分であろう。その不十分さを無視したところに、日本のプロレタリア文学の失敗があった。そしてその失敗を強行させたところに、日本の近代社会の構造的欠陥があったと考えられる。人間を抽象的自由人なり階級人なりと規定することは、それ自体は、段階的に必要な操作であるが、それが具体的の完き人間像との関連を絶たれて、あたかもそれだけで完全な人間であるかのように自己主張をやり出す性急さから日本の近代文学のあらゆる流派と共にプロレタリア文学も免れていなかった。(中略)見捨てられた暗い片隅から、全き人間性の回復を求める苦痛の叫び声が起るのは当然といわなければならない。(強調は引用者)
注目すべきは、ここで「段階的に」や「性急さ」といった留保が設けられている点である。note上では詳述は避けるが、竹内の議論はあくまでも歴史的な段階論に依拠しており(「二段階革命」)、まずは日本の封建制を内在的に通過した「「正しい」ナショナリズム」(竹内)に依拠しなければ「プロレタリア文学」ないしは「マルクス主義」を云々できないということであった。後年の竹内がこの角度から部落問題にも関わってゆくことを思えば、国民文学論争など各時期でその強弱はあるとはいえ、概ね竹内は段階的な発展論を基礎にして主張を展開していたと言える。ちなみに、引用中の「見捨てられた暗い片隅」とは封建制をスプリングボードとして「ウルトラ・ナショナリズム」にまで飛躍した「日本浪曼派」を指しており、それを日本の近代化の歪みがもたらした必然的な帰結とするがゆえに竹内のロマン派(保田與重郎)への高い評価があった。
対照的に、柄谷の論考では、もはや竹内には見られた段階的な近代化の発想は取り払われており、歴史的な移行を前提にしてたはずのその議論が平面的に開かれている(例えば、「Ⅲ アジア主義」≒「日本浪曼派」と「Ⅳ マルクス主義」は図上で併存する。あるいは、大江論ではこの二つの方向性が「鷹四」と「蜜三郎」のような兄弟の関係をとって同時に存在する、と柄谷は主張する)。この図においては発展的な時間性が考慮されておらず、もはや近代化のプログラムは武装解除されている。柄谷は竹内のパースペクティブを継承しているかに見えて、実は両者の間には断層が走っている。この点が今回のハイライト。(また、竹内は「大東亜戦争」に「アジア」に対する侵略/解放の不可分な二重性を読み取っていたが、それもまたこの図式では不可分であるという抑制を解かれて上下にクリアに開かれてしまっている。このことは、同じく竹内のテーゼを継承した谷川雁→平岡正明のラインを辿る、第二回でより突っ込んだ議論となるだろう)。
なお、梶谷懐は大江作品にて「アジア」が「無意識」として抑圧されていると述べた柄谷の論に、むしろ柄谷自身の近年までに至る「アジア」への不可思議な固執を見ている(『日本と中国、「脱近代」の誘惑―アジア的なものを再考する」』)。
この著作は、そもそも本読書会を企画する上で、議論の立脚点になっている本でもある。2017年に行なったあるシンポジウムの打ち上げの場では、梶谷さんからは私的に近年の柄谷の動きについて色々とご教示いただいた(その時の問題意識が、この読書会に発展したと言ってもいい)。最近でも、台湾のデジタル大臣、オードリー・タンが柄谷の議論に言及していることが話題を呼んだ。冷戦後の柄谷の「アジア論的転回」については、今後も検討の余地がありそうである。
◎第2回(21/2/7)
◆【日時・場所・参加者】
21年2月7日、オンラインにて開催。参加者6人。
◆【時代】
1970年代、全共闘運動期における「アジア」(担当:赤井浩太)
◆【主要テキスト】
・谷川雁『戦闘への招待』(現代思潮社、1961)
・平岡正明『日本人は中国で何をしたか』(潮出版、1972)
・唐十郎『少女と右翼――満州浪人伝』(徳間書店、1972)
◆【議論の要点メモ】
「戦争を知らない子どもたち」による侵略戦争総括/竹内好テーゼから谷川雁「日本の二重構造」、そして平岡正明へ/68年以後における「創価学会」=潮出版と新左翼のコラボレーション/唐十郎とサブカル、偽史と満州イデオロギー
◆【報告者コメント】
今回の報告では、1970年代の平岡正明を中心に「日本帝国主義総括」および「右翼思想史論」(『日本人は中国で何をしたか』+いわゆる「あねさん待ちまちルサンチマン」シリーズ)を紹介した。
前回の松田による報告でも論点になった、日本の帝国主義戦争における「二重性(解放/侵略)」に関する竹内好のテーゼが、ここでも議論の基軸となる。実は、柄谷行人と同年生まれである安保世代の平岡正明は、竹内好のテーゼに応答した谷川雁の「日本の二重構造」(現代思潮社・61)を参照しつつ、戦後左派批判を通じてこの問題に接近したと言える。例えば、「天佑侠とハイジャッ鬼」で述べられた歴史観は、次のようなものである(『三田新聞』70・4・28→『西郷隆盛における永久革命』新人物往来社・73)。
朝鮮にらみの遠近法について一言すると、日本近代史を右翼の方向からながめると朝鮮の地はなまなましく近い。しかし左翼の方向からながめると、ことに戦後左翼の角度からながめると朝鮮は世界でいちばん遠い国だった。近いも道理、日韓合併(中略)によって、朝鮮は日本の一部だったからである。遠いも道理、戦後民主主義は尻に帆かけて朝鮮問題から逃げだしたからである。朝鮮戦争を無為無策で逃げすごした戦後左翼は、日本軍国主義の戦前・戦中にわたる朝鮮支配を忘れた。
こうした左右の「遠近法」を把握していたからこそ、平岡は日本の植民地問題や侵略戦争に関して右翼思想史論的なアプローチで介入し、また『日本人は中国で何をしたか』では、平岡と他四人は(平岡は「戦争を知らない五人の者」とそのメンバーを自称する)は復員兵の証言や軍事資料等を参照しつつ、三光作戦や南京大虐殺についてより具体的に論じた。
このとき重要なことは、こうした平岡らの調査および著作の刊行等のバックアップを行ったのが、「創価学会」を母体とする潮出版だということである。1968年の雑誌『潮』では、池田大作が「アジアに陽光を―日本と中国の進むべき道―」(『潮』68・11)で日中国交回復を訴えている。そして1972年に実現する日中国交正常化の前年には、「特別企画 大陸中国での日本人の犯罪――100人の証言と告白」(『潮』71・7)をはじめとして、戦争関係の証言特集が毎号組まれ、竹内好や武田泰淳などが、これらの特集に参加している。あまり注目されることがないが、平岡正明たちによる侵略戦争総括は、こうした潮出版の企画特集と並行して進められていたのである。これが1968年以後の「アジア」を捉える際の一つの側面であることは確実だ。
また、今回の報告では唐十郎『少女と右翼――満州浪人伝』をサブテキストに挙げたが、議論としてはこちらの方が盛り上がった。

『少女と右翼』の版元である徳間書店は、その後雑誌『アニメージュ』を1978年に創刊することになる出版社であるが、そうした経緯も踏まえ、サブカル的な想像力をテーマに「満州と偽史」について議論になった。『少女と右翼』の扉のページには、次のような言葉が掲げられている。
――これは歴史を偽造するものである
つまり見てきたような嘘だから
だから歴史的時間のお手玉だ
黒竜会の内田良平を主人公とする本作は、一頁目から「何物かにとりつかれた」内田が、「赤い鬼火の燃える満蒙の処女地を横切りながら、満州おろしの中で何物かと固い契りを交わしたものの、そしてそれが黒竜会の秘めたる謎であったにも拘わらず、内田硬石はそれ以来、裏切りの激流にのまれるのだ」と書かれる。
今回の議論では、こうした想像力が先行する「戦後文学」が捉えてきた「アジア」よりも、むしろ現代に繋がるサブカルチャー的な「アジア」理解へと変質しており、やはり六〇年代から七〇年代に政治的にも文学的にもある転換が生じていることが、作品の冒頭から「偽史」であることをあからさまに宣言した唐の小説を通じて確認された。議論の中で出てきた、この作品では小説空間がある種のテマティスム・形式性によって、成り立っているという指摘もそれに関連する点であろう(例えば、頻出する「三」の主題)。
最後に、余談として話が出たのは、時代を下れば、このような変遷が東アジア反日武装戦線「狼」から押井守へと繋がるラインにも認められるだろう、ということである。押井は、「狼」の発行していた「都市ゲリラ兵士の読本腹腹時計」を元ネタに、『腹腹時計の少女』という作品を書いている。


唐と押井、いずれも「少女」をモチーフにしているのは偶然であろうか。戦後文学/サブカルチャーにおける「アジア」の扱いについては、今後も持続的に考えていきたい。(文責・赤井浩太)
◎第3回(21/4/18)
◆【日時・場所・参加者】
21年4月18日、オンラインにて開催。参加者7人。
◆【時代】
1940s〜1950s、敗戦復員兵にとってのアジア
◆【主要テキスト】
・大岡昇平「野火」(『展望』1951・1~8→新潮文庫、1954・4)
・小島信夫「小銃」(『新潮』1952・12)
◆【議論の要点メモ】
・「野火」
「きけわだつみのこえ」などに対する反動としてのナラティブ/表象不可能性を前提/「映像」→言葉への変換に揺らぎがない/「野火」の自然描写は本当にリアリズムなのか/大岡の推理小説論とリアリズム論の関連
・「小銃」
小銃=女のシンボリズムとその揺らぎ/リアリティーのなさ/1、6章と2~5章の断絶/寝取られ男の想像力/「女」の表象
【報告者コメント】
今回の報告では、前回、平岡正明が「わだつみ派文献」に『三光』(光文社、1957・3)を始めとする戦中のアジアにおける日本兵の加害証言を対置していたことを踏まえ、占領末期から占領終了直後の加害証言を小説から読み解くことを主眼とした。
『きけわだつみのこえ』は、1949年に出版された戦没学生の遺稿集である。戦没学生たちの文章である以上、そこで書かれているのは学徒兵たちの悲惨な運命であった。戦死者、および戦争に行った兵士たちは国家に対して被害者であるという意識が1940年代後半にはあった。占領下においては占領軍の政策として旧体制の暴露や告発が歓迎されることとなった。そして『きけわだつみのこえ』は戦争批判の文脈で流行し、戦争を描くナラティブを規定した。

しかし、これまでの研究会でも見てきたように、日本の兵士たちは被害者である半面、アジアに対して加害者でもあった。であるならば、被害の言説だけでなく、加害の証言も戦後には多く出てきてよいはずであった(研究会では、『わだつみのこえ』の編集自体に、渡辺一夫や小田切秀雄ら敗戦直後の言説をリードした人々が関わっていることにも論点が及んだ)。
高橋三郎が「「戦記もの」の四〇年と戦友会ほか」(『共同研究・戦友会』田畑書店、1983・9)で指摘するように、「遺族を読者とする以上、遺族を著しく悲しませ、落胆させることは避けねばならず」、なおかつ未だ生きている戦争関係者が存在する以上、戦争犯罪の告発といった言説を書くことは当時において避けられねばならなかった。では、そのような趨勢の下で、加害の告発は、いかにして可能だったのか?
こうしたテーマから選定したのが、大岡昇平「野火」(『展望』1951・1~8→新潮文庫、1954・4)と、小島信夫「小銃」(『新潮』1952・12)である。前者はフィリピンにおける女性の殺害の問題を、後者は中国内陸部での捕虜虐殺の問題を描いている。両者が書かれた時期は、上でも触れた「わだつみ」的な言説の後であり、主流的な「戦争」のナラティブに「小説」の形で作家らはいかにして抗したか、ということを今回検討した。
大岡の「野火」は人肉食に着目されることが多い作品ではあるが、人肉食よりもむしろ女を銃で殺す場面を重点的に読むべきではないかとも思われる。小田実との対談において大岡は、以下のように述べている(大岡昇平・小田実「国家・南方・戦争」『群像』1973・3→『作家の体験と創造』潮出版社、1974・4)。
大岡 ぼくミンドロ島に半年駐留したんですが、十九年八月はもう負け戦だし、おまけにわれわれオッサン部隊だし全然元気がないから、何も悪いことしてないんですけども、自分がそこにいるというだけで悪い、フィリピン人に迷惑をかけているという感じがあったんです。われわれは旧軍隊の被害者であったけれど、フィリピンに対しては加害者であったという実感があるんで、これも何かの因縁で、東南アジアでぼくはフィリピンのことだけ気をつけているんです。(強調は引用者)
大岡が「フィリピンに対しては加害者であったという実感がある」と述べるとき、「旧軍隊」の徴発や強姦、殺人を指しているだろう。「野火」における人肉食は極限状況における人間の倫理の問題ではあるけれども、フィリピンへの加害ではない。つまり、「野火」を人肉食の観点からのみ読む時、アジアに対する加害の問題が骨抜きに――少なくとも弱められてしまうのだ。
小島の「小銃」においても、現地の女の殺害が描かれる。
私の銃イ62377は私の肩で躍つた。私はそのまゝ着け剣をして走りだした。女の首がうなだれているのと、血が胸を染めているのを走りながら見た。次第に人の姿が大きくなつてきた。走りつゞけるうちに私は道具になり、小銃になり、たゞ小銃に重みと勢いと方向をあたえる道具になつた。習いおぼえたように、ふみきると、私の腕はひとりでにのびた。私の任務と演習は終つた。
「小銃」が「野火」と異なる点は、題名が示す通り、「私」が示す三八式小銃への愛着である。先行論では、シンボリズム(江藤淳)やフェティシズム(柄谷行人)とも言い換えられるその偏執は、道具へと向けられてはいるが、殺人のための武器という面には向けられていない。だが、銃殺の場面では「私の銃イ62377は私の肩で躍つた」と、「私」の意思とは無関係であるかのように、銃の武器としての本質が露呈され、機械的に殺人が遂行されてゆく。こうした三八式小銃が作中において見せるイメージの揺らぎが、「小銃」を難解な小説としている一因であろう(作中では三八式小銃は男性にも女性にも喩えられており、その掴み所のなさが議論の主要な話題となった)。
「小銃」と「野火」に共通しているのは、三八式小銃で民間人の殺害を行うという点である。一方は、軍の員数であり(「小銃」)、もう一方は「菊花の紋が、バッテンで消してあった」(「野火」)小銃であるが。最近ちくま学芸文庫から再刊された加登川幸太郎の『三八式歩兵銃 日本陸軍の七十五年』(筑摩書房、2021・3)に代表されるように、この三八式小銃という兵器はそれ自体が日本の軍隊と関わる重要な表象であると思われる。

「戦争」を叙述するナラティブは、時代を経るごとに変化を見せている。それが過去どのようにあり、どのような変化を経て現在へと至るのか(村上春樹の描く中国戦線と、小島の戦争描写が似ているのではという話も出た)。その点について、今後、小説の読解を絡めながら考えていきたい。(文責・星住優太)
◎第4回(21/8/7)
◆【日時・場所など】
2021年8月7日、オンライン開催、参加者7人
◆【時代】
1930~1940年代、日本帝国支配下の朝鮮人文学
◆【主要テキスト】
・ 金史良「光の中に」(『文藝首都』1939年10月)
【議論の要点メモ】
1930~1940年代の日本の時代背景――日本浪曼派、文芸復興期、革命運動の転向、植民地同化政策(内鮮一体、創始改名)/第10回芥川賞と戦争期の文壇/外国語の文字表記/物語のメルヘン性/主人公の階級問題
【報告者コメント】
今回の報告では、在日朝鮮人文学の金史良の「光の中に」(『文藝首都』1939年10月)の時代背景と物語の性格に着目した議論を行った。1939年は、日中戦争の最中であり、文芸復興期の到来と転向作家の登場など文学も戦時下の変動の時期であった。こういった状況のもとで、植民地朝鮮における同化政策(内鮮一体、創始改名など)の影響で、日本文壇にも「朝鮮ブーム」とも言える現象が到来する。この時代の文壇が帝国主義を拡張してゆく国家の傾向に同調している様子は、菊池寛や小林秀雄などの文学者を中心に「文藝銃後運動」が展開されているという表面的な面に止まらない。より隠微な形で体制に迎合しているのである。

(「糞尿譚」で第6回芥川賞を受賞した火野葦平に日本から賞状を携えて中国杭州を訪れた小林秀雄)
例えば、菊池寛が創設した芥川賞には、この時代に多数の朝鮮出身作家が選定されている。「光の中に」が惜しくも受賞を逃した第10回受賞作は、北海道のアイヌ民族の問題を扱った寒川光太郎「密猟者」であった。芥川賞の作品選定には、帝国主義的傾向を増大させてゆく当時の時代性が反映されていると考えられるのである。また、金史良は治安維持法にもとづく予防拘禁の対象になり、検挙されることで朝鮮へ帰国することになるが、こういった暴力的な状況が金史良の「光の中に」が芥川賞候補作に選ばれた背景に想定されるだろう。作品の背景にかかわる議論では、以上のような指摘が交わされた。
作品内部においては、「語り」に関する議論が行われた。語り手は「私=南(みなみ)先生」である。「私が語らうとする山田春雄は、実に不思議な子供であつた。」(『文藝首都』1939年10月(以下同)一章)と語りがはじまるが、こういった語りの特徴は安藤宏によると、「告白回想モード」の語りである。安藤宏は、以下のように指摘している。
一人称小説の最大利点はなんといってもまず、「当事者のリアリティ」にある。事件に直接かかわった当人が事実をそのまま語ってくれている、という迫真性である。(中略)一人称小説は非現実的な内容にリアリティを与えたり、ありきたりの日常を眺め変えたてみたりするためにこそ有効な手立てでもある、ということになる。(中略)一人称による「告白」は、さらに次の二つの形態に分けて考えることができるだろう。
告白モード (1)告白・回想モード
(2)告白・対話モード
(『「私」をつくる――近代小説の試み』、岩波新書、2015年11月)
安藤宏は、このように一人称の物語で、日記形式の自分の秘密を語るといった叙述を「告白回想モード」と名付けている。「光の中に」の「私=南(みなみ)先生」の語りの形態はこれに属する。

しかし、過去のことを回想する語りであるが、語り手は自分の記憶に対して、非常にあいまいな姿勢をとっている。「さう云えば私はこの協會の中では、いつの間にか南(みなみ)先生で通つてゐた。」(一章)、「最初に山田春雄を見た瞬間から私の眼の前には、半兵衛の映像がかすかながらの光芒をもつてちらつてゐた筈だつた。だが私はそれが半兵衛であることに氣付くことが出來なかつた。或は春雄に對する愛情からして、ひそかにそれが半兵衛であることを私は怖れてゐたのかも知れない。」(三章)など、過去のことを回想している「私の語り」は、回想にもかかわらず、情報の信用度を軽減しリアリティ性を欠如させる姿勢をとっている。私の語りは、実際あることをそのまま語るといった回想ではなく、過去の出来事をしばしば否認し、作品全体に作り物めいた感覚を生み出している。在日朝鮮人であるが、「南(みなみ)先生」と周囲から日本人名で呼ばれ、「南(ナン)」という本来の呼び名を本人も意識しないうちにいつのまにか捨てているという状態もそれに対応しているだろう。
そのことを踏まえて、在日朝鮮人が日本において苦難を強いられる様子を描いているにもかかわらず、物語の性格がややメルヘン的ではないかという議論に発展していった。実際、作中では、正確な時代背景に関する情報は示されておらず、人物や物をメルヘン童話で扱われるような題材の動物(作中では、虫、イルカ、蟹など)に喩えているケースが多く見受けられる。先に見た語り手の姿勢と物語のあいまいさもまた、「光の中に」のメルヘン的な雰囲気を増加させる機能を果たしていると考えられるだろう。対照的に、主人公の前で在日朝鮮人としての出自が明かされる幼児・春雄の母親の貞順に対しては、「死」「死者」などの陰鬱な比喩が用いられていることは、興味深い。
詳しい説明は避けるが、このほかに、貞順の台詞における朝鮮語なまりの特徴が取り上げられた。また、それに比して、東京帝国大学生の「私=南先生」の言葉遣いはなまりがない標準語として記され、この差異はインテリと労働者階級といった階級問題にもつながる可能性を持っていることが議論された。金の作品のみならず、これは、日本文学における外国人の日本語をどう表記するかという問題に発展していく可能性があるだろう。
また、金史良は、日本の文壇においては三年というわずか短い期間にだけ活動していた作家であり、彼の朝鮮における『国民文学』での執筆など従来の研究では考察されていない点が多い。しかし、金史良の作品は、在日朝鮮人文学の主要な題材となる言語の問題や階級の問題、また、母に対する感覚などに多岐にわたっている。そのため、彼に続く金達寿、李良枝、李恢成などの作家の活動との関係とその影響を考えていく上でも重要なキーとなると考えられる。
(文責・金善泰、関西学院大学文学部日本文学日本語学専修)
◎第5回(21/10/9)
◆【日時・場所など】
2021年10月9日、オンライン開催、参加者8人
◆【時代】
1970~1980年代、引き揚げ文学の評価とその後
◆【主要テキスト】
・ 日野啓三「あの夕陽」(『新潮』、74・9→『あの夕陽』新潮社、75・3)
・ 吉田知子「満州は知らない」(『新潮』、83・11→新潮社『満州は知らない』、85・2)
◆【議論の要点メモ】
(1)時代背景
芥川賞の政治性/引き揚げ文学に対する評価軸
(2)「あの夕陽」
日野啓三の「原風景」と奥野健男からのその影響/軍政下のソウルの表象の希薄さ/引き揚げ体験を描かない文学は「引き揚げ文学」と言えるか
(3)「満州は知らない」
主人公に関する人称の揺らぎ/作品構造の循環性/身体感覚と埋もれた記憶との関連
◆【報告者コメント】
今回の報告は、前回の議論で出てきた問題、すなわち戦時下で日本が植民地政策を推し進めていた時期に金史良の『光の中に』が芥川賞の候補作として選ばれたのが政治的な意味合いを持つことを改めて確認することから討論を始めた。1970年代には、旧植民地からの引き上げ体験を持つ作家たちが芥川賞を続々と受賞し始める。そこで、まずは、発表の冒頭で、1970年代前後の芥川賞の受賞作と背景にある社会的な問題を整理しておいた。
当時の芥川賞は、1969年の清岡卓行「アカシアの大連」を皮切りに、1974年の日野啓三「あの夕陽」に至るまで、17作品中8作品の受賞作家が引き揚げ体験者である。1972年を除き、毎年引き揚げ作家が受賞している。

この背景には、1960年代後半に引揚者に対する社会的な関心が高まり、1968年8月「引揚者に対する特別交付金の支給に関する法律」(昭和42年8月1日法律第114号)が交付されたという事象があるだろう。引き揚げという現象自体に注目が集まった時代であったのである。こうした社会的な背景が芥川賞の選考へと暗に影響を与えたのか、それとも戦中期と同じく体制補完的な意味でより政治的な背景から選ばれたのかは、今後ほかの受賞作を含めて検討すべき課題であろう。
なお、発表時の意見としても、1976年には被差別部落に出自を持つ中上健次も芥川賞を受賞しているとの指摘もあり、「アジア」というテーマを超えて、芥川賞にまつわる政治的・歴史的な背景は、より発展してゆく可能性を持った議題だと言える。
ところで、七〇年代ごろから芥川賞を契機に引き揚げ文学に対する評価が与えられてゆくのとは裏腹に、文壇での議論は往々にして「引き揚げ」という現象自体の政治的な論議とはかけ離れていた、と朴裕河は『引揚げ文学論序説 新たなポストコロニアルへ』(人文書院 、2016・11)で指摘している。
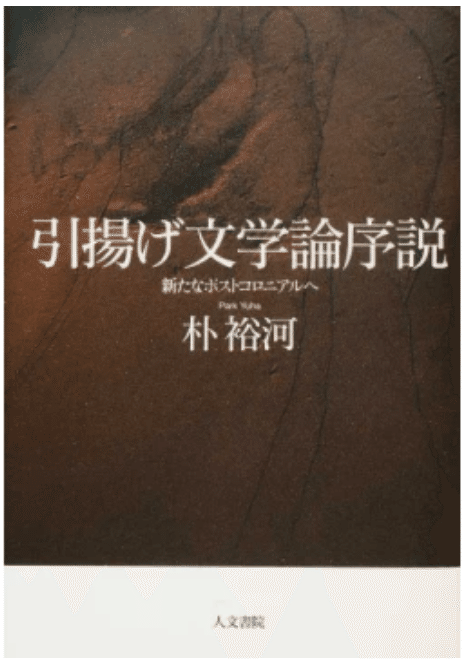
朴が指摘するように、今回扱った日野啓三・吉田知子の作品はいずれも「幻想文学」に分類され、しばしばその内向的な性格が指摘されることが多い。日野は「内向の世代」の一員と見做され、吉田は泉鏡花風の幻想文学者として現代では評価されている。どちらかと言えば、朴が政治性を脱色したものとしてあまり注目していないタイプの作家や作品と言えるだろう。その「幻想性」と引き揚げ体験との関連を具体化してゆくことが、今回の報告の中心的なテーマであった。
私の眼の前で彼女が死ぬことがあっても――と、ごく自然に思った明け方の気分が、また少しずつ甦ってきた。(中略)整理箪笥の表面にくっきりと木目のうねりを炙りだしながら、いま西陽の色はかすかな赤色さえ含んで黄色い。光のなかにも影を溶かしこんでいるような明るすぎる暗さだ。
記憶の深みで、緑色の淵の水面が燐光のように光っている。危ないからあそこは言ってはいけないと、学校でも家でも禁じられていた。(中略)淵は気味悪い緑色に仄明るかった。
ソウルの古い離宮の庭園にもそんな池があった。(中略)ミス李と知り合って間もない春先のまだ風の冷い日曜の午後に、私たちは見物客の多い宝物殿のあたりを過ぎ、古い土塀の蔭の小道を辿って、いつのまにか深い林の奥のその池のほとりに出ていた。入り組んだ透かし彫りの欄干をめぐらした亭が、ひとつだけ岸にたっていて、入ると腐りかけた床板がみしみしと音をたて、風化した欄干の木の粉が掌に白く残った。(日野啓三「あの夕陽」、強調は引用者)
日野啓三「あの夕陽」では、「私」の見る「幻想」が上記のように書かれる。ここでは「私」の胸中は、〈現在の日本〉→〈過去の日本〉→〈ソウルの記憶〉という形で、徐々に現在の日本から離れていく。だが、逆に、色の表現は、「明るすぎる暗さ」→「緑色に仄明るかった」→「白く残った」といま・こことの距離が開くほど、暗→明に移り変っていく。つまり、「私」にとっては〈現在の日本〉=暗=リアリティーのない土地、〈ソウルの記憶〉=明 =リアリティーのある土地という対比構造が存在しているのである。ここでは省くが、報告ではそれが、他の場面の文章表現や日本人の妻と「ミス李」との対比関係にもつながっていることを指摘した。
その後の議論のなかでは、当時の朝鮮は軍政下で厳しい社会的背景があるにも関わらず、作中では「私」にとってはそれが明るいソウルとして表象されていることへの違和感が口にされた。また、朝鮮に対する加害者意識の希薄さも議題に挙がった。
しかし、むしろ日野の場合は戦争に直接加担していない世代の作品だからこそ、このような表現になったと言えるのではないか。場合によっては、帰国した後の日本人からの差別や貧困の方がむしろ引き揚げ前の生活以上に厳しい――「あの夕陽」にもそのことは部分的に描かれている――という「引き揚げ」なる現象自体の持つ複雑さが根底にあると思われる。
さらに、「あの夕陽」に限っては引き揚げ体験を直接描いておらず、それを「引き揚げ文学」に分類することができるのかという指摘もあった。朴裕河が提示した「引き揚げ文学」の枠組みを継承しつつ、その内実をより具体的に示すことができるかは今後の報告者の課題である。

続いて、吉田知子の「満州は知らない」では、作品の複雑な構造や表現の難解さから、なかなか議論の中心テーマを見つけられずにいた。が、討論を通じて、主人公の「吉沢静香」の満州への想起のトリガーとなっているのが、「シェレン」という中国名の音声や、作中で頻繁に登場する「白い布」という視覚情報に由来しているとの指摘があり、それを契機に彼女が抱える幼少期の満州体験には身体的な感覚が強烈に結び付けられていることがテクストの記述をもとに様々に論じられた。
本作の難解さないしは「幻想性」もまた、作品構造や文体がそのように個人的な体験や身体感覚に依拠したものとして描かれていることに由来するのではないだろうか。
今回は、「引き揚げ文学における幻想性」というテーマで、「あの夕陽」と「満州は知らない」を扱った。その上で、「引き揚げ文学」という概念をさらに明確化してゆくためには、作品構造や文体と引き揚げ体験の結び付きをより多くの作家や作品から見てゆく必要があると実感された。
(文責・濵本政孝、神戸大学文学部人文学科近代文学専修卒業生)
◎第6回(21/12/18)
◆【日時・場所など】
2021年12月18日、オンライン開催、参加者8人
◆【時代とテーマ】
1920年代、日本統治時代の植民地台湾を旅する
◆【主要テキスト】
・ 佐藤春夫「女誡扇綺譚」(『女性』1925.5、プラトン社→『女誡扇綺譚』1926.2、第一書房→『霧社』1936.7、昭森社→『女誡扇綺譚』→『佐藤春夫台湾小説集 女誡扇綺譚』2020.8、中公文庫)
◆【議論の要点】
(1)主人公「私」の表象
「台湾」から距離をとる「私」/他者に語らせる新聞記者/回想モードの話法
(2)言語の問題
聞き取れない「女」の言葉/人語を話す鸚鵡/ポー「大鴉」の影響
(3)風景の問題
「我々の語彙」と景物の不一致/画家・梅原龍三郎のオリエンタリズム/表現に適した風景を求める「旅」
◆【報告者コメント】
今回の報告では、植民地としての台湾に対する佐藤春夫の姿勢と、それが作品にどのように表象されているのかを検討した。日本語文学で台湾を描いた代表的な作品として高く評価される本作は、発表以後――特に日本による台湾統治の時代には――作中の「異国情緒」が殊に取り上げられ称賛されてきた。

(佐藤春夫『霧社』特製版、1936年、昭森社。梅原龍三郎の裝幀。台湾文学虚擬博物館より)
近年では、そのような流通・受容の姿勢に対する「日本版オリエンタリズム」(藤井省三『台湾文学この百年』東方書店、1998年)という批判もあり、評価するにしても慎重な検討が必要である。本発表では、そのいずれの理解にも陥らない形で、丁寧に本文を精査してゆくことを試みた。
「女誡扇綺譚」は、台南の「廃市」を旅する日本人の「私」と、その案内役の友人で台湾人である「世外民」とが、ある廃屋で「幽霊」の声を聞いたことから廃屋にまつわる過去を辿り、「幽霊」の真相に迫ってゆくというミステリー風の作品となっている。しかし、謎解き自体は中盤であっけなく終わり、実はさらなる真相として、当時の台湾の人々が置かれた現状が見えてくるという複雑な仕掛けになっている。
まず、議論の対象となったのは「私」と「世外民」との関係である。「新聞記者」でありながら世間から逃げるように日々を送る「私」は、佐藤自身を思わせる人物造形となっているものの、「事実、私は歴史なんてものにはてんで興味がないほど若かった」と、歴史や政治の問題に踏み込む場面では徹底して距離を取ろうとしている。
対して、世外民は「支那人の血を受けた詩人」として設定されている。合理的・現実的な「私」と、ロマンチックな「世外民」の対比は繰り返し強調されるが、植民地化によって非エリートに転落した「世外民」と世俗の人生で苦しむ「私」との間には共通性がある。世外民が「私」に宛てた詩にあるように、彼らはともに「離群を嘆く孤雁」であり、「君夢我時我夢君」というように表裏一体の存在(「君」=「我」)として描かれている。
このように、いずれも世相から離れたいと望む存在であるからこそ、彼らは「禿頭港」という沼地の奧の廃屋で幽霊を目撃してしまうのだ。

(「私」と「世外民」が幽霊の正体を論じる「酔仙閣」の現在の姿。ここから遠くない「禿頭港」に幽霊の出た廃屋があり、その周囲は海に面した沼地で、あたかもポーの作品世界のような妖気に満ちた場所として描かれる。)
後の議論では、それに加えて、幽霊の目撃など重要な局面では、事態の説明や当事者としての責任を、「老婆」や「世外民」といった現地人に任せてしまっているという指摘が挙がった。
それが殊に顕著なのは、「エピロオグ」である。そこに至るまでの説明は省くが、「私」は最終的に廃屋での行動を後悔するが、一方で、「私は対して興味はなかった。しかし世外民が大へん面白がった。」と述べている。ここには「幽霊」には心を動かされないという自身の合理性が強調された上で、世外民に責任を押し付けようとする「私」の様子が現れている。
また、本作全体が回想形式で構成されているため、「私」の過去の言動は現在の視点から自嘲気味に語られる反面、いまの「私」の感情や考えは描かれない。ここには、本作の語りが回想というよりもむしろ、過去を突き放し自衛する語りとして性格付けられるのではないかという指摘もあった。このような「私」の非当事者的態度は、最終的には幽霊の正体とされる下婢、あるいは植民地に対する「私」の無意識の暴力性へと繋がっている。
次に検討したのは、言語についての問題である。本作の重要なセリフが「どうしたの?なぜもっと早くいらっしゃらない」という幽霊の声であるが、それは「私には判らない言葉で、だから鳥の叫ぶような声に思えたのは一層へんであった。」と語られ、「世外民」の説明で初めて泉州言葉(中国南方系の方言)であったとわかる。
最終的に、これは幽霊ではなく、下婢の言葉であったことが判明する。植民地において抑圧された下婢の言葉が、「鳥の叫ぶような声に思えた」というのはいかにも象徴的である。作中には「私」と「世外民」の会話で用いられる日本語、「私」にも一部聞き取れる「厦門の言葉」、「私」には人語と思えない泉州語という複数の言語が登場するが、言語の階層性がそのまま植民地内部の階層性と結びついているのである。
また、それとは対照的に、本作には人語を話す鳥が登場する。エピロオグで描かれる鸚鵡である。鸚鵡は事件の真相を聞きに来た「私」に対して、「汝来仔請坐」(お座りください)と叫ぶ。この言葉は漢字にフリガナつきで表記されているので、「私」がこの言葉を聞き取れたことが示されている。話す内容も廃墟で聞こえた「どうしたの?なぜもっと早くいらっしゃらない」に対応するかのように、来客を歓迎するものとなっている。さらには、下婢=幽霊は姿が見えないままであるのに対して、鸚鵡は下婢の姿を隠すかのように振る舞う。
作中ではこのように下婢と鸚鵡の対比・対応が繰り返されるが、それが何を示すのか、最終的にはっきりとした結論を出すことはできなかった。しかし、その後の議論の中では、人語を話す鳥のイメージはエドガー・アラン・ポオの『大鴉』からではないかとの指摘があった。佐藤にはポーの影響がしばしば指摘されるものの、管見のかぎり、本作と『大鴉』との対応を論じたものは見当たらない。

実際に、作中でも、以下の場面で「アッシャ家の崩壊」が引き合いに出されている。
私にもし、エドガア・アラン・ポオの筆力があったとしたら、私は恐らく、この景を描き出して、彼の「アッシャ家の崩壊」の冒頭に対抗することが出来るろうに。
私の目の前に展がったのは一面の泥の海であった。黄ばんだ褐色をして、それがしかもせせっこましい波の穂を無数にあとからあとからと飜えして来る、十重二十重という言葉はあるが、あのように重ねがさねに打ち返す浪を描く言葉は我々の語彙にはないであろう。
(『佐藤春夫台湾小説集 女誡扇綺譚』中公文庫、p.13、強調引用者)
ここに挙げた本作の冒頭では、メインストーリーといえる廃屋や「幽霊」の話題は全く出てこないままに、風景描写だけがひたすら続き、植民地台湾における「荒廃の美」が論じられている。
そして重要なのは、そうした「荒廃の美」が「我々の語彙にはない」とされ、景物と言葉との不一致が指摘されている点である。本作がポー的なゴシックロマンスを狙ったものであると仮定して、植民地台湾で初めて可能になったその「荒廃の美」は、しかし、日本語の語彙や描写方法では表現できないものであることが記されているのである。ポー的なゴシックロマンの実現を可能にした植民地台湾の景物は、伝統的な日本語の語彙と描写法を超えているのだ。
ここにポーを早くから受容していた大正モダニズムの知的爛熟と、それによって描かれる対象としてアジアの景物とが交錯してゆく点がある。これはルノワールに学び、近代絵画の手法を身につけた上で、描くべき景物を求めて植民地へと向かっていった画家・梅原龍三郎の動きとも重なるであろう。

(梅原の描いた紫禁城。1940年作。梅原は本書の装丁も手がけた。)
佐藤自身の台湾への旅も、本作冒頭に見られるように、大正期に獲得されたモダニズム的な語彙・表現に適した景物を求める旅であったと言えるのではないか。実際、後に「私」は泥の海が「港」であったことを教えられ、「『港』の一語は私に対して一種霊感的なものであった。今まで死んでいたこの廃屋がやっと霊を得たのを私は感じた。」と、内地におけるそれとは異なった言葉と景物の結びつきにこそ、感動を味わっているのだ。
『女誡扇綺譚』は、言語によって台湾内部の階層を表し、「世外民」や「私」といった内地における被抑圧的存在が、実は外地の下婢のような存在をさらに抑圧していること、そしてそのことに無自覚であったことを幽霊譚の形式を用いて暴いた作品であった
ただし、本作は同時に、漢学の土台の上にポオなどの作品を受容したモダニズム作家の外地への視線や、同時代の芥川や谷崎らの中国趣味、後に春夫を師とあがめてゆく日本浪曼派との繋がりなど、多様な方面の問題にも開かれている。今後、佐藤春夫を起点に、大正から戦中期日本の文壇の「アジア」への目線を検討したい。
(文責:丸山栞和、神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了生)
◎第7回(22/3/9)
◆【日時・場所など】
2月23日、オンラインにて開催。参加者6名。
◆【時代とテーマ】
1990~2000年代、ポスト冷戦期におけるアジア「現代史」
◆【主要テキスト】
・ 船戸与一『金門島流離譚』(毎日新聞社、04・3→新潮社、07・2)
・ 丸川哲史『台湾ナショナリズム 東アジア近代のアポリア』(講談社、10・5)
◆【議論の要点】
アジア「現代史」における台湾/豊浦志朗から船戸与一への連続線、ならびに平岡正明ら同時代人との関連/ハードボイルドとはなにか――「金門島流離譚」の文体と語り/「政治」をめぐる問題、丸谷才一『裏声で歌へ君が代』を視座に/「瑞芳霧雨情話」における「民族」
◆【報告者コメント】
今回の報告では、前回の佐藤春夫の台湾を舞台とした小説群に引き続いて、21世紀における台湾の問題について議論を行うべく、船戸与一『金門島流離譚』を対象テキストにとりあげた。

(『金門島流離譚』装丁。「アジア・ノワール」と銘打たれている。)
また、今回の対象である小説家・船戸与一は本研究会でも以前(第2回)検討を行った平岡正明とも人脈的なつながりを有していることが、選定の端緒となっている。
そのような事情から、まずもって船戸与一という小説家が何者であるのかを把握することを、小説テキストおよびポスト冷戦期のアジアという問題についての議論への導入とした。
周知のように、船戸には複数のペンネームがある。ルポルタージュ作家・豊浦志朗、『ゴルゴ13』の原作脚本家・外浦吾朗などの名義が代表的である。
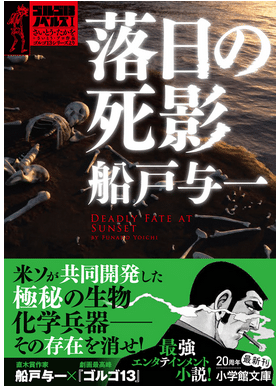
(例えば、後年刊行された、上記『ゴルゴ13 ノベルズ』というシリーズは、船戸与一が外浦吾郎(吾朗)の筆名で脚本を担当した約30作品から船戸が自選した作品を改めて小説化したものである。)
船戸与一を名乗る以前に用いた豊浦志朗名義では『硬派と宿命』(世代群評社、75・4)、『叛アメリカ史』(ブロンズ社、77・11)が上梓されている。この二冊に解説を寄せた平岡正明が、「革命思想とは帝国主義の現実と別のものではない。帝国主義の分析である。それが彼の小説だ」(『叛アメリカ史』筑摩書房、89・4)と、豊浦志朗から船戸与一への連続線を引くように、冷戦期における船戸の小説はアメリカが揺るぎない中心的存在として描かれる。
ブロンズ社刊の初刊『叛アメリカ史』において、「アメリカ帝国主義は衰弱過程にはいった」との言葉が読まれるように、豊浦=船戸は七〇年代後半の段階でヴェトナム戦争以後のアメリカ「帝国」の終焉を予言していた。さらに、ソ連の崩壊を二年後に控え、冷戦の名目上の終結と軌を一にして再刊された『叛アメリカ史』において、次のようにいう。
叛史の攻撃目標がアメリカ合衆国という二十世紀の頂点にあった権力構造からもっと大きな広がりを持つものへ広がっていく過程のような気もするのだ。つまり、ヨーロッパ的な価値観の全否定へと。ユダヤ・キリスト教的なものへの否へと。私はこのことを地域的に、あるいは民族的に限定して言ってるのではない。たとえば、日本人は総体としてヨーロッパ人以上にヨーロッパ的なものへどっぷり漬ってるとしか思えないのだ。(豊浦志朗『叛アメリカ史』)
船戸において、冷戦の終結はそれがアメリカ的な権威のみならず、「ヨーロッパ的な価値観の全否定」をも、もたらすものであった。西欧近代社会の理念を借り受けた「日本」もまた「叛史」の標的となることを免れない。しかし、ソ連崩壊以後のポスト冷戦期にこうした見通しが現実となるにつれて、情勢の変化は小説家船戸与一の活動にも失調をきたした。アメリカ9・11テロ発生の半年前のインタビューに船戸は次のように答えている。
ベルリンの壁が壊れたとき、あちこちの新聞社から、冷戦構造が崩れると、あなたの書くような小説は書きにくくなるだろう、という質問をされたけど、東西関係の視点から世界を見てきたわけじゃないので、そんなことはないと思うと答えたんだよ。しかし、現実には東西関係と南北関係はリンクしていて、座標軸はくっついているから一つの軸が崩れると、南北軸というものも非常にあいまいになってくる。次第にボディーブローのように効いてくるわけだ。 俺も物心ついたときはすでに冷戦時代で、なんだかんだ言いながら、冷戦構造のなかでの感覚とか知識とか抜けきらない。やがて物語が書きにくくなったことに気づかされ、多少のあせりも生じたね。(船戸与一『望星』01・4)
ソ連崩壊と中国の市場化によって、社会主義という「革命の先行モデル」が消失した結果、アメリカを含む先進国の延命装置としての「グローバリズム」が各国を覆い、経済的帝国主義が地理的な間隔を無化してアジアを周縁化する。
このような船戸の冷戦期以後の認識が裏打ちされたのが、2000年代以降の直木賞受賞作『虹の谷の五月』(集英社、00・5)をはじめとするアジアを舞台とした作品である。現在進行形の経済的な国家間の相互依存関係と20世紀の歴史の回帰点としてのアジアの現在をみるにあたって、船戸の作品が重要である所以は、現在/歴史=「現代史」によってアジアにおける物語がいかに創出もしくは規定されるのかを文学の側から提示している点にある。
なお、今回の報告後の議論では、船戸与一と平岡正明における同時代的なつながりに関する補足や、新左翼に出自を持つ作家たちの左派イデオロギーを通じた歴史の物語化に関する右派への先行性(左派=68年世代からの歴史修正主義)についての指摘がなされた。
こうした経緯を把握したうえで、議論は対象テキストである『金門島流離譚』へと進んだ。表題作の「金門島流離譚」は中国厦門にほど近い距離に実在する台湾が実効支配する領土である「金門島」を舞台に、主人公・藤堂義春が行う偽造品ビジネス(酒、ブランド洋服、海賊版のCDなど)と中国国家安全部の暗躍や中台マフィアの水面下の抗争が交錯する内容となっている。

(世界地図上の金門島の位置。中国本土と台湾の間に位置するその微妙な地政学的位置から、殺人・密売・密入国など、本作の「アジア・ノワール」的世界が演出されてゆく。)
「金門島」は小説内では、「台湾領だという国際法的な根拠はどこにも」存在せず、「領土的にはどこにたいしても帰属意識がない」「現代史の未解決部分」であると説明される。このような手つかずの「現代史」の空白が物語の中心に置かれている。「金門島流離譚」は藤堂の犯罪ビジネスと繰り返される殺人によって、空白であるはずの「金門島」という地理的存在が揺らぎつつあるさまを描く。
台湾の「実効支配」下におかれながらも、国家への「帰属意識」をもたない「金門島」は、「現代史」から見かけ上は疎外された土地であり、同時に違法なビジネスの拠点となり、先進諸国の享楽的な資本流通の昂進を阻害する場所としてアジアのなかに立ち現れている。
報告者の側からは「金門島流離譚」における「政治」と「現代史」の問題を、台湾と「国家」を主題とした丸谷才一『裏声で歌へ君が代』(新潮社、82・8)と関連して読み解く報告を行った。

「金門島流離譚」のなかでは、語り手の藤堂を通じて「政治」とはなにかが語られている。
犯罪ビジネスを行う人間は厭でも政治に関心を持たざるをえない。ある意味では犯罪とは政治的な行為であり、政治とは犯罪行為なのだ。そして、政治への興味は犯罪ビジネス関係者に豊かな想像力を与える。わたしは自信を持って言おう。犯罪者こそ最高のイマジネーションの持主だ。(略)このまま共産党が衰弱していくと、ロシアの民族主義が弱まり経済が最優先課題となる。そのとき北方領土の日本への返還が現実的に討議されはじめるだろう。それは土地の補償問題として浮上する。日本政府にべらぼうな額を支払わせるためには土地を取得していなければならない。そう説明したのだ。ふつうの人間ならこんな発想は生まれもしない。(『金門島流離譚』)
作中の叙述によれば、「政治」と「犯罪」が両義的な行為であるとされる。「犯罪者」とは国家的な「政治」の弱点につけ入ることで「ビジネス」を成立させる人間であり、「犯罪」は「政治」への意識を欠いては成り立たない行為である。このような小説の主題は、丸谷が『裏声で歌へ君が代』に記した跋文に照らすことでより強く前面化される。
政治的人間という言葉がある。政治が人生のいちばん大事な主題である人間、という意味だらう。わたしは政治的人間ではない。
しかし、そんな人間にこそ政治は襲ひかかるし、あるいは、そんな人間ほど、政治に襲ひかかられたと感じるものらしい。すくなくともわたしは幼いころからずつと、そんなふうに感じて鬱陶しい思ひをしながら、現代史とつきあつてきた。案外、たいていの人がさうなのではなかろうか。
そのへんの消息をわたしは何とか書いてみたいと思つた。そこからはいつてゆけば、現代人を悩ましてゐる、そしてわたしを子供のころから悩ましている、国家とは何かという問いの答も、おぼろげに浮びあがるかもしれないといふ気がした。
つまりこれは非政治的人間の書いた政治小説である。(『裏声で歌へ君が代』跋文)
丸谷においては、「たいていの人」=大衆とは「政治」から無意識的に距離を置く生活者であり、一方で「政治的人間」とは政治が「人生」の「主題」であるような人間を指す。『裏声で歌へ君が代』が、「台湾独立運動」という現実の政治にコミットする人物と、それとは対照的に戦後日本に安住するインテリ的人物たちの軽やかな政治的談義をつうじて、「国家」とはなんであるかを素描する小説であるとすれば、日本人や中国・台湾人、東欧の犯罪ブローカーや中東の新興武装勢力に属する人物を登場させ、それぞれの思惑のもとに「犯罪」=「政治」へと踏み込むさまを描き、国家間の情勢の暗部を照らし上げる「金門島流離譚」は、「犯罪者」=「政治的人間」(丸谷)たちの行動によって21世紀的な「現代史」の構造を暴く物語にほかならない。そして、こちらでは「金門島」を含んだ「国家」なるものは「犯罪者」たちの行動によって反措定される。
さらに、丸谷、船戸の作品にはどちらも「参考文献一覧」が記されており、両名ともに台湾出身の歴史学者・戴国煇(1931~2001)の著作を第一参照先として挙げている(丸谷は『台湾と台湾人』[研文出版、77・11]、船戸は『台湾―人間・歴史・心性―』[岩波書店、88・10]を挙げる)。このことから作品を論じるうえで、丸谷と船戸が戴の台湾史観からいかなる影響を受け、その解釈にどのような開きがあるのかをさらに考える必要があると思われる。
ここでは詳述する余裕を持たないが、報告では、小説が展開するにつれて藤堂を襲う危機は政治/犯罪へと足を踏み入れたものの宿命であり、作品の末尾において藤堂の生存への「虚妄」が潰える瞬間に、国家の隔たりを超越した政治性の限界点としての死が待ち受けることを読みこんだ。
また、「金門島流離譚」をめぐる議論では、「金門島」という場所の名称自体が作品のメタファーとして読まれるのではないかという指摘や、小説の冒頭に附されたエピローグ部分に関する時制の問題を物語全体と重ねていかに読解することができるのかについて様々に意見が出された。
『金門島流離譚』に併録された、もう一つの作品「瑞芳霧雨情話」についても報告と議論を行った。
「瑞芳霧雨情話」は日本統治時代に開鑿された「瑞芳鉱山」を舞台に展開している。この瑞芳は、1980年代以降の台湾ニューシネマの文脈に位置し、「二・二八」事件(1948年におきた国民党による市民の武装弾圧)を題材にした89年公開の侯孝賢監督『悲情城市』の舞台となった土地であることが作中でも言及される。

(「瑞芳霧雨情話」には、『悲情城市』の舞台である九份が、その映画の大ヒットによって植民地時代の鉱山労働の実態を覆い隠し、日本人観光客の訪れる観光地となってしまったことが苦々しく描かれている。)
「瑞芳鉱山」労働者の生き残りである老人・呉興福に語り手の「ぼく」=梅宮俊夫は鉱山労働の実態調査の聞き取りを行う。
台湾と中国における資本の問題を描いた「金門島流離譚」と対照的に「瑞芳霧雨情話」は日本の植民地時代における台湾のプロレタリアートの問題を物語に介在させている。歴史的にこのことを見た場合、「瑞芳」において浮上するのはプロレタリアートと民族の問題である。
作品の終盤において、婚約者の汪成美を凌辱された「ぼく」は同じく凌辱された興福の孫・麗花の婚約者・姚桐盛とともに復讐を決意するが、そこで描かれるのは「ぼく」の戦いの場における無力感である。徴兵期間にあり自動小銃を武器に闘う姚桐盛と対照的に、「ぼく」には汚辱のイメージが付与される。興福、姚桐盛、「ぼく」には、闘いの場面での民族的な差が強調される。この意味で、「瑞芳霧雨情話」の物語は、「金門島流離譚」が語り残した日本とアジアにおける「民族」の問題を相補的に描いた作品として、この両作品が表裏一体の関係をなすように構成されているといえるだろう。また、議論に際しては、両作品に関連する物語における女性の役割やそのイメージの定型性に関する指摘があがった。
第7回目となる今回の船戸与一をとりあげた報告と議論では、主に台湾を舞台とした小説『金門島流離譚』に焦点を当てた。しかし、先に記したように船戸与一にはフィリピンを舞台とした直木賞受賞作『虹の谷の五月』や日本と韓国と台湾を舞台とした短篇集『三都物語』(新潮社、03・9)などの作品、そして遺作となったものの八年もの年月を経て完結した一連の「満州国演義」が存在する。さらに、豊浦志朗としての活動を彷彿とさせる『国家と犯罪』(小学館、97・5)の著書もある。船戸与一におけるアジアの問題を検討するためには、これらの著作の連関から作家の問題意識を読み解く総合的な視点が必要となるだろう。
(文責・西田正慶)
◎第8回(22/4/23)
◆【日時・場所など】
2022年4月23日、オンライン開催、参加者10人
◆【時代とテーマ】
1910年代、韓国併合期の文学
◆【主要テキスト】
・ 高浜虚子「朝鮮」(『大阪毎日新聞』1911年6月19日~8月27日(途中で掲載中止)/『東京日日新聞』1911年6月19日~11月25日→『朝鮮』実業之日本社、1912年2月)
◆【議論の要点メモ】
当時の朝鮮の状況/朝鮮と日本の歴史/先行作品の朝鮮イメージ/小説と文/受容・読まれ方/改稿/人称と人物設定/朝鮮語・朝鮮表象
◆【報告者コメント】
今回は、高浜虚子「朝鮮」における朝鮮イメージと同時代の文壇の状況を踏まえた作品の位置づけについて報告を行った。近代日本文学史上、植民地としての朝鮮を描いた嚆矢と目される本作において虚子が何をどのように描いたのかを検討することは、この後に植民地を描いた文学作品の位置を探る上で、あるいは文壇の主流においてアジアが描かれなかったことを考える上では重要な意味を持つだろう。

(高浜虚子「朝鮮」は入手が難しいが、現在、国会図書館デジタルコレクションにて、閲覧可能である。)
当時の文壇においては、明40年前後からの描写論議が一定の水準に達したことで落ちつきを見せ、描写法ではなく作者の内部や観察にあらわれる人生観などが作品評価の重要な要素として見なされるようになっていた。
そのような中で虚子の作品は、近松秋江が次に述べるように、日本的であるという点においてその特質が見出されている。
同じ敗残な性格を書くにしても、殊更に近代人がらうとあせる之れまでの新作家の書いたものは、妙に西洋の作の中にあるものを翻案したやうな、或は西洋の作を読んで、さう云ふ性格に対する一つの哲学を呑み込んで其の哲学を以て作り上げたやうなところがあつて、其の敗残な性格に憧憬して居るやうに見える。本当に日本に生れ日本の土に培はれた性格を自象的に書いて居るのは殆どない。(略)日本人の書いた小説を、日本くさいと云つて批難の理由とする人もあるが、虚子氏の作などは、此の日本くさい所に価値があるのだ。(「虚子氏に対する雑感」『新潮』1911年11月)
今回の報告の一つのポイントは、植民地の描き方という観点が議論の中心を占めてきた本作の作品評価に、上記の評に見られるような、この時期の文壇における虚子の位置取りという観点を導入するものであった。詳細は省くが、例えば、報告の中では「俳趣味」「俳諧趣味」という観点による俳句界の議論も視野に入れた。
作品内部を見ていくと、「余」とその妻が大邱から京城、平壌と巡っていく中でさまざまな旧跡を訪れ、歴史を確認していることが注目される。同時代から言及されてきたように、本作が旅行書として読まれてきた側面である。

(作中には、このように旅情=異国情緒を際立たせる挿絵も添えられている)
京城の宿では閔妃事件や莞島事件を知り、王宮では戦いの跡を、大同江では文禄・慶長の役や日清戦争の舞台を訪ねている。これら「余」たち夫婦が訪ねる朝鮮の歴史の跡の中心は、日本と朝鮮との間の戦いの跡が中心となっている。当時の統監であった寺内正毅が韓国併合を秀吉の朝鮮出兵の延長線上に見ていたことを考え合わせると、ここでたどられている歴史の選択の意味は検討に値するだろう。
なお、虚子は改造社版全集で、次のような興味深いエピソードを紹介している。
明治四十四年大阪毎日、東京日日両紙上に連載したもの。之に就いての一つの挿話は、之を其後一冊子として実業之日本社から出版した時、意外にも時の朝鮮総督であつた寺内大将〔引用者注・寺内正毅〕から――別に贈呈もしなかつたのに――態々使を以て此「朝鮮」について謝意を表されたことであつた。併合当時の朝鮮にあつた内鮮人の状態と国威の北遷して行く勢とを写し且つ朝鮮の大陸的風光を描くことを目的とした点が、或は植民政策から見て有効な一書とされたものかもしれなかつた。(高浜虚子『朝鮮』、強調は引用者)
一方で、描かれる朝鮮のイメージは、先行作品と共有するものである。半井桃水の「胡砂吹く風」や服部徹の「小説東学党」などにすでに見られる〈母なる朝鮮〉の像や政治小説的なイメージが本作にも導入されている。本作には、日本と関わりのある朝鮮の歴史、日本における朝鮮を描いた文学作品のイメージがふんだんに導入されているのである。
汽車が江岸で客を吐き出してゐたり、ヨツトが直に其客を収容して動き始めやうとしてゐたり、白い石造のホテルが何間かの窓を灯し連ねてゐたりする光景を目の前に髣髴しつゝ余は話した。さうして平壌といふ土地に存在するであらう多くの事情は一切問はず、又斯く成就する迄に費すべき時間をも考へず一画図のやうに其光景を描き出して見る点に興味を持つた。(高浜虚子『朝鮮』、強調は引用者)
しかし、上記の叙述に読まれるように、それらの歴史やイメージが示唆されつつも同時に消去され、その上にこそ「余」の想像が介入していることは見のがせない。作品後半に多く見られるこの「余」による想像の部分は、本作が紀行文ではなく小説として定められていることについて考える上で重要である。
議論の中では、この作品が小説というジャンルとして規定されていることについて多くの意見が交わされた。一つにはこの作品がどのような点において小説と呼べるのかという疑問が呈され、他方ではむしろ文として見ることで開かれる可能性について指摘があった。

(巻末の広告からは、このように、あくまで本作が「小説」として銘打たれていたことが窺い知れる)
夫婦が子供を失ったという作品冒頭における設定が単行本化の際に削除されたことについては、小説的構成力が失われているのではないかという指摘があった。作品形式上の問題では「余」による視点と「余」を含めた夫婦を描く際の視点の違いや前後半でのレトリックの差異などについても、本作が小説というジャンルに定められたことを考える要素として議論の俎上にのった。
文というジャンルに関しては、本作のプロット展開に紀行文的性質や日本の古典的文学作品の影響が見られるのではないかという指摘があった。前々回の佐藤春夫の作品検討において、絵画界とも通底したモダニズム的語彙・表現に適した風景を求める傾向が指摘されていたこととは対照的に、日本的な語彙・表現によって植民地の風景を描いた作品として本作を位置づけることが可能ではないか、という見通しも立てられた。

この見通しの先に、西洋由来の自然文学主義ではなく、俳諧や戯作など日本的なエクリチュールの進展の下に、もう一つの日本近代文学の流れを見る江藤淳の評価(『リアリズムの源流』)もあるのではないか、という観点が得れたことも今回の収穫である。江藤はそこでとりわけ、虚子を高く評価してたのであった。先に述べたように虚子の作品が同時代において「日本的」という点において評価されたことや自然主義者との対抗関係、民俗学との関連を視野に入れてこの点をさらに考えていきたい。
その他、作中の朝鮮語やルビの使い方などを含め、朝鮮表象の問題についても議論が重ねられたが、これについては同時代言説や周辺の作品をも視野に入れた上で再検討する余地が残った。日本を語ることがアジアを語ることとなってしまう、というような問題を考える上でも、今後、本作のような日韓併合期の文学作品をより広く見ていく必要があるだろう。
(文責・都田康仁)
アジア論研究会「第1期」総括(2022年7月14日)
◆【アジア論研究会の運営について】
当研究会は、「日本文学にとって「アジア」とは何(だった)か」という問いを考えていくことを主眼としている。研究会は約2カ月に1回のペースで開催し、2020年11月から2022年7月まで合計9回、報告および討論をおこなうことができた。冷戦体制崩壊期(中上健次)に始まり、最終的には韓国併合期(高浜虚子)までさかのぼって、批評と小説を中心に様々な言説や作品を検討した。


約1年半のあいだ途切れることなく研究会を開催した。神戸大学の大学院生を中心に7人で始めたが、半クローズドな研究会として行ってきたにもかかわらず、第8回には12人まで増えた(「第二期」に入った22年7月現在は、14人)。現在は関西以外、加えて日本国外からも参加者がいるので、オンラインを中心とする現体制はそのままで進めてゆきたいと考えている。
当研究会は、松田樹と赤井浩太が主宰している。吉永剛志『NAM総括』(航思社、2021)の編集に携わった2人だが、基本的には同著作に関わった際と同じく、毎回プロジェクトベースで人を集めて動いている。例えば、2022年3月には、ここに竹永知弘を加えた3人で、『国文論叢』第59号の特集企画(「政治と文学」再考:七〇年代の分水嶺)を立案・運営し、刊行した。

当研究会と同時進行で進めたこの企画は、たんに一つの成果となっただけでなく、当研究会にとっても今後の指針となった。というのも、研究会での報告・検討を通して、こちらでも特集企画ないしは書籍化企画を立ち上げることが一つの目標として浮上したからである。
特集企画に関しての感想を述べれば、学会誌を刊行するまでのプロセス全体が非常に良い経験になった。むろんこれは個人の「実績」になることでもあるが、それ以上に企画立案、論文執筆、全体進行管理、合評会開催、企画広報などの全プロセスに関わることは、大きな経験値になった。この「経験値」とは、こうした企画をやる際に、まず何をどんな手順で準備すべきか、そして何に注意すべきか、また企画において何を大事にすべきか、といったことが肌身に染みて分かるようになるということである(この実務的な観点は、『NAM総括』でも強調されていたことだった)。
研究者とは本質的に自営業者のことに他ならないが、しかし一人でできる実務には限界がある。とりわけ、その分野の研究を成り立たせているゲームの盤面自体を、そもそも抜本的に変えようとする場合には、同業者といわば「業務提携」することも重要な仕事だろう。
アジア論研究会は、今後、「第二期」として仕切り直すにあたって、たんなる勉強会を越えて、上記のような実践的な場としたい。今後必要なことを備忘的にメモしておくと、このようになるだろうか。
1.研究会(発表・討論・記事)
2.学会誌(企画立案・論文執筆・合評会・広報活動)
3.書籍(企画立案・版元交渉・論文執筆・合評会・広報活動)
1から3へとボトムアップ式に研究成果を積み上げてゆくことを目指す。研究会は基本的に松田・赤井が主導するが、学会誌企画では特集テーマに合わせて研究会メンバーがチームを組んで企画の立案・進行係とする。研究会→学会誌を繰り返す過程で、研究成果を書籍化するための企画案・目次案を練っていく。3の実現は数年後になると予想されるが、コンセプトの強い論集本を作ることが最終目標である(当研究会の構想に関心のある書き手・編集者の方がいましたら、松田樹のメールアドレスまで)。
◆【アジア論研究会の内容について】
本研究会の「第1期」では、先にも述べたように、冷戦体制崩壊期から韓国併合期までさかのぼり、日本の小説作品に影を落とす「アジア」の存在について、時代を跨いで巨視的な観点から焦点を当ててきた。また同時に、しばしばその小説作品とセットで読みうる文芸批評および批評家における「アジア」というテーマの扱いにこだわってきたことも、この読書会の特徴であると言えよう。
あらためて、以下にこれまでの題目と主要なテキストをまとめておく。
第1回(松田報告):1990年代、冷戦体制崩壊期における「アジア」
①柄谷行人『終焉をめぐって』
②中上健次『南回帰船』『異族』
第2回(赤井報告):1970年代、全共闘運動期における「アジア」
①平岡正明『日本人は中国で何をしたか』
②唐十郎『少女と右翼』
第3回(星住報告):1940~1950年代、敗戦復員兵にとっての「アジア」
①大岡昇平「野火」
②小島信夫「小銃」
第4回(金報告):1930~1940年代、日本帝国支配下の朝鮮人文学
金史良「光の中に」
第5回(濱本報告):1970~1980年代、引き揚げ文学の評価とその後
①日野啓三「あの夕陽」
②吉田知子「満州は知らない」
第6回(丸山報告):1920年代、日本統治時代の植民地台湾を旅する
佐藤春夫「女誡扇綺譚」
第7回(西田報告):1990~2000年代、ポスト冷戦期におけるアジア「現代史」
①丸川哲史『台湾ナショナリズム』
②船戸与一「金門島流離譚」
第8回(都田報告):1910年代、韓国併合期の文学
高浜虚子「朝鮮」
見られる通り、「第1期」では、1910年代から2000年代までの作品を取り上げ、それを通して日本近現代文学に現れた「中国(あるいは満州)、台湾、朝鮮、フィリピン」の影を広く検討してきた。また、議論のなかではしばしば、絵画・漫画・映画・アニメなどの他ジャンルも参照すべきものとして話題に上った。たとえば、これまでの研究会を例に取るなら、第6回「1920年代、日本統治時代の植民地台湾を旅する」(丸山報告)では、佐藤春夫の風景描写、エドガー・アラン・ポーのゴシック・ロマンス、梅原龍三郎の近代絵画が話題に上った。
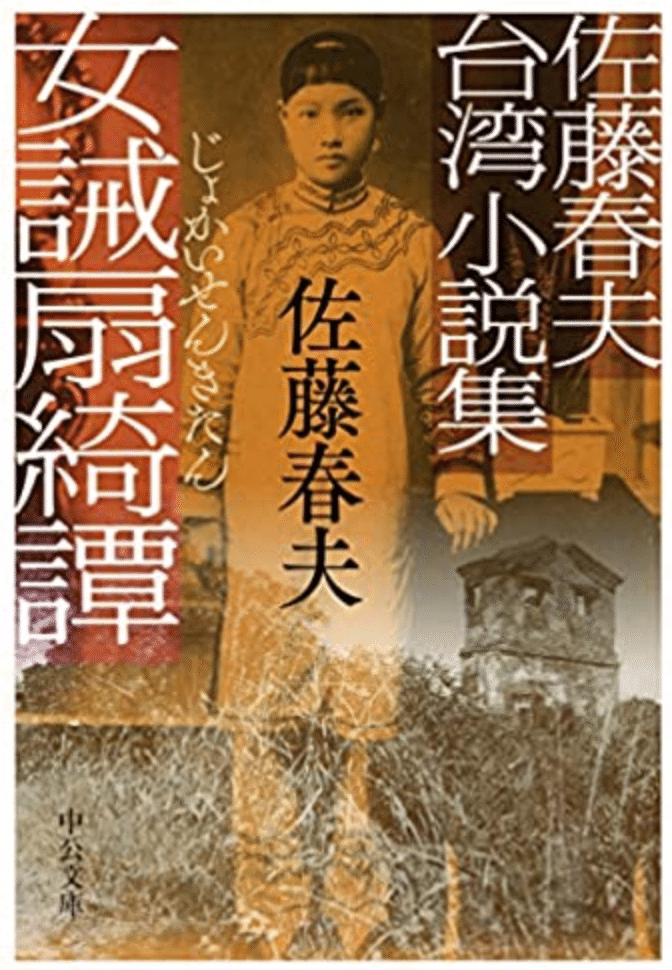


第7回「1990~2000年代、ポスト冷戦期におけるアジア「現代史」」(西田報告)では、船戸与一のハードボイルド、丸谷才一の『裏声で歌へ君が代』、台湾ニューシネマについて詳細な報告が行われた。



このように、「アジア」を捉えるならば、純文学とエンタメという文学研究内部の境界線だけでなく、アカデミックな場ではしばしば切断されてしまう絵画と文学、映画と文学、漫画と文学、といった線引きを取り除く必要がある。「アジア」に注目し、その観点から上記のさまざまな分野を串刺しにすることで、既存の文学研究のゲームを変えることができるのだ。
批評的なテキストは、その手がかりに過ぎない。文芸批評の歴史を一つの参照枠として用いながら、様々な芸術形式(詩・文・小説・絵画・映画・漫画・アニメ)を横断し、「アジア表象」を歴史化してゆくことが我々の目的である。この作業は、文学の領域を手放してしまうのではなく、むしろ日本近現代の文学はアジア地域に対してどのような帝国主義的欲望を持ち、かつその反面で何を反省的に問うてきたのかを明らかにするためのものである。これ自体が、批評の問いでもあろう。
◆【アジア論研究会「第2期」に向けて】
今秋(次回は9月4日開催予定)からは学会誌での企画化を目指して、研究会のメンバーから企画書を提出してもらい、その内容に沿って研究会を進めていく予定である。また、「1期」以上に批評を読むことも「2期」の中心的な課題となるだろう。メンバー間で「アジア」に関する問題設定を共有していくことが重要である。
当研究会は、「アジア論」の研究拠点として、息の長い運営をしていくつもりである。ただし、単なる勉強会にとどまらず、「アジア」を共通項にしながら、各々が明確な研究成果を出すことを目指して今後も運営を続けていきたい。
(文責・赤井浩太+松田樹)
《この記事終わり》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
