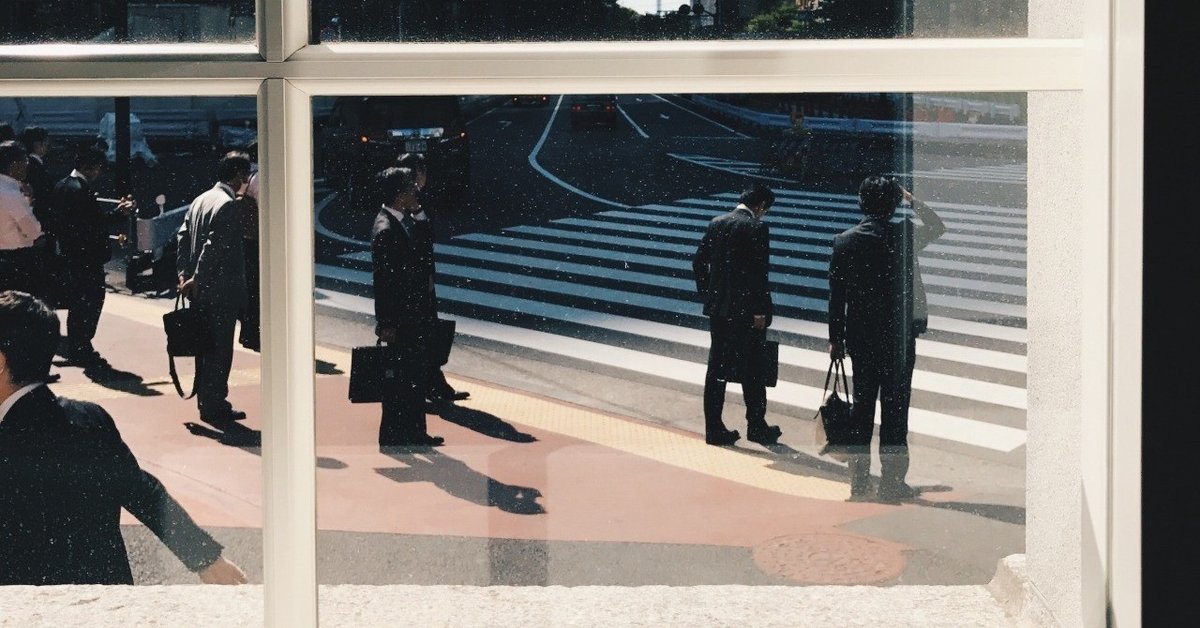
本を書いています。
Vol.18 ビジネスライク症候群
子どもの頃、いわゆる学芸会的なものが苦手でした。
幼稚園とか、本当に小さい頃は何も気にしていなかったと思うのですが、あるときから人前に出て何かを演じるということに対して、恥じらいを感じるようになりました。いま思うと、もしかしてそれが「自我の目覚め」だったのかもしれないな、とも思ったりします。
なぜ人前で歌ったり踊ったり大声でセリフを読まなければいけないのか、まったく意味がわからなかったのです。恥ずかしいだけじゃないか、もっと普通に喋ればいいじゃないか、と。正直、ミュージカルなどを見るのも、ちょっと苦手でした。
今でこそプレゼンテーションや講義、講演などはだいぶ慣れたものですが、それは「演じる」というよりは「伝える」という行為です。私は、プレゼンするときは「いつも通り話して、いつも通り聞く。」ということを意識しています。もちろん、時と場合にもよりますが…。
人は、仕事の場になるとなぜかガラリとスイッチが切り替わり、「ビジネスライク」な喋り方に変わります。あれは日本特有のものなのでしょうか。最もわかりやすい例は、「なんだかビジネスっぽいカタカナ語」でしょう。
「それはto Bなのかto Cなのか、お互いのコンセンサスを取りながらアジャイルしつつPDCAを回してですね…いや、そこはアウトソーシングしてコンバージョンレートを上げることに集中しないと。あくまでもジャストアイデアですが。」
…みたいな。テキトーですが。まさに「大人語のナゾ」です。「あとからキャッチアップさせてください!」と言って、本当にキャッチアップしてる人をあまり見たことがありません。
メールの作法も同様です。目上には「了解しました」じゃなくて「承知しました」だろー!とかなんとか、ホントにもう。
たまに冷静になってメタ的な視点で見てみると、ギャグにしか見えないことすらあります。つまるところ、ビジネスの場とされるものは「劇場型」なんじゃないかと思うのです。ビジネス劇場。まぁそんな偉そうなこと言いながら、もちろん自分も劇団の一員なのですが…。
話し言葉やメールの文面など、それが礼儀だとされるのなら、無理に逆らう理由もなく、とりあえず郷に従っておけばいいと思うのですが、闇雲に「ビジネスの現場というものは真面目にせねばならぬ!」といったような固定観念は、正直いかがなものかと思ったりもします。もっと簡単にことを進めればいいものを、わざわざ難しくしてしまうような人が、みなさんのまわりにもいたりしないでしょうか。
最近、私はそういうのを「ビジネスライク症候群」と、心の中で読んでいます。愛と尊敬の念をを込めて。
もちろん、場をわきまえずに悪ふざけしたりするのはダメです。ただ、やたらと難しい顔して固〜い話しかしないような現場に、面白いアイデアなんて出るはずもありません。どんなことでも、少しは「遊び」が必要なんです。
ここで言う「遊び」とは、歯車と歯車の間の「遊び」と同じで、いわば「余裕」ということです。少しの「遊び」がないと歯車が回らないのと同じように、ビジネスの現場にだって「余裕」が必要なのです。
このことは、もうすぐ発売になる拙著「面白い!」のつくり方 の中でも重要な考え方になっています。面白い表現をするためには、まずはそれを考えるだけの「余裕」が必要なのです。
ところでこの本、ジャンルとしては「ビジネス本」ということになっていますが、いわゆるビジネス本のような固い印象はまったくなく、ほどよくゆるい内容になっています。まったくビジネスライクではありません。そういう意味では「ビジネス本」というジャンルに入るものなのかどうか…いや、そもそも「ビジネス本」って何なんでしょう。
ちなみに、出版社のページでは「はじめに」と「章立て」をチラ見することができます。
はい。どう見てもビジネスライクではなさそうですね。ご期待ください。
Photo by Jon Spectacle on Unsplash
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
