
「うやまわんわん〜犬将軍を崇める一族〜」第八章 大団円(その1)
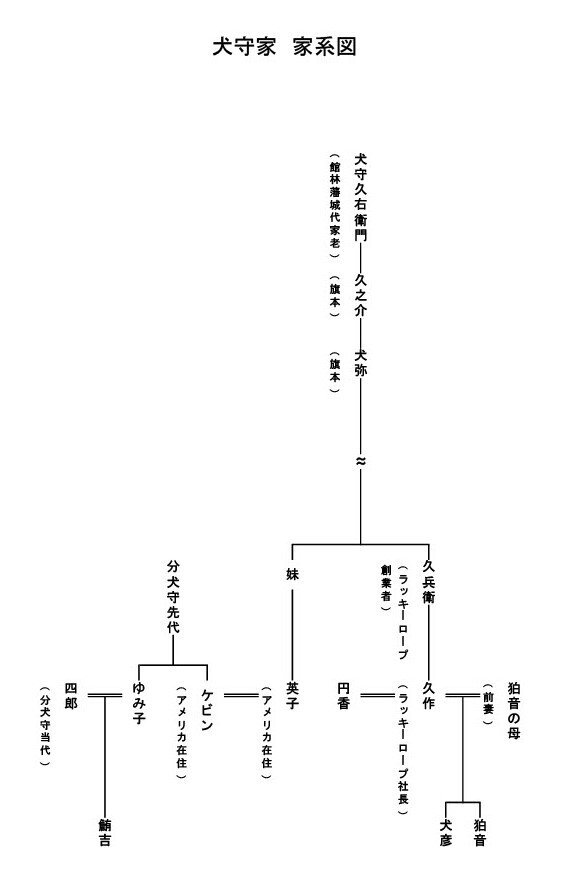
1
久作さんの手紙をたずさえて、狛音と分犬守の屋敷をたずねた。道すがら狛音は口数が少なく、瓦屋根の門の前に立つとため息をついた。
「いらっしゃい」
藤色の着物姿のゆみ子さんが格子戸をあけ、僕らを招き入れた。
ツナキチが玄関まで出迎えにきてくれたが、クンクンと鼻を鳴らすと座敷にもどり、いつものテーブルの下でからだを丸めた。
なにかを嗅ぎとったのだろうか。僕と再会したよろこびのあまり、うれションした前回とは大違いだった。
ゆみ子さんとテーブルをはさんで向かい合った。老眼鏡をかけたゆみ子さんは、渡された手紙を黙々と読んでいたが、
「犬奥の側室が懐妊……」
その部分だけ聞こえるか聞こえないかの声でつぶやいた。
検査の結果、側室の犬が綱プーの子供を授かっていることが判明した。
それを聞いて、僕は綱プーを失った喪失感を少しだけ埋められた気がしたが、公方様の継承問題でひと悶着ありそうだと心配にもなった。
「そういうわけで、新しい公方様は生まれてくる子供になりました」
狛音の声は緊張していた。僕は当たり散らされるのを覚悟した。
養子縁組の迎えの駕籠をすっぽかされ、うさん臭い理由で延期されたと思ったら、犬奥の側室が亡くなった綱プーの子供を妊娠しており、公方様の世継ぎの話はなくなったというのだから身勝手だった。
ゆみ子さんの握った手紙にしわが走り、僕は思わず身がまえた。
そのとき、ツナキチがムクっと起きあがり、ゆみ子さんのとなりの椅子に飛び乗った。クーンと鳴いて、心配そうに主人を見つめる。ゆみ子さんはツナキチを抱きよせ、そっと頬をあてた。
「世の中うまくいかないものね」
ゆみ子さんは涙を流していた。
「分家とはいえ、伝統と格式を重んじてそれなりの暮らしを守ってきたのに、父が借金を残して逝ってからは食べていくことで精一杯。綱吉様と鮪吉の将来だけがわが家の希望だったのに」
ツナキチが頬をなめて主人の涙をぬぐってあげる。ゆみ子さんはすがりつくようにツナキチを抱きしめ、僕らの前でおいおいと泣いた。
綱プーの病気はゆみ子さんのお百度のせいでなく、人間椅子が陰陽師に依頼したという呪いが原因だった。没落した彼女には神仏にすがるしかなかったのかもしれない。
いつも勝気な彼女の弱々しい姿を見ていると、いたたまれない気持ちになってきた。
ゆみ子さんを許せなかった狛音も、責める気持ちはしぼんだのか、身を寄せあう主人と飼い犬のすがたを少しうらやましそうに見ていた。
「ユウちゃんいる?」
鮪吉くんの部屋をたずねた。狛音がふすま越しに声をかけたが、返事はなかった。ゆっくりふすまを開けると、
「お姉ちゃん、来てくれるのひさしぶりだね」
鮪吉くんはベッドにいて、スイッチに目を落としたまま言った。「みくるって子と仲良しなんでしょ。ぼくのこと忘れちゃった?」
綱プーの葬儀のとき、円香さんの娘のみくるを家族として迎え入れたと分犬守に紹介していた。
「忘れてなんかないよ。公方様のこととかいろいろあって来れなかっただけ」
狛音があわてて説明すると、
「そっか……。ごめんなさい」
鮪吉くんはやっと顔をあげた。「お兄ちゃんはなんで来たの?」
すこしイラっとした。
「お姉ちゃんの付き添い」
首輪の回収にきたことは内緒だった。側室の妊娠を知らせる久作さんの手紙を届けにきたことを伝えると、
「綱吉様、もう公方様になれないんだ……」
子供ながらに理解しているのか、鮪吉くんの声はかなしげだった。狛音はじゅうたんに膝をつくと、
「ママ、落ちこんでたから、ユウちゃんが支えてあげて」
「うん、わかった」
力強くマッシュルームカットの前髪がゆれた。甘ったれているようで、意外と芯は強そうだ。
インベーダーゲームの上は相変わらず物置のようだった。無造作に置かれた算数セットのまわりには、インベーダーのように綿ぼこりが潜んでいる。
鮪吉くんがスイッチにもどると、狛音はポケットからカギを取り出し、ゲーム機から料金箱を引っぱり出した。
「あれ?〝夢丸の首輪〟がない!?」
狛音が声をあげた。料金箱のなかには、知らないビーズ織りの首輪が納まっていた。彼女が手にとると、首輪にはビーズで「YUMEMARO」と文字が織りこんである。鮪吉くんがゲームの手をとめ、
「お姉ちゃんちの家宝の首輪がなくなったって聞いたから、お姉ちゃんの誕生日にプレゼントしようと思って、ぼくがビーズでつくったんだ」
〝夢丸の首輪〟のかわりなら「YUMEMARU」だが。これでは〝夢麿の首輪〟になってしまう。
「ママ、お姉ちゃんちの首輪を嫌ってるから、プレゼントの首輪も隠しといたんだ」
「ユウちゃん、LINEで〈はやくゲームしたいからカギ返して〉って言わなかった?」
狛音が重い前髪の下の目をのぞきこむ。「カギもってたんだ」
「じつはスペアキーがあって」
「スペアキー?」
「……うん。お姉ちゃんにカギ貸したら、動物園に連れてってくれたから、カギはひとつしかないことにして、スイッチまでおねだりしちゃった……ごめんなさい」
鮪吉くんは泣きそうな顔で、スイッチを没収されないように抱きしめた。
「スペアキーが使えないのはほんとだよ。ママがもってて、カギがないってバレたら怒られちゃうから。でも、お兄ちゃんがママからカギをもらって来てくれて」
スイッチをやらせてくれなかったのは、僕を利用してカギを手に入れるためだったのか。誘拐の件にしろ、今回のことにしろ、悪知恵の働くガキである。
「スイッチ、取んないよ。あたしが勝手に隠してたのが悪いんだし」
狛音はインベーダーのカギを鮪吉くんに返す。「箱に入ってた〝夢丸の首輪〟はどうしたの?」
「人間椅子さんにこっそり渡した」
「人間椅子さんに?」
僕は思わず声が裏返った。
「うん。お兄ちゃんと一緒にきたとき」
ゆみ子さんの相談話が長引きそうだったので、僕は先に帰ったが、そのあとの話だろうか。
「人間椅子が持ってたんなら、なんで教えてくれなかったんだろう?」
狛音は首をひねると、鮪吉くんお手製の〝夢麿の首輪〟をポケットに仕舞った。
「本物が見つかったら、僕の首輪いらないんでしょ」
鮪吉くんがさびしそうに言うと、狛音は彼の目をまっすぐ見て、
「そんなことないよ。誕生日はまだだけど、首輪は大事にする。ありがとね、ユウちゃん」
妙にこまっしゃくれているので忘れそうになるが、まだ鮪吉くんは小さな子供なのだ。狛音やゆみ子さんを思う気持ちは、子供らしい純真なものに思えた。
スペルの間違いは黙っておくことにしよう。
2
夜になっても、屋敷に人間椅子のすがたは見当たらなかった。お手伝いさんに訊いてみたが、行方はわからないという。みくるがいる狛音の部屋には行きづらかったので、
〈人間椅子さん、帰ってこないね〉
自分の部屋からLINEを送った。
〈首輪、うちに置いてあるのかな?〉
すぐに狛音から返信があった。綱吉廟で見かけた空箱のことを思い出し、
〈公方様の剥製が並べてあった部屋に、首輪を入れる箱みたいなのがあったよ。そこにあるかも〉
〈公方様の剥製?〉
歴代の公方様の剥製を祭る綱吉廟の習わしと、工房さんはその剥製をつくるために雇われていること、なぜか綱吉廟のなかに和犬の剥製が並んでいることを説明した。
既読はついたが、それきり返事がかえってこなくなる。狛音はショックを受けたのかもしれない。よそ者の僕ですらそうだったのだから、彼女のショックの度合いはなおさらだろう。
待つのをあきらめてユーチューブを観ていると、LINEの通知がきた。
〈もう一回、あの部屋行ってみる?〉
狛音は生あくびをくり返していた。綱吉廟へむかう彼女の足どりは重く、鉄球でも引きずっているみたいだった。
奇怪な習わしのことを知ってなお、綱吉廟に行こうとしているのは、家を継ぐ覚悟をきめたからだろうか。狛音の背中を押す犬彦くんの幻影を見たような気がした。
相変わらず廊下の照明は切れていた。手探りでドアノブを握ったが、鍵はかかっていなかった。
ドアを開けると、おろしていたほうの腕をつかまれた。幽霊のように手は冷たかったが、腕をつかんでいたのは狛音の手だった。部屋のなかを見た彼女の顔は嫌悪感にゆがんでいた。
暗い部屋のなかに、ピチャピチャと唾液の音がひびいている。
足を踏み入れると、2本の蝋燭に火が灯してあり、ひざまずいた男がプードルの剥製の目に舌をはわせているのがぼんやりと見えた。知っている男の影だった。
「人間椅子さんが〝夢丸の首輪〟を持っていたようです。どこにいるか工房さんは知りませんか?」
ドキドキしながら声をかけると、うっとりとした表情の工房さんがふり返った。
「安部公房の『人魚伝』という小説を知ってるかい? 緑色の人魚に心うばわれた男の話だが、主人公が人魚の眼球に口づけして涙をすするのが妙にエロティックなんだ」
ガラス玉の眼球から引いた糸が光った。工房さんは部屋の奥のほうを見て、
「あの箱を見にきたんだろう? あいにく箱はからっぽのままさ。〝夢丸の首輪〟は人間椅子さんが燃やしたそうだ。犬守家の因習を終わらせるとかでね」
綱プーのお墓のそばにあった焚火のあとを思い出した。夜風に灰が舞っていた。綱プーに手をかけた人間椅子ならやりかねないことだった。今のいままで気づかなかった。
ふうっと、狛音が深い息をつくのが背中から聞こえた。カチッと音がして、たちまち部屋が明るくなる。彼女が電気をつけたようだ。
蛍光灯の下、前後2段に並べられた歴代の公方様の剥製が照らし出されていた。端から目でかぞえてみると、柴犬の剥製が13体、プードルの剥製が10体置いてあった。
「なぜ柴犬の剥製が祭ってあるんですか? 工房さんも剥製をつくったんですよね」
「暢くん、綱吉廟の習わしのことを知ってるようだね。そう、俺は剥製師。誰から聞いたか知らないが、それも店じまいだよ。ご存知のとおり、公方様の遺体は土のなかさ」
手前にある最新のものとおぼしきプードルの剥製は、57世の公方様だろうか。そこで剥製はとぎれていた。明治時代から続いてきたしきたりにも変化があったようだ。
「剥製はじつに美しい。ありし日の姿をとどめたまま、一瞬を永遠に生きつづける存在だ」
工房さんはニヤリと笑い、また剥製の眼球をひとなめした。「そしてこのとおり、どんな猛獣も人形同然となる。みんな俺の恋人だよ」
「だから、なんで公方様が途中まで柴犬なわけ? さっさと答えてよ、ヘンタイ!」
苦虫を噛みつぶしたような顔で狛音が叫ぶと、
「狛音ちゃんの涙は人魚みたいに、ひりひりした刺激的な味なんだろうな」
工房さんが舌なめずりをした。おえっと、狛音はえずいた。
「公方様の剥製の仕事もなくなったし、家伝はもうじき完成する。俺はお払い箱だろうから、本当のことを教えてあげよう」
工房さんは立ちあがり、歴代の公方様の剥製の前をゆっくりと歩いた。
「綱吉公がオランダ商館長の飼っていたプードルの子供に生まれ変わったという伝説のことは、いぜん話しただろう?」
「犬なのに綱吉公の元側用人に漢文を詠んだとか」
「あれはフィクション、俺がつくった偽の歴史なんだ。むかし小説の習作でずいぶん書いたが、実在の旧家の偽史を書くことになるとは思わなかった。ご当主に頼まれた、れっきとした仕事だよ」
「パパ、歴史まで捏造して犬守家の伝統にこだわってたの? 300年の公方様の伝統とかバカみたい。そのせいで犬彦は自殺したのに」
狛音はあきれ返ったように言ったが、その目はかなしみに沈んでいた。
「狛音ちゃん、それは早合点だ。公方様が綱吉公の生まれ変わりの犬の子孫だという伝説の真偽は知らないよ。生まれ変わりとされる犬が大蛇から先祖を救った記録は残っている。
あくまで俺が創作したのは、オランダ商館長の死んだプードルの子供に生まれ変わったという部分だけだ。まさか現実に、犬奥の牝犬が公方様の忘れ形見を授かることになるとは思わなかったが」
「それが公方様の剥製の半分が柴犬なのと関係あるんですね」
「ご名答だ、暢くん」
工房さんはあるプードルの剥製の前で足をとめた。そこが柴犬とプードルの境目になっている。
剥製の前に置かれた小さな机のわきには立て札があったが、ここからでは字が小さくて読めなかった。
「この『四十八世公』と書かれたプードルが、太平洋戦争末期から戦後にかけて生きたとされる公方様だ。なぜここからプードルに変わっているかというと、本物の48世公は柴犬であり、戦争中に殺されてしまったからだ」
「プードル以降の公方様は偽物なんですね」
綱プーも含めて、戦後70年の公方様はすべて偽物の血統だったということだ。
だから、綱吉公がプードルの子供に生まれ変わったという歴史を創作しなければならなかった。久作さんが工房さんに家伝をつくらせるわけだ。
「そうなの?」
狛音があらためて問うと、工房さんは首を縦にふった。
「戦争中、民間のシェパードなどの飼い犬が軍用犬として献納されていた。出征のときには紅白のたすきをかけられ、盛大に戦地に送り出されたそうだ」
工房さんは一歩進み、柴犬の公方様の頭をなでた。
「やがて、柴犬なんかも対象とした献納運動がはじまる。これは兵隊の防寒用の毛皮を調達するためで、戦争末期に軍需省から通達が出されると本格化していった。通達は一般家庭にも飼い犬を供出しろというものだった。
まもなく犬守家に公方様を警察署に連れてくるよう回覧板がまわってくる。飼い犬は登録制であり、警察に名簿があるので逃れることはできなかった。
官憲に工作を試みるなど手をつくしたが、名門の犬守家でも例外扱いとはならなかった。公方様は地元では知られた存在で、名家であればこそ模範的な行動を求められた。
当時、国民学校……いまの小学校1年生だった先代は、最後の晩餐として、泣きながら公方様に白米と鰯をたらふく食べさせたそうだ。
一家総出で警察署まで送り届けると、公方様は檻に入れられた。犬たちが悲鳴をあげるなか、一様に青ざめた飼い主たちが檻に背をむけて帰っていく。供出された犬は丸太で殴り殺された。犬守家はかなしみに暮れ、先代は毎晩泣き明かした。
いっぽうで、分家の綱吉様は山奥に隠されて逃げおおせたらしい。本家の嫌がらせで公的に存在を認められなかったことが功を奏したようだ」
「ひどい、殴り殺されるなんて……」
狛音は両腕で自分のからだを抱いてふるえている。小次郎が丸太で殴り殺されるのを想像したら、僕もたまらなかった。
「殺害の現場は血に染まって凄惨をきわめた。あちこちに死体が転がっており、犬たちは立ちこめる血のにおいに半狂乱で抵抗したという。殺された犬はすぐに皮を剥がされ、毛皮は傷まないよう塩漬けにされた」
ニタニタしながら工房さんがつけ加えた。殺気を帯びた目で狛音がにらむと、
「話をもどそう。なぜ公方様がプードルになったかだ」
工房さんは咳払いして話をつづけた。「館林を襲った昭和20年の空襲により、本家のお屋敷は全焼してしまう。バラックで途方に暮れているうちに、一家は終戦を迎えた。
終戦直後は進駐軍に食いこみ、米軍物資を横流ししてもらって口を糊したとされる。このへんは黒歴史なのか闇に包まれている」
「ヤミ市ってやつですか?」
「暢くん、よく知ってるな。横流し品を売って大金を手にしたヤミ成金も少なくなかったが、犬守家の人々も衣食には事足りたようだ。
だが、江戸時代からの伝統である公方様をうばわれ、失意のどん底にあった。
そんなおり、進駐軍の兵士からプードルを譲り受けた。愛犬家のマッカーサーの意向により、B-29で大量のペット犬が持ちこまれていたんだ。
一家は慰みものとして、このプードルを新しい公方様にすえることにした。
戦後の混乱期を抜けると、しだいに日本でもペットを飼うような余裕が生まれ、犬の輸入が再開された。
犬守家は占領時代のツテを頼りに、アメリカ産のドッグフードを輸入販売していたが、このころ大黒柱である先々代が日本脳炎で亡くなってしまう。先代は父の事業を引き継ぎ、若くして一家を支えることになった。
先代はラッキーロープ社の前身である『綱吉商会』を設立し、高度成長期にペット用品の製造販売で財をなした。そして館林の地に念願だった現在のお屋敷を建てた。
いぜんのお屋敷にあった公方様の銅像は、戦争中に軍に徴収されてしまったが、新築を機に2代目の銅像を建立し、そのさい柴犬からプードルに像の犬種をすり替えたわけだ」
「待ってください」
ひとまず久兵衛さんの遺言の「アメリカのプードルが原因」の意味はわかったが、不審に思って口をはさんだ。
「そんなあからさまに、公方様がプードルに変わったら、分犬守が黙ってるはずないですよ。分犬守の綱吉様が生きてるならなおさら」
「それが運よく柴犬時代を知っている者が残っていなかったんだ。ゆみ子夫人の父親、つまり分犬守の先代は戦後生まれで知るよしもない。
先々代は身ごもった妻をおいて出征し、南方で戦死したとされる。その妻も先代が幼いころ栄養失調で亡くなってしまった。
両親とも失った先代は女中に育てられたが、そのじつ生活費は本家から提供されていたらしい。女中が口を割るはずもない」
「公方様は地元で有名だったんですよね? 隠せっこないですよ」
「地元の人々も空襲や戦後の混乱で散りぢりになったし、そうでない場合も犬守家の財力の前に口をつぐんだ。柴犬の公方様はいつしか忘れ去られ、まんまと履歴の隠蔽に成功することになった」
「まるで見てきたみたいにしゃべりますね」
「すべて『久兵衛翁日記』に克明に記録してある。当代が俺を雇って歴史の改竄に乗り出したわけさ」
「これは犬彦の位牌?」
狛音のこわばった声が聞こえてきた。部屋の奥に目をむけると、小さな祭壇があり、いつのまにか彼女がその前に立っていた。
いぜんこの部屋をのぞき見したとき、久作さんは位牌にむかって号泣していたようだ。
「そう、位牌は犬彦くんのものだ。その前に置いてある桐の箱に〝夢丸の首輪〟は納まっていた」
紫の光沢ある布が敷かれた箱がうつろな顔を天井に向けていた。狛音は箱をじっと見下ろしているが、どこかさびしそうな目をしていた。
犬彦くんから託された首輪が永遠に失われたと知って、彼女はなにを思ったのだろう? 工房さんは歪んだ笑みを浮かべ、
「アメリカからもらったプードルを由緒ある公方様の血筋と偽った先代も先代だが、後妻の連れ子の娘を亡くなった総領息子と偽った当代も当代だ。詐欺師の血は争えないね。
偽物の公方様と偽物の長男にすがってまで守ろうとする家の伝統ってなんだろうな。綱吉公に由来する300年の伝統だとか、とんだお笑い草だよ」
工房さんの嘲笑が綱吉廟にこだました。
空虚な伝統を背負わされたプードルが、ガラス玉の瞳で虚空を見つめている。いつのまにか蝋燭の火は消えており、犬守家の欺瞞を煮詰めたような部屋を、蛍光灯の実直な光がさらけ出していた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

