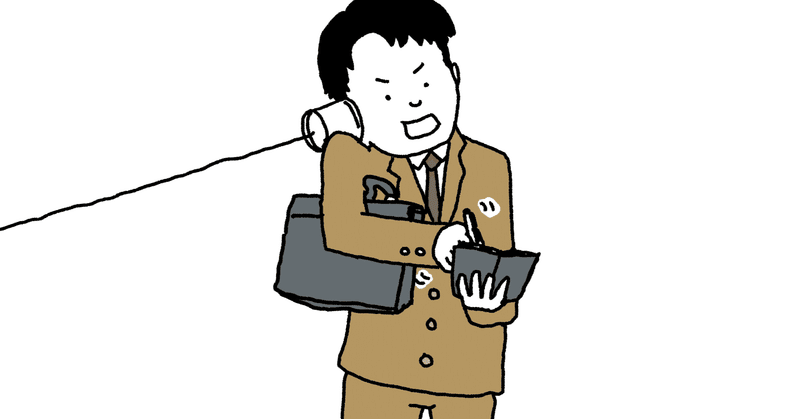
【セミナー要約】採用と人員定着に困っていたら相談しよう、そうしよう。あともっと知りたいことがある。
はい、みなさんこんにちは!
セミナー要約のお時間ですよ。
今回のセミナーは、toretaさん主催のこちら!
【飲食店経営者のための
採用×定着テクニック】
2024年5月28日 14:00~15:00
3社が順番に、採用と定着という、「人回り」のテクニックを教えてくれる。
①採用 →アルバイトタイムスさん
②定着 →トレタさん
③定着 →MSコンサルティングさん
セミナーは上記の順番であったが、要約は①、③、②の順番で書いています。
本当に自店舗も人がいなくて、ほぼ毎日タイミーさん頼りだよ、、、。
(そしてタイミーさん経由で2人採用したよ)
人員不足の店舗様において、少しでもお役に立てれば幸いです!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
①採用
株式会社アルバイトタイムス
営業企画課 課長
小堤 慎介(おづつみ しんすけ)さん
求職者に選ばれる飲食店になるには?
・中・長期軸での採用活動
・訴求点の整理・言語化
・詳述性の高い求人作成
求人原稿を仕事を探している方に刺さるようにちゃんと書こうね。
という話ではあるのだけれど、まず、
「求人原稿はお店の魅力を伝えて、ぜひ働いてください」というメッセージなんだ。
それを誰に何を伝えて、どのように伝わるようにするか、を整理整頓してくれる。
そして、実際の事例を参考にしながら、求人票のどこがポイントなのか、
表現方法をこう変えたら、応募数もこう変わった。というテクニックを教えてくれる。
(店舗事例では、店舗名も出てきている為、どこまでセミナー内容を言っていいか分からないので、ふんわりしていて恐縮です)
一番いいな〜、と思ったのは、「中・長期軸での採用活動」の説明。
仕事を探す人の意識の変化、そして3ヶ月〜5ヶ月かけて採用活動を行った、店舗事例。
そして、それに見合うような求人の価格設定!!(月額3~4万)
さらには、大事な求人原稿の作成&運用をお任せできる。これホント助かる!
人がいないから求人を出すのであって、毎日の営業でいっぱいいっぱいの中、最初の原稿提出はともかく、「運用」ってなかなか難しい。
1ヵ月経過後、反応が思わしく無かったら、原稿の内容を修正してみる。
というのがセオリーなのだが、そこまで手が回らないのが実態。
それをお任せできて、月額3〜4万って、分かってるね〜!!って感じで感動してしまった。
リアルに相談しようとしています。(ちなみに社員求人も出来るのかしら、、、おいくら万円ですか?)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
②のtoretaさんは後述!!
③の定着の話
株式会社MS&Consulting
執行役員
リレーション事業本部 本部長
相崎 哲史(あいざき てつし)さん
いわいる「MS=ミステリーショッパー」を使った顧客満足度調査をしている会社さん。
約20分間の中で、話詰め込み過ぎ。
でも、約20分間、うなずきっぱなし。首がもげるくらいうなずいた。
簡単にまとめてしまうと、
「定着率を高めるには、従業員エンゲージメントを高めること。
飲食店でのスタッフのエンゲージメントで鉄板は、
”お客様から喜ばれている実感”を感じてもらうこと。
その為にはこれをやる!やることはお店のレベル感によって違う。
店舗事例はこれとこれとこれ!以上!やってみてね!あと相談にものるからね!」
です。
(倍速再生じゃないのに、倍速に感じたぜ、、、)
”定着”の観点から言うと、スタッフがやりがいを持って働いている状態が続けば、そりゃ辞めないよね。という至極当たり前のことに思えるけど、
それをデータ検証して表やグラフ・数字で根拠を示してもらえるので、
もう、うなずくしかない。説得力すごい。
大事なのは、「自店舗の現在地を知ること」かな、と思った。
客観性を持って、自店舗が従業員エンゲージメントのレベルで、どの程度なのか。
いまココ、が分からないと目的地が分かっていても、徒歩でいいのか新幹線なのか、船や飛行機を使わないといけないのか、が分からない。
(これ、とある本の受け売りだけど~。とても参考になる視点だと思いました。)
そして、これが「アドバイスをもらう」価値なんだよね。
それに価値が無いと「コンサルタント」ってお金貰えないもんね、さすがだな〜。
(嫌味とかではない。本当にすごいよな~、、、これが今のところ自分には無いから、コンサルタントって名乗るのやめたのよ)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そして②の定着
株式会社トレタ
トレタO/X セールス&マーケティング部 COO室
石塚 智浩 (いしづか ともひろ)さん
なんか、今回聞いて違和感を持った。
“定着”の観点から、「人員不足で忙しすぎてお店が回らず、サービスまで手が届かなくて、スタッフがストレスを受け続けると辞めてしまう。それをDXで改善してスタッフのストレスを軽減し、ちゃんとサービスを出来るお店にして定着させましょう」
という話なんだけど、なぜか「そうか?」と思ってしまった。
この「そうか?」と思ってしまう違和感の正体はどこなんだろう??
今回はそれを考えてみたい。
(以降、丁寧語語尾と言い切り型語尾が混在し、文章としての座りが統一されない感じになりますがスルーの程お願いいたします。トレタさんも読んでるかも、と思ったらトンマナおかしくなっちゃった😅)
本当にそれでスタッフのストレスが減るのか
スタッフの「忙しくてお店が回っていなくてストレス」は、「波」=お客様に「すみません」と呼ばれるときに、やることが発生する「同期型コミュニケーション」
その「同期型コミュニケーション」をDXによって「非同期型に変更」し、店舗の「波」を平準化させましょう。
(「同期型」「非同期型」の詳細は↓こちら参照↓)
これは、最近toretaさんのセミナーでよく聞く話。
自身も3回くらい聞いている。
なんか、違和感があった。
今回、私自身がいま働いている店舗も人員・人材不足。
その改善の為、なにか出来ることを持って帰ろう、と思ってセミナーを聞いている。
アルバイトタイムスさんは、実際相談して求人出してもらおう、と思った。
MSコンサルティングさんは、決裁者を説得できれば、従業員アンケートやってみたいな、と思った。
toretaさんのモバイルオーダーは、実際いまの店舗で導入しても、「非同期型にはならんな」と思ってしまったんだ。
なぜか?
うちのお店ではそれにより、さらにホールの手間が増える未来が見えた。
(「う〜ん、携帯出すの?めんどくさいなぁ。ちょっとちょっとこれとこれちょうだい!」
「これのやり方、よく分からないんだけど、どうすればいいの?」)
さらにお会計においても、お客様対応、ご要望がある。(個別会計がいいな、領収書の宛名の要望、領収書を複数枚用意して欲しいんだけどetc…)
で、結局なにかしらの同期型対応が生じる。
非同期にならんぞ。
こういうDX導入では、従業員の教育はもちろん、お客様へも導入の理解や、慣れるまでのサポートなどのイメージが、導入店舗側に見えてこないと、
導入のメリットよりもボトルネックがいっぱい浮かんできて、
導入しない理由が強くなってしまう。
また、
・店舗でホールが何人体制で行っているか。
・席数は何席か。
・1人が何組に対応する想定か。
などによっても導入メリットの事情が変わってくる。
→1人だったら、いっぱい料理やドリンクのオーダーが入っちゃったら、作る人&運ぶ人が1人だから結局ドリンク作れなくてクレームになったり、運べなくて料理が冷めるよ。
→→2人だったら、いっぱいオーダーが入っても、対応できるのか?2人で対応できる最大値・席数、客数ってどれくらい?スタッフのストレスっていう視点だったら、ストレスは変わらなくない?
→→3人だったら1人はサービス(顧客満足度向上)担当、2人はランナー的な業務担当(残りの料理提供、バッシング)で出来るのか?
→→出来るとしたら、顧客満足度向上の対応って何をするのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これは、導入によって効率化、効果が出る店舗もあるんだろう。
ただ、現在の自分が勤めているお店で導入された想像をすると、こうなる。
飲食店と一括りに言っても、業態・客単価・利用するお客様の目的・お客様の層、によって利用方法が異なり、スタッフの人数も席数や入店数によって決まっているわけではない。お店のやることによって、サービスの人数は異なってくる。
つまりは、「同期型を非同期型に変更する」という説明では、
ざっくりしすぎている。
ということなのではないでしょうか。
「オーダー」という店舗オペレーションの中の1つにがっつり入り込むサービスだからこそ、個々の店舗の規模や席数、スタッフの配置など、各店のオペレーションを深掘りして入り込む内容でないと、導入メリットもイメージも沸いてこなかった。
toretaさんの今回の説明では、「うちには合わないから関係ないな」というDX排除な店舗が出てきてしまう気がした。
それは、とてももったいない。
事例が、人件費や時間の削減だけではなく、どういった規模のお店で、どういう活用をされていて、オーダーテイクをしない分、オペレーションがこう変わった...…というのが見えてくると、また違った印象だったかもしれない。
そして、toretaさんのDXの価値って、「同期型を非同期型に変更する」ことにあるのでしょうか?
これからの価値を創る
飲食店の経営は「波との戦い」なのではなく、
サービスの本質が、「同期型=サービスの提供と消費が同時に起こる」ことなのではないでしょうか?
本質だとしたら、それを無くすことはできない。極力波の高低をなだらかにしていく、というのは理解できる。ただ、ことモバイルオーダーの本質は「波の高低をなだらかにしていく」ことなのでしょうか。
モバイルオーダーの本質は、効率化だけではなく、
「人が行うよりも顧客満足度向上に貢献できる、DXの得意分野がある」
というダイナミズムなのではないでしょうか?
これだけ、動画になれた人々に、シズル感ある料理動画が、
オーダー時に訴求できる。
それに合ったドリンクのおススメができる。
注文履歴からお客様の好みに合わせておススメできる。
今までは顔見知りになって、熟練度があるスタッフしか出来なかったことが、モバイルオーダーがあれば出来るようになる。
もちろん、オーナーだけのお店で、毎日店頭に立っている人が同じ、、、
というお店だったら必要ないかもしれない。
ただ、これからの時代、超がつく人材不足がやってくる
という文脈にあって、
オーダーテイクする時間が無くなる代わりに、ドリンクを作ったり料理提供をしたり、というまだまだ人に替わる方法がない領域を担当する。
それでもドリンク・料理提供時にお客様とコミュニケーションを取る方法を考えよう!という接客サービスの変容や、
それ以外にも、人材不足解決策としてタイミーを代表する「1日だけアルバイト」で運営せざるを得ない店舗があったとしても、オーダーテイクにおいての「顧客体験・顧客満足度」は変わらず維持しますよ。
経営者の望む「人と人とのコミュニケーション」では無くなるかもしれないけど、また違った形の「顧客満足度」を創出しますよ。
、、、というのが、DXの価値なのではないでしょうか。
定着の観点からも、顧客満足度の観点からも
トレタさんがそう言っていたならゴメン。
それを受け取れなかった自分の理解力不足。
ただ、「飲食店の人員不足」はもう待ったなしのフェーズに入っている。
「営業時間の短縮」や「入店の制限」のフェーズだ。
無理やり入店してもらったとしても、「すみません」と呼ばれたって対応することが出来ないレベルの人手不足。顧客満足度だだ下がりの未来が目に見えているので、入店を制限する。
今いるスタッフの人数・出来ることに合わせて対応できる人数しか入れない。入れられない。
だから猫の手も借りたいし、どんなやり方でも「平常運転」したいのだ。
だから、人が1人いなくてもDXで「平常運転できますよ」と思いたいのだ。
さらには、DXだけが創ることができる価値がありますよ、と言って欲しいのだ。
よく言われることだが、人手不足は今に始まったことではない。
恥ずかしげもなく言うけど、12年前の店長時代、満席のフリをして新規のお客様を断っていたことがある。(思い出したくもない12月25日、、、)
これは分かり切った繁忙期にシフトが集められないダメ店長の例だけど。
ただ、今がより深刻なのは「所属人数」レベルで人員不足だ、ということ。
市場レベルで、飲食業界に限らず人員不足だということ。
他業界と人の奪い合いをしなきゃいけない。
差がつけられるとするのなら、他業界より働くのが魅力的だね!と
思ってもらうこと。
それを実現するには、”発信力”と”本当に魅力的な現場”を作ること。
12年前と今が違うのは、やっぱり「テクノロジーの進歩」だと思うのだ。
”本当に魅力的な現場”を作るために、DXはなくてはならない、
と考えています。
だから、自分達もDXのことを知りたいと思っている。
そして、本当に活用するためにはどうすればいいのか、
を本気で考えているんだ。
なので今回、書いたことは全然批判とかではない。
ただ感じたことを書いた。
どう思うのか、toretaさんにも聞いてみたい。
他の店舗の方にも。
DXを過信しすぎなのか?それとも、もっと捉え方が違うのか?
もっと知りたい。考えたい。
現場からは以上です!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
