
教室の外という学びのフィールド - BEAU LABO 7期 ディレクター紹介 vol.02 谷保 梓樹- Inside BEAU Op.103
初めまして!今回の7期、学生パートナーとして関わらせていただくことになりました、谷保梓樹(たにほ・あずき)です。よろしくお願いします。
僕は高校、大学と硬式野球部に所属して活動している傍ら、大学では「農業×地域おこしでむらの未来を創る」をコンセプトに活動している、むら塾というサークルにも所属しています。
むら塾では現在、福島県飯舘村を舞台としたプロジェクトと大学生を対象とした地域密着型のプランコンテストむらコン2022の企画に深く関わっています。

むら塾でも活動をしているのは僕が中学生の頃から地方都市、地方農村のまちづくりや地域活性化事業に興味を持っているからです。
高校時代にもそんな興味の追求にかけた時間がかなりあります。今回のnoteではそのことに触れつつ今回のBEAU LABO7期に臨むにあたっての僕自身の決意表明をしていきたいと思います。

僕は高校時代に学校のあった市内の主要駅(主要と言っても全国単位で見れば田舎の小さな駅に過ぎないのですが…)とその駅前通りの商店街を舞台にした、活性化イベントを2回、中心になって企画、運営しました。
イベント企画をすることになった経緯は長くなってしまうので今回は省かせていただきますが、ざっくりいうと、元々は大型ショッピングセンターの出店が検討されていたことを踏まえて市にまちづくり計画案を提出しようとしたものの挫折し、計画案を考えていた時の目標「地域をより魅力的な場所にする」を実現するための、別方面からのアプローチはないかと検討した結果、活性化イベントを主催することになったということになります。
6人ほどのチームを作って、僕が代表として進めていったのですが、ゼロから作っていく初めての取り組みだったため、うまくいくかどうかは誰にもわからず、大変なことは多々ありました。
イベントの目的、コンセプト、対象者、内容の検討、イベント会場の確保、会場管理者や市役所の方との調整、広報方法の検討とポスターやチラシのデザイン、印刷と配布、商店街など関係する地域の方への説明と協力の依頼、出演者との調整、機材の貸し借り、当日の準備など何から何まで取り組み、今考えるとよくあんな大変なことやったな…と自分でも思ってしまうほどです。
結果的にイベントはどうだったのかと言いますと、一回目高校2年の11月末ではそれなりの人数の方には来ていただけたものの、活性化イベントとしてイベントの盛り上がりを地元の活性化につなげていくためにはやや不足している感が否めませんでした。
それを踏まえ、ワークショップを開催して市民の方々の生の声も頂きつつ、コンセプトやコンテンツ、広報にかなり改善を加えて迎えた12月末の2回目のイベントでは1回目よりも商店街各店を含む多くの地域の方を巻き込むことができたうえ、運営側の手が回らなくなるほど(手が回らないというのもイベントとしてはまずいので反省点として残ってはしまいましたが…)多くの方に来ていただき、非常に達成感を感じました。

また、高3の8月に行われた地元の小さなコンテストで、僕たちが行ったイベントをまとめたものが特選を受賞した際は、とある地元の方が涙を流して僕たちの取り組みを褒めてくださり、自分たちのやってきたことが僅かであるとは思いますが地域の方々にも影響を与えることができたのだと実感して胸に込み上げてくるものがありました。
僕にとっては好きなこと、楽しいと思うことを追求し続けた結果であったこのイベント運営ですが、その中で学んだことは本当に数え切れないほどありますしその全てが今の自分にとってかけがえのない経験として記憶に残っています。例えばありきたりではありますが答えのない課題にどのようにアプローチしていくのか。
このイベントでずっとテーマであったのが「イベントにいかに多くの人を巻き込んで盛り上げていくか」、そして「いかにイベントの熱狂を商店街の活性化に繋げていくか」の二点です。
僕たちは一つ目については1回目のイベントで、二つ目については2回目のイベントで、段階的に達成していくことを目標に掲げ、ミーティングを重ねました。
現状分析ではできるだけ現場に足を運び、机上の空論にならないようにする、理想を明確にし、現状との差をきちんと捉えたうえでその差を埋めるための具体的なアイデアを出し合う、などの作業を通し、2回目のイベントでは商店街を訪れた人がイベントにも足を運び、イベントを知った人が商店街にも足を運ぶというサイクルを小規模ではありましたが達成できました。
他にも相手に正確に自分の意図を伝えるための言葉選び、簡単なデザイン技術、メールや手紙、依頼におけるマナー、先を見通して行動する力、コミュニケーション能力などを身につけることができました。
こうした学びは日々の学校における教室に座っての授業ではなかなか身につかないことだと思います。

確かにイベント運営は大変で時間も労力もたくさん使いました。しかし、すでに述べた多くの貴重な経験をできた点で、やってよかったなと心から思っています。
僕の周りにも同じように自分の興味を追求した人が多くいました。缶サット甲子園、知の甲子園、まちおこしイベント、サマーラボへの参加、トビタテを使っての留学等々、それらに参加した友達みんながそれぞれ文字通り目を輝かせながら各自の貴重な経験について、たくさん話をしてくれたのを今でも覚えています。高校の時に教室を飛び出しての経験は多くの出会いと刺激と発見と気づきにつながるとても大切なものなのではないか、そんなふうに思いました。

このBEAU LABOもそんな素晴らしい体験ができる場所の一つなのではないでしょうか?僕自身何度かzoomで顔合わせした7期の学生パートナーの方々からすでにたくさんの刺激をもらっていますし、今後一緒にプログラムに取り組んでいくことになる意欲にあふれる高校生との出会いも非常に楽しみです。
今回の7期も学生パートナーとして出会いを大切に、僕自身も関わる全ての人から刺激を受けながら高校生と一緒に学びを深めていきたいと思っています。
「教室を飛び出しての学びはかけがえのない人生の1ページになる」
これが今回の3ヶ月間で検証したい僕の仮説です。
3ヶ月後には活動に関わった全ての高校生にとって、そして僕自身にとってこの言葉が確信に変わるような、そんな充実した時期を一緒に創り上げていきたいと思います。僕にとっても初めての挑戦で、至らない点も多くあるとは思いますが、改めて、どうかよろしくお願いします。
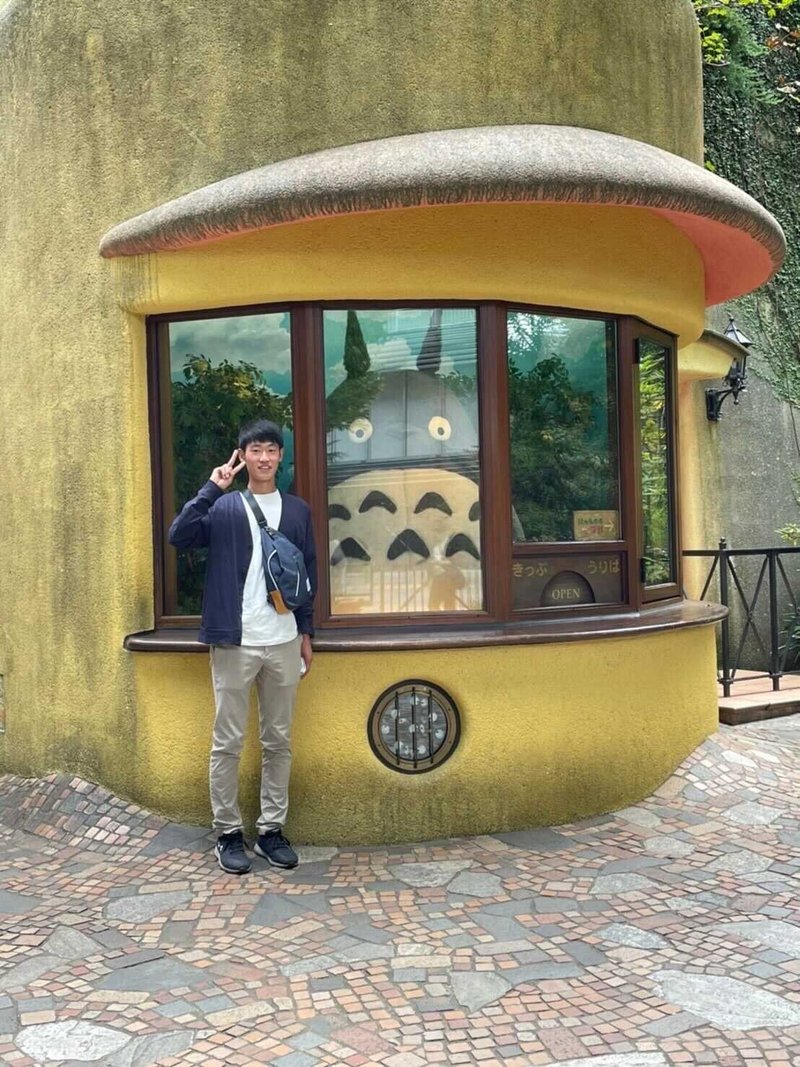
谷保 梓樹(たにほ・あずき)
BEAU LABO 7期 地域経済ラボ ディレクター
東京大学教養学部1年
あなたもBEAUのパートナーとして、地域の教育格差や日本の教育の未来に一緒に取り組んでいきませんか?
