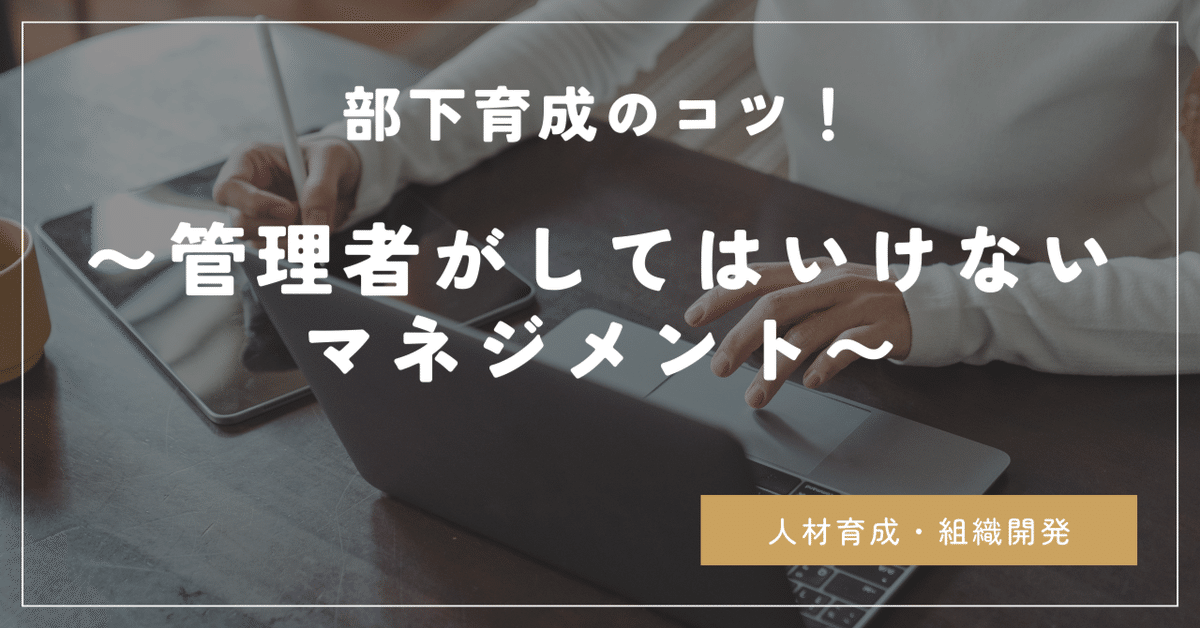
部下育成のコツ!〜管理者がしてはいけないマネジメント〜
多くの管理職の方は、自分に部下が出来た時に「部下に成長してほしいな。仕事でも成果を出して、自分に自信をつけてほしい」そんな風に思うものではないでしょうか?そして、その想いが強くて「失敗させないように」と先に手を回したり、すべてにおいてやり方や指示をだしてはいないでしょうか?そうであれば、一度考えてほしいのです。それは、部下の成長を妨げている要因であるかもしれないことを!
今回は部下に成長してほしいなら、”してはいけない部下育成のコツ”について書きます。
■なにからなにまで教えていませんか?
「部下には、早めに声をかけて軌道修正をする」「こまめな指導が部下を成長させる」「丁寧に時間をかけて、寄り添って指導すればそれだけ部下の成長は早い」という意見を聞くことがあります。
確かに、手取り足取り、ひとつひとつ何をするにも教えれば、失敗もしないでしょうし、目先の小さな結果は出せるようになるかもしれません。しかしそれは一時的なことです。成長と思えた変化は長く続かず、成長は止まってしまいます。
企業は利益を上げるためにも、効率よく生産性を上げていかなくてはなりません。そのためにも「人材を効率よく成長させたい。」と思うのは当然のことでしょう。無駄な時間はかけられません。しかし、そこが「成長」に必要な経験と時間まで削ってしまっている行為になっていることに、気がつかなければいけません。
「部下が成長しない」「自分で考えようとせず、受け身でいる」と嘆く管理者は多いのですが、
・部下が自分で考える前に「どう動けばいいか」を指示しすぎていませんか?
・部下の行動に常に口出し、過保護な状況になっていませんか?
部下が自分で考え、行動をした上で、結果がだせたのなら、部下にとって自身の大きな喜びになるでしょうし、伴わない場合は、自分の行動に対して「なぜ、できなかったのか?」を考えるようになります。時間もかかるでしょうが、
上司が待てずに、しびれを切らして先に手を出し続ければ、部下は、常に指示を待つことが当たり前になってしまい、自分で判断することも改善することもできない考えない社員、つまり指示待ち社員になってしまいます。
■経過ではなく結果を管理
ではどのように部下を管理していけばいいのでしょうか。
上司は、部下が目標に向かって「行動している経過を管理」しようとすれば、口を出し過ぎてしまいがちです。経験があるので不足している部分が目についてしまうからです。そのため、上司は経過は管理せず結果のみを管理するべきです。
まずは、具体的なゴールを設定をし、決めた日程に報告させます。例えば、営業メンバーであるならば、まず「今週の目標は、訪問件数が20件と売上げ100万円」など具体的な目標を設定し、決められた日時までに”結果が達成できたか”を報告してもらいます。
その際に確認することは
・目標の数値の設定は簡単すぎないか、高すぎてはないか?
(アポを取るための行動、訪問件数、売上げ)
・行動計画の現状、見直し
(行動して結果が出る行動だったか?出なかったらどうすればいいか?トーク、プレゼン資料、課題の聞き取りなど)
経過であっても必ず定量的な目標を定めて結果を求めます。決めただけ
でなく、振り返りを必ず行います。
■行動を改善する内容も結果で報告させる
部下が目標を達成するように行動した結果、目標を達成できればいいのですが、場合によっては、出来ずに終わることもあります。目標に届かず不足している部分があれば、その不足を埋めるために何を改善するかも同時に報告させます。
つまり「出来ませんでした」だけではなく、「次は何が課題であり、それをどうすれば解決できるようになるか?」という改善案を添えて報告をさせることが大切です。
また、結果を出すためにどう改善するのか、その行動の結果どうであったか、自身で考え、行動をするように促し、PDCAを回していくことで工夫するようになり、結果へとつなげていける人材に成長していきます。
■部下の仕事、行動にこと細かく口を出さない
・ひとは自分の選択で動きたいもの
ひとに「しなさい」と言われて、そのまますることを多くの人は好みません。自分で選択し、自分で行動したいものです。また、人からとやかく言われたくなものですね。
よく就学期のお子さんを持つ親と子との会話で言われる例えですが「宿題したの?まだなら、早くしなさい!」とぴしゃりと言う親の前で、こどもが「言われたからやる気なくしたよ。」のを聞いたことがあると思います?実は大人も同じですよね。
・結果に焦点をあてること
もし、上司が部下の仕事に細かく口を出してしまった場合、結果が出なかったときに「なぜ、もっと積極的にアプローチしなかったのか?」「なぜ、違う角度から説明をしなかったのか?」など言ってしまいがちです。
このようなことを言ったところで、部下から返ってくる言葉は「わたしなりにはアプローチはしました」「違う角度でという考えがありませんでした」など、言い訳の言葉を口にするだけで、メリットも生産性もないやり取りです。
それよりも、未来に目を向けることが重要です。上司は部下が目標を達成「できたのか」「できなかったのか」の確認と、「目標達成のために今後どうしていくのか」結果を出すための行動の精度を求めるようにし、次の結果を良いものとするような管理をします。
以上のように、上司が管理すべきは部下の結果です。「どういう行動で結果につなげるか」というプロセスは部下が考えることで、上司が口出しし過ぎては部下の思考を止めてしまいます。
■まとめ
いかがだったでしょうか?もしかしたら、意外なものもあったかもしれませんね?もちろん業務的に必要な知識やスキルを教えることは、必須のことです。しかし、なにからなにまで、手を先に回して教えること、行動を指示することは違います。
「上司がなにからなにまで教えない」「部下の仕事に口を出さず部下に適した目標を設定する」こと、そして「PDCAを回していく」ことで、良い結果の出せる人材に成長していき、本人もその成長を喜び、会社に貢献していく。人材と会社の発展がともに出来るように、管理・育成していくことが上司の役割といえるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
