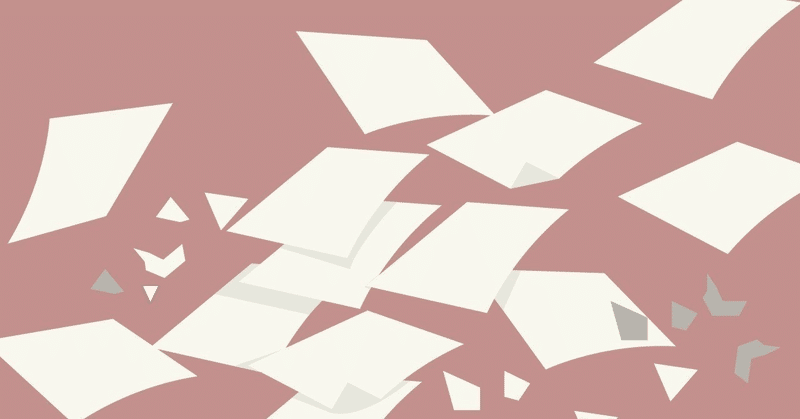
REDD+参照レベル:国際審査の現場から
森林減少が気候変動に及ぼす影響が世界的に認識される中、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)が実施するREDD+(読み方:レッドプラス)の参照レベルの国際審査にて、昨年初めて審査員を務めることができました。あくまでも個人的な見解ながら、この経験から得られた3つの発見を皆さんに共有したいと思います。
REDD+と参照レベルとは?
その前に、REDD+と参照レベルについて簡単におさらいしてみましょう。REDD+とは、UNFCCCの下で合意された、熱帯林の減少によって引き起こされる温室効果ガス排出量を削減するための政策枠組みです。この枠組みに基づき、ここ10年来、国際的に様々な取り組みがなされてきました。そのひとつが、REDD+に参加する国の「参照レベル」の開発とその審査です。
REDD+では、ある途上国が森林保全活動や持続可能な管理によって熱帯林減少を抑止し、何も対処しなければ排出されていたであろう温室効果ガス排出量を減少させた場合、先進国がその減少分に対して支払いを行うことができます。参照レベルとは、この「何も対処しなければ排出されていたであろう」温室効果ガス排出量を指します。参照レベルの設定方法は、UNFCCCの国際交渉によって、ガイダンス[i]が合意されています。
各国の参照レベルは、このガイダンスに従って構築されているかどうか(例えば、過去のトレンドに関するデータが十分に考慮されているかどうか)について、専門家チームが審査します。このプロセスは正式には「締約国から提出された森林参照排出レベル/森林参照レベルに対する技術的アセスメント」と呼ばれています。
発見①:審査の鍵は再現性
参照レベル作成のための国際的なガイダンスには実に様々な要件が含まれています。私たち審査員は、その要件に沿っているかどうかを判断するわけですが、いざ提出物を目にすると、「沿っているとも言えるし沿っていないとも言える」と悩ましく感じることがしばしばありました。何より、途上国による参照レベルの開発は強制ではなく自主的な取り組みなので、そもそも参照レベルを開発しているだけで国際的な取り組みに協力しているという見方もできます。技術的かつ細かい点をどれだけ考慮すべきかについて悩みつつ審査員向けのガイダンスを開いてみると、「審査員が与えられた説明で参照レベルを再構築できるかどうか」が判断上の重要な視点であるとの記述がありました。なるほど、再現性が重要だというわけです。それからは、ほぼ迷うことなく審査を進められました。
発見②:審査の姿勢は対話形式
繰り返しになりますが、途上国によるREDD+の参照レベルの提出は自主的な取り組みです。REDD+に参加することで自国の熱帯林保全策を強化でき、さらに国際的にも温室効果ガス排出量削減に貢献できると考えた国が参加しているとも言えるでしょう。審査員は、ともすれば色々と勝手な指摘をする立場ともなりうるわけです。例えば、途上国の現状を無視してより精緻なモニタリングを要求するなどです。そのようなことを防ぐためには、審査員と対象国の目的は同じという意識を持つことがとても重要です。つまり、審査を受けている国の参照レベルが改善されることで、REDD+を通してその国の熱帯林保全が少しでも前進した結果として地球温暖化対策が進むということを忘れてはなりません。審査は対話形式で進むので、この視点さえずれなければより双方の理解が深まると実感しました。実際、審査は最終審査報告書の完成までに約1年かかるので、両者の関係構築は非常に重要です。
発見③:審査は一発勝負ではない
REDD+は、各国の状況や能力に応じて段階的に取り組みを進められるよう、そもそも衡平性に配慮した仕組みとなっています。ある国で熱帯林減少が抑止できても、他の国で抑止できなければ、単に熱帯林伐採の場所が移るだけだとわかっているため、すべての国で取り組みが進むことが重要と考えられているからです。この段階的な進め方は、参照レベルの開発にも適用されており、REDD+に参加する国は、新たなデータを入手できたときなどに参照レベルを更新することができます。また、審査員からの指摘をもとに審査の途中でも参照レベルを再提出することもできます。この場合、審査員は再提出された参照レベルを審査し直すことになりますが、すでに改善の経緯を理解しているので、この審査は最終確認といった位置づけで進められます。
以上、初めての審査に参加した経験を共有しました。企業のネットゼロへの関心の高まりとともにREDD+の炭素クレジットへの需要も急速に伸びていると聞きます。クレジットが作り出されるその舞台裏について、少しでもお伝えできたなら幸いです。
[i] FCCC/CP/2013/10/Add.1. Guidelines and procedures for the technical assessment of submissions from Parties on proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels
**********************************************************************************
「もっと知りたい世界の森林最前線」では、地球環境戦略研究機関(IGES)研究員が、森林に関わる日本の皆さんに知っていただきたい世界のニュースや論文などを紹介します。(このマガジンの詳細はこちら)。
**********************************************************************************
文責:梅宮 知佐 IGES気候変動とエネルギー/生物多様性と森林領域 リサーチマネージャー(プロフィール)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
