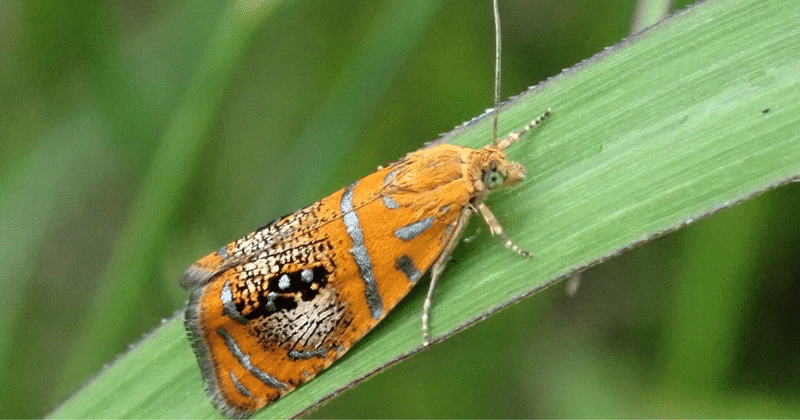2023年1月の記事一覧
微小甲虫の楽園としての「芝生の裏側」―チビミズギワゴミムシとコケシマグソコガネ―
はじめに私が現在居住する賃貸住宅の庭には5 $${\text{m}^2}$$ほどの小さな芝生がある(下写真)。
いくら虫屋でも、こんなつまらなそうな場所でわざわざしゃがみ込んで虫を探そうという発想にはなかなか至らないものであるが、たまたま妻に頼まれた作業を玄関前で行っていたのがきっかけで、この芝生にチビミズギワゴミムシとコケシマグソコガネが生息しているのを発見した。いずれの種も、こんな身近過ぎる