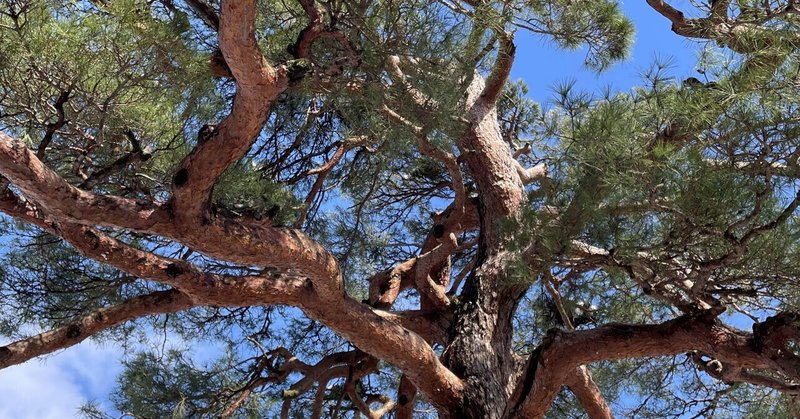
Episode 665 理解の幅が狭いのです。
共稼ぎの私たち…2月最後の日曜日(2/26)は久しぶりにパートナーと休みが合いまして、「何処かへ出かけよう」ってことになったのですよ。
勤務がシフト制のパートナーと、水・日曜日が定休の私、休みが合うのは平均して月に2~3回のこと。
場合によっては月に1回も休みが合う日はないってこともあり得るワケでして、そんな2月は2回…前回は私の実母の確定申告に付き合って終わった感じ。
2人ともフリーでいられる休みは久しぶりだったのですよ。
私の住む地域の冬場の天候は良くないことが多くて、その辺りの兼ね合いもあってか、天気予報の言う「晴れ」と現地在住の庶民の「晴れ」の感覚にズレがあるようです。
私は生まれてこの方ずっとこの地域に本籍があるのですが、イロイロな都合で住み始めたのはひと回りほど前…40歳を過ぎてからのことで、なかなかこの「晴れ」の感覚に馴染めませんでした。
何と言うのでしょうか、雲の面積が空全体の半分以上を占めていても、雨や雪が降っていなくて日差しがあれば、それは「晴れ」と表現される感じでしょうかね。
先日(2月26日)もそんな感じだったのですよ…ご当地的に「晴れ」だから、大きな公園にスノーハイクに行こうってね。
目的地の近くまで行って、ご当地のB級グルメ「洋風カツ丼」に舌鼓を打って、「さて!」というタイミングでまさかの吹雪…。
まぁ…そもそもがご当地的な「晴れ」ですからね、そんなこともあろうかと思って次点を用意してあったのですけどね。
ASDの私には大事なですよ、予定通りに行かなかった時の準備。
コレがあると、「どうしよう…」って慌てなくて済むから。
「次点の準備」が必要な理由は、下線部のリンクから過去記事に飛んでいだだくとしてですね、今回の話題はそんな下準備が上手く行った…というハナシではないのです。
訪れた博物館でイロイロな発見がありましてね。
「新潟県立歴史博物館」は、新潟県に所縁のある歴史的な資料などを展示し、この地域の地誌学的な研究と情報発信に力を入れているようです。
(地誌学とは…という問いについては、立正大学 地域環境科学部 地理学科による学部学科紹介の記事が分かりやすいです。)
特にこの地域については「火焔型土器」と呼ばれる縄文土器が多く出土していることから、縄文文化と暮らしについての展示や、雪深い地域の暮らしの知恵などの展示内容は大変興味深いものなのですよ…私のような「人間の営み」を歴史学的な知恵と文化という観点から読み取ることに面白さを覚えるような人にとってはね。

ガラスケース内の文化財展示とかだけじゃなくて、縄文時代や雪に埋もれた「当時の人々の暮らし」を目に見える形にするにはどうしたら良いか…を、考えたんだろうね。
「実物大ジオラマ」とか、来館者を飽きさせない工夫がたくさんあったよね。
この引用枠内の言葉は、私のものではありません…一緒に行ったパートナーの感想(要約)です。
恐らく、コレが一般的な感想なのだろうと思います。
でも、私は展示されたものを見て、「そう思う」ことが出来なかったのです。
そもそも私は「歴史に絡む地域性の研究」という分野が大好物でして、展示されたものを見てイロイロと想いを巡らせることはできるのです。
当然、小学生くらいの児童も来館者として受け入れる博物館ですから高度な専門性だけで成り立っているワケではありません。
その知っている知識も含めて、新たな発見は今回もあった…でも。
どうやったら楽しんでもらえるのか、どうやったら興味を持ってもらえるのか…という、博物館を運営する学芸員さんたちの視点や苦労という点がね、私には薄いのです。
視点の切り替え…というのでしょうか、子ども連れの家族がそれぞれに展示された「仕掛け」を見ているのですが、ご両親(引率者)はお子さんの楽しんでいる姿を確認しながら…のハズ。
ここには「私が展示物を」という視点と、「子どもたちが展示物を」という視点があって、その先にはどういう仕掛けが子どもたちの興味を引き出すのかという子どもの反応から想像する学芸員さんの努力という視点も存在するのですよね。
私たち以外の来館者の行動を見て、サラリとそんなことを言うパートナーのスゴさに、私は驚くのです。
以前に「長男がツバメの営巣の写真をワザワザ撮ってLINEで送ってくれた件」で、相手を慮る視点のハナシを書いたのですが、どうしても私の視点は単視点になりがちなのです。
だから「私が見た」と「モノ」との一対一の関係しか見えてこないのでしょう。
コレはASD的な「想像力の欠如」と言われてしまう現象のポイントになるエピソードなのかもしれません。
視点切り替えができないということは、こういうことなのでしょう。
あなたの視点から見えてくるものの理解が乏しいことが、私の想像力を限定してしまうということかもしれないと、そんなことを思ったのです。
そうそう、この博物館の展示で「映像を浴びる」という発見もあったのですが、その件についてはまた次回に…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
