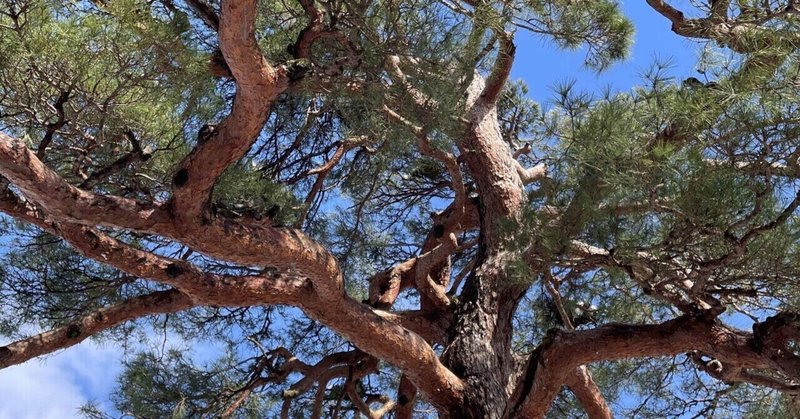
Episode 668 普通が「不通」を招くのです。
「発達障害を持つ人は、クルマの運転ができる(得意か不得意かというニュアンスを含む)のか?」ということは、定期的に話題になることが多くて、「またこの話題が出たね…」などと私は思うことがあるのです。
まぁ…定期的に話題になるということは、それだけ多くの人の関心を引いているワケですよね。
話題の範囲としては、入門編クラスのハナシ…身の回りの「できるできないについて」というカテゴリのものなのでしょう。
このハナシは結局のところ「得意な人もいれば苦手な人もいる」という答えに落ち着くワケでして、強いて言えば発達障害を持つ人の方が得意不得意のムラが大きい分、「運転が苦手か得意か」も、極端に分かれる結果になるのではないか…などと私は思うのです。
そういう私はクルマの運転を苦にしません。
フォークリフトによる荷役作業を生業にしている私は、決して上手だとは言いませんが、道路通行で迷惑になるほどクルマの運転が下手だとは思っていないのです。
私がクルマの免許を取ったのは1989(平成元)年のこと…当時の免許制度にはまだAT限定の免許設定がなくて、クルマの免許を取るにはMT車の操作ができることが必要でした。
クルマの操縦方法の習得という意味で、当時は少なくとも今よりも免許取得の難易度は高かっただろうとは思います。
運転席から見える情報…前方視界に限らず、バックミラーやドアミラー、インパネに映る計器類の情報から必要なものを選択する…は、クルマの運転で必須。
— ዘዐ+(ዘዐፕልነ) (@HOTAS10001) March 5, 2023
ここでなにを選択すべきかの判断が遅れる…なら、恐らくクルマの運転に向いていない。
この傾向がWAISの凸凹が強いことで顕著に現れるとしたら?
この「運転適性」の問題は、運転するクルマ本体の操縦難易度をベースにしながらも、その操縦ができることを前提にして、視覚をメインにした五感から得た空間認知情報を駆使した適切な判断で、「安全に」クルマを動かせるのか…ということなワケです。
私は私の運転免許取得当時の免許区分によって、車両総重量8㌧(4tトラッククラス)までの車両を運転することが可能ですが、流石に今すぐには4t車格のクルマの運転には手がでない…それは「そのサイズのクルマの挙動把握に自信がない」ということです。
「運転適性」があるのなら、練習による車体感覚の習得で運転が可能でしょうけれど、適性が弱いとなると、練習や訓練で安全に運転できるレベルの運転技術が習得できる…とは思えない、そういうことです。
このハナシはあくまでも空間認知をベースにした物理的な「見る」と「判断」のハナシです。
その一方で、この空間認知と関連する判断を求める「見る」とは別に、ものごとを心情的に理解する「見る」が存在するワケですね。
それがここのところ話題にしている映像のハナシになるワケですが…。
私はこれほど「良く見える眼」を持ちながら、「全く気が付かない視点」を同時に抱えます。
そして「全く気が付かない視点」の存在には、なかなか気が付かなかったし、「気が付かない」ということに気が付いてからも、気付きの改善は難しいのです。
なぜ気が付かないことに気が付かないのか?
その理由は極めて単純で、「全く気が付かない視点」が途中喪失したものではなく、先天的なものだからというのが大きな理由なのだと私は感じているのです。
このことは、自覚できないマイノリティは、自分の感覚は「普通」であると思って疑わない「無自覚ゆえの保守派」という例えで説明できます。
何故ASDの自覚が出来ないのか?
それは、既得権益の上での安定を目指す保守の思想を持ち続けるから。
困りごとを問題提起するには、困りごとの理解が必要なのですよ。
ところが、困りごとの自覚が持てない…なぜならば先天的で比較すべき対象がないから。
そして、この「無自覚ゆえの保守派」を支えるもうひとつの理由が、ひとつの「できる」ことからその人の能力を推測して「できるだろう範囲」を割り出すことで発生する「みなしできる」という定型(典型)発達的な能力予想です。
人間には発達段階という年齢相応の「心身の発達状態の平均値」があって、基本的にはその通りに発達する人が多い…ということです。
だから、発達段階の速い遅いはあっても、発達段階に合わせて全てが均等に発達していると「錯覚」してしまうのだろうと私は思うのです。
発達障害と診断された人は、この「均等だ」と認識される枠を逸脱した凸凹がある…ということです。
私は「良く見える眼」を持ち、見ることに自信を持ってきました。
その「見る能力」を使って仕事をしてきたのも事実なのです。
だから私の眼は良く見えるもの…と思ってきたのだと思います。
ここに「良く見てる」と一般的に表現される「物理的に見える」と「多角的な視点」というふたつの事象があり、その混同があった可能性が高い理由が見えてくるワケですね。
定型(典型)発達者から見れば、物理的に見る能力の高さから、視点切り替えによる多角的視点も持ち合わせているだろう「みなしできる」が発動しているだろうし、発達障害当事者から見れば、元々できないものを「できない」と分かるワケもなく、自分の物理的に良く見える眼について「良く見えるね」と言われれば、見るというのはそういうものだ…と思うでしょうしね。
恐らくこの世の中の標準的な社会を作り上げている普通の概念が、ASDの理解を難しくしているのだと思うのです。
この「普通」を挟んだ定型(典型)発達者のあなたとASDの私は、同じように「普通」という言葉を使い、違う「普通」の中で生きているように思うのです。
冒頭に戻り、定型(典型)発達者側から見たASDの苦手を探るための「クルマの運転はできますか?」という問いの根本には、社会を作りあげているマジョリティ側のクルマの運転ができるレベルの…という「普通」の感覚が滲み出ているのだと思います。
定型(典型)発達者にもクルマの運転が苦手な人はいるハズですけど…と、私は感じてしまうのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
