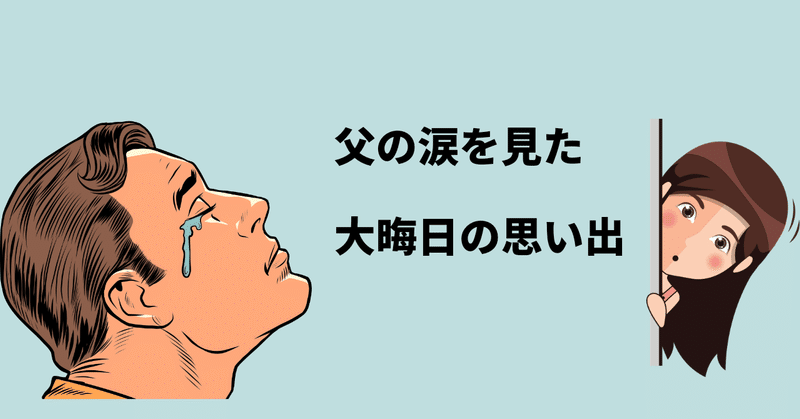
父の涙を見た、大晦日の思い出。:一年間 読んでくださった皆さんへ感謝を込めて
2021年も残りあと半日弱となりました。
今日、今年最後の投稿は、エッセイ。
お世話になった皆さん、いつも読んでくださった皆さん お一人お一人を思いうかべつつ、綴りました。
ぜひ、お読みいただけたら嬉しいです。
☆☆☆
中学1年の大晦日のことだ。
家族で朝食をとっていると、ふと父が箸を止めてつぶやいた。
「今日、墓参りに行ってきてもいいかな、年始に買い足すものは帰りに買ってくる」
そして、私の方に向かって静かにまた呟く。
「ほしまる、パパに付き添ってくれるか?」
母はにこやかに私に言う。
「うん、いってらっしゃいよ。
ほしまるも行ってきなさい?
買い足すものは、あとで言うから、よろしくね」
私も、断る理由がなかったので
頷いた。
父は私が頷くのを見守ると、照れ臭そうに新聞を開く。
そういうわけで、その年の大晦日、私は父に付き添って お墓参りに行くことになった。
☆
私の父方の祖父は、私が小学校6年生、2月に亡くなった。
最後に祖父と話したのは、希望の中学合格を知らせた電話だった。
「おじいちゃん、私、受かったよ!」
「そうか、そうか...! ほしまる、よく頑張ったな、おめでとう」
涙を流しながら喜ぶおじいちゃんとしばらく話した。
父方の親族の中では、私が唯一心を開いていたおじいちゃん。
私なりにもショックで悲しかったが、
子ども心に一番覚えているのは
父が とてもショックを受けていたことだ。
喪主として、また 祖父が兄弟たちと立ち上げた会社の 社員として
気丈には見せていたが、
父は悲しみのあまり壊れてしまいそうな雰囲気すらあった。
「おつまみさんは、繊細だから」
おつまみさん、というのは、父の名前からもじった あだ名だ。
父の姉弟や、親戚たちは、真面目な父をいつも酒の席で嘲笑していた。
通夜振る舞いの席でも、やはり親族/親戚たちは 悲しみのあまりたまに挙動不審になる父を見て笑った。
悔しくてたまらない。
父をけなす親族にはとにかく嫌悪感しかなかった。
☆
今、振り返っても本当に 父が気の毒なのだが、
相続においても、姉弟、祖母の間でかなり難航して、最終的にやたらとややこしく、おかしな相続の分配方法になった。
そんなおかしな相続をしたおかげで
父と母、妹が 亡くなった時には
私自身が ややこしい立場になり辟易したのだが。
とにかく、おじいちゃん 以外、父方の親族/親戚 とは 昔からまともに話す気にもならないほど、私は全員嫌っていた。
おじいちゃんは 東京と埼玉のちょうど県境の辺りのお寺、先祖代々お世話になっている場所に埋葬された。
私の実家からは 電車とバス/タクシーで一時間半くらい。
なので、お墓参りに行くときは
私にとっては、軽い日帰り旅行の気分だった。
☆
午前中に家を出て、
お寺から近い駅に着いた時には、もうお昼を過ぎていた。
「ほしまる、お昼食べてから行くか?」
「うん、お腹空いたー」
「それにしてもよく寝てたな」
「だって、こんなに乗ってるとさすがに眠くなるよ」
父は笑って、お店を探す。
指を指したのは、お蕎麦屋さんだった。
暖簾をくぐって扉を開ける。
さすがに、お昼時。
年末は、都内だと
どこでもある程度空いているはずなのだが、
大晦日のお蕎麦屋は通常より忙しそう。
「なに食べようか」
「あたしは決まってるよ。
年越しそばは、ママが用意してるだろうから。」
「うん、鍋焼きうどんだろ?」
「あたりー」
父に簡単に見破られて悔しい反面、
父はやはり私の好みを小さい頃から見てきた人なんだと改めて思う。
父は 天ぷらうどん。
父もやはり 母の年越し蕎麦を楽しみにしているようだ。
☆
お昼を済ませてから、花を買い、
タクシーに乗る。
お寺に着いて、ご住職と挨拶してから
おじいちゃんのお墓へ向かった。
「お父さん、桶に水いれてくる」
「じゃあ先行ってるよ」
中学に入った辺りから 私は、父と母を呼ぶときに 「パパ/ママ」と「お父さん/お義母さん」を無意識に使い分けていた。
この時も住職と奥様がまだそう遠くないところにいらしたので
さっと「お父さん」と呼んだ。
桶に水を入れてゆっくりとおじいちゃんのお墓へ向かう。
おじいちゃんのお墓の区画へ来て、私は立ち止まった。
父が声をあげながら泣いていたのだ。
見ちゃいけなかったかもしれない。
もっとゆっくり来ればよかったかもしれない。
父に申し訳ない気持ちだった。
きっと父は、何か墓前に、おじいちゃんに語りかけていたかもしれない。
その思いが溢れて泣いているのかもしれない。
しばらく私はそのまま動かずにいた。
どのくらい時間が経ったかわからない。
父の泣く声が静まったのを確認して
私は父の元に向かった。
「ごめん、ごめん。一度こぼしちゃってさ。また桶に入れ直してたの」
「そうか」
父は目を擦りながら桶を受けとる。
私はそのまま無言で花器に花を挿す。
「おじいちゃん喜んでるかねぇ」
お水をかけながら、私も泣きそうになっていた。
☆
あの時、なんで父が私を付き添わせたのか
あの時、なんで母は私に行ってきなさい、と行ったのか
今ならなんとなくわかる。
きっと 中学生の私のことも信頼してくれていたんだろう。
父が泣くだろうということ、
きっと父自身も 母も、わかっていたからこそ、
一人になりたく/させたくなかったのかもしれない。
年を重ねて、改めてわかってきた。
なぜなら、私も あの時の父と同じように
その数年後、母がおば(母の妹)を亡くした時のように
私自身も 父 と 母 そして 妹を失って
未だに涙を流すことがあるからだ。
☆☆☆
一年間読んでくださり、ありがとうございました。
そしてコメントなどで交流くださったことも感謝しています。
来る年が皆さんにとって、健やかで幸多き1年となりますよう、心からお祈りしつつ。
良いお年をお迎えくださいね。
それでは、皆さん、また(^-^)/
☆☆☆
この記事を気に入っていただけたら、サポートしていただけると、とても嬉しく思います。 サポートしていただいたお金は、書くことへの勉強や、書籍代金に充てたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
