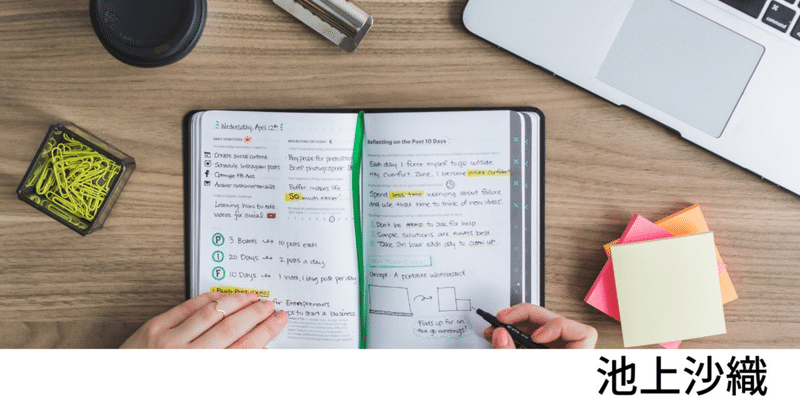
「私の死体を探してください。」 第4話
前話へ /このお話のマガジンへ/ 次話へ
「盗聴器ってことは……まさか」
ようやく私が何を言いたいかに気づいた正隆氏の鈍さにイライラした。
「先生は私と正隆さんの関係に気づいていたんです」
もう先生に聞かれている可能性があったとしても、仕方ないと思ってスマートフォンに文字を打つのはやめて、正隆氏に返事をした。
森林先生が一番信頼する編集者は私でなければいけなかったのに、これでいよいよすべてが台無しになったような気がした。先生のブログには新作と、人気シリーズのプロットを編集者に託していると書かれていた。
新作はまだしも、あの人気シリーズは先生と私が立ち上げた企画だ。あのシリーズの完結版のプロットを私はいただいていない。私が持っていないのはあまりにも不自然すぎる。私は編集長にはプロットは確かに預かっているけれど、先生の病気のことや安否は分からないと伝えて、編集部を飛び出してここにやってきた。
手ぶらでは帰れない。
もちろん、先生の安否が一番気がかりだけど、新作の原稿と人気シリーズのプロットが私以外の人間の手に渡っているのかもしれないと思うと悔しくて気が狂いそうだ。
それなのに肝心の正隆氏は何も知らないと言う。リビングでウイスキーを飲んでいた。
この別荘も、あの大きなランドクルーザープラドも、左腕で自己主張している入手困難なモデルのロレックスも、全部この人のお金で買ったものじゃないのに、なんてのんきなんだろう。
「正隆さんもね、作家志望なの」
森林麻美の夫はヒモだ。という話を他社の編集者から聞いたばかりのころに、先生は正隆氏について私にそう話した。
「そうなんですか。どういったものを書かれているんですか?」
「それは私にも分からないの。一度も見せてもらったことがないのよ」
そう言って苦笑する先生の顔を見て先生が疑わなくても私は正隆氏について疑った。ひとつも最後まで書き上げたことのないワナビーなんじゃないかなって。
かつてどんなに頑張っても小説を書き上げることができなかった自分のことを思い出されて、より疑いの色は濃くなった。
どんなに高尚なものを作り上げようが、どんなに素晴らしい企画や新しいこころみであろうが、完成されない作品はこの世に存在しないという点で、どんな陳腐な作品にも劣るのだ。それを森林先生ほどの方が分かっていないとも思えなかった。
そして、正隆氏は本当に何もしない男だった。家事はすべて森林先生が行っていた。丁寧で几帳面な主婦ぶりだった。東京のマンションも山中湖の別荘も隅々まで掃除が行き届き、食事も味噌まで手作りしているような徹底ぶりだった。家事に費やしている時間の一部でも自由になれば、森林先生はもっと作品作りに集中できたのではないだろうかと私は感じていた。
「森林先生、せめて掃除だけでも、外注したらどうですか? かなりご負担になっているように見えるんですけど」
「そうねえ……」
気のない返事だった。でも、その気のない返事の理由は私にもすぐに分かった。森林先生には正隆氏以外にも重荷があった。
正隆氏の母親だ。
あの姑は森林家の家計をすべてを担っているのは森林先生だということを分かっていないみたいだった。正隆氏が母親になんと言っているのかは想像に難くない。
息子の嘘を信じ続ける愚かな母親。
そして、一人息子の正隆氏をとことん甘やかし、根拠のない自信と自尊心を育てていったのはこの母親だろう。甘やかされるのがあたりまえで、茶碗ひとつ片付けようとはしない男に育て上げた母親。
正隆氏の母親はそのバトンをどうしても森林先生に渡したいようだった。
前話へ /このお話のマガジンへ/ 次話へ
↓マガジンから最新話までまとめて読めます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
